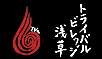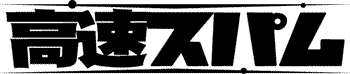『裸足の1500マイル』を観ました。
舞台は1931年のオーストラリア。当時、オーストラリアでは先 住民アボリジニの混血児たちを家族から隔離し、 白人社会に適応させようとする"隔離同化政策”がとられていた。 その政策の対象となり、強制的に収容所に連れ去られた少女3人 は、母の待つ故郷へ帰るため、2400キロに及ぶ行路を歩き始めた。
オーストラリアに限らず、コロンブスの新大陸発見によって切り開かれた植民地文化は、この種の同化政策をあらゆる非ヨーロッパ人に対して行ってきました。野蛮な彼らを救わなくてはいけない、絶対的正義であるキリスト教に啓蒙しなくてはいけない、という阿呆な使命感のもと、異なる文化を持つ民族に対して、文化と道徳と強要を押し付けてきたのです。ほんっと阿呆でしょ、白人。絶対的価値観の存在を本気で信じているのね、彼らは。あ、なんかぼく、適当な偏見を書きそう。このような歴史的見解の正しいところは、この映画に言及するすべてのサイトで書かれていると思うのでそちらをどうぞ。
白人による同化政策の犠牲になったのは、アボリジニだけではありません。「同化隔離政策」という言葉でぼくが連想するのは、アボリジニと同様に土地を侵略されたインディアンたちで、彼らの背負う悲劇の歴史を思うと、胸に強い痛みを感じます。コロンブスのアメリカ大陸発見に始まった植民地政策っていうか侵略に対抗するインディアンの運動は、三世紀に渡って続きますが、1890年のウーンデッド・ニー虐殺事件で事実上の終わりを迎えます。そして、土地を奪われたインディアンが次に強制されたのは、「白人の生き方」を強いられる同化政策でした。子供は親と引き離され、女性は子供を埋めないように手術をされ、アニミズムに基づく彼らの汎神論は否定され、キリスト教と英語を強要される。彼らの文化は野蛮と切り捨てられ、迫害者にとっての文明的な生活を送るように強制される。そのような過酷な時代を、インディアンたちは経てきたのです。
『日常礼讃—フェルメールの時代のオランダ風俗画』の著者であるツヴェタン・トドロフは、このような民族的差異を無視したアメリカナイゼーションのことを、「自己固有の価値観と一般的な価値を同一視し、私と宇宙を同一視し、要するに、世界はひとつなのだと確信している自己中心主義」と言っています。いやはやまったく同感ではありますが、ここでツヴェタンがアメリカナイゼーション(アメリカ同化政策)として言っていることは、決して他人事ではなく、よくよく考えてみれば、「世界は(自分の有する価値観に準じて)ひとつなのだと確信している自己中心主義」な人というのは、身の回りにたくさん存在しませんか?そしてそのように考えたとき、自分自身はどうでしょうか。
ぼくたちが信じている価値観の絶対性は、それが些細なものであろうとも、人の差異を無視し、他人と他人という関係の意味を無効にしてしまう危険性を孕んでいます。恐ろしいのは、あまりにも膨大な意味の中に生きている人は、その意味の存在にすら気付かないということで、例えば「世界はひとつなのだと確信している自己中心主義」者は、『裸足の1500マイル』を観て感動しても、自分が「自己中心主義」であるということに気付かないものです。だから人は過ちを繰り返すし、歴史は反省をしない。もちろん、そのような自己中心主義者たちの中に、ぼく自信も含まれていることは、悲しいけれど否定しません。
この種の問題は本当に難しいものでして、明確なポリシーや答えを持っているわけではないのでこの辺でやめておきますが、人が人と接するときに持つべきなのは、優越を計る定規ではなく、敬意であるべきなのではないか、とそんなことを思ってしまったり。
話は突然変わりますが、スパイク・リーによって黒人映画が誕生したのであれば、インディアン(ネイティヴ・アメリカン)映画はシャーマン・アレクシーとクリス・エアによって誕生したといえるかもしれません。1998年のサンダンス映画祭で複数の賞を受賞した『スモーク・シグナル』は、シャーマン・アレクシー原作のロードムービーで、ネイティブ・アメリカンのスタッフ・キャストによる初めての映画です。驚くべきことに、この映画の前には、ネイティブ・アメリカンによって制作された作品は存在しませんでした。母なる大地を奪われたインディアンの末裔が、ようやくその才能を発揮し始めたのです。
『スモーク・シグナル』のストーリーは以下の通り。
ワシントン州スポーカン族のインディアン保留地。ヴィクターは、何年もめに家を出ていった父親がはるか南のアリゾナ州で死んだという知らせを受けた。遺灰をとりにいくのも大陸を横断するほど金がない。家を捨てた親父に対する穏やかならない感情もある。そこへ、どこからともなく幼なじみのトマスが現われ、金を貸すから一緒に連れてってくれといいだした。友達とも呼べない仲なのに、それにストーリーテラーのくせしてつまらない話ばかりしてだれもがうんざりしているトマスなんかと一緒に旅だって?
この映画の原作となったシャーマン・アレクシーの『ローン・レンジャーとトント、天国で殴り合う』は大好きな小説のひとつで、ぼくはインディアンではないけれど、げらげら笑って読みました。リザベーションに閉じこめられたインディアンの末裔たちの、なんともいえず滑稽で悲しい日常を描いた短編集で、ここ数年で読んだ小説のなかでも、かなり上位に位置する面白さです。(この小説に関しては、後ほどもっと詳しく書きたいと思っています)
『裸足の1500マイル』の中で、十四才のモリーは、妹である八歳のデイジー、従姉妹である十才のグレイシーと共に、ジープによって収容所に隔離され、そこから2400キロを歩いて母親のいる故郷へ帰ります。三人の少女ほどの距離ではありませんが、『スモーク・シグナル』のトマスとヴィクターも映画の中で歩きます。そしてストーリーテラーであるトマスは、歩きながら次のように語ります。
どこまで歩く?
どれくらい歩けば目的地につく?ずっと歩いてる。
コロンブス以来、先祖は浜から追い立てられた
カスター将軍のせいで土地に住めなくなった
僕らは歩き続け、トルーマンは原爆実験
それでも歩き続ける。
原爆の閃光の中でも道は見える
インディアンも、アボリジニも、歩いて歩いて歩いて迫害者たちに抵抗を続けます。歩いて、歩いて、歩いて。『裸足の1500マイル』が素晴らしいのは、年端もいかない少女たちが、車という白人文化によって奪われた自由を、歩くという彼らの文化によって取り戻そうとするところにあるのではないでしょうか。(ちなみにアボリジニは本来、一ヶ所に定住することのない狩猟民族でした)。

政治的に正しく言えば、黒人はアフリカン・アメリカンだし、インディアンはネイティブ・アメリカンになるのだと思うのですが、黒人はやっぱり黒人の方がかっこいいし、インディアンもインディアンのほうがかっこいいので、上の文章ではそのように使いました。シャーマン・アレクシーも自分のことはインディアンと呼んで欲しいと言っているし。敬意をもってそう呼ばせて頂きます。ですから、ぼくのこともカントリーサイド・ジャパニーズではなくて栃木野郎と呼んで下さい。そのほうがかっこいい。
去年の六月ぐらいの少し古い話なのですが、スターバックスの広告が9.11を彷彿とさせるという理由で回収になったそうです。(fromインサイター)
■Collapse into Cool(Rumors of War)
同じサイトには、こんな記事も出ております。これも去年ちょぴっと話題になりましたね。
上のふたつの記事を紹介しているUrban Legends Reference Pagesというサイトは、いわゆる都市伝説(Urban Legends)を紹介しているサイトで、巷間に伝わる都市伝説をカテゴライズして、さらにそれぞれの伝説をClaim、Status、Example、Variations、Origins、と詳細に説明してくれています。一度読み始めるととまりませんよ、これ。カテゴリだけで42もあるし。
ちなみに「Japan」で検索をしてみたところ、三十数件ほど引っ掛かかりました。日本のデパートで、クリスマスのデコレーションに、笑顔のサンタクロースが十字架にかけられている絵が飾られていた、とか、自動販売機で女子高生の使用済みパンティが売っていたとか(これは本当の話なんだって)、最近の日本の流行はシースルーのすけすけスカートだとか、Sonyは「Standard Oil of New York」の略だとか、日本で新しく発売された水素ビールを飲んでカラオケをすると、声が高くなって青い炎を吐きながら歌うことができるなどは、都市伝説として取り上げることが理解できるのですが、「スシは全部生魚(刺身)である」って都市伝説として語るにはいかがなものでしょう。
都市伝説というよりも、事件として興味深いものもあって、たとえば以下の記事。
■Japanese woman dies in Minnesota while engaged in a search for money buried by a fictional character from the film Fargo.
(日本人女性、映画「ファーゴ」の登場人物が埋めた身代金を探索中にミネソタで死亡)
これ、事実なんですって。映画「ファーゴ」でスティーブ・ブシェミ演じる誘拐犯が雪の中に埋めた大金を探しに来た日本人女性のお話。興味深い話(不謹慎?)だったので、拙訳してみました。
2001年11月、ノース・ダコタ州ビスマルクで、コニシタカコ(Konishi Takako)という28才の日本人女性が、埋立て地にあるトラック・ストップでさまよっているところを発見された。コニシさんは、11月9日にミネソタ州ミネアポリスに到着し、バスでビズマークまでやってきて、翌日、彼女が道に迷って困っているのだろうと思って声をかけてきた男性に助けられた。男性は(彼女の英語力の問題で)コニシさんとうまく会話ができなかったため、彼女をビズマークの警察署へ連れていった。彼女はそこで、警察官に高速道路の横に木がある手書きの大ざっぱな地図を見せた。それは白のタイプ用紙に書かれており、どうやら彼女は映画『ファーゴ』の登場人物が埋めた大金を探索しているらしかった。
(中略)
ビズマーク警察は、映画『ファーゴ』がフィクションであり、ノースダコタ州のどこを探しても、雪の中に埋められた埋蔵金を発見することはできない、ということを説明したが、無駄だった。彼女はなんらの法も侵しておらず、正規のビザを持ち、十分な資金を所有したので、引き止めることも、報告書を書く理由も見つからなかった。コニシさんが身振りでファーゴへ行きたいことを示したので(おそらくは、映画の登場人物によって埋められたあるはずのない大金の探索を続けるために)、警察はバスの停車場まで彼女を送った。彼女はバスに乗ってファーゴへ向かい、そこでタクシーをひろって、星を見るためにミネソタ州デトロイトレークスに行った(獅子座流星群が見たかったのかもしれない)。
数日後、あるハンターがデトロイトレークの松の木立で、偶然コニシさんの死体を発見した。検屍官は死の直接的な原因を特定することはできなかったが、彼女が鎮静剤を服用していたことと、野ざらしの状態であったことが死因ではないかと思われた。後に、彼女がビズマークから家族に送った手紙に自殺をほのめかす記述が発見されると(彼女はビズマークを去る前に、所有物のほとんどを処分していた)、彼女の死は自殺であると断定された。
コニシさんはなぜ、存在しない財宝を求めてビズマークに来たのか。そして自殺したのか。謎だけが残る。
これって日本でも記事になったのかしら。初めて聞いたよ。なんだか、切ない事件であります。彼女がファーゴに行った本当の目的は、なんだったのだろう。
日本で定番の都市伝説で、旅行先で行方不明になった娘(恋人、妻)が、数年後に見せ物小屋で発見されたというのがあるのですが、このサイトにもやっぱりありました。下の記事では、進行旅行で行った先のパリで、あるブティックの試着室に入ったまま行方不明。数年後に発見されるのですが・・・・。もちろん、これは完全な都市伝説ですよ。
誘拐された女性は、やっぱり日本人なんですね。海外で広まったのであれば、広まって行く過程でその国の女性に変わってしまってもおかしくないように思うのですが。
で、ぼくが個人的に一番面白かったのはこれなんですけど
ジョン・スタインベックの『The Grapes of Wrath』のタイトルが、日本では『The Angry Raisins』になっている、というもので、日本語の『怒れる葡萄』という邦訳はなかなか正しいと思うのですが、それを逆翻訳すると『The Angry Raisins』として伝わって、これはアメリカ人にしてみれば『おこったほしぶどうくん』みたいなニュアンスになってしまうといういわゆる「語翻訳」話で、明治の初めに日本に来たワーグマンが「to be or not to be that is the question」を「あります、ありません、あれはなんですか」と訳したという話と同じようなものです。
けれどもこの記事が面白いのは、そのような「誤翻訳」のおもしろさに焦点を当てているわけではなくて、このような話がどのような過程を経て少しずつ変化して行くのかを解説しているところにあります。興味のある方はぜひ読んでみてください。

どうでも良いのですが、一番最初のスターバックスのタゾ・シトラスティがとてもおいしそう。これって日本のスターバックスにありませんよね?
■裏マニュアルでGO!
ーそば屋の流儀の通信簿 変な「こだわり」要注意
とてもお利口さんで模範的なそばへのこだわりを語ってくれております。全然裏マニュアルじゃないのですけど。
妙に敷居が高く、こだわりすぎの店主には、意味不明の小道具を使ってひるませる。文具好きな山陽さんはたまたま持っていた分度器を卓上でもてあそんで「この客は何者?」という顔をさせた。以来、分度器は秘密兵器。さりげなく取り出すのがこつだ。
意味がわからないし。
ところで、そばの食い方に関しては、やはり池波正太郎さんのそれは相当おつなものでして、例えばちょいとした感じでこんなことをおっしゃります。
そばを食べるときに、食べにくかったら、まず真ん中から取っていけばいい。そうすればうまくどんどん取れるんだよ。端のほうから取ろうとするからグジャグジャになってなかなか取れない。そばというのは本当は、そういうふうに盛ってあるものなんだよ。そういうふうになっていないそば屋は駄目なんだよ。
素敵でしょ。
作法などというものは、結局は趣味によるところの数多に存在するものでありまして、畢竟正解などというものはなく、選んだ作法によって人それぞれの品というものが定まります。ですからそれは、人から押し付けられるものでも、人に押しつけるものでもなく、あくまでも個人が各々の趣味によって選択しなくてはいけないものなのであります。

そのようなことを考えながら、身についていない作法を気取り、ひとり黙々とそばをいただきました。ごっそさん。