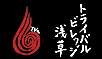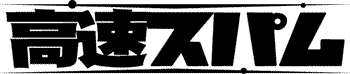『裸足の1500マイル』を観ました。
舞台は1931年のオーストラリア。当時、オーストラリアでは先 住民アボリジニの混血児たちを家族から隔離し、 白人社会に適応させようとする"隔離同化政策”がとられていた。 その政策の対象となり、強制的に収容所に連れ去られた少女3人 は、母の待つ故郷へ帰るため、2400キロに及ぶ行路を歩き始めた。
オーストラリアに限らず、コロンブスの新大陸発見によって切り開かれた植民地文化は、この種の同化政策をあらゆる非ヨーロッパ人に対して行ってきました。野蛮な彼らを救わなくてはいけない、絶対的正義であるキリスト教に啓蒙しなくてはいけない、という阿呆な使命感のもと、異なる文化を持つ民族に対して、文化と道徳と強要を押し付けてきたのです。ほんっと阿呆でしょ、白人。絶対的価値観の存在を本気で信じているのね、彼らは。あ、なんかぼく、適当な偏見を書きそう。このような歴史的見解の正しいところは、この映画に言及するすべてのサイトで書かれていると思うのでそちらをどうぞ。
白人による同化政策の犠牲になったのは、アボリジニだけではありません。「同化隔離政策」という言葉でぼくが連想するのは、アボリジニと同様に土地を侵略されたインディアンたちで、彼らの背負う悲劇の歴史を思うと、胸に強い痛みを感じます。コロンブスのアメリカ大陸発見に始まった植民地政策っていうか侵略に対抗するインディアンの運動は、三世紀に渡って続きますが、1890年のウーンデッド・ニー虐殺事件で事実上の終わりを迎えます。そして、土地を奪われたインディアンが次に強制されたのは、「白人の生き方」を強いられる同化政策でした。子供は親と引き離され、女性は子供を埋めないように手術をされ、アニミズムに基づく彼らの汎神論は否定され、キリスト教と英語を強要される。彼らの文化は野蛮と切り捨てられ、迫害者にとっての文明的な生活を送るように強制される。そのような過酷な時代を、インディアンたちは経てきたのです。
『日常礼讃—フェルメールの時代のオランダ風俗画』の著者であるツヴェタン・トドロフは、このような民族的差異を無視したアメリカナイゼーションのことを、「自己固有の価値観と一般的な価値を同一視し、私と宇宙を同一視し、要するに、世界はひとつなのだと確信している自己中心主義」と言っています。いやはやまったく同感ではありますが、ここでツヴェタンがアメリカナイゼーション(アメリカ同化政策)として言っていることは、決して他人事ではなく、よくよく考えてみれば、「世界は(自分の有する価値観に準じて)ひとつなのだと確信している自己中心主義」な人というのは、身の回りにたくさん存在しませんか?そしてそのように考えたとき、自分自身はどうでしょうか。
ぼくたちが信じている価値観の絶対性は、それが些細なものであろうとも、人の差異を無視し、他人と他人という関係の意味を無効にしてしまう危険性を孕んでいます。恐ろしいのは、あまりにも膨大な意味の中に生きている人は、その意味の存在にすら気付かないということで、例えば「世界はひとつなのだと確信している自己中心主義」者は、『裸足の1500マイル』を観て感動しても、自分が「自己中心主義」であるということに気付かないものです。だから人は過ちを繰り返すし、歴史は反省をしない。もちろん、そのような自己中心主義者たちの中に、ぼく自信も含まれていることは、悲しいけれど否定しません。
この種の問題は本当に難しいものでして、明確なポリシーや答えを持っているわけではないのでこの辺でやめておきますが、人が人と接するときに持つべきなのは、優越を計る定規ではなく、敬意であるべきなのではないか、とそんなことを思ってしまったり。
話は突然変わりますが、スパイク・リーによって黒人映画が誕生したのであれば、インディアン(ネイティヴ・アメリカン)映画はシャーマン・アレクシーとクリス・エアによって誕生したといえるかもしれません。1998年のサンダンス映画祭で複数の賞を受賞した『スモーク・シグナル』は、シャーマン・アレクシー原作のロードムービーで、ネイティブ・アメリカンのスタッフ・キャストによる初めての映画です。驚くべきことに、この映画の前には、ネイティブ・アメリカンによって制作された作品は存在しませんでした。母なる大地を奪われたインディアンの末裔が、ようやくその才能を発揮し始めたのです。
『スモーク・シグナル』のストーリーは以下の通り。
ワシントン州スポーカン族のインディアン保留地。ヴィクターは、何年もめに家を出ていった父親がはるか南のアリゾナ州で死んだという知らせを受けた。遺灰をとりにいくのも大陸を横断するほど金がない。家を捨てた親父に対する穏やかならない感情もある。そこへ、どこからともなく幼なじみのトマスが現われ、金を貸すから一緒に連れてってくれといいだした。友達とも呼べない仲なのに、それにストーリーテラーのくせしてつまらない話ばかりしてだれもがうんざりしているトマスなんかと一緒に旅だって?
この映画の原作となったシャーマン・アレクシーの『ローン・レンジャーとトント、天国で殴り合う』は大好きな小説のひとつで、ぼくはインディアンではないけれど、げらげら笑って読みました。リザベーションに閉じこめられたインディアンの末裔たちの、なんともいえず滑稽で悲しい日常を描いた短編集で、ここ数年で読んだ小説のなかでも、かなり上位に位置する面白さです。(この小説に関しては、後ほどもっと詳しく書きたいと思っています)
『裸足の1500マイル』の中で、十四才のモリーは、妹である八歳のデイジー、従姉妹である十才のグレイシーと共に、ジープによって収容所に隔離され、そこから2400キロを歩いて母親のいる故郷へ帰ります。三人の少女ほどの距離ではありませんが、『スモーク・シグナル』のトマスとヴィクターも映画の中で歩きます。そしてストーリーテラーであるトマスは、歩きながら次のように語ります。
どこまで歩く?
どれくらい歩けば目的地につく?ずっと歩いてる。
コロンブス以来、先祖は浜から追い立てられた
カスター将軍のせいで土地に住めなくなった
僕らは歩き続け、トルーマンは原爆実験
それでも歩き続ける。
原爆の閃光の中でも道は見える
インディアンも、アボリジニも、歩いて歩いて歩いて迫害者たちに抵抗を続けます。歩いて、歩いて、歩いて。『裸足の1500マイル』が素晴らしいのは、年端もいかない少女たちが、車という白人文化によって奪われた自由を、歩くという彼らの文化によって取り戻そうとするところにあるのではないでしょうか。(ちなみにアボリジニは本来、一ヶ所に定住することのない狩猟民族でした)。

政治的に正しく言えば、黒人はアフリカン・アメリカンだし、インディアンはネイティブ・アメリカンになるのだと思うのですが、黒人はやっぱり黒人の方がかっこいいし、インディアンもインディアンのほうがかっこいいので、上の文章ではそのように使いました。シャーマン・アレクシーも自分のことはインディアンと呼んで欲しいと言っているし。敬意をもってそう呼ばせて頂きます。ですから、ぼくのこともカントリーサイド・ジャパニーズではなくて栃木野郎と呼んで下さい。そのほうがかっこいい。