
02年07月22日(月)
アメリカ文学のお話。
少し前になりますが、ドン・デリーロの「アンダーワールド」の翻訳本が出版されました。
「来たるべき作家たち」なんかでは、1998年の段階で翻訳が「来年出版予定」と書いてあったのですが、結局今年までかかってしまったみたいです。
本屋でかるく立ち読みしたのですが、とにかく分厚い。分厚いのが二冊。翻訳される前は、「読みたいよ!読みたいよ!早く翻訳してくれよ!」とずっと思っていたのですが、いざ出版されるとなかなか読む気にも、買う気にもなりません。
リチャード・パワーズの「ガラテイア2.2」なんかもずーっと翻訳されるのを待っていたのですが、いざ出版されるとどうしても読む気になれません。すげー面白そうなんですけどね。
単に人工知能がテーマの小説なのかと思っていたら、群像に載っていた横田創さんの「ガラテイア2.2」の書評なんかを読むと、そんな単純なものではなさそうですね。(当たり前?)
何だか書いているうちに、『アンダーワールド』と『ガラテイア2.2』が無性に読みたくなってきました。今週末は読書三昧しようかしら。
ポール・オースターは『The Red Notebook: True Stories』が出たり。
とりあえずAmazonでペーパーバックを購入してみましたけど、内容的にはあちこちに収録されているエッセイの寄せ集めです。
でも、
「Why write?」とかも収録されていますし。これ、かなりおもしろいですよ。
さらに本屋を徘徊していると、スティーブン・ミルハウザーの『マーティン・ドレスラーの夢』が出ているのを見つけたり、マイケル・シェイボンの『悩める狼男たち』なんかも読みたいなあと思ったり、読みたい本は山ほどあれど、日常の細事に追われ、思うままには読む能わず。
ところで、デリーロとパワーズといえば、新潮の2000年12月号には、以下のような記事が載っていました。
■Beyond Words—テロ惨劇に呼び起こされた、アメリカ作家たちの“声”
去年の10月11日にニューヨークで行われた「Beyond Words(言葉では言い尽くせない)」というタイトルの朗読会から、現在のアメリカ文学界の現状までを新元良一さんがレポートしています。
言葉を表現の手段としている文学者達が、言葉を越えた(Beyond Words)世界を経験したとき、どのような物語が誕生するのか。
というレポートです。
(言葉を越えた世界というのは、言うまでもなく9.11のことです。)

少し前になりますが、ドン・デリーロの「アンダーワールド」の翻訳本が出版されました。
「来たるべき作家たち」なんかでは、1998年の段階で翻訳が「来年出版予定」と書いてあったのですが、結局今年までかかってしまったみたいです。
本屋でかるく立ち読みしたのですが、とにかく分厚い。分厚いのが二冊。翻訳される前は、「読みたいよ!読みたいよ!早く翻訳してくれよ!」とずっと思っていたのですが、いざ出版されるとなかなか読む気にも、買う気にもなりません。
リチャード・パワーズの「ガラテイア2.2」なんかもずーっと翻訳されるのを待っていたのですが、いざ出版されるとどうしても読む気になれません。すげー面白そうなんですけどね。
単に人工知能がテーマの小説なのかと思っていたら、群像に載っていた横田創さんの「ガラテイア2.2」の書評なんかを読むと、そんな単純なものではなさそうですね。(当たり前?)
『息を呑むほど壮大で華麗なインチキ』であるこの小説は、自分の『インチキ』を証明するために書かれている。そして今、賭けられているのは、この小説をトレーニングしている(読んでいる)私たちなのだ。『中心になる時制は現在だ。物語の要点は、あなたが物語をどうするかにある。』ああ、やっぱり面白そうだな。
何だか書いているうちに、『アンダーワールド』と『ガラテイア2.2』が無性に読みたくなってきました。今週末は読書三昧しようかしら。
ポール・オースターは『The Red Notebook: True Stories』が出たり。
とりあえずAmazonでペーパーバックを購入してみましたけど、内容的にはあちこちに収録されているエッセイの寄せ集めです。
でも、
Auster again explores events from the real world —large and small, tragic and comic—that reveal the unpredictable, shifting nature of human experience.なんていう説明を読むと、買わずにはいられませんよ。
「Why write?」とかも収録されていますし。これ、かなりおもしろいですよ。
さらに本屋を徘徊していると、スティーブン・ミルハウザーの『マーティン・ドレスラーの夢』が出ているのを見つけたり、マイケル・シェイボンの『悩める狼男たち』なんかも読みたいなあと思ったり、読みたい本は山ほどあれど、日常の細事に追われ、思うままには読む能わず。
ところで、デリーロとパワーズといえば、新潮の2000年12月号には、以下のような記事が載っていました。
■Beyond Words—テロ惨劇に呼び起こされた、アメリカ作家たちの“声”
去年の10月11日にニューヨークで行われた「Beyond Words(言葉では言い尽くせない)」というタイトルの朗読会から、現在のアメリカ文学界の現状までを新元良一さんがレポートしています。
言葉を表現の手段としている文学者達が、言葉を越えた(Beyond Words)世界を経験したとき、どのような物語が誕生するのか。
というレポートです。
(言葉を越えた世界というのは、言うまでもなく9.11のことです。)

02年07月21日(日)
昨日の日記にも書きましたが、ウィリアム・T・ヴォルマンの「蝶の物語たち」を購入し、現在読書中です。
最初はすげー読みづれーとか思っていましたが、読んでいくうちにどんどんはまっていく。随所にちりばめられたヴォルマン自身による挿し絵が、とてもよい効果を出しております。
こんな挿し絵。かわいいでしょ。

東南アジアに旅行に行くからというわけではないけれど、ヴォルマンは個人的にそうとう気になっていた作家さんでして、彼の書くものと言ったら、世界中を旅して娼婦やドラッグやピストルや国境や正義や難民なんかを描いた旅行記とか、あるいはアメリカの歴史がこれでもかこれでもかとばかり滔々と書きつづられている歴史小説とか、あるいはタイで売春婦を救出する様を描いたアクションもの(っていうかノンフィクションなのですが)とか、そのような作品ばかりなのです。
アメリカの歴史を描いた「Seven Dreams」というシリーズは、全7巻になりますが、いまのところまだ4巻しかでていなくて、全部で15年をかけるつもり(フィネガンズ・ウェイク!)らしいので、全部が完成するのは2005年になるそうです。
建国以来200年少ししか経っていないアメリカという国を、千年の時間を遡って描き、「ヴォルマンの体内に流れるアメリカ人という血の中に、先祖代々から受け継がれたさまざまな記憶を読み解き、言葉に変えていこうとする試みなのだ。」(『ヴォルマン、お前は何者だ!』より)
これ、翻訳をするのはかなり大変だとは思いますが、なんとか翻訳してくれないかしら。とても読みたいのだけど。
世界百二十六都市を巡るヴォルマンの旅をもとに描かれた「The Atlas」という作品は、川端康成の「掌の小説」に着想を得て書かれたもので、各都市を描いたショート・ストーリーをすべて読むと、内在しているテーマが見えてくる、という手法で書かれています。もちろんトーキョーオーサカも入っていますよ。この作品も未訳です。
それでは一体どの作品が翻訳されているのかというと、
■ザ・ライフルズ
(Amazonの紹介文)「北西航路」を探して北極圏で全滅した19世紀英国のフランクリン探検隊。領土確保のために同地への移住を余儀なくされた、ケベック州のイヌイットたち。凍てつく極北の地を舞台に、2つの物語が時空を越えて結びつく。
■蝶の物語たち(現在読書中)
(Amazonの紹介文)愛する娼婦ヴァンナが消えた!?アメリカ人ジャーナリストは彼女を探し、地雷と密林、タイ—カンボジア国境を越える—東南アジアの純真をセクシュアルに描く極熱のラブストーリー。
■ハッピー・ガールズ、バッド・ガールズ
(Amazonの紹介文)娼婦、ドラッグディーラー、ポルノグラファー、ポン引き、手錠フェチ、現代アメリカのオブセッションを描く、若き鬼才の傑作。どこか壊れてしまった人間たち、崩壊せざるを得ない人間たちの姿。
の三作品で、その他
■ヴォルマン、お前はなに者だ!—地球のオルタナティヴを描く記録天使
というヴォルマン特集雑誌も出ています。この本がなかったら、ぼくがヴォルマンに興味を持つことなんておそらくなかったでしょう。
あと、ぼくのお気に入りの小説集に「Positive 01-ポストモダン小説、ピンチョン以後の作家たち」があるのですが、その中にも「The Grave of Lost Stories」という作品が翻訳されています。これは「Thirteen Stories and Thirteen Epitaphs」に収められている作品のひとつなのですが、「Thirteen〜」の邦訳である「ハッピー・ガールズ、バッド・ガールズ」に収められているものとは訳者が違うみたいです。
娼婦が大好きで、アジアの各国に現地妻がいるという噂もありますが、本人は否定していて、何年か前には正式に結婚もしたみたいです。いっそのこと、アジアの娼婦とかと結婚すれば良かったのに。坪内逍遥みたいに。
しかし、このヴォルマン君、中島君の弟さんに顏がそっくりなのです。
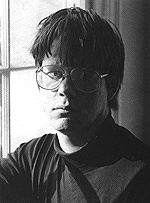
ですから、「蝶の物語たち」を読んでいると、ぼくの頭の中には、中島君の弟が娼婦の恋人を探して東南アジアをさまよっている姿が浮かんで仕方がありません。
最初はすげー読みづれーとか思っていましたが、読んでいくうちにどんどんはまっていく。随所にちりばめられたヴォルマン自身による挿し絵が、とてもよい効果を出しております。
こんな挿し絵。かわいいでしょ。

東南アジアに旅行に行くからというわけではないけれど、ヴォルマンは個人的にそうとう気になっていた作家さんでして、彼の書くものと言ったら、世界中を旅して娼婦やドラッグやピストルや国境や正義や難民なんかを描いた旅行記とか、あるいはアメリカの歴史がこれでもかこれでもかとばかり滔々と書きつづられている歴史小説とか、あるいはタイで売春婦を救出する様を描いたアクションもの(っていうかノンフィクションなのですが)とか、そのような作品ばかりなのです。
アメリカの歴史を描いた「Seven Dreams」というシリーズは、全7巻になりますが、いまのところまだ4巻しかでていなくて、全部で15年をかけるつもり(フィネガンズ・ウェイク!)らしいので、全部が完成するのは2005年になるそうです。
建国以来200年少ししか経っていないアメリカという国を、千年の時間を遡って描き、「ヴォルマンの体内に流れるアメリカ人という血の中に、先祖代々から受け継がれたさまざまな記憶を読み解き、言葉に変えていこうとする試みなのだ。」(『ヴォルマン、お前は何者だ!』より)
これ、翻訳をするのはかなり大変だとは思いますが、なんとか翻訳してくれないかしら。とても読みたいのだけど。
世界百二十六都市を巡るヴォルマンの旅をもとに描かれた「The Atlas」という作品は、川端康成の「掌の小説」に着想を得て書かれたもので、各都市を描いたショート・ストーリーをすべて読むと、内在しているテーマが見えてくる、という手法で書かれています。もちろんトーキョーオーサカも入っていますよ。この作品も未訳です。
それでは一体どの作品が翻訳されているのかというと、
■ザ・ライフルズ
(Amazonの紹介文)「北西航路」を探して北極圏で全滅した19世紀英国のフランクリン探検隊。領土確保のために同地への移住を余儀なくされた、ケベック州のイヌイットたち。凍てつく極北の地を舞台に、2つの物語が時空を越えて結びつく。
■蝶の物語たち(現在読書中)
(Amazonの紹介文)愛する娼婦ヴァンナが消えた!?アメリカ人ジャーナリストは彼女を探し、地雷と密林、タイ—カンボジア国境を越える—東南アジアの純真をセクシュアルに描く極熱のラブストーリー。
■ハッピー・ガールズ、バッド・ガールズ
(Amazonの紹介文)娼婦、ドラッグディーラー、ポルノグラファー、ポン引き、手錠フェチ、現代アメリカのオブセッションを描く、若き鬼才の傑作。どこか壊れてしまった人間たち、崩壊せざるを得ない人間たちの姿。
の三作品で、その他
■ヴォルマン、お前はなに者だ!—地球のオルタナティヴを描く記録天使
というヴォルマン特集雑誌も出ています。この本がなかったら、ぼくがヴォルマンに興味を持つことなんておそらくなかったでしょう。
あと、ぼくのお気に入りの小説集に「Positive 01-ポストモダン小説、ピンチョン以後の作家たち」があるのですが、その中にも「The Grave of Lost Stories」という作品が翻訳されています。これは「Thirteen Stories and Thirteen Epitaphs」に収められている作品のひとつなのですが、「Thirteen〜」の邦訳である「ハッピー・ガールズ、バッド・ガールズ」に収められているものとは訳者が違うみたいです。
娼婦が大好きで、アジアの各国に現地妻がいるという噂もありますが、本人は否定していて、何年か前には正式に結婚もしたみたいです。いっそのこと、アジアの娼婦とかと結婚すれば良かったのに。坪内逍遥みたいに。
しかし、このヴォルマン君、中島君の弟さんに顏がそっくりなのです。
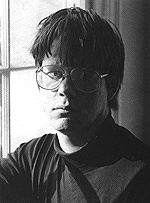
ですから、「蝶の物語たち」を読んでいると、ぼくの頭の中には、中島君の弟が娼婦の恋人を探して東南アジアをさまよっている姿が浮かんで仕方がありません。
02年07月20日(土)
ある時、尊敬する友人のひとりが、ドイツの思想家であるエルンスト・ブロッホの'Darkness of the lived moment'という言葉を引用しながら、休みの日は山や川のそばで、何もしないでぼーっと本でも読んでいるのが良い、ということを言っていました。
「休みの日はぼーっとしたほうがいい」なんてことは、誰もが思っていることで、箴言でも何でもないわけですが、'Darkness of the lived moment'という言葉と一緒にそれを聞いた時、ぼくはなぜかとても感動をしてしまい、その言葉を心の中で何度も反芻しました。
直訳すると、「生かされている瞬間の闇」ということになるのでしょうか、ブロッホがどのようなつもりでその言葉を述べたのかはわかりませんが、この言葉を口に出して言うと、気付いていない何かに気付かされたような気持ちになります。
それで先日、その友人と久しぶりに会ってお話をする機会があったのですが、その時に夏休みの予定の話になり、ぼくが「ちょっと東南アジアへ行ってきます」と言ったところ、「なんで?」と聞かれました。
心の中では、「いやあ、何もないラオスの川や海の近くで読書でもしながらぼーっとしていようかと思って。」などと答えて、「いやあ、君、なかなかいいね。感性がぼくと似ているんじゃない?」などと言われたいなあ、と思いつつも、日ごろの癖でついつい「まあねえ、本当はヨーロッパに行きたいのですけど、ヨーロッパって物価高いですからねえ、安くて馬鹿なアジアがお似合いですよ、ぼくには。ほら、馬鹿でしょう、アジア人。くせえっつーのね、あいつら、ねえ。」などと心にもないことを口走ってしまいました。
小学生の頃のひねくれた性格が、いまだ直っておりません。
貧乏性のぼくには、旅行先でハンモックに揺られながら何も考えずに一日読書なんてことはできそうにありませんが、それでも今回の旅行は、魂のお洗濯ということで、最小限の予定しかたてずに、できるだけゆっくりとしてこようと思っています。
ぼくの行く予定の南ラオスは、本当に何もない地域で、そこに行くと言うと、ラオスの人にさえ呆れられるそうです。
ラオスの方々は、みなさんとても心がやさしいということなので、この汚れた魂を少しでも洗い流せれば良いですけれど。
とても楽しみ。
「休みの日はぼーっとしたほうがいい」なんてことは、誰もが思っていることで、箴言でも何でもないわけですが、'Darkness of the lived moment'という言葉と一緒にそれを聞いた時、ぼくはなぜかとても感動をしてしまい、その言葉を心の中で何度も反芻しました。
直訳すると、「生かされている瞬間の闇」ということになるのでしょうか、ブロッホがどのようなつもりでその言葉を述べたのかはわかりませんが、この言葉を口に出して言うと、気付いていない何かに気付かされたような気持ちになります。
それで先日、その友人と久しぶりに会ってお話をする機会があったのですが、その時に夏休みの予定の話になり、ぼくが「ちょっと東南アジアへ行ってきます」と言ったところ、「なんで?」と聞かれました。
心の中では、「いやあ、何もないラオスの川や海の近くで読書でもしながらぼーっとしていようかと思って。」などと答えて、「いやあ、君、なかなかいいね。感性がぼくと似ているんじゃない?」などと言われたいなあ、と思いつつも、日ごろの癖でついつい「まあねえ、本当はヨーロッパに行きたいのですけど、ヨーロッパって物価高いですからねえ、安くて馬鹿なアジアがお似合いですよ、ぼくには。ほら、馬鹿でしょう、アジア人。くせえっつーのね、あいつら、ねえ。」などと心にもないことを口走ってしまいました。
小学生の頃のひねくれた性格が、いまだ直っておりません。
貧乏性のぼくには、旅行先でハンモックに揺られながら何も考えずに一日読書なんてことはできそうにありませんが、それでも今回の旅行は、魂のお洗濯ということで、最小限の予定しかたてずに、できるだけゆっくりとしてこようと思っています。
ぼくの行く予定の南ラオスは、本当に何もない地域で、そこに行くと言うと、ラオスの人にさえ呆れられるそうです。
ラオスの方々は、みなさんとても心がやさしいということなので、この汚れた魂を少しでも洗い流せれば良いですけれど。
とても楽しみ。







