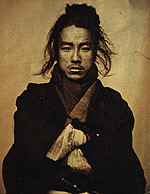02年07月16日(火)
02年07月15日(月)
朝九時、あまりの暑さに起床。
頭がぐにゅぐにゅしていたので、すっきりする映画が観たいと思い、渋谷に『ゴースト・オブ・マーズ』を観に行きました。
予想はしていたものの、劇場に入るとそこはまるでダニエル・クロウズの「Ghost World」のようで、ぶつぶつ何かを言っているでぶとか、しきりに頭の髪の毛を気にしているハゲとか、ブラックジャック並に右半分がやたら黒いやつとか、必要以上にいちゃついている中年のカップルとか、おしっこの臭いを漂わせている浮浪者風の男とか、BMIが15を切っているのではないかというくらい痩せたガリとか、1秒間に五回ぐらい眼鏡の位置を気にしている眼鏡君とか、その中にいて全然違和感のない僕とか、月曜日の第一回目の上映を観ようなんていう人間にろくな奴はいません。
けれども、こうして見渡すと、鉄割の稽古場と何も変わらないことに気付く。
『ゴースト・オブ・マーズ』は、阿部和重とか中原昌也とかがあちこちのメディアで大絶賛していただけあって、とても面白かったです(ぼくはこの両者共、作品を読んだことはないのだけど)。ぐじゅぐじゅしていた頭がむにゅむにゅになりました。未来の世界を描いたこの映画は、全然未来っぽくなくて、それがとても良かったです。やっぱり、スカッとするにはレーザービームではなくて、マシンガンでしょう。殺されるためだけに出てくる火星の先住民の幽霊たちには愛おしさすら感じました。
頭がぐにゅぐにゅしているときに観る映画は、何の期待もなく観れて、観ている間は集中できて、観終えたらすっかり忘れてしまうような映画に限ります。
まさしくジョン・カーペンター。
ところで、『ゴースト・オブ・マーズ』のオフィシャルのサイトは、他の映画のサイトと比べると、いろいろな人のエッセイやらコメントやらが長文で読めて、訪れてとても楽しいサイトだと思うのですけど、いかがでしょうか。
映画館を出て、ブックファースト1によって新刊本を物色。
特に面白そうな新刊がないので、スタジオボイスの今月号(「ポストモダン・リターンズ」)と堀江敏幸「郊外へ」、前から読みたかった武田百合子「富士日記(上)」、ウィリアム・T・ヴォルマン「蝶の物語たち」などを購入。一気にトートバックが重くなる。うーん。
その後、渋谷から原宿まで歩く。途中、明治通り沿いにあるブリスターに寄ってアメリカのコミック系アーティストのオムニバス「9.11」を購入。Vol.2も売っていたけれど、とりあえずVol.1を読んでみよう。
そのままさらに歩いて、相当歩いて図書館に行く。その図書館の二階に上がる階段の正面には、馬鹿でかい「熊野路」の絵が飾られていて、それを観るたびに那智の滝に呼ばれているような気がする。
いくら呼ばれても、今年はぼくは東南アジアに行ってしまうのよ。ごめんね。
図書館で、絶版になっている松山巌の「百年の棲家」などを借る。
帰りにちょっと贅沢して高めの白桃を買う。
頭がぐにゅぐにゅしていたので、すっきりする映画が観たいと思い、渋谷に『ゴースト・オブ・マーズ』を観に行きました。
予想はしていたものの、劇場に入るとそこはまるでダニエル・クロウズの「Ghost World」のようで、ぶつぶつ何かを言っているでぶとか、しきりに頭の髪の毛を気にしているハゲとか、ブラックジャック並に右半分がやたら黒いやつとか、必要以上にいちゃついている中年のカップルとか、おしっこの臭いを漂わせている浮浪者風の男とか、BMIが15を切っているのではないかというくらい痩せたガリとか、1秒間に五回ぐらい眼鏡の位置を気にしている眼鏡君とか、その中にいて全然違和感のない僕とか、月曜日の第一回目の上映を観ようなんていう人間にろくな奴はいません。
けれども、こうして見渡すと、鉄割の稽古場と何も変わらないことに気付く。
『ゴースト・オブ・マーズ』は、阿部和重とか中原昌也とかがあちこちのメディアで大絶賛していただけあって、とても面白かったです(ぼくはこの両者共、作品を読んだことはないのだけど)。ぐじゅぐじゅしていた頭がむにゅむにゅになりました。未来の世界を描いたこの映画は、全然未来っぽくなくて、それがとても良かったです。やっぱり、スカッとするにはレーザービームではなくて、マシンガンでしょう。殺されるためだけに出てくる火星の先住民の幽霊たちには愛おしさすら感じました。
頭がぐにゅぐにゅしているときに観る映画は、何の期待もなく観れて、観ている間は集中できて、観終えたらすっかり忘れてしまうような映画に限ります。
まさしくジョン・カーペンター。
ところで、『ゴースト・オブ・マーズ』のオフィシャルのサイトは、他の映画のサイトと比べると、いろいろな人のエッセイやらコメントやらが長文で読めて、訪れてとても楽しいサイトだと思うのですけど、いかがでしょうか。
映画館を出て、ブックファースト1によって新刊本を物色。
特に面白そうな新刊がないので、スタジオボイスの今月号(「ポストモダン・リターンズ」)と堀江敏幸「郊外へ」、前から読みたかった武田百合子「富士日記(上)」、ウィリアム・T・ヴォルマン「蝶の物語たち」などを購入。一気にトートバックが重くなる。うーん。
その後、渋谷から原宿まで歩く。途中、明治通り沿いにあるブリスターに寄ってアメリカのコミック系アーティストのオムニバス「9.11」を購入。Vol.2も売っていたけれど、とりあえずVol.1を読んでみよう。
そのままさらに歩いて、相当歩いて図書館に行く。その図書館の二階に上がる階段の正面には、馬鹿でかい「熊野路」の絵が飾られていて、それを観るたびに那智の滝に呼ばれているような気がする。
いくら呼ばれても、今年はぼくは東南アジアに行ってしまうのよ。ごめんね。
図書館で、絶版になっている松山巌の「百年の棲家」などを借る。
帰りにちょっと贅沢して高めの白桃を買う。
02年07月14日(日)
待ちに待ったみんなのトニオちゃんがとうとう単行本化されました。
かわいらしいトニオちゃんやジャイ太やスネ郎が、毎週のようにぶっ殺されていくこの漫画、以前SPA!で連載していたときは毎週楽しみに読んでいたのですが、いきなり終わってしまって残念に思っていたので、単行本化はぼくにとってとても喜ばしいことなのです。
この漫画は、よく哲学的であると言われますが、漫画の中で書かれている哲学的なことって、じつは誰もが思春期に考えたことがあるようなことで、それだけでこの漫画を読むと、ちょぴっと拍子抜けしてしまうかもしれません。
けれども、それがどうしてこんなにも面白いのかというと、精神科医である斉藤環氏が解説で書いているように、「文体、すなわち語り口がある」からなのです。
たとえば、仲俣暁生は「ポスト・ムラカミの日本文学」の中で、村上龍の「限りなく透明に近いブルー」を、ドラッグ小説としてしか読むことが出来なかった中上健次に言及して、次のように書いています。
それはともかく、トニオちゃんのぶっ殺されぶりをゆっくりと楽しませていただきます。
かわいらしいトニオちゃんやジャイ太やスネ郎が、毎週のようにぶっ殺されていくこの漫画、以前SPA!で連載していたときは毎週楽しみに読んでいたのですが、いきなり終わってしまって残念に思っていたので、単行本化はぼくにとってとても喜ばしいことなのです。
この漫画は、よく哲学的であると言われますが、漫画の中で書かれている哲学的なことって、じつは誰もが思春期に考えたことがあるようなことで、それだけでこの漫画を読むと、ちょぴっと拍子抜けしてしまうかもしれません。
けれども、それがどうしてこんなにも面白いのかというと、精神科医である斉藤環氏が解説で書いているように、「文体、すなわち語り口がある」からなのです。
菅原はその発想のみによって評価されるべきではない。発想だけなら中学生にもできる。この解説は「みんなのトニオちゃん」をとても的確に評価しているように思うのですが、どのような漫画でも、小説でも、映画でも、いわゆる作品と呼ばれるものにとって、もちろん発想の斬新さというものは大切ですし、重要な要素のひとつであることは間違いありませんが、発想だけの作品というものは、概してつまらない作品なってしまうものです。小説なんかでも、それが面白いかどうかは「文体」にかかっていますからね。
そうした問いへと読者を誘発する手つきの見事さこそが、彼の本領にほかならないのだ。
(解説より)
たとえば、仲俣暁生は「ポスト・ムラカミの日本文学」の中で、村上龍の「限りなく透明に近いブルー」を、ドラッグ小説としてしか読むことが出来なかった中上健次に言及して、次のように書いています。
一読してわかるのは、言葉が即物的な記述のためだけに使われていることです。心理描写を排し、主人公である語り手のリュウに無人格なカメラの役割を果たさせながら、徹頭徹尾、映像的にものごとを記述する。そのことを意識的におこなったのがこの作品の新しさでした。「心理のない記述」を、中上健次は「ラリッてる」のだと誤解したのです。でも、この小説が衝撃的だったのは、ドラッグやセックスといった退廃的な若者風俗を描いたからではなく、映像的に清々しい文章にありました。いま読んでも十分に新鮮なのはそのせいです。
それはともかく、トニオちゃんのぶっ殺されぶりをゆっくりと楽しませていただきます。