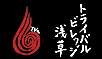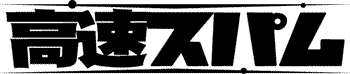02年07月08日(月)
今月号のユリイカは「高野文子」特集です。
新刊である「黄色い本」をまだ読んでいなかったので、ユリイカと一緒に購入、帰りにコーヒーを飲ませてくれるお店に立ち寄って、一気に読んだのですが、期待を裏切らずにかなり面白いい。
『黄色い本』は、「チボー家の人々」に魅せられた女子高生実ッコが、現実と小説の世界の混在した日々を送る姿を描いた作品です。
ひとコマひとコマに、温かさが溢れていて、読んでいてなんだかほわわんとしてしまいます。
図書館で借りた『チボー家の人々』にはまっている実ッコちゃんをみて、おやじさんが言う「実ッコ、その本買うか?」という台詞にまたじんわりとしてしまいます。
『棒がいっぽん』という単行本に収められている「美しい町」という作品は、昭和中期のある平凡な夫婦の日常の物語です。物語の最期のシーンで、徹夜でがり版を切り、印刷をした夫婦が、部屋のインクの臭いを消すためにドアを開けます。
三十年経ったあとで、ふと思い出すのはこんな日なのかもしれない。二人とも、同じことを考えているのに、二人とも、そのことを知らない。三十年後に、ふたりが同時に今日のことを思い出したとしても、お互いが同じことを思い出していることも知らないでしょう。でもそれが素敵ね。
同じ単行本に収められている『奥村さんのお茄子』は、高野文子の作品の中でも特に人気のある作品のひとつで、突然現れた宇宙人の遠久田さんに、「一九六八年六月六日木曜日、お昼何めしあがりました?」と詰問される奥村さんの物語です。
物語は、全般を通して記憶の再生をテーマとして進行します。遠久田さんは、先輩の無実の罪をはらすために、奥村さんの一九六八年六月六日(二十数年前)のお昼ごはんが茄子であったことを証明しようと、奥村さんに当時の記憶を取り戻してもらおうと懸命になります。
けれども、そんなことはもちろん不可能です。二十数年前のある日のお昼ご飯なんて、普通思い出すことは出来ません。
遠久田さんは言います。
当たり前のことではありますが、今この瞬間にも、同じ時間に異なる人々が、異なる行為をして、異なることを考えています。そのあたりまえのことが、『奥村さんのお茄子』ではとてもあたりまえに描かれています。
保坂和志は、「私が遠く離れた誰かのことを考えているとき、相手のその人は『私が今考えている』ということを、まったくわからないのだろうか、それともわかる可能性があるのだろうか」というモチーフのもとに『コーリング』『残響』という作品を書いています。。
『コーリング』は、美緒と浩二と恵子という三人の人物が、同じ時間に異なる場所でそれぞれが考えていることを、保坂和志の表現を借りれば、テレビのチャンネルを回すようにガチャ、ガチャ、ガチャと切り替わって描かれていきます。
保坂和志は、自らのホームページ内で、『コーリング』について以下のように語っています。
ところで、『コーリング』の中で土井浩二は「せつなさ」について次のように言っています。
河合隼雄は、『ブッダの夢』という対談集の中で、次のようなことを言っています。
なんだか思いつくままに書いていったら止まらなくなってしまいました。しかも書いてあることも自分でもよくわからなくなってしまいました。
そういうわけで、ぼくは『黄色い本』に収められている『マヨネーズ』という作品の主人公であるたきちゃんのような女性が、とても好きです。
新刊である「黄色い本」をまだ読んでいなかったので、ユリイカと一緒に購入、帰りにコーヒーを飲ませてくれるお店に立ち寄って、一気に読んだのですが、期待を裏切らずにかなり面白いい。
『黄色い本』は、「チボー家の人々」に魅せられた女子高生実ッコが、現実と小説の世界の混在した日々を送る姿を描いた作品です。
ひとコマひとコマに、温かさが溢れていて、読んでいてなんだかほわわんとしてしまいます。
図書館で借りた『チボー家の人々』にはまっている実ッコちゃんをみて、おやじさんが言う「実ッコ、その本買うか?」という台詞にまたじんわりとしてしまいます。
『棒がいっぽん』という単行本に収められている「美しい町」という作品は、昭和中期のある平凡な夫婦の日常の物語です。物語の最期のシーンで、徹夜でがり版を切り、印刷をした夫婦が、部屋のインクの臭いを消すためにドアを開けます。
「工場が見えました」(これは、言葉で書くと感動が全然伝わらないと思いますが、作品の中ではナレーションとして、間(ま)と、セリフと、絵柄が絶妙に描かれています。)
「耳をすますとモーターの音が聞こえてきます。」
「さっきなにかのブザーの音も鳴りました。」
「たとえば三十年たったあとで」
「今の、こうしたことを思いだしたりするのかしら」
「子供がいて、おとなになって、またふたりになって」
「思いだしたりするのかしら」
「ノブオさんは、そんなふうなことを思っていました」
「サナエさんも、そんなふうなことを思っていました」
「この町で」
三十年経ったあとで、ふと思い出すのはこんな日なのかもしれない。二人とも、同じことを考えているのに、二人とも、そのことを知らない。三十年後に、ふたりが同時に今日のことを思い出したとしても、お互いが同じことを思い出していることも知らないでしょう。でもそれが素敵ね。
同じ単行本に収められている『奥村さんのお茄子』は、高野文子の作品の中でも特に人気のある作品のひとつで、突然現れた宇宙人の遠久田さんに、「一九六八年六月六日木曜日、お昼何めしあがりました?」と詰問される奥村さんの物語です。
物語は、全般を通して記憶の再生をテーマとして進行します。遠久田さんは、先輩の無実の罪をはらすために、奥村さんの一九六八年六月六日(二十数年前)のお昼ごはんが茄子であったことを証明しようと、奥村さんに当時の記憶を取り戻してもらおうと懸命になります。
けれども、そんなことはもちろん不可能です。二十数年前のある日のお昼ご飯なんて、普通思い出すことは出来ません。
遠久田さんは言います。
「楽しくてうれしくて、ごはんなんかいらないよって時も、楽しくてせつなくてなんにも食べたくないよって時も、どっちも6月6日の続きなんですものね」『奥村さんのお茄子』の最後の数ページは、「三秒間、自分以外のだれかを見て、その誰かについて考える。」という現象が描かれています。誰かが誰かを見て、その誰かについて考える。見られている誰かは、他の誰かを見て、その誰かについて考える・・。
当たり前のことではありますが、今この瞬間にも、同じ時間に異なる人々が、異なる行為をして、異なることを考えています。そのあたりまえのことが、『奥村さんのお茄子』ではとてもあたりまえに描かれています。
保坂和志は、「私が遠く離れた誰かのことを考えているとき、相手のその人は『私が今考えている』ということを、まったくわからないのだろうか、それともわかる可能性があるのだろうか」というモチーフのもとに『コーリング』『残響』という作品を書いています。。
『コーリング』は、美緒と浩二と恵子という三人の人物が、同じ時間に異なる場所でそれぞれが考えていることを、保坂和志の表現を借りれば、テレビのチャンネルを回すようにガチャ、ガチャ、ガチャと切り替わって描かれていきます。
土井浩二が三年前にわかれた美緒の夢の途中で目が覚めた朝、美緒はもちろん浩二の夢など見ていなかったし思い出しもしていなかった。ぼくは『コーリング』のこの書き出しが大好きで、何度読んでも素晴らしいなあと思うのですが、この書きだしのような表現は、このあとも何度も出てきて、『コーリング』の登場人物は、誰かが誰かのことを思ったり、あるいは別のきっかけによって、どんどんと切り替わっていきます。
保坂和志は、自らのホームページ内で、『コーリング』について以下のように語っています。
このガチャンガチャンの軋みも含めて、『コーリング』の繋がっていき方は素晴らしく、文句がないと思う。が、しかし、それが文句がない理由は、本当のところ手法によるものではない(『コーリング』や『残響』のような小説を書くと手法のことばかり言われて本当に嫌になる)。全体を貫く「せつなさ」のようなものだ。あるいは、それぞれの人間が別の環境にいてもかつての環境を基準にして今いる環境を測定しているような、心の態勢(?)のようなものだ。高野文子の漫画にしても、保坂和志の小説にしても、どうしてこんなに好きなのか自分でも不思議なのですけれど、その理由のひとつには、彼らの作品が「記憶」と「時間」と「意識」という現象の素晴らしさや悲しみを描き、「記憶」というものが余韻であるということを描き、死とか、別れとか、思い出とか、そのような悲しい出来事をともなう書き方ではなくて、単なる「記憶」と「時間」と「意識」についてだけ書いてある作品だから、ということがあると思います。
(創作ノート『コーリング』&『残響』 より引用)
ところで、『コーリング』の中で土井浩二は「せつなさ」について次のように言っています。
十代のせつなさやさびしさは、原因らしい原因も持たないし対象もない。だから他人はつまらないと一蹴するが、原因も対象もないからこそ逆に解消されようもない。せつなさやさびしさは、それを抱えている当人にはとてもやっかいなものなんだ。保坂和志の小説のすばらしいところは、このように感動的な発見をさらりと書いてしまうところで、例えば、失恋をしてせつなければ失恋から立ち直ればせつなさも感じなくなるし、友人とけんかをしてさびしければ、友人と仲直りをすればさびしくなくなる。問題は、原因や対象を持たないせつなさやさびしさで、原因を持たない以上、そのせつなさは解消のしようもない(土井浩二は「十代のせつなさ」と限定しているけれど、それは限定する必要はないと思います)。そして、土井浩二のいう「せつなさ」を、『コーリング』『残響』という両作品の登場人物の中で一番強く感じているのは、おそらく『残響』の堀井早夜香で、ぼくは堀井早夜香の独白を読んでいると、それだけで感動してしまいます。
河合隼雄は、『ブッダの夢』という対談集の中で、次のようなことを言っています。
最近、宮沢賢治についてちょっと書かされた時に、「非情な悲しみ」と書いたんです。情ではない。で、悲しみなんです。非情って、情に非ずです。宮沢賢治のことではないですけれども、最近アメリカで講演した時に、人生のいちばん根本にあるのはインパーソナル・ソロー(非個人的な悲しみ)という言い方をしたんです。個人的な感情を越えている。宮沢賢治は、非情な悲しみを言ってるんだけど、ちょっと浅く取ってしまった人は、センチメンタルなほうに行ってしまうし、そうでない人は、わからないという感じ。たとえば『銀河鉄道の夜』の中でもね、悲しいとかさびしいという言葉が多いです。それらは僕に言わせると、非常の悲しみが多い。それはまったくセンチメンタルとは違う。ちょっと飛躍気味ではありますが、ここで河合隼雄がいっている「非情な悲しみ」ということは、そのまま土井浩二のいう「せつなさ」に通じるところがあると思います。『銀河鉄道の夜』を読んだことがある人であれば、『銀河鉄道の夜』に感動したことがある人であれば、河合隼雄のいう「非情な悲しみ」の意味と、保坂和志のいう「せつなさ」の意味がわかってもらえるのではないでしょうか。
なんだか思いつくままに書いていったら止まらなくなってしまいました。しかも書いてあることも自分でもよくわからなくなってしまいました。
そういうわけで、ぼくは『黄色い本』に収められている『マヨネーズ』という作品の主人公であるたきちゃんのような女性が、とても好きです。