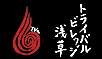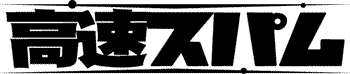02年07月01日(月)
「彼女を見ればわかること」を観ました。
五人の女性のストーリーがオムニバス風に描かれているこの映画の監督は、ガルシア・マルケスの息子さんであるロドリゴ・ガルシアです。
一番最初のグレン・クローズのストーリーから始まって、五人のストーリー全部がすべて素晴らしかった。
愛とか出会いとか別れとか、そのような感情に訴えかけるような感動ではなくて、作品の素晴らしさとラストの素晴らしさに感動して泣いてしまいました。「アイ・アム・サム」と同じぐらい泣いた。全然泣くような映画ではないのですけど。女じゃなくてもわかるのよ、こういう映画。
ところで、日本では、この映画のちらしに、フランチェスコ・クレメンテが書いた彼の奥さんの絵の一部が使われていました。
全体図は、下のリンクで観ることが出来ます。
■Francesco Clemente, Alba
この絵、すごく素敵ではないですか?欲情するでしょう。
米国の公式サイトや映画関係のページを見たかぎりでは、向こうでは使われていなかったみたいですね。映画のイメージにもぴったりだと思うのですけど。
クレメンテの作品は、映画「大いなる遺産」においても、主人公である画家のフィンが描く絵画として、ふんだんに使われています。
映画のなんとも言えない雰囲気の中で、クレメンテの絵が絶妙の効果をもたらしています。
この映画も大好き。グウィネス・パルトロウが美しすぎて、もう大変なの。
五人の女性のストーリーがオムニバス風に描かれているこの映画の監督は、ガルシア・マルケスの息子さんであるロドリゴ・ガルシアです。
一番最初のグレン・クローズのストーリーから始まって、五人のストーリー全部がすべて素晴らしかった。
愛とか出会いとか別れとか、そのような感情に訴えかけるような感動ではなくて、作品の素晴らしさとラストの素晴らしさに感動して泣いてしまいました。「アイ・アム・サム」と同じぐらい泣いた。全然泣くような映画ではないのですけど。女じゃなくてもわかるのよ、こういう映画。
ところで、日本では、この映画のちらしに、フランチェスコ・クレメンテが書いた彼の奥さんの絵の一部が使われていました。
全体図は、下のリンクで観ることが出来ます。
■Francesco Clemente, Alba
この絵、すごく素敵ではないですか?欲情するでしょう。
米国の公式サイトや映画関係のページを見たかぎりでは、向こうでは使われていなかったみたいですね。映画のイメージにもぴったりだと思うのですけど。
クレメンテの作品は、映画「大いなる遺産」においても、主人公である画家のフィンが描く絵画として、ふんだんに使われています。
映画のなんとも言えない雰囲気の中で、クレメンテの絵が絶妙の効果をもたらしています。
この映画も大好き。グウィネス・パルトロウが美しすぎて、もう大変なの。
02年07月02日(火)
古本屋で「太陽」の南方熊楠特集を購入。
帰宅して、さあ読もうとページを開いたところ、中に新聞の切り抜きがたくさん挟まっていました。
切り抜きは、主に粘菌に関するもので、粘菌に知性があるかもしれないという記事や、鉱物を五万点集めた、ある料亭のおやじさんの記事などなど。各切り抜きには、赤ペンで日にちと新聞名が書き込まれていました。普段であれば、気にも止めない記事ではありますが、ひとつひとつを丹念に読み込んでしまいました。
古本をよく買う人であれば知っていると思いますが、古本を買うと、このように特別な「おまけ」が付いてくることがあります。お菓子のカスとか、ページの一部が切り抜かれているとか、迷惑なおまけがついてくることもありますが、押し花で作られた栞や、書きかけのメモなど、以前の持ち主の性格を仄めかすような、そのようなおまけが付いてくると、なんとなく嬉しくなってしまいます。
物ではなくては単なる書き込みのおまけが付いてくることもあります。
深田久弥の「日本百名山」を買ったときには、「登山済みの山 ○」と、「これから登る山 △」と書いてあって、各ページに印が付いていました。江藤淳の「漱石の時代」の一番最後のページには「まあまあ。引用多し。」と赤ペンで書いてあっておもわず笑ってしまったし、梅原猛の「仏像 心とかたち」の各章の最期には、細かい疑問点や感想が書かれていて、なるほどこんなことを考えるのかと、感心してしまいました。
遠藤周作の「幻の女」という短編は、古本屋で買った「長い雨」という翻訳小説の裏表紙に書かれていた、前の持ち主の名前と住所、そしてある箇所に引かれた線がもとになって、主人公が前の持ち主である菅原綾子に対して殺人の疑惑を抱き、独自に調査を行なうという物語です。
お気に入りの遠藤周作の作品はいくつもあるのですが、そのなかでもこの「幻の女」が忘れられないのは、そのような古本の「おまけ」に対して、個人的な思い入れがあるからなのかもしれません。
帰宅して、さあ読もうとページを開いたところ、中に新聞の切り抜きがたくさん挟まっていました。
切り抜きは、主に粘菌に関するもので、粘菌に知性があるかもしれないという記事や、鉱物を五万点集めた、ある料亭のおやじさんの記事などなど。各切り抜きには、赤ペンで日にちと新聞名が書き込まれていました。普段であれば、気にも止めない記事ではありますが、ひとつひとつを丹念に読み込んでしまいました。
古本をよく買う人であれば知っていると思いますが、古本を買うと、このように特別な「おまけ」が付いてくることがあります。お菓子のカスとか、ページの一部が切り抜かれているとか、迷惑なおまけがついてくることもありますが、押し花で作られた栞や、書きかけのメモなど、以前の持ち主の性格を仄めかすような、そのようなおまけが付いてくると、なんとなく嬉しくなってしまいます。
物ではなくては単なる書き込みのおまけが付いてくることもあります。
深田久弥の「日本百名山」を買ったときには、「登山済みの山 ○」と、「これから登る山 △」と書いてあって、各ページに印が付いていました。江藤淳の「漱石の時代」の一番最後のページには「まあまあ。引用多し。」と赤ペンで書いてあっておもわず笑ってしまったし、梅原猛の「仏像 心とかたち」の各章の最期には、細かい疑問点や感想が書かれていて、なるほどこんなことを考えるのかと、感心してしまいました。
遠藤周作の「幻の女」という短編は、古本屋で買った「長い雨」という翻訳小説の裏表紙に書かれていた、前の持ち主の名前と住所、そしてある箇所に引かれた線がもとになって、主人公が前の持ち主である菅原綾子に対して殺人の疑惑を抱き、独自に調査を行なうという物語です。
お気に入りの遠藤周作の作品はいくつもあるのですが、そのなかでもこの「幻の女」が忘れられないのは、そのような古本の「おまけ」に対して、個人的な思い入れがあるからなのかもしれません。
02年07月03日(水)
CNNの「こぼれ話」より。
■山中でこのまま凍死か…そのとき、携帯電話が鳴った
衛星かしら。
■イタリア副議長、レイプ魔の「去勢」提唱——はさみで
カルデロリ副議長曰く「かつて、化学的な手段での去勢を提唱した人がいたが、個人的にはもっと簡単に切り落としてしまうほうが良いと考える。例えば、消毒していないようなはさみで。」
カルデロリ、いいこというじゃあん。
■湖畔で堂々の「愛の交歓」、新聞で謝罪する羽目に
石神井公園でも、夜になるとファックしているカップルなどがいますが。
この記事の見出しよりも、本文中の「この判決を下した裁判官は、『創造的な裁断』を打ち出すことで地元では有名だという。」という一文のほうが気になる。
■山中でこのまま凍死か…そのとき、携帯電話が鳴った
南米アンデス山脈山中で遭難した登山家が、助けを呼ぼうと携帯電話を取り出した。しかし、プリペイド式の電話には度数が残っておらず、どこにも電話がかけられない。このまま凍死か──と思ったところで呼び出し音が鳴り、登山家は一命を取り留めた。電話を鳴らしたのは、携帯電話会社のオペレーターで、プリペイドの度数追加を促すためだった携帯電話というものは、アンデスの山の中でも通じるのね。
衛星かしら。
ディアスさんは「あなたは天使だ。私は雪山で遭難している」と答えた。ベルサウスは米国の会社だが、南米でも営業展開している。電話を切られたディアスさん、その時の様子を想像すると、不謹慎ながら笑ってしまいます。
この答えに、冗談を言ってると考えたマリアさんは一度電話を切ってしまった。
■イタリア副議長、レイプ魔の「去勢」提唱——はさみで
カルデロリ副議長曰く「かつて、化学的な手段での去勢を提唱した人がいたが、個人的にはもっと簡単に切り落としてしまうほうが良いと考える。例えば、消毒していないようなはさみで。」
カルデロリ、いいこというじゃあん。
■湖畔で堂々の「愛の交歓」、新聞で謝罪する羽目に
石神井公園でも、夜になるとファックしているカップルなどがいますが。
この記事の見出しよりも、本文中の「この判決を下した裁判官は、『創造的な裁断』を打ち出すことで地元では有名だという。」という一文のほうが気になる。
02年07月04日(木)
映画「ロード・オブ・ザ・リング」の次回作の予告編が公開されたので、そろそろ公式サイトにもなにか情報が掲載されているかと思い見てみると、「『ロード・オブ・ザ・リング』字幕翻訳に関する発表」なるものが、発表されていました。
その中でこんな一文が
■「超」整理日記 2002/06/08 ネット上の字幕改善運動
■字幕改善運動
■(ザ・)ロード・オブ・ザ・リング(ズ)日本ヘラルド株式会社に物申す!!
■映画「the Lord of the Rings」脳内字幕構想の拠点
簡単に言うと、「ロード・オブ・ザ・リング」の戸田奈津子さんの日本語字幕は、物語の内容を湾曲するものであるから改善して欲しい、というのが上記のサイト群の趣旨です。
上記のサイトを一通り見れば、映画「ロード・オブ・ザ・リング」における字幕と台詞の相違、誤訳の物語への影響等がよくわかります。
翻訳から誤訳をなくすということのは、奥村君のおちんちんを小さくするようなもので、ほとんど不可能なことだとは思いますが、「ロード・オブ・ザ・リング」の訳に関して言えば、そのような次元の問題ではないようです。
僕は原作も読んでいないし、台詞を聞き取れるほど英語力もないので、この問題に関してこれ以上のことを言うことは出来ません。
けれども、映画にしても小説にしても漫画にしても、物語を愛し、原作の内容を十分に理解している人(解釈は別としても)に翻訳をして欲しいものです。その被害を被るのはぼくたちなのですから。
とにかく、戸田奈津子さんには、よい翻訳をしてがんばって頂きたいものです。
その中でこんな一文が
第一部のビデオ(VHS、DVDなど)の日本語字幕スーパー版は、戸田奈津子氏の原稿を使用しておりますが、劇場とは違い、文字数の制限が多少緩和されるため、上記の原稿にビデオ版としての手直しを施しております。なんでこんなことをいちいち報告するのかしら、と思ってちょっと調べてみたら、以下のようなサイトを発見しました。
■「超」整理日記 2002/06/08 ネット上の字幕改善運動
■字幕改善運動
■(ザ・)ロード・オブ・ザ・リング(ズ)日本ヘラルド株式会社に物申す!!
■映画「the Lord of the Rings」脳内字幕構想の拠点
簡単に言うと、「ロード・オブ・ザ・リング」の戸田奈津子さんの日本語字幕は、物語の内容を湾曲するものであるから改善して欲しい、というのが上記のサイト群の趣旨です。
上記のサイトを一通り見れば、映画「ロード・オブ・ザ・リング」における字幕と台詞の相違、誤訳の物語への影響等がよくわかります。
翻訳から誤訳をなくすということのは、奥村君のおちんちんを小さくするようなもので、ほとんど不可能なことだとは思いますが、「ロード・オブ・ザ・リング」の訳に関して言えば、そのような次元の問題ではないようです。
僕は原作も読んでいないし、台詞を聞き取れるほど英語力もないので、この問題に関してこれ以上のことを言うことは出来ません。
けれども、映画にしても小説にしても漫画にしても、物語を愛し、原作の内容を十分に理解している人(解釈は別としても)に翻訳をして欲しいものです。その被害を被るのはぼくたちなのですから。
手直し作業には、原作「指輪物語」の共訳者の一人であられる田中明子氏(ご参考までに、もう一人の共訳者であられる瀬田貞二氏は既に亡くなられております)と、版元である評論社の方々に、ご協力を頂いております。って、最初から原作の翻訳者に協力してもらいなさいよ、と突っ込みたくなります。
とにかく、戸田奈津子さんには、よい翻訳をしてがんばって頂きたいものです。
02年07月05日(金)
■マガジンハウス、「雑誌」のようなデザインを採用したWebマガジンを創刊
雑誌「Mutts」がデジタル・ペーパーになったそうです。
ここまで完全に、というか強引に、雑誌をそのままWebにしたのは初めてなのではないでしょうか。PDFも使わずに。
といいますか、雑誌をそのままWebにしても、ちょっと・・。
今後を見守りたいと思います。偉そうでごめんなさい。
今のところtrial issueの文字が見えるのですが、将来的には課金の方向に進むのかしら。
雑誌「Mutts」がデジタル・ペーパーになったそうです。
ここまで完全に、というか強引に、雑誌をそのままWebにしたのは初めてなのではないでしょうか。PDFも使わずに。
といいますか、雑誌をそのままWebにしても、ちょっと・・。
今後を見守りたいと思います。偉そうでごめんなさい。
今のところtrial issueの文字が見えるのですが、将来的には課金の方向に進むのかしら。
02年07月06日(土)
■Worst Case Scenarioes:Online
を眺めて休日を過ごす。
このサイト、「The Worst-Case Scenario Survival Handbook」という一連のシリーズ物のオンライン版で、ワニと戦う方法とか、海に沈んでいく車から脱出する方法とか、飛行機を着陸させる方法など、本の一部が公開されています。
なにが起こるかわからない世の中、このようなサイトや本を読んで、生きる術を身につけましょう。日本人は平和ぼけし過ぎておりますのよ、本当に。
個人的には、熊に襲われた時の対処の方法を知りたい。あと、たまに森とかで迷ってしまうので、森で迷ったときに抜け出す方法も知りたい。あと、賞味期限が切れた牛乳を飲んでも腹痛を起こさない方法とか。結構重要よ、これ。あと、気になる人からメールが来なくなったときの対処方法。落ち込まない方法とか。
ところで、このシリーズの中には「Dating and Sex」などもあり、Amazonの紹介文では「危ないヤツやストーカーをふりきり、結婚サギ師やナンパ男をかきわけて、素敵な恋人とおつきあいするために。恋愛もまたサバイバルなのである!」などと書かれております。
これは是非とも読んで有事に備えなくては。
他には「Holiday」「Golf」などなど。今後は一体どんなものでてくるのでしょう。
ちなみに、シリーズの最初の一冊は、日本語版も出版されているようです。
■この方法で生きのびろ!
「この方法で生きのびろ!」って、普通に生きていたらなかなか言われない言葉でしょう。
こんな言葉を言われたら惚れちまうね。
を眺めて休日を過ごす。
このサイト、「The Worst-Case Scenario Survival Handbook」という一連のシリーズ物のオンライン版で、ワニと戦う方法とか、海に沈んでいく車から脱出する方法とか、飛行機を着陸させる方法など、本の一部が公開されています。
なにが起こるかわからない世の中、このようなサイトや本を読んで、生きる術を身につけましょう。日本人は平和ぼけし過ぎておりますのよ、本当に。
個人的には、熊に襲われた時の対処の方法を知りたい。あと、たまに森とかで迷ってしまうので、森で迷ったときに抜け出す方法も知りたい。あと、賞味期限が切れた牛乳を飲んでも腹痛を起こさない方法とか。結構重要よ、これ。あと、気になる人からメールが来なくなったときの対処方法。落ち込まない方法とか。
ところで、このシリーズの中には「Dating and Sex」などもあり、Amazonの紹介文では「危ないヤツやストーカーをふりきり、結婚サギ師やナンパ男をかきわけて、素敵な恋人とおつきあいするために。恋愛もまたサバイバルなのである!」などと書かれております。
これは是非とも読んで有事に備えなくては。
他には「Holiday」「Golf」などなど。今後は一体どんなものでてくるのでしょう。
ちなみに、シリーズの最初の一冊は、日本語版も出版されているようです。
■この方法で生きのびろ!
「この方法で生きのびろ!」って、普通に生きていたらなかなか言われない言葉でしょう。
こんな言葉を言われたら惚れちまうね。
02年07月07日(日)
02年07月08日(月)
今月号のユリイカは「高野文子」特集です。
新刊である「黄色い本」をまだ読んでいなかったので、ユリイカと一緒に購入、帰りにコーヒーを飲ませてくれるお店に立ち寄って、一気に読んだのですが、期待を裏切らずにかなり面白いい。
『黄色い本』は、「チボー家の人々」に魅せられた女子高生実ッコが、現実と小説の世界の混在した日々を送る姿を描いた作品です。
ひとコマひとコマに、温かさが溢れていて、読んでいてなんだかほわわんとしてしまいます。
図書館で借りた『チボー家の人々』にはまっている実ッコちゃんをみて、おやじさんが言う「実ッコ、その本買うか?」という台詞にまたじんわりとしてしまいます。
『棒がいっぽん』という単行本に収められている「美しい町」という作品は、昭和中期のある平凡な夫婦の日常の物語です。物語の最期のシーンで、徹夜でがり版を切り、印刷をした夫婦が、部屋のインクの臭いを消すためにドアを開けます。
三十年経ったあとで、ふと思い出すのはこんな日なのかもしれない。二人とも、同じことを考えているのに、二人とも、そのことを知らない。三十年後に、ふたりが同時に今日のことを思い出したとしても、お互いが同じことを思い出していることも知らないでしょう。でもそれが素敵ね。
同じ単行本に収められている『奥村さんのお茄子』は、高野文子の作品の中でも特に人気のある作品のひとつで、突然現れた宇宙人の遠久田さんに、「一九六八年六月六日木曜日、お昼何めしあがりました?」と詰問される奥村さんの物語です。
物語は、全般を通して記憶の再生をテーマとして進行します。遠久田さんは、先輩の無実の罪をはらすために、奥村さんの一九六八年六月六日(二十数年前)のお昼ごはんが茄子であったことを証明しようと、奥村さんに当時の記憶を取り戻してもらおうと懸命になります。
けれども、そんなことはもちろん不可能です。二十数年前のある日のお昼ご飯なんて、普通思い出すことは出来ません。
遠久田さんは言います。
当たり前のことではありますが、今この瞬間にも、同じ時間に異なる人々が、異なる行為をして、異なることを考えています。そのあたりまえのことが、『奥村さんのお茄子』ではとてもあたりまえに描かれています。
保坂和志は、「私が遠く離れた誰かのことを考えているとき、相手のその人は『私が今考えている』ということを、まったくわからないのだろうか、それともわかる可能性があるのだろうか」というモチーフのもとに『コーリング』『残響』という作品を書いています。。
『コーリング』は、美緒と浩二と恵子という三人の人物が、同じ時間に異なる場所でそれぞれが考えていることを、保坂和志の表現を借りれば、テレビのチャンネルを回すようにガチャ、ガチャ、ガチャと切り替わって描かれていきます。
保坂和志は、自らのホームページ内で、『コーリング』について以下のように語っています。
ところで、『コーリング』の中で土井浩二は「せつなさ」について次のように言っています。
河合隼雄は、『ブッダの夢』という対談集の中で、次のようなことを言っています。
なんだか思いつくままに書いていったら止まらなくなってしまいました。しかも書いてあることも自分でもよくわからなくなってしまいました。
そういうわけで、ぼくは『黄色い本』に収められている『マヨネーズ』という作品の主人公であるたきちゃんのような女性が、とても好きです。
新刊である「黄色い本」をまだ読んでいなかったので、ユリイカと一緒に購入、帰りにコーヒーを飲ませてくれるお店に立ち寄って、一気に読んだのですが、期待を裏切らずにかなり面白いい。
『黄色い本』は、「チボー家の人々」に魅せられた女子高生実ッコが、現実と小説の世界の混在した日々を送る姿を描いた作品です。
ひとコマひとコマに、温かさが溢れていて、読んでいてなんだかほわわんとしてしまいます。
図書館で借りた『チボー家の人々』にはまっている実ッコちゃんをみて、おやじさんが言う「実ッコ、その本買うか?」という台詞にまたじんわりとしてしまいます。
『棒がいっぽん』という単行本に収められている「美しい町」という作品は、昭和中期のある平凡な夫婦の日常の物語です。物語の最期のシーンで、徹夜でがり版を切り、印刷をした夫婦が、部屋のインクの臭いを消すためにドアを開けます。
「工場が見えました」(これは、言葉で書くと感動が全然伝わらないと思いますが、作品の中ではナレーションとして、間(ま)と、セリフと、絵柄が絶妙に描かれています。)
「耳をすますとモーターの音が聞こえてきます。」
「さっきなにかのブザーの音も鳴りました。」
「たとえば三十年たったあとで」
「今の、こうしたことを思いだしたりするのかしら」
「子供がいて、おとなになって、またふたりになって」
「思いだしたりするのかしら」
「ノブオさんは、そんなふうなことを思っていました」
「サナエさんも、そんなふうなことを思っていました」
「この町で」
三十年経ったあとで、ふと思い出すのはこんな日なのかもしれない。二人とも、同じことを考えているのに、二人とも、そのことを知らない。三十年後に、ふたりが同時に今日のことを思い出したとしても、お互いが同じことを思い出していることも知らないでしょう。でもそれが素敵ね。
同じ単行本に収められている『奥村さんのお茄子』は、高野文子の作品の中でも特に人気のある作品のひとつで、突然現れた宇宙人の遠久田さんに、「一九六八年六月六日木曜日、お昼何めしあがりました?」と詰問される奥村さんの物語です。
物語は、全般を通して記憶の再生をテーマとして進行します。遠久田さんは、先輩の無実の罪をはらすために、奥村さんの一九六八年六月六日(二十数年前)のお昼ごはんが茄子であったことを証明しようと、奥村さんに当時の記憶を取り戻してもらおうと懸命になります。
けれども、そんなことはもちろん不可能です。二十数年前のある日のお昼ご飯なんて、普通思い出すことは出来ません。
遠久田さんは言います。
「楽しくてうれしくて、ごはんなんかいらないよって時も、楽しくてせつなくてなんにも食べたくないよって時も、どっちも6月6日の続きなんですものね」『奥村さんのお茄子』の最後の数ページは、「三秒間、自分以外のだれかを見て、その誰かについて考える。」という現象が描かれています。誰かが誰かを見て、その誰かについて考える。見られている誰かは、他の誰かを見て、その誰かについて考える・・。
当たり前のことではありますが、今この瞬間にも、同じ時間に異なる人々が、異なる行為をして、異なることを考えています。そのあたりまえのことが、『奥村さんのお茄子』ではとてもあたりまえに描かれています。
保坂和志は、「私が遠く離れた誰かのことを考えているとき、相手のその人は『私が今考えている』ということを、まったくわからないのだろうか、それともわかる可能性があるのだろうか」というモチーフのもとに『コーリング』『残響』という作品を書いています。。
『コーリング』は、美緒と浩二と恵子という三人の人物が、同じ時間に異なる場所でそれぞれが考えていることを、保坂和志の表現を借りれば、テレビのチャンネルを回すようにガチャ、ガチャ、ガチャと切り替わって描かれていきます。
土井浩二が三年前にわかれた美緒の夢の途中で目が覚めた朝、美緒はもちろん浩二の夢など見ていなかったし思い出しもしていなかった。ぼくは『コーリング』のこの書き出しが大好きで、何度読んでも素晴らしいなあと思うのですが、この書きだしのような表現は、このあとも何度も出てきて、『コーリング』の登場人物は、誰かが誰かのことを思ったり、あるいは別のきっかけによって、どんどんと切り替わっていきます。
保坂和志は、自らのホームページ内で、『コーリング』について以下のように語っています。
このガチャンガチャンの軋みも含めて、『コーリング』の繋がっていき方は素晴らしく、文句がないと思う。が、しかし、それが文句がない理由は、本当のところ手法によるものではない(『コーリング』や『残響』のような小説を書くと手法のことばかり言われて本当に嫌になる)。全体を貫く「せつなさ」のようなものだ。あるいは、それぞれの人間が別の環境にいてもかつての環境を基準にして今いる環境を測定しているような、心の態勢(?)のようなものだ。高野文子の漫画にしても、保坂和志の小説にしても、どうしてこんなに好きなのか自分でも不思議なのですけれど、その理由のひとつには、彼らの作品が「記憶」と「時間」と「意識」という現象の素晴らしさや悲しみを描き、「記憶」というものが余韻であるということを描き、死とか、別れとか、思い出とか、そのような悲しい出来事をともなう書き方ではなくて、単なる「記憶」と「時間」と「意識」についてだけ書いてある作品だから、ということがあると思います。
(創作ノート『コーリング』&『残響』 より引用)
ところで、『コーリング』の中で土井浩二は「せつなさ」について次のように言っています。
十代のせつなさやさびしさは、原因らしい原因も持たないし対象もない。だから他人はつまらないと一蹴するが、原因も対象もないからこそ逆に解消されようもない。せつなさやさびしさは、それを抱えている当人にはとてもやっかいなものなんだ。保坂和志の小説のすばらしいところは、このように感動的な発見をさらりと書いてしまうところで、例えば、失恋をしてせつなければ失恋から立ち直ればせつなさも感じなくなるし、友人とけんかをしてさびしければ、友人と仲直りをすればさびしくなくなる。問題は、原因や対象を持たないせつなさやさびしさで、原因を持たない以上、そのせつなさは解消のしようもない(土井浩二は「十代のせつなさ」と限定しているけれど、それは限定する必要はないと思います)。そして、土井浩二のいう「せつなさ」を、『コーリング』『残響』という両作品の登場人物の中で一番強く感じているのは、おそらく『残響』の堀井早夜香で、ぼくは堀井早夜香の独白を読んでいると、それだけで感動してしまいます。
河合隼雄は、『ブッダの夢』という対談集の中で、次のようなことを言っています。
最近、宮沢賢治についてちょっと書かされた時に、「非情な悲しみ」と書いたんです。情ではない。で、悲しみなんです。非情って、情に非ずです。宮沢賢治のことではないですけれども、最近アメリカで講演した時に、人生のいちばん根本にあるのはインパーソナル・ソロー(非個人的な悲しみ)という言い方をしたんです。個人的な感情を越えている。宮沢賢治は、非情な悲しみを言ってるんだけど、ちょっと浅く取ってしまった人は、センチメンタルなほうに行ってしまうし、そうでない人は、わからないという感じ。たとえば『銀河鉄道の夜』の中でもね、悲しいとかさびしいという言葉が多いです。それらは僕に言わせると、非常の悲しみが多い。それはまったくセンチメンタルとは違う。ちょっと飛躍気味ではありますが、ここで河合隼雄がいっている「非情な悲しみ」ということは、そのまま土井浩二のいう「せつなさ」に通じるところがあると思います。『銀河鉄道の夜』を読んだことがある人であれば、『銀河鉄道の夜』に感動したことがある人であれば、河合隼雄のいう「非情な悲しみ」の意味と、保坂和志のいう「せつなさ」の意味がわかってもらえるのではないでしょうか。
なんだか思いつくままに書いていったら止まらなくなってしまいました。しかも書いてあることも自分でもよくわからなくなってしまいました。
そういうわけで、ぼくは『黄色い本』に収められている『マヨネーズ』という作品の主人公であるたきちゃんのような女性が、とても好きです。
02年07月09日(火)
たまには少し時間をかけて家に帰ろうと思い、西武新宿線の上石神井駅で降りて、石神井川に沿って家まで歩きました。
ぼくの家は西武池袋線の石神井公園駅付近なので、上石神井からだと結構歩くことになるのです。
上石神井からの石神井公園に続く石神井川は、人通りの少ない裏通りを流れているので、心静かに散歩ができます。
カルガモが泳いでいたり、コイが泳いでいたり、鳩がたむろっていたりするぐらいで、何もないのが歩いていてとても楽しい。
この川はどこまで続くのだろう。このまま川に沿って、永遠に歩き続けてしまいそうです。
あんなことを考えたり、こんなことを考えたり。
噂によると、武蔵野側の源流は、東小金井公園の近くにある、とても源流とは思えないような、ちょろちょろとした湧き水だそうです。
今度、時間があるときにでも、見に行ってこよう。
ぼくの家は西武池袋線の石神井公園駅付近なので、上石神井からだと結構歩くことになるのです。
上石神井からの石神井公園に続く石神井川は、人通りの少ない裏通りを流れているので、心静かに散歩ができます。
カルガモが泳いでいたり、コイが泳いでいたり、鳩がたむろっていたりするぐらいで、何もないのが歩いていてとても楽しい。
この川はどこまで続くのだろう。このまま川に沿って、永遠に歩き続けてしまいそうです。
あんなことを考えたり、こんなことを考えたり。
噂によると、武蔵野側の源流は、東小金井公園の近くにある、とても源流とは思えないような、ちょろちょろとした湧き水だそうです。
今度、時間があるときにでも、見に行ってこよう。
02年07月10日(水)
■JRバス運転手、合計1リットルの酎ハイ飲んでいた
このような記事を読むと、とても不謹慎だとは思うのですが、本当に、このバスに乗っていた方々の恐怖とか、接触された乗用車に乗っていた方のこととかを考えると、とてもとても不謹慎だとは思うのですが、どうにもぼくという人間のいい加減さというか、責任感のなさというか、まあ、幸いなことに亡くなった方もいないので、こういう事を考えてしまうことを許して欲しいのですが、それは結果論だろうと言われるとそれまでですが、考えてしまうものは仕方がないと、ぼくという人間の未熟さゆえの発言であるということを前提に聞いて欲しいのですが、この記事を読んで、
運転手さん、やるじゃん
などと思ってしまいました。だって、お酒を一リットル飲んでバスの運転って、よほど反骨精神かユーモアの精神がないと出来ないことですよ。なにか反抗したかったんじゃないの、この運転手さん。腐敗した政治とかに。
同様に、下の記事に関しても
■世界に恥さらした「日本のバカップル」
このグローバル社会の時代に日本人の平和ぼけを世界に露呈したとか、撃たれて痛い目を見ればよかったのにとか、日本国内でも非難轟々だったし、世界中のマスコミからも叩かれていたし、たしかにまあ生きるか死ぬかの毎日を送っている向こうの国の人たちからしたらとても迷惑な二人であることは間違いないのですが、それでもやはりね、どうにも思ってしまうのですが、こういうことを考えてしまうのはとても問題だと思うし、本当にぼくはどうしてこんなに何も考えていないのか我ながら悲しくなりますが、ついつい思ってしまうのは
君たち、本当に素敵だよ
ということでして、わかっているのですよ、世間は厳しいし、彼らのしたことがどれだけ大変なことかは。でも、ガイドブックに夢中でまわりの状況が判断できないって、よほど二人の旅行が素敵だったのでしょう。じゃなければ、気づくって、普通。あるいは何かに対する反抗でしょう。無気力な現代社会とかに一石投じたかったのではないでしょうか。
ときどきいるでしょう、良い意味で、よく今まで生きてこれたな、という人。そういう人の話を聞くと、不謹慎であるということは重々承知しながらも、すごく素敵に見えてしまうのです。
例えば
■旧石器発掘ねつ造問題
この人なんか、「石器なんか、埋めればいいじゃん!」とか思って生きてきたわけでしょう。すごいことですよ、これ。石器を埋め続けて理事長になってしまったのですから。これは嫌みとかではなくて、本当に尊敬をしてしまいます。心の底から
あんたのように生きたかった
とか思ってしまいますよ。
なんども言いますが、この方のしたことによって、大変多くの方々が被害を被り、大変な思いをしたということは承知しているし、本当に、二度とおこってはいけないことだとも思いますけど、でもやっぱりすごいよ。歴史というものは、結局のところ学者たちによって認定された真実でしかないのよってことを世界中に分からせてくれたし。
シド・ビシャスなんかよりも、藤村さんのほうを映画化をして欲しい。エンディングで「マイ・ウェイ」を歌って欲しい。記者会見の時の前かがみの姿勢で。
このような記事を読むと、とても不謹慎だとは思うのですが、本当に、このバスに乗っていた方々の恐怖とか、接触された乗用車に乗っていた方のこととかを考えると、とてもとても不謹慎だとは思うのですが、どうにもぼくという人間のいい加減さというか、責任感のなさというか、まあ、幸いなことに亡くなった方もいないので、こういう事を考えてしまうことを許して欲しいのですが、それは結果論だろうと言われるとそれまでですが、考えてしまうものは仕方がないと、ぼくという人間の未熟さゆえの発言であるということを前提に聞いて欲しいのですが、この記事を読んで、
運転手さん、やるじゃん
などと思ってしまいました。だって、お酒を一リットル飲んでバスの運転って、よほど反骨精神かユーモアの精神がないと出来ないことですよ。なにか反抗したかったんじゃないの、この運転手さん。腐敗した政治とかに。
同様に、下の記事に関しても
■世界に恥さらした「日本のバカップル」
このグローバル社会の時代に日本人の平和ぼけを世界に露呈したとか、撃たれて痛い目を見ればよかったのにとか、日本国内でも非難轟々だったし、世界中のマスコミからも叩かれていたし、たしかにまあ生きるか死ぬかの毎日を送っている向こうの国の人たちからしたらとても迷惑な二人であることは間違いないのですが、それでもやはりね、どうにも思ってしまうのですが、こういうことを考えてしまうのはとても問題だと思うし、本当にぼくはどうしてこんなに何も考えていないのか我ながら悲しくなりますが、ついつい思ってしまうのは
君たち、本当に素敵だよ
ということでして、わかっているのですよ、世間は厳しいし、彼らのしたことがどれだけ大変なことかは。でも、ガイドブックに夢中でまわりの状況が判断できないって、よほど二人の旅行が素敵だったのでしょう。じゃなければ、気づくって、普通。あるいは何かに対する反抗でしょう。無気力な現代社会とかに一石投じたかったのではないでしょうか。
ときどきいるでしょう、良い意味で、よく今まで生きてこれたな、という人。そういう人の話を聞くと、不謹慎であるということは重々承知しながらも、すごく素敵に見えてしまうのです。
例えば
■旧石器発掘ねつ造問題
この人なんか、「石器なんか、埋めればいいじゃん!」とか思って生きてきたわけでしょう。すごいことですよ、これ。石器を埋め続けて理事長になってしまったのですから。これは嫌みとかではなくて、本当に尊敬をしてしまいます。心の底から
あんたのように生きたかった
とか思ってしまいますよ。
なんども言いますが、この方のしたことによって、大変多くの方々が被害を被り、大変な思いをしたということは承知しているし、本当に、二度とおこってはいけないことだとも思いますけど、でもやっぱりすごいよ。歴史というものは、結局のところ学者たちによって認定された真実でしかないのよってことを世界中に分からせてくれたし。
シド・ビシャスなんかよりも、藤村さんのほうを映画化をして欲しい。エンディングで「マイ・ウェイ」を歌って欲しい。記者会見の時の前かがみの姿勢で。
02年07月11日(木)
HotWired Japanで、暗号ソフトウェアPGPの開発者であるフィル・ジマーマンのインタビューが公開されています。
■フィル・ジマーマン <暗号ソフトウェアPGP開発者> インタビュー──われわれはプライバシーを捨てるべきではない
僕も含めて、一般にインターネットを使っている人で暗号化を意識している人は少ないのではないでしょうか。
いきなり暗号とか、プライバシーとか言われてもいまいちピンとこないでしょう。
ゴルゴ13に『最終暗号』という章があります。誰にも解読することのできない最終暗号を開発したために、アメリカのNSA(国家安全保障局)に命を狙われることになった数学者である佐久シゲルを、ゴルゴ13が援護して最終暗号を開発させる、というお話なのですが、このお話しが結構おそろしい話でして。
物語の中で、NSAはアメリカ国家の安全を保つために、世界中のあらゆる情報を盗聴、調査します。事件は未然に防がれるものの、そこには個人のプライバシーという考え方は微塵もありません。その情況に不安を抱いた佐久は、最終暗号を開発、公開しようとしますが、そのことを知ったアメリカ政府は、アメリカ大統領を通して日本政府に警告を与えます。慌てた日本政府は佐久を呼び出しますが、佐久は彼らに対して以下のように説明します。
■これが佐久暗号だ!
これは漫画の中の話ではありますが、あながち作り話というわけでもなくて、上記のジマーマンのインタビューや、(ぼくはまだ読んでいませんが)サイモン・シンの『暗号解読—ロゼッタストーンから量子暗号まで」なんかを読むと、このあたりの事がとてもよくわかるのではないでしょうか。
『暗号解読』に関しては、浅田彰さんが「暗号の世界を解読する』という書評を書いています(ジマーマンに関してもちょこっとだけ触れています)。
訳は亀井よし子さん。この方は、最近は「ブリジット・ジョーンズの日記」で有名ですけれど、ぼくの中ではアン・ビーティーの翻訳家というイメージがいまだに強い。
暗号に対する規制の是非に関しては、とてもデリケートな問題ですし、知識の無いぼくにはなにも言及することはできません。しかし、今後インターネットやパソコンはどんどん家電化するだろうし、それを使う人たちはパソコンに関しての知識がなくても使えようになるでしょう。そうなったときに、それを使う各個人のプライバシーが全部盗聴されているかもしれないという危険性に関しては、心に留めておく必要があるかもしれません。
ある意味、みんなサトラレみたいになっちゃうかもね。それはそれで楽しいのかな。
■フィル・ジマーマン <暗号ソフトウェアPGP開発者> インタビュー──われわれはプライバシーを捨てるべきではない
僕も含めて、一般にインターネットを使っている人で暗号化を意識している人は少ないのではないでしょうか。
いきなり暗号とか、プライバシーとか言われてもいまいちピンとこないでしょう。
ゴルゴ13に『最終暗号』という章があります。誰にも解読することのできない最終暗号を開発したために、アメリカのNSA(国家安全保障局)に命を狙われることになった数学者である佐久シゲルを、ゴルゴ13が援護して最終暗号を開発させる、というお話なのですが、このお話しが結構おそろしい話でして。
物語の中で、NSAはアメリカ国家の安全を保つために、世界中のあらゆる情報を盗聴、調査します。事件は未然に防がれるものの、そこには個人のプライバシーという考え方は微塵もありません。その情況に不安を抱いた佐久は、最終暗号を開発、公開しようとしますが、そのことを知ったアメリカ政府は、アメリカ大統領を通して日本政府に警告を与えます。慌てた日本政府は佐久を呼び出しますが、佐久は彼らに対して以下のように説明します。
「今はインターネットの時代だが、通信回路を伝送される情報を裸でやりとりしているために、簡単に彼らに盗聴されている・・・もともと、インターネットは、一九六九年、米国防省が核戦争の被害で、破壊が予想される通常の通信システムに代わって、緊急の通信網として作ったものだ。軍事的なものを世界中の人に開放すると彼らが言った時、おかしいと、思うべきだったのだ。」『最終暗号』の中で、佐久シゲルが生みだした暗号の根本となる定理の数式に関しては、以下のようなサイトまであります。
「一見、自由主義が確立したように思える現代だが、内情はもはや個人にプライバシーは無い。検閲社会が秘密裏に達成されているのだ・・」
■これが佐久暗号だ!
これは漫画の中の話ではありますが、あながち作り話というわけでもなくて、上記のジマーマンのインタビューや、(ぼくはまだ読んでいませんが)サイモン・シンの『暗号解読—ロゼッタストーンから量子暗号まで」なんかを読むと、このあたりの事がとてもよくわかるのではないでしょうか。
『暗号解読』に関しては、浅田彰さんが「暗号の世界を解読する』という書評を書いています(ジマーマンに関してもちょこっとだけ触れています)。
もとより、暗号というのはプロの外交官や軍人の領域に属し、一般人とはほとんど縁のないものだった。その閉ざされた領域で、暗号作成者と暗号解読者の密かで熾烈な戦いが歴史を通じて続いてきたことを、シンは雄弁に物語る。カエサルに遡る換字式暗号(アルファベットを何文字かずらせて置き換える)。頻度分析でそれを打ち破ったアラビアやヨーロッパの解読者たち。複数のアルファベットを組み合わせるというアルベルティ以来のアイディアを発展させ、26個のアルファベットを組み合わせることによって強力な暗号をつくりだしたヴィジュネル。さらにそれを打ち破ったバベッジ(コンピュータの先祖のひとつに数えられる階差機関の発明者でもある彼は、しかし、おそらく機密保持のためにヴィジュネル暗号の解読を公表できなかった)とカシスキー。さまざまな分野で名の知られた人々が暗号という閉ざされた領域で展開するドラマは、実に興味深い。ちなみに、シンは、ヤングやシャンポリオンらの古代文字の解読や、ドイルやポーらの文学における「暗号的想像力」*[1]にも説き及んでおり、この本に文化史的な厚みを加えている。ついでにもうひとつ。セアラ・フラナリーの「16歳のセアラが挑んだ世界最強の暗号」は、セアラという16歳の少女が、家族や友人の協力の中でCP法という暗号システムを発見するまでの経緯を描いた本です。暗号システムの入門書としても、少女の青春物語としても、どちらの読み方でも楽しめる本です。
訳は亀井よし子さん。この方は、最近は「ブリジット・ジョーンズの日記」で有名ですけれど、ぼくの中ではアン・ビーティーの翻訳家というイメージがいまだに強い。
暗号に対する規制の是非に関しては、とてもデリケートな問題ですし、知識の無いぼくにはなにも言及することはできません。しかし、今後インターネットやパソコンはどんどん家電化するだろうし、それを使う人たちはパソコンに関しての知識がなくても使えようになるでしょう。そうなったときに、それを使う各個人のプライバシーが全部盗聴されているかもしれないという危険性に関しては、心に留めておく必要があるかもしれません。
ある意味、みんなサトラレみたいになっちゃうかもね。それはそれで楽しいのかな。
02年07月12日(金)
■Things Other People Accomplished When They Were Your Age
「あんたと同じ年齢で、他の人が成し遂げてたこと知ってる?」みたいな感じで、自分の年齢を入れると、その年齢の時に歴史上の人物が行なったことが表示されます。
僕の年齢だと、ブッダが出家して家族と財産を遺棄することを決心したり、グラハム・ベルがはじめて電話で文章全体を送信することに成功したり、アガサ・クリスティが処女作を完成させたり、マイケル・ファラデーが電磁循環説を主張したり、カートパトラック・マクミランが自転車を発明したり、エミリー・ジェーン・ブロンテが「嵐が丘」を書いたり、キャロル・キングがベストセラーアルバム「Tapestry」をリリースしたり、ジョージ・ダゴベルトが比較解剖学という科学分野を設立しております。
皆さん、一生懸命に生きていたみたいです。
ちなみに、0才で検索をすると
イエス・キリストが聖母マリアの子として生まれる。
から始まり、
フリードリッヒ・ハインケンが八ヶ月で通じるドイツ語を話し始める。
ウィリアム・J・サイディスが六ヶ月でアルファベットを覚える。
モード・アダムスが六ヶ月で初舞台を踏む。
レオナルド・バーンスタインが一歳になる前に、彼の初めてのピアノ・ノート(?)を演奏する。
100歳以上で検索をすると
アリス・ポルロックが102歳で処女作「Portrait of My Victorian Youth」を出版する。
ジェン・カルメントが119歳で世界最高齢と認定される(1997年に122歳で御臨終)。
聖書にしるされた族長メトセラが969歳で死亡。
などなど。
だからどうしたと言われると、それまでですが。
「あんたと同じ年齢で、他の人が成し遂げてたこと知ってる?」みたいな感じで、自分の年齢を入れると、その年齢の時に歴史上の人物が行なったことが表示されます。
僕の年齢だと、ブッダが出家して家族と財産を遺棄することを決心したり、グラハム・ベルがはじめて電話で文章全体を送信することに成功したり、アガサ・クリスティが処女作を完成させたり、マイケル・ファラデーが電磁循環説を主張したり、カートパトラック・マクミランが自転車を発明したり、エミリー・ジェーン・ブロンテが「嵐が丘」を書いたり、キャロル・キングがベストセラーアルバム「Tapestry」をリリースしたり、ジョージ・ダゴベルトが比較解剖学という科学分野を設立しております。
皆さん、一生懸命に生きていたみたいです。
ちなみに、0才で検索をすると
イエス・キリストが聖母マリアの子として生まれる。
から始まり、
フリードリッヒ・ハインケンが八ヶ月で通じるドイツ語を話し始める。
ウィリアム・J・サイディスが六ヶ月でアルファベットを覚える。
モード・アダムスが六ヶ月で初舞台を踏む。
レオナルド・バーンスタインが一歳になる前に、彼の初めてのピアノ・ノート(?)を演奏する。
100歳以上で検索をすると
アリス・ポルロックが102歳で処女作「Portrait of My Victorian Youth」を出版する。
ジェン・カルメントが119歳で世界最高齢と認定される(1997年に122歳で御臨終)。
聖書にしるされた族長メトセラが969歳で死亡。
などなど。
だからどうしたと言われると、それまでですが。
02年07月13日(土)
■芥川・直木賞:日本文学振興会が候補作を発表 選考委は17日
ある尊敬する知人に勧められて、今回の芥川賞の候補にもなっている吉田修一の「パレード」を読みました。
この「パレード」という本は、何ヶ月か前に書店で川上弘美の「パレード」と並んで売っていたときに、ぱらぱらとめくって斜め読みはしていたのですが、良くあるタイプの小説かと思い購入はしませんでした。
今回もほとんど期待しないで読み始めたのですが、これが読み始めてみると、とてつもなく面白い。電車の中で最初の第一章を読みはじめたのですが、本を閉じることが出来なくなってしまい、電車を降りてすぐに喫茶店に入って続きを読み、読んでいる途中で喫茶店が閉店になってしまい、仕方なく続きは次の日に用事先に向かう電車の中で読み、最期の一章まで読んだところで目的地についてしまったので、やむを得ず本を閉じ、次の日に一日の用事をすべて済ませてから夕方にカフェに行って最期の一章を読みました。
物語の骨子は良くあるタイプのものでして、友人同士でルーム・シェアリングをしている五人の若者の青春小説です。各章ごとにその五人の誰かが語り手となって、それぞれに思っていることや体験した出来事を一人称で語っていきます(ブギーポップは笑わないとか、そんな構成じゃありませんでしたっけ?)。
ひとりひとりの登場人物がとても上手に描けているし、ユーモアのセンスもすごいあるので、最初は電車の中で読んでいて何度も笑ってしまいました。
けれども、第一章から最終章にかけて、登場人物の心情や状況が少しずつ深刻になっていき、最終章に入ると読んでいるこちら側に語り手の内面が浸透してくるような、そのような緊張感を感じました。
最終章をカフェで読み終えた瞬間、ネタバレになるので詳しくは書きませんが、頭がぼーっとしてしまい、しばらく動くことが出来ませんでした。吉田修一の語り口があまりにも上手で、今読んだものが現実なのか小説なのかわからなくなって、頭が混乱していたせいかもしれません。
この本を貸してくれた方も言っていたことなのですが、この小説の帯には「素顔のままでは生きにくい。」とか書かれていて、このコピーを読むかぎり、よくありがちな感傷的青春小説というふうに受け取られてしまう可能性があると思います。現にぼくもそう思っていたぐらいですから。っていうか、物語の中盤までは、そう思っていたし。
けれども、読んでみればわかります。そんなものは、ばっこーんと越えていますから。この本を貸してくれた人は、物語のラストに感動していて、中盤の進行にはあまり気をやっていなかったみたいだけど、ぼくは逆にラストに行くまでのすべての章に感動してしまいました。
まあ、個人個人の好みがありますからね。
それで、これはちょっと吉田君を見逃していました、急いで他のも読んでみましょう、ということで、早速本屋に行って吉田修一の本を捜したところ、「最期の息子」と「熱帯魚」を発見。「最期の息子」は文学界新人賞を受賞した作品を含む短編集で、「熱帯魚」は、平成十年ぐらいから「文学界」に掲載された短編を収めた短編集です。とりあえず、評判の良い「最期の息子」を購入。そのまま図書館に行って「文学界」のバックナンバーを捜して、「熱帯魚」にふくまれている短編「突風」「熱帯魚」や、「Flowers」コピー。さらに一番新しい短編で今回の芥川賞の候補にもなっている「パーク・ライフ」もコピー。ついでに、今月号の新潮に保坂和志の新作「カンバセーション・ピース」の連載第一回目が掲載されていたので、それもコピー。コピー、コピー、コピー。(ぼくはコピーが大好きで、なんでもかんでもコピーしてしまう癖があります。)
そんでもって今、「最期の息子」を読み終えたところなのですが、正直なところ「パレード」の方が面白かったですけれど、それでもこの「最期の息子」もとても面白い。面白いというか、とても良かった。
これは残りの短編も楽しみです。
「パレード」の最期の章で、伊原直輝という登場人物が、ヘッドフォンで「アンドレア・シェニエ」の「なくなった母を」を聞きながらジョギングをするシーンがあるのですが、そのシーンがとても印象的で、やっぱり音楽はいいなあなどと思い、ついついMDウォークマンを買ってしまいました。
今までもMDウォークマンは持ってはいたのですが、相当昔に買ったもので、バックに入れて持ち運ぶだけでバックの重量が変わってしまうようなものですので、まあ、よい機会だからなどと自分に言い聞かせながら。
これからは夕方の石神井公園を、MDウォークマンで音楽を聴きながらジョギングするつもりです。
ところで、普通に考えた場合、「パレード」の最終章を読んでジョギングをしたいと思う人間はそうそういないと思うので、「パレード」を読まれる方はそこらへんは御了承ください。
ある尊敬する知人に勧められて、今回の芥川賞の候補にもなっている吉田修一の「パレード」を読みました。
この「パレード」という本は、何ヶ月か前に書店で川上弘美の「パレード」と並んで売っていたときに、ぱらぱらとめくって斜め読みはしていたのですが、良くあるタイプの小説かと思い購入はしませんでした。
今回もほとんど期待しないで読み始めたのですが、これが読み始めてみると、とてつもなく面白い。電車の中で最初の第一章を読みはじめたのですが、本を閉じることが出来なくなってしまい、電車を降りてすぐに喫茶店に入って続きを読み、読んでいる途中で喫茶店が閉店になってしまい、仕方なく続きは次の日に用事先に向かう電車の中で読み、最期の一章まで読んだところで目的地についてしまったので、やむを得ず本を閉じ、次の日に一日の用事をすべて済ませてから夕方にカフェに行って最期の一章を読みました。
物語の骨子は良くあるタイプのものでして、友人同士でルーム・シェアリングをしている五人の若者の青春小説です。各章ごとにその五人の誰かが語り手となって、それぞれに思っていることや体験した出来事を一人称で語っていきます(ブギーポップは笑わないとか、そんな構成じゃありませんでしたっけ?)。
ひとりひとりの登場人物がとても上手に描けているし、ユーモアのセンスもすごいあるので、最初は電車の中で読んでいて何度も笑ってしまいました。
けれども、第一章から最終章にかけて、登場人物の心情や状況が少しずつ深刻になっていき、最終章に入ると読んでいるこちら側に語り手の内面が浸透してくるような、そのような緊張感を感じました。
最終章をカフェで読み終えた瞬間、ネタバレになるので詳しくは書きませんが、頭がぼーっとしてしまい、しばらく動くことが出来ませんでした。吉田修一の語り口があまりにも上手で、今読んだものが現実なのか小説なのかわからなくなって、頭が混乱していたせいかもしれません。
この本を貸してくれた方も言っていたことなのですが、この小説の帯には「素顔のままでは生きにくい。」とか書かれていて、このコピーを読むかぎり、よくありがちな感傷的青春小説というふうに受け取られてしまう可能性があると思います。現にぼくもそう思っていたぐらいですから。っていうか、物語の中盤までは、そう思っていたし。
けれども、読んでみればわかります。そんなものは、ばっこーんと越えていますから。この本を貸してくれた人は、物語のラストに感動していて、中盤の進行にはあまり気をやっていなかったみたいだけど、ぼくは逆にラストに行くまでのすべての章に感動してしまいました。
まあ、個人個人の好みがありますからね。
それで、これはちょっと吉田君を見逃していました、急いで他のも読んでみましょう、ということで、早速本屋に行って吉田修一の本を捜したところ、「最期の息子」と「熱帯魚」を発見。「最期の息子」は文学界新人賞を受賞した作品を含む短編集で、「熱帯魚」は、平成十年ぐらいから「文学界」に掲載された短編を収めた短編集です。とりあえず、評判の良い「最期の息子」を購入。そのまま図書館に行って「文学界」のバックナンバーを捜して、「熱帯魚」にふくまれている短編「突風」「熱帯魚」や、「Flowers」コピー。さらに一番新しい短編で今回の芥川賞の候補にもなっている「パーク・ライフ」もコピー。ついでに、今月号の新潮に保坂和志の新作「カンバセーション・ピース」の連載第一回目が掲載されていたので、それもコピー。コピー、コピー、コピー。(ぼくはコピーが大好きで、なんでもかんでもコピーしてしまう癖があります。)
そんでもって今、「最期の息子」を読み終えたところなのですが、正直なところ「パレード」の方が面白かったですけれど、それでもこの「最期の息子」もとても面白い。面白いというか、とても良かった。
これは残りの短編も楽しみです。
「パレード」の最期の章で、伊原直輝という登場人物が、ヘッドフォンで「アンドレア・シェニエ」の「なくなった母を」を聞きながらジョギングをするシーンがあるのですが、そのシーンがとても印象的で、やっぱり音楽はいいなあなどと思い、ついついMDウォークマンを買ってしまいました。
今までもMDウォークマンは持ってはいたのですが、相当昔に買ったもので、バックに入れて持ち運ぶだけでバックの重量が変わってしまうようなものですので、まあ、よい機会だからなどと自分に言い聞かせながら。
これからは夕方の石神井公園を、MDウォークマンで音楽を聴きながらジョギングするつもりです。
ところで、普通に考えた場合、「パレード」の最終章を読んでジョギングをしたいと思う人間はそうそういないと思うので、「パレード」を読まれる方はそこらへんは御了承ください。
02年07月14日(日)
待ちに待ったみんなのトニオちゃんがとうとう単行本化されました。
かわいらしいトニオちゃんやジャイ太やスネ郎が、毎週のようにぶっ殺されていくこの漫画、以前SPA!で連載していたときは毎週楽しみに読んでいたのですが、いきなり終わってしまって残念に思っていたので、単行本化はぼくにとってとても喜ばしいことなのです。
この漫画は、よく哲学的であると言われますが、漫画の中で書かれている哲学的なことって、じつは誰もが思春期に考えたことがあるようなことで、それだけでこの漫画を読むと、ちょぴっと拍子抜けしてしまうかもしれません。
けれども、それがどうしてこんなにも面白いのかというと、精神科医である斉藤環氏が解説で書いているように、「文体、すなわち語り口がある」からなのです。
たとえば、仲俣暁生は「ポスト・ムラカミの日本文学」の中で、村上龍の「限りなく透明に近いブルー」を、ドラッグ小説としてしか読むことが出来なかった中上健次に言及して、次のように書いています。
それはともかく、トニオちゃんのぶっ殺されぶりをゆっくりと楽しませていただきます。
かわいらしいトニオちゃんやジャイ太やスネ郎が、毎週のようにぶっ殺されていくこの漫画、以前SPA!で連載していたときは毎週楽しみに読んでいたのですが、いきなり終わってしまって残念に思っていたので、単行本化はぼくにとってとても喜ばしいことなのです。
この漫画は、よく哲学的であると言われますが、漫画の中で書かれている哲学的なことって、じつは誰もが思春期に考えたことがあるようなことで、それだけでこの漫画を読むと、ちょぴっと拍子抜けしてしまうかもしれません。
けれども、それがどうしてこんなにも面白いのかというと、精神科医である斉藤環氏が解説で書いているように、「文体、すなわち語り口がある」からなのです。
菅原はその発想のみによって評価されるべきではない。発想だけなら中学生にもできる。この解説は「みんなのトニオちゃん」をとても的確に評価しているように思うのですが、どのような漫画でも、小説でも、映画でも、いわゆる作品と呼ばれるものにとって、もちろん発想の斬新さというものは大切ですし、重要な要素のひとつであることは間違いありませんが、発想だけの作品というものは、概してつまらない作品なってしまうものです。小説なんかでも、それが面白いかどうかは「文体」にかかっていますからね。
そうした問いへと読者を誘発する手つきの見事さこそが、彼の本領にほかならないのだ。
(解説より)
たとえば、仲俣暁生は「ポスト・ムラカミの日本文学」の中で、村上龍の「限りなく透明に近いブルー」を、ドラッグ小説としてしか読むことが出来なかった中上健次に言及して、次のように書いています。
一読してわかるのは、言葉が即物的な記述のためだけに使われていることです。心理描写を排し、主人公である語り手のリュウに無人格なカメラの役割を果たさせながら、徹頭徹尾、映像的にものごとを記述する。そのことを意識的におこなったのがこの作品の新しさでした。「心理のない記述」を、中上健次は「ラリッてる」のだと誤解したのです。でも、この小説が衝撃的だったのは、ドラッグやセックスといった退廃的な若者風俗を描いたからではなく、映像的に清々しい文章にありました。いま読んでも十分に新鮮なのはそのせいです。
それはともかく、トニオちゃんのぶっ殺されぶりをゆっくりと楽しませていただきます。
02年07月15日(月)
朝九時、あまりの暑さに起床。
頭がぐにゅぐにゅしていたので、すっきりする映画が観たいと思い、渋谷に『ゴースト・オブ・マーズ』を観に行きました。
予想はしていたものの、劇場に入るとそこはまるでダニエル・クロウズの「Ghost World」のようで、ぶつぶつ何かを言っているでぶとか、しきりに頭の髪の毛を気にしているハゲとか、ブラックジャック並に右半分がやたら黒いやつとか、必要以上にいちゃついている中年のカップルとか、おしっこの臭いを漂わせている浮浪者風の男とか、BMIが15を切っているのではないかというくらい痩せたガリとか、1秒間に五回ぐらい眼鏡の位置を気にしている眼鏡君とか、その中にいて全然違和感のない僕とか、月曜日の第一回目の上映を観ようなんていう人間にろくな奴はいません。
けれども、こうして見渡すと、鉄割の稽古場と何も変わらないことに気付く。
『ゴースト・オブ・マーズ』は、阿部和重とか中原昌也とかがあちこちのメディアで大絶賛していただけあって、とても面白かったです(ぼくはこの両者共、作品を読んだことはないのだけど)。ぐじゅぐじゅしていた頭がむにゅむにゅになりました。未来の世界を描いたこの映画は、全然未来っぽくなくて、それがとても良かったです。やっぱり、スカッとするにはレーザービームではなくて、マシンガンでしょう。殺されるためだけに出てくる火星の先住民の幽霊たちには愛おしさすら感じました。
頭がぐにゅぐにゅしているときに観る映画は、何の期待もなく観れて、観ている間は集中できて、観終えたらすっかり忘れてしまうような映画に限ります。
まさしくジョン・カーペンター。
ところで、『ゴースト・オブ・マーズ』のオフィシャルのサイトは、他の映画のサイトと比べると、いろいろな人のエッセイやらコメントやらが長文で読めて、訪れてとても楽しいサイトだと思うのですけど、いかがでしょうか。
映画館を出て、ブックファースト1によって新刊本を物色。
特に面白そうな新刊がないので、スタジオボイスの今月号(「ポストモダン・リターンズ」)と堀江敏幸「郊外へ」、前から読みたかった武田百合子「富士日記(上)」、ウィリアム・T・ヴォルマン「蝶の物語たち」などを購入。一気にトートバックが重くなる。うーん。
その後、渋谷から原宿まで歩く。途中、明治通り沿いにあるブリスターに寄ってアメリカのコミック系アーティストのオムニバス「9.11」を購入。Vol.2も売っていたけれど、とりあえずVol.1を読んでみよう。
そのままさらに歩いて、相当歩いて図書館に行く。その図書館の二階に上がる階段の正面には、馬鹿でかい「熊野路」の絵が飾られていて、それを観るたびに那智の滝に呼ばれているような気がする。
いくら呼ばれても、今年はぼくは東南アジアに行ってしまうのよ。ごめんね。
図書館で、絶版になっている松山巌の「百年の棲家」などを借る。
帰りにちょっと贅沢して高めの白桃を買う。
頭がぐにゅぐにゅしていたので、すっきりする映画が観たいと思い、渋谷に『ゴースト・オブ・マーズ』を観に行きました。
予想はしていたものの、劇場に入るとそこはまるでダニエル・クロウズの「Ghost World」のようで、ぶつぶつ何かを言っているでぶとか、しきりに頭の髪の毛を気にしているハゲとか、ブラックジャック並に右半分がやたら黒いやつとか、必要以上にいちゃついている中年のカップルとか、おしっこの臭いを漂わせている浮浪者風の男とか、BMIが15を切っているのではないかというくらい痩せたガリとか、1秒間に五回ぐらい眼鏡の位置を気にしている眼鏡君とか、その中にいて全然違和感のない僕とか、月曜日の第一回目の上映を観ようなんていう人間にろくな奴はいません。
けれども、こうして見渡すと、鉄割の稽古場と何も変わらないことに気付く。
『ゴースト・オブ・マーズ』は、阿部和重とか中原昌也とかがあちこちのメディアで大絶賛していただけあって、とても面白かったです(ぼくはこの両者共、作品を読んだことはないのだけど)。ぐじゅぐじゅしていた頭がむにゅむにゅになりました。未来の世界を描いたこの映画は、全然未来っぽくなくて、それがとても良かったです。やっぱり、スカッとするにはレーザービームではなくて、マシンガンでしょう。殺されるためだけに出てくる火星の先住民の幽霊たちには愛おしさすら感じました。
頭がぐにゅぐにゅしているときに観る映画は、何の期待もなく観れて、観ている間は集中できて、観終えたらすっかり忘れてしまうような映画に限ります。
まさしくジョン・カーペンター。
ところで、『ゴースト・オブ・マーズ』のオフィシャルのサイトは、他の映画のサイトと比べると、いろいろな人のエッセイやらコメントやらが長文で読めて、訪れてとても楽しいサイトだと思うのですけど、いかがでしょうか。
映画館を出て、ブックファースト1によって新刊本を物色。
特に面白そうな新刊がないので、スタジオボイスの今月号(「ポストモダン・リターンズ」)と堀江敏幸「郊外へ」、前から読みたかった武田百合子「富士日記(上)」、ウィリアム・T・ヴォルマン「蝶の物語たち」などを購入。一気にトートバックが重くなる。うーん。
その後、渋谷から原宿まで歩く。途中、明治通り沿いにあるブリスターに寄ってアメリカのコミック系アーティストのオムニバス「9.11」を購入。Vol.2も売っていたけれど、とりあえずVol.1を読んでみよう。
そのままさらに歩いて、相当歩いて図書館に行く。その図書館の二階に上がる階段の正面には、馬鹿でかい「熊野路」の絵が飾られていて、それを観るたびに那智の滝に呼ばれているような気がする。
いくら呼ばれても、今年はぼくは東南アジアに行ってしまうのよ。ごめんね。
図書館で、絶版になっている松山巌の「百年の棲家」などを借る。
帰りにちょっと贅沢して高めの白桃を買う。
02年07月16日(火)
02年07月17日(水)
たまには鉄割の人とも交流をしなくてはいけないなと思い、中島君と内倉君と三人で「プレッジ」を観に行ってきました。
ショーン・ペンの監督作品を観るのは初めてだったのですが、とても面白い映画でした。一緒に行った中島君は、食事のシーンがあまりないことが残念だったみたいですが、クロッシング・ガードよりは面白かったみたいで、ショーン・ペンが監督した過去の三作品に順位をつけると、一位がインディアン・ランナー、二位がプレッジ、三位がクロッシング・ガードだと言っていました。
インディアン・ランナー、いろいろな方が絶賛しているので、今度観てみよう。
映画自体はストーリーが好みだし、映像も素敵だったので満足しているのですが、冒頭とラストのジャック・ニコルソンの演技が宗形に見えて仕方がなくて、そのことを二人に話すと、中島君はベニシオ・デル・トロの演技が宗形に見えて仕方がなかったと言い、内倉君はミッキー・ロークの演技が宗形に見えて仕方がなかったそうです。
いい加減、宗形の呪縛から解放されたい。
映画館を出たあと、男三人で恵比寿で食事をしました。内倉君が、「ぼくは思うんだけど、自分の頭で考える、自分の力で稼ぐ、当たり前のことだよね」と言っていたので、「それ、矢沢永吉が同じこと言ってたよ」と突っ込んだところ、テーブルの空気がおかしくなりました。大人の関係って難しい。
ところで、オープニングの雪山のシーンを観ていたら、数年前に観た『スウィート・ヒアアフター』がまた観たくなって、帰りにビデオレンタルで借りて観たのですが、数年間にみたときよりもずっと面白かった。ぼくのまわりでこの映画を面白いと言っている人はひとりもいないけど、とても良い映画だと思いました。前回観たときはこんなに面白い映画だと思わなかったのですが。
米国の『The Sweet Hereafter』のオフィシャルサイトでは、Screenplayが読めてしまったりします。
ぼくはイアン・ホルムが地味に好きなのですが、彼がこの映画でかぶっていたロシアン帽がとてもかわいかったので、今年の冬はロシアン帽で勝負をしたいと思います。
ショーン・ペンの監督作品を観るのは初めてだったのですが、とても面白い映画でした。一緒に行った中島君は、食事のシーンがあまりないことが残念だったみたいですが、クロッシング・ガードよりは面白かったみたいで、ショーン・ペンが監督した過去の三作品に順位をつけると、一位がインディアン・ランナー、二位がプレッジ、三位がクロッシング・ガードだと言っていました。
インディアン・ランナー、いろいろな方が絶賛しているので、今度観てみよう。
映画自体はストーリーが好みだし、映像も素敵だったので満足しているのですが、冒頭とラストのジャック・ニコルソンの演技が宗形に見えて仕方がなくて、そのことを二人に話すと、中島君はベニシオ・デル・トロの演技が宗形に見えて仕方がなかったと言い、内倉君はミッキー・ロークの演技が宗形に見えて仕方がなかったそうです。
いい加減、宗形の呪縛から解放されたい。
映画館を出たあと、男三人で恵比寿で食事をしました。内倉君が、「ぼくは思うんだけど、自分の頭で考える、自分の力で稼ぐ、当たり前のことだよね」と言っていたので、「それ、矢沢永吉が同じこと言ってたよ」と突っ込んだところ、テーブルの空気がおかしくなりました。大人の関係って難しい。
ところで、オープニングの雪山のシーンを観ていたら、数年前に観た『スウィート・ヒアアフター』がまた観たくなって、帰りにビデオレンタルで借りて観たのですが、数年間にみたときよりもずっと面白かった。ぼくのまわりでこの映画を面白いと言っている人はひとりもいないけど、とても良い映画だと思いました。前回観たときはこんなに面白い映画だと思わなかったのですが。
米国の『The Sweet Hereafter』のオフィシャルサイトでは、Screenplayが読めてしまったりします。
ぼくはイアン・ホルムが地味に好きなのですが、彼がこの映画でかぶっていたロシアン帽がとてもかわいかったので、今年の冬はロシアン帽で勝負をしたいと思います。
02年07月18日(木)
最近気になった記事やサイトなどを。
■The 50 Worst Movies of All Time
全時代、全ジャンルから選ばれたうんこ映画ワースト50。
栄えあるうんこ映画第一位に選ばれたのは『バットマン&ロビン』です。おめでとう。
うんこ入り確実の『バットマン対スーパーマン』ももうすぐ公開。
■モンティ・パイソン作の寸劇、初の一般上演へ
グラハム・チャップマンの未発表のスケッチが発見されて、それを上演するそうです。一本4分ぐらいで、三本。鉄割にもやらせて欲しい。
下のオフィシャルサイトに、スケッチの内容などが詳しく書かれています。
■"LOST" GRAHAM CHAPMAN SKETCHES TO PREMIERE AT EDINBURGH FESTIVAL
と思ったら、上のページが消えている。どうしてだろう。昨日見たときはあったのに。
(記憶が不鮮明だけど、病的な救世主の話とか、DNAが狂った猫の話とか、そんなだった気がする)
■Japan conquered, Puffy ready for U.S.
現在北米ツアー中のPuffyがCNN.comで取り上げられています。
アメリカには既にPuffyと呼ばれているおっちゃんがいるので、混同しないようにPuffy AmiYumiという名前で活動してるんだって。
■弟子の作品からラファエロの筆跡が発見される
特に思うところは無いのですが、ぼくは一応ラファエロ好きということになっているので。
■Today In Literature
世界文学史における「今日」を紹介。
ちなみ本日7月18日は、『高慢と偏見』のジェーン・オースティンが41歳でお亡くなりになった日です。
■Amazon Light
軽量型Amazon.com。すばらしい。Amazon.co.jp版も作って欲しい。
■「タイムマシン」43年ぶりに映画化
曾爺ちゃんの小説を曾孫が監督。
ウェルズのSF小説は大好きなので、とても楽しみ。全然期待はしていないけど。
■特定遺伝子増やしネズミの脳巨大化 米グループ
ねずみちゃんの遺伝子をいじったら脳みそがでっかくなっちゃったよ!っていう記事なんですけど、これちょっとこわいよ。
SF小説なんかでは、高度な知能を持った動物が人間を殺すというテーマの作品がよく書かれますけど、それが現実になりそうで。
映画「ディープ・ブルー」なんかも、高度な知能を持つサメに人間が翻弄されるという話でした。こわいこわい。こわいよー。
■鬼平犯科帳の彩色江戸名所図解
これはたまらない。このサイトを知ったときは、興奮で震えてしまいました。
池波正太郎さんが『鬼平犯科帳』を書くとき参考にした『江戸名所図会』『江戸買物独案内』と江戸の切絵図をもとに、『鬼平』の各章を解説しましょう、という趣旨のサイトなのですが、その他にも、当時の隠密が集めた情報を記録した「よしの冊子」や、鬼平の関連資料など、サイト内のどのページを観ても興奮しまくり間違いなしです。
今のところ、絵解きは第二巻までしかされていませんが、順次更新されていくようです。たーのーしーみー。
そんでスパイダーマンが踊る。
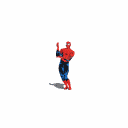
さらにみんなも踊る。
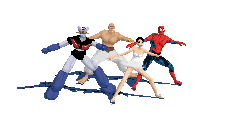
■The 50 Worst Movies of All Time
全時代、全ジャンルから選ばれたうんこ映画ワースト50。
栄えあるうんこ映画第一位に選ばれたのは『バットマン&ロビン』です。おめでとう。
うんこ入り確実の『バットマン対スーパーマン』ももうすぐ公開。
■モンティ・パイソン作の寸劇、初の一般上演へ
グラハム・チャップマンの未発表のスケッチが発見されて、それを上演するそうです。一本4分ぐらいで、三本。鉄割にもやらせて欲しい。
下のオフィシャルサイトに、スケッチの内容などが詳しく書かれています。
■"LOST" GRAHAM CHAPMAN SKETCHES TO PREMIERE AT EDINBURGH FESTIVAL
と思ったら、上のページが消えている。どうしてだろう。昨日見たときはあったのに。
(記憶が不鮮明だけど、病的な救世主の話とか、DNAが狂った猫の話とか、そんなだった気がする)
■Japan conquered, Puffy ready for U.S.
現在北米ツアー中のPuffyがCNN.comで取り上げられています。
アメリカには既にPuffyと呼ばれているおっちゃんがいるので、混同しないようにPuffy AmiYumiという名前で活動してるんだって。
■弟子の作品からラファエロの筆跡が発見される
特に思うところは無いのですが、ぼくは一応ラファエロ好きということになっているので。
■Today In Literature
世界文学史における「今日」を紹介。
ちなみ本日7月18日は、『高慢と偏見』のジェーン・オースティンが41歳でお亡くなりになった日です。
■Amazon Light
軽量型Amazon.com。すばらしい。Amazon.co.jp版も作って欲しい。
■「タイムマシン」43年ぶりに映画化
曾爺ちゃんの小説を曾孫が監督。
ウェルズのSF小説は大好きなので、とても楽しみ。全然期待はしていないけど。
■特定遺伝子増やしネズミの脳巨大化 米グループ
ねずみちゃんの遺伝子をいじったら脳みそがでっかくなっちゃったよ!っていう記事なんですけど、これちょっとこわいよ。
SF小説なんかでは、高度な知能を持った動物が人間を殺すというテーマの作品がよく書かれますけど、それが現実になりそうで。
映画「ディープ・ブルー」なんかも、高度な知能を持つサメに人間が翻弄されるという話でした。こわいこわい。こわいよー。
■鬼平犯科帳の彩色江戸名所図解
これはたまらない。このサイトを知ったときは、興奮で震えてしまいました。
池波正太郎さんが『鬼平犯科帳』を書くとき参考にした『江戸名所図会』『江戸買物独案内』と江戸の切絵図をもとに、『鬼平』の各章を解説しましょう、という趣旨のサイトなのですが、その他にも、当時の隠密が集めた情報を記録した「よしの冊子」や、鬼平の関連資料など、サイト内のどのページを観ても興奮しまくり間違いなしです。
今のところ、絵解きは第二巻までしかされていませんが、順次更新されていくようです。たーのーしーみー。
そんでスパイダーマンが踊る。
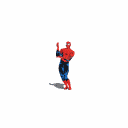
さらにみんなも踊る。
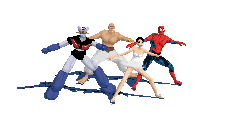
02年07月19日(金)
ちょっと古いニュースですが
■「ムーアの法則は続く」——Moore氏、勲章を手に語る
「ムーアの法則」とは、「チップに集積されるトランジスタの数は2年(18ヶ月じゃなかったけ?)おきに2倍になる」という恐ろしい法則でして、ぼくなんかはもうパソコンの技術の進歩は止まってしまっても良いのではないですか、と思っているのですが、いまだこの法則通りに進歩を続けているみたいです。
パソコンの世界には、ビル・ジョイというとても偉い人がいるのですが、彼は「Why the future doesn't need us(未来は人類を必要としているか?)」というエッセーの中で「ムーアの法則」に言及して、「2030年までには現在のパソコンの100万倍の処理能力を持つマシーンがお目見えすることになりそうだ」と書いています。
上記の記事によると、ムーア氏は「物質が原子でできているという事実から受ける制約は大きい」として、トランジスタの増加ペースの低減を示唆していますけれど、実際のところはどうなのでしょうね。100万倍のパソコンなんて、なにに使えばいいのかわからないわ。
ところで、この素晴らしいエッセーは、Wired.comに掲載されたエッセーで、日本語の翻訳もMacLifeに掲載されました。
最新のコンピュータ技術に携わる開発者であるビル・ジョイは、このエッセーの中で、その他先端技術の進歩を追及することよって生じる危険な側面を、さまざまな例(ロボット工学、遺伝子工学、GNRなど)を挙げて指摘しています。
彼は、レイ・カーツウェルの著書『スピリチュアル・マシーン—コンピュータに魂が宿るとき』のなかで、彼の友人であり優れたコンピュータ設計者であるダニー・ヒリスが以下のように語っているのを読み、ショックを受けたと書いています。
人間の脳の構造を解析して、その状態をコンピュータ上に再現し、そこに人間の意識をダウンロードして近似的な不死を実現しようというのです。
ビル・ジョイは以下のように書いています。
彼は、『森の生活』のH.D.ソローの言葉を引用して以下のように書いています。
ビル・ジョイは、続けて書きます。
ところで、ぼくはエッセーというものが大好きで、下手すると小説よりもエッセーの方が読んでいるのではないかと思うのですが、エッセーの中でも、個人の考えや経験を滔々と書き連ねているだけのエッセーも確かに面白いですが、このように著者の博識がいやみではなく自然に挿入されているエッセーが大好きです。
最先端の科学技術を説明するのに、アリストテレスからユナボマーまで、古今東西の様々な文献を参照し、彼の身近にいる優れた科学者達の発言を引用し、最先端技術に関する知識を全然持っていないぼくにでも理解できるように丁寧に書かれてあり、一度読み始めると止めることが出来ません。
ぼくがもっとも愛しているエッセーは、トマス・ピンチョンの『Sloth(怠惰)』と、この『Why the future doesn't need us』なのです。
■「ムーアの法則は続く」——Moore氏、勲章を手に語る
「ムーアの法則」とは、「チップに集積されるトランジスタの数は2年(18ヶ月じゃなかったけ?)おきに2倍になる」という恐ろしい法則でして、ぼくなんかはもうパソコンの技術の進歩は止まってしまっても良いのではないですか、と思っているのですが、いまだこの法則通りに進歩を続けているみたいです。
パソコンの世界には、ビル・ジョイというとても偉い人がいるのですが、彼は「Why the future doesn't need us(未来は人類を必要としているか?)」というエッセーの中で「ムーアの法則」に言及して、「2030年までには現在のパソコンの100万倍の処理能力を持つマシーンがお目見えすることになりそうだ」と書いています。
上記の記事によると、ムーア氏は「物質が原子でできているという事実から受ける制約は大きい」として、トランジスタの増加ペースの低減を示唆していますけれど、実際のところはどうなのでしょうね。100万倍のパソコンなんて、なにに使えばいいのかわからないわ。
ところで、この素晴らしいエッセーは、Wired.comに掲載されたエッセーで、日本語の翻訳もMacLifeに掲載されました。
最新のコンピュータ技術に携わる開発者であるビル・ジョイは、このエッセーの中で、その他先端技術の進歩を追及することよって生じる危険な側面を、さまざまな例(ロボット工学、遺伝子工学、GNRなど)を挙げて指摘しています。
彼は、レイ・カーツウェルの著書『スピリチュアル・マシーン—コンピュータに魂が宿るとき』のなかで、彼の友人であり優れたコンピュータ設計者であるダニー・ヒリスが以下のように語っているのを読み、ショックを受けたと書いています。
誰もが自分の肉体が好きだし、私もそうだ。だが、もし200歳まで生きることができるのなら、シリコンの体に交換されてしまっても構わないと思う。現在のロボット技術は、人間のかわりに労働をするロボットを開発するという技術段階から、人間の意識をロボットにダウンロードして、人類に永遠の生命を与えようとする研究に発展しようとしています。
人間の脳の構造を解析して、その状態をコンピュータ上に再現し、そこに人間の意識をダウンロードして近似的な不死を実現しようというのです。
ビル・ジョイは以下のように書いています。
意識としての私たちがテクノロジーへとダウンロードされていくとなると、人類自身はいったい、どうやって人類でありつづけることができるのだろう。エッセーに書かれていることのすべてををここで説明することは不可能ですが、このエッセーの中でビル・ジョイが言っているのは、単なる先進的科学に対する根拠のない誹謗ではなくて、それらの技術の有用性は認めつつも、「ただ科学をやっているだけで、倫理的問題のことはお留守になってしまっていては困る」、それ故に「今後姿を現すと考えられる先進の技術に備えて、社会の準備を整える」べきであるということなのです。
彼は、『森の生活』のH.D.ソローの言葉を引用して以下のように書いています。
「私たちが鉄道の上を通っているのではない。鉄道が私たちの上を通っているのだ(G.D.ソロー)」。これこそがいま、私たちが戦っていかねばならない対象だ。もんだいは、主導権を握るのがどちらになるのか、だ。人類は生き残れるのか。それとも生き残るのはテクノロジーなのか。映画『マンハッタン』で、「なぜ人生には生きる価値があるのか?」という質問に対して、ウッディ・アレンが自分自身の人生に価値をもたらしているものが何であるかを思い巡らせるシーンがあります。それは、グルーチョ・マルクス、ウィリー・メイズ、モーツァルトのジュピター交響曲第二章、ルイ・アームストロングの「ポテト・ヘッド・メイズ」、スウェーデンの映画、フローベールの小説「感情教育」、マーロン・ブランド、フランク・シナトラ、セザンヌ描くりんごやなし、サム・ウォーのレストランのカニ料理、彼の恋人トレーシー。
ビル・ジョイは、続けて書きます。
人は誰しも大事に思っているものがある。そして、それを大事にすることによって、自分の人間存在の本質を知る。目前にある危機に人類はきっと立ち向かっていくはず、と私が期待するのは、つまるところ、人にはモノや人を大事に思うという、すばらしい能力があるからなのだ。このエッセーの分量は、Webで公開されているものを見れば分かると思いますが、結構長めです。ここでぼくが取り上げているのは、その中の本当にほんの一部、本当にさわり程度なので、これだけを読むと単なる科学批判のエッセーのように思われてしまうのではないかととても不安です。
ところで、ぼくはエッセーというものが大好きで、下手すると小説よりもエッセーの方が読んでいるのではないかと思うのですが、エッセーの中でも、個人の考えや経験を滔々と書き連ねているだけのエッセーも確かに面白いですが、このように著者の博識がいやみではなく自然に挿入されているエッセーが大好きです。
最先端の科学技術を説明するのに、アリストテレスからユナボマーまで、古今東西の様々な文献を参照し、彼の身近にいる優れた科学者達の発言を引用し、最先端技術に関する知識を全然持っていないぼくにでも理解できるように丁寧に書かれてあり、一度読み始めると止めることが出来ません。
ぼくがもっとも愛しているエッセーは、トマス・ピンチョンの『Sloth(怠惰)』と、この『Why the future doesn't need us』なのです。
02年07月20日(土)
ある時、尊敬する友人のひとりが、ドイツの思想家であるエルンスト・ブロッホの'Darkness of the lived moment'という言葉を引用しながら、休みの日は山や川のそばで、何もしないでぼーっと本でも読んでいるのが良い、ということを言っていました。
「休みの日はぼーっとしたほうがいい」なんてことは、誰もが思っていることで、箴言でも何でもないわけですが、'Darkness of the lived moment'という言葉と一緒にそれを聞いた時、ぼくはなぜかとても感動をしてしまい、その言葉を心の中で何度も反芻しました。
直訳すると、「生かされている瞬間の闇」ということになるのでしょうか、ブロッホがどのようなつもりでその言葉を述べたのかはわかりませんが、この言葉を口に出して言うと、気付いていない何かに気付かされたような気持ちになります。
それで先日、その友人と久しぶりに会ってお話をする機会があったのですが、その時に夏休みの予定の話になり、ぼくが「ちょっと東南アジアへ行ってきます」と言ったところ、「なんで?」と聞かれました。
心の中では、「いやあ、何もないラオスの川や海の近くで読書でもしながらぼーっとしていようかと思って。」などと答えて、「いやあ、君、なかなかいいね。感性がぼくと似ているんじゃない?」などと言われたいなあ、と思いつつも、日ごろの癖でついつい「まあねえ、本当はヨーロッパに行きたいのですけど、ヨーロッパって物価高いですからねえ、安くて馬鹿なアジアがお似合いですよ、ぼくには。ほら、馬鹿でしょう、アジア人。くせえっつーのね、あいつら、ねえ。」などと心にもないことを口走ってしまいました。
小学生の頃のひねくれた性格が、いまだ直っておりません。
貧乏性のぼくには、旅行先でハンモックに揺られながら何も考えずに一日読書なんてことはできそうにありませんが、それでも今回の旅行は、魂のお洗濯ということで、最小限の予定しかたてずに、できるだけゆっくりとしてこようと思っています。
ぼくの行く予定の南ラオスは、本当に何もない地域で、そこに行くと言うと、ラオスの人にさえ呆れられるそうです。
ラオスの方々は、みなさんとても心がやさしいということなので、この汚れた魂を少しでも洗い流せれば良いですけれど。
とても楽しみ。
「休みの日はぼーっとしたほうがいい」なんてことは、誰もが思っていることで、箴言でも何でもないわけですが、'Darkness of the lived moment'という言葉と一緒にそれを聞いた時、ぼくはなぜかとても感動をしてしまい、その言葉を心の中で何度も反芻しました。
直訳すると、「生かされている瞬間の闇」ということになるのでしょうか、ブロッホがどのようなつもりでその言葉を述べたのかはわかりませんが、この言葉を口に出して言うと、気付いていない何かに気付かされたような気持ちになります。
それで先日、その友人と久しぶりに会ってお話をする機会があったのですが、その時に夏休みの予定の話になり、ぼくが「ちょっと東南アジアへ行ってきます」と言ったところ、「なんで?」と聞かれました。
心の中では、「いやあ、何もないラオスの川や海の近くで読書でもしながらぼーっとしていようかと思って。」などと答えて、「いやあ、君、なかなかいいね。感性がぼくと似ているんじゃない?」などと言われたいなあ、と思いつつも、日ごろの癖でついつい「まあねえ、本当はヨーロッパに行きたいのですけど、ヨーロッパって物価高いですからねえ、安くて馬鹿なアジアがお似合いですよ、ぼくには。ほら、馬鹿でしょう、アジア人。くせえっつーのね、あいつら、ねえ。」などと心にもないことを口走ってしまいました。
小学生の頃のひねくれた性格が、いまだ直っておりません。
貧乏性のぼくには、旅行先でハンモックに揺られながら何も考えずに一日読書なんてことはできそうにありませんが、それでも今回の旅行は、魂のお洗濯ということで、最小限の予定しかたてずに、できるだけゆっくりとしてこようと思っています。
ぼくの行く予定の南ラオスは、本当に何もない地域で、そこに行くと言うと、ラオスの人にさえ呆れられるそうです。
ラオスの方々は、みなさんとても心がやさしいということなので、この汚れた魂を少しでも洗い流せれば良いですけれど。
とても楽しみ。
02年07月21日(日)
昨日の日記にも書きましたが、ウィリアム・T・ヴォルマンの「蝶の物語たち」を購入し、現在読書中です。
最初はすげー読みづれーとか思っていましたが、読んでいくうちにどんどんはまっていく。随所にちりばめられたヴォルマン自身による挿し絵が、とてもよい効果を出しております。
こんな挿し絵。かわいいでしょ。

東南アジアに旅行に行くからというわけではないけれど、ヴォルマンは個人的にそうとう気になっていた作家さんでして、彼の書くものと言ったら、世界中を旅して娼婦やドラッグやピストルや国境や正義や難民なんかを描いた旅行記とか、あるいはアメリカの歴史がこれでもかこれでもかとばかり滔々と書きつづられている歴史小説とか、あるいはタイで売春婦を救出する様を描いたアクションもの(っていうかノンフィクションなのですが)とか、そのような作品ばかりなのです。
アメリカの歴史を描いた「Seven Dreams」というシリーズは、全7巻になりますが、いまのところまだ4巻しかでていなくて、全部で15年をかけるつもり(フィネガンズ・ウェイク!)らしいので、全部が完成するのは2005年になるそうです。
建国以来200年少ししか経っていないアメリカという国を、千年の時間を遡って描き、「ヴォルマンの体内に流れるアメリカ人という血の中に、先祖代々から受け継がれたさまざまな記憶を読み解き、言葉に変えていこうとする試みなのだ。」(『ヴォルマン、お前は何者だ!』より)
これ、翻訳をするのはかなり大変だとは思いますが、なんとか翻訳してくれないかしら。とても読みたいのだけど。
世界百二十六都市を巡るヴォルマンの旅をもとに描かれた「The Atlas」という作品は、川端康成の「掌の小説」に着想を得て書かれたもので、各都市を描いたショート・ストーリーをすべて読むと、内在しているテーマが見えてくる、という手法で書かれています。もちろんトーキョーオーサカも入っていますよ。この作品も未訳です。
それでは一体どの作品が翻訳されているのかというと、
■ザ・ライフルズ
(Amazonの紹介文)「北西航路」を探して北極圏で全滅した19世紀英国のフランクリン探検隊。領土確保のために同地への移住を余儀なくされた、ケベック州のイヌイットたち。凍てつく極北の地を舞台に、2つの物語が時空を越えて結びつく。
■蝶の物語たち(現在読書中)
(Amazonの紹介文)愛する娼婦ヴァンナが消えた!?アメリカ人ジャーナリストは彼女を探し、地雷と密林、タイ—カンボジア国境を越える—東南アジアの純真をセクシュアルに描く極熱のラブストーリー。
■ハッピー・ガールズ、バッド・ガールズ
(Amazonの紹介文)娼婦、ドラッグディーラー、ポルノグラファー、ポン引き、手錠フェチ、現代アメリカのオブセッションを描く、若き鬼才の傑作。どこか壊れてしまった人間たち、崩壊せざるを得ない人間たちの姿。
の三作品で、その他
■ヴォルマン、お前はなに者だ!—地球のオルタナティヴを描く記録天使
というヴォルマン特集雑誌も出ています。この本がなかったら、ぼくがヴォルマンに興味を持つことなんておそらくなかったでしょう。
あと、ぼくのお気に入りの小説集に「Positive 01-ポストモダン小説、ピンチョン以後の作家たち」があるのですが、その中にも「The Grave of Lost Stories」という作品が翻訳されています。これは「Thirteen Stories and Thirteen Epitaphs」に収められている作品のひとつなのですが、「Thirteen〜」の邦訳である「ハッピー・ガールズ、バッド・ガールズ」に収められているものとは訳者が違うみたいです。
娼婦が大好きで、アジアの各国に現地妻がいるという噂もありますが、本人は否定していて、何年か前には正式に結婚もしたみたいです。いっそのこと、アジアの娼婦とかと結婚すれば良かったのに。坪内逍遥みたいに。
しかし、このヴォルマン君、中島君の弟さんに顏がそっくりなのです。

ですから、「蝶の物語たち」を読んでいると、ぼくの頭の中には、中島君の弟が娼婦の恋人を探して東南アジアをさまよっている姿が浮かんで仕方がありません。
最初はすげー読みづれーとか思っていましたが、読んでいくうちにどんどんはまっていく。随所にちりばめられたヴォルマン自身による挿し絵が、とてもよい効果を出しております。
こんな挿し絵。かわいいでしょ。

東南アジアに旅行に行くからというわけではないけれど、ヴォルマンは個人的にそうとう気になっていた作家さんでして、彼の書くものと言ったら、世界中を旅して娼婦やドラッグやピストルや国境や正義や難民なんかを描いた旅行記とか、あるいはアメリカの歴史がこれでもかこれでもかとばかり滔々と書きつづられている歴史小説とか、あるいはタイで売春婦を救出する様を描いたアクションもの(っていうかノンフィクションなのですが)とか、そのような作品ばかりなのです。
アメリカの歴史を描いた「Seven Dreams」というシリーズは、全7巻になりますが、いまのところまだ4巻しかでていなくて、全部で15年をかけるつもり(フィネガンズ・ウェイク!)らしいので、全部が完成するのは2005年になるそうです。
建国以来200年少ししか経っていないアメリカという国を、千年の時間を遡って描き、「ヴォルマンの体内に流れるアメリカ人という血の中に、先祖代々から受け継がれたさまざまな記憶を読み解き、言葉に変えていこうとする試みなのだ。」(『ヴォルマン、お前は何者だ!』より)
これ、翻訳をするのはかなり大変だとは思いますが、なんとか翻訳してくれないかしら。とても読みたいのだけど。
世界百二十六都市を巡るヴォルマンの旅をもとに描かれた「The Atlas」という作品は、川端康成の「掌の小説」に着想を得て書かれたもので、各都市を描いたショート・ストーリーをすべて読むと、内在しているテーマが見えてくる、という手法で書かれています。もちろんトーキョーオーサカも入っていますよ。この作品も未訳です。
それでは一体どの作品が翻訳されているのかというと、
■ザ・ライフルズ
(Amazonの紹介文)「北西航路」を探して北極圏で全滅した19世紀英国のフランクリン探検隊。領土確保のために同地への移住を余儀なくされた、ケベック州のイヌイットたち。凍てつく極北の地を舞台に、2つの物語が時空を越えて結びつく。
■蝶の物語たち(現在読書中)
(Amazonの紹介文)愛する娼婦ヴァンナが消えた!?アメリカ人ジャーナリストは彼女を探し、地雷と密林、タイ—カンボジア国境を越える—東南アジアの純真をセクシュアルに描く極熱のラブストーリー。
■ハッピー・ガールズ、バッド・ガールズ
(Amazonの紹介文)娼婦、ドラッグディーラー、ポルノグラファー、ポン引き、手錠フェチ、現代アメリカのオブセッションを描く、若き鬼才の傑作。どこか壊れてしまった人間たち、崩壊せざるを得ない人間たちの姿。
の三作品で、その他
■ヴォルマン、お前はなに者だ!—地球のオルタナティヴを描く記録天使
というヴォルマン特集雑誌も出ています。この本がなかったら、ぼくがヴォルマンに興味を持つことなんておそらくなかったでしょう。
あと、ぼくのお気に入りの小説集に「Positive 01-ポストモダン小説、ピンチョン以後の作家たち」があるのですが、その中にも「The Grave of Lost Stories」という作品が翻訳されています。これは「Thirteen Stories and Thirteen Epitaphs」に収められている作品のひとつなのですが、「Thirteen〜」の邦訳である「ハッピー・ガールズ、バッド・ガールズ」に収められているものとは訳者が違うみたいです。
娼婦が大好きで、アジアの各国に現地妻がいるという噂もありますが、本人は否定していて、何年か前には正式に結婚もしたみたいです。いっそのこと、アジアの娼婦とかと結婚すれば良かったのに。坪内逍遥みたいに。
しかし、このヴォルマン君、中島君の弟さんに顏がそっくりなのです。

ですから、「蝶の物語たち」を読んでいると、ぼくの頭の中には、中島君の弟が娼婦の恋人を探して東南アジアをさまよっている姿が浮かんで仕方がありません。
02年07月22日(月)
アメリカ文学のお話。
少し前になりますが、ドン・デリーロの「アンダーワールド」の翻訳本が出版されました。
「来たるべき作家たち」なんかでは、1998年の段階で翻訳が「来年出版予定」と書いてあったのですが、結局今年までかかってしまったみたいです。
本屋でかるく立ち読みしたのですが、とにかく分厚い。分厚いのが二冊。翻訳される前は、「読みたいよ!読みたいよ!早く翻訳してくれよ!」とずっと思っていたのですが、いざ出版されるとなかなか読む気にも、買う気にもなりません。
リチャード・パワーズの「ガラテイア2.2」なんかもずーっと翻訳されるのを待っていたのですが、いざ出版されるとどうしても読む気になれません。すげー面白そうなんですけどね。
単に人工知能がテーマの小説なのかと思っていたら、群像に載っていた横田創さんの「ガラテイア2.2」の書評なんかを読むと、そんな単純なものではなさそうですね。(当たり前?)
何だか書いているうちに、『アンダーワールド』と『ガラテイア2.2』が無性に読みたくなってきました。今週末は読書三昧しようかしら。
ポール・オースターは『The Red Notebook: True Stories』が出たり。
とりあえずAmazonでペーパーバックを購入してみましたけど、内容的にはあちこちに収録されているエッセイの寄せ集めです。
でも、
「Why write?」とかも収録されていますし。これ、かなりおもしろいですよ。
さらに本屋を徘徊していると、スティーブン・ミルハウザーの『マーティン・ドレスラーの夢』が出ているのを見つけたり、マイケル・シェイボンの『悩める狼男たち』なんかも読みたいなあと思ったり、読みたい本は山ほどあれど、日常の細事に追われ、思うままには読む能わず。
ところで、デリーロとパワーズといえば、新潮の2000年12月号には、以下のような記事が載っていました。
■Beyond Words—テロ惨劇に呼び起こされた、アメリカ作家たちの“声”
去年の10月11日にニューヨークで行われた「Beyond Words(言葉では言い尽くせない)」というタイトルの朗読会から、現在のアメリカ文学界の現状までを新元良一さんがレポートしています。
言葉を表現の手段としている文学者達が、言葉を越えた(Beyond Words)世界を経験したとき、どのような物語が誕生するのか。
というレポートです。
(言葉を越えた世界というのは、言うまでもなく9.11のことです。)

少し前になりますが、ドン・デリーロの「アンダーワールド」の翻訳本が出版されました。
「来たるべき作家たち」なんかでは、1998年の段階で翻訳が「来年出版予定」と書いてあったのですが、結局今年までかかってしまったみたいです。
本屋でかるく立ち読みしたのですが、とにかく分厚い。分厚いのが二冊。翻訳される前は、「読みたいよ!読みたいよ!早く翻訳してくれよ!」とずっと思っていたのですが、いざ出版されるとなかなか読む気にも、買う気にもなりません。
リチャード・パワーズの「ガラテイア2.2」なんかもずーっと翻訳されるのを待っていたのですが、いざ出版されるとどうしても読む気になれません。すげー面白そうなんですけどね。
単に人工知能がテーマの小説なのかと思っていたら、群像に載っていた横田創さんの「ガラテイア2.2」の書評なんかを読むと、そんな単純なものではなさそうですね。(当たり前?)
『息を呑むほど壮大で華麗なインチキ』であるこの小説は、自分の『インチキ』を証明するために書かれている。そして今、賭けられているのは、この小説をトレーニングしている(読んでいる)私たちなのだ。『中心になる時制は現在だ。物語の要点は、あなたが物語をどうするかにある。』ああ、やっぱり面白そうだな。
何だか書いているうちに、『アンダーワールド』と『ガラテイア2.2』が無性に読みたくなってきました。今週末は読書三昧しようかしら。
ポール・オースターは『The Red Notebook: True Stories』が出たり。
とりあえずAmazonでペーパーバックを購入してみましたけど、内容的にはあちこちに収録されているエッセイの寄せ集めです。
でも、
Auster again explores events from the real world —large and small, tragic and comic—that reveal the unpredictable, shifting nature of human experience.なんていう説明を読むと、買わずにはいられませんよ。
「Why write?」とかも収録されていますし。これ、かなりおもしろいですよ。
さらに本屋を徘徊していると、スティーブン・ミルハウザーの『マーティン・ドレスラーの夢』が出ているのを見つけたり、マイケル・シェイボンの『悩める狼男たち』なんかも読みたいなあと思ったり、読みたい本は山ほどあれど、日常の細事に追われ、思うままには読む能わず。
ところで、デリーロとパワーズといえば、新潮の2000年12月号には、以下のような記事が載っていました。
■Beyond Words—テロ惨劇に呼び起こされた、アメリカ作家たちの“声”
去年の10月11日にニューヨークで行われた「Beyond Words(言葉では言い尽くせない)」というタイトルの朗読会から、現在のアメリカ文学界の現状までを新元良一さんがレポートしています。
言葉を表現の手段としている文学者達が、言葉を越えた(Beyond Words)世界を経験したとき、どのような物語が誕生するのか。
というレポートです。
(言葉を越えた世界というのは、言うまでもなく9.11のことです。)

02年07月23日(火)
オリバー・ストーン監督の『U・ターン』を観ました。
リブ・タイラーが目当てで観たのですが、観終えたときにはそんなことはすっかり忘れていました。友達が「結構面白いよ」と言っていたのですが、結構どころか最高に面白かったです。始まりから終わりまで、全部面白かった。オリーバー・ストーン監督の作品って、正直あまり好きではないのですが、この映画は別です。とても満足してしまいました。けど、ビデオレンタルでこのビデオをリブ・タイラーの棚に置くのはやめて欲しい。五秒ぐらいしか出てないじゃん。
あまりにもストーリーが良かったので、この映画の原作は一体誰なのだろうと思いクレジットを観たところ、ジョン・リドリーという人で、一応肩書きは映画監督ということらしいのですが、実際に何を監督したのかは不明です。脚本なんかは結構書いているらしく、「U・ターン」の脚本も担当しているし、『スリー・キングス』の原案なんかも彼の作品だそうです。
それで、早速『U・ターン』の原作である『Stray Dogs』の邦訳『ネヴァダの犬たち』を古本屋で探して購入、読んでみたのですが、これが死ぬほどおもしろい。最初に『U・ターン』の脚本を書いて、その後にこの小説を書いたということなので、内容は映画にかなり忠実ですが、映画を観ないでこの小説を読んだとしても、十分に面白いと思います。
で、ストーリーですが、ぼくが説明するよりも、本のディスクリプションを読んだほうが分かりやすいと思いますので、下にそのまま引用します。
「ノアール(暗黒)」という言葉に関しては、山田宏一さんが詳しく説明しているので、孫引用になってしまいますが、下に引用します。
ジョン・リドリーのその他の作品はというと、借金地獄の元脚本家志望ジェフティ・キトリッジが、どん底から這い出て真実の愛を見つけようとペテン計画を企てる『Love is Rocket(邦題:愛はいかがわしく)』、ジャッキー・マンという黒人のコメディアンが、人種差別の吹き荒れる公民権運動の揺籃期に、ハリウッドでスターダムへとのし上がる過程を描いた『A Conversation with the Mann: A Novel』、何をやっても長続きしないパリス・スコットという青年が、自殺したロックスターのテープと、盗んだドラッグから得たお金をもとに夢をかなえようとする『Everybody Smokes In Hell』などなど。さらに、来月には新作『The Drift』なんかも出るみたいです。
とりあえず、あと何冊か読んでみることにしましょう。
正直、ぼくはこの辺のジャンルにとても弱いので、もし詳しい人がいたらお勧めとかを教えて下さい。宗形君とかが詳しいのでしょうね。多分。

「計画?人間の計画はあてにならん。みんな計画外だ。俺の目も、お前がここに来たのも、こうしているのもな。」(盲目のインディアンが、ボブ・クーパに)
リブ・タイラーが目当てで観たのですが、観終えたときにはそんなことはすっかり忘れていました。友達が「結構面白いよ」と言っていたのですが、結構どころか最高に面白かったです。始まりから終わりまで、全部面白かった。オリーバー・ストーン監督の作品って、正直あまり好きではないのですが、この映画は別です。とても満足してしまいました。けど、ビデオレンタルでこのビデオをリブ・タイラーの棚に置くのはやめて欲しい。五秒ぐらいしか出てないじゃん。
あまりにもストーリーが良かったので、この映画の原作は一体誰なのだろうと思いクレジットを観たところ、ジョン・リドリーという人で、一応肩書きは映画監督ということらしいのですが、実際に何を監督したのかは不明です。脚本なんかは結構書いているらしく、「U・ターン」の脚本も担当しているし、『スリー・キングス』の原案なんかも彼の作品だそうです。
それで、早速『U・ターン』の原作である『Stray Dogs』の邦訳『ネヴァダの犬たち』を古本屋で探して購入、読んでみたのですが、これが死ぬほどおもしろい。最初に『U・ターン』の脚本を書いて、その後にこの小説を書いたということなので、内容は映画にかなり忠実ですが、映画を観ないでこの小説を読んだとしても、十分に面白いと思います。
で、ストーリーですが、ぼくが説明するよりも、本のディスクリプションを読んだほうが分かりやすいと思いますので、下にそのまま引用します。
「この世には神も、仏も、ロン・ハバードもいないのか!?」とジョンは天を仰いだ。愛車’64年型マスタングがネヴァダ砂漠でオーバーヒートしてしまったのだ。明日の午前0時までに、ラスベガスのギャングのところまで借金1万3千ドルを返しに行かなければならないというのに。身から出たサビ、八百長カードゲームでこしらえた借りだが、返さないことにはこの身が危ない。マスタングをなだめすかし、ようやくちっぽけな町、シエラにたどりついたが…熱さにさらされた町の住人は、どこかが変だ。鄙には稀な美貌の人妻グレースはいきなりジョンを誘惑し、冷たい飲み物を飲みに入った店では強盗に大事な1万3千ドルを奪われ、そのためにマスタングの修理代も払えず町を出ることすらできない。ギャングとの約束の時間は刻々と近づいてくる。そして、ジョンの運命は際限なく悪い方へ転がり落ちていった。『ネヴァダの犬たち』の巻末の解説によると、この小説は「新しいパルプ・ノアール(B級暗黒もの)」と呼ばれているそうです。「パルプ・ノアール」というのは、「ザラ紙に刷られた大衆雑誌(パルプ)の持つ雰囲気を、トンプスンらクライム・ノヴェル作家によるペイパーバック作品の暗黒(ノワール)性と重ね合わせた」作風のことです。
「ノアール(暗黒)」という言葉に関しては、山田宏一さんが詳しく説明しているので、孫引用になってしまいますが、下に引用します。
山田宏一『映画的なあまりに映画的な美女と犯罪』よりクライム・フィクションというジャンルは、ジェイムズ・エルロイぐらいしかきちんと読んだことがないのですが、なんだかとてもおもしろそうです。どうしてもタランティーノを思い出してしまいますけど。
<フィルム・ノワール>とは何かー「アメリカ映画序説」の著者スティーブン・C・アーリーによれば、「戦前のギャング映画に飽き始めた大衆を惹きつけるために、ハリウッドが1940年代に、暗いペシミズムのムードで味付けして生み出した新しいタイプの犯罪スリラー」である。それを<フィルム・ノワール>と呼んだのは、(中略)<アメリカン・スタイル>に魅惑されたフランスの映画狂たちで、1945年にマルセル・デュアメル監修でパリのガリマール社から発売されるやブームを巻き起こした有名な犯罪推理小説叢書<セリ・ノワール>(暗黒叢書)もあやかって、暗黒(ノワール)の形容がアメリカの犯罪映画に対するオマージュとして付されたのであった。
(「女の犯罪、女の活劇ー<フィルム・ノワール>断章」)
ジョン・リドリーのその他の作品はというと、借金地獄の元脚本家志望ジェフティ・キトリッジが、どん底から這い出て真実の愛を見つけようとペテン計画を企てる『Love is Rocket(邦題:愛はいかがわしく)』、ジャッキー・マンという黒人のコメディアンが、人種差別の吹き荒れる公民権運動の揺籃期に、ハリウッドでスターダムへとのし上がる過程を描いた『A Conversation with the Mann: A Novel』、何をやっても長続きしないパリス・スコットという青年が、自殺したロックスターのテープと、盗んだドラッグから得たお金をもとに夢をかなえようとする『Everybody Smokes In Hell』などなど。さらに、来月には新作『The Drift』なんかも出るみたいです。
とりあえず、あと何冊か読んでみることにしましょう。
正直、ぼくはこの辺のジャンルにとても弱いので、もし詳しい人がいたらお勧めとかを教えて下さい。宗形君とかが詳しいのでしょうね。多分。

「計画?人間の計画はあてにならん。みんな計画外だ。俺の目も、お前がここに来たのも、こうしているのもな。」(盲目のインディアンが、ボブ・クーパに)
02年07月24日(水)
あるお友達から、暇だから遊びましょうと電話が来たので、『ルーブルの怪人』を観に行ってきました。
久しぶりに映画館で気持ち良く眠りました。
何となく消化不良で、同じソフィー・マルソーが出演しているミケランジェロ・アントニオーニ監督の『愛のめぐりあい』をビデオレンタルで借りて観ました。
この映画は、映画監督である主人公(ジョン・マルコビッチ)を軸として、複数の愛の不毛をオムニバス風に描いている作品なのですが、いやあ、何度観ても素晴らしい。
男性が女性の肌に触れないようにして、体の線を撫でるようにぎりぎりのところをたどっていくシーンがあるのですが、そのシーンがとても良かったので、一度個人的なセックスでまねをしてみたことがあるのですが、僕がやるとただのこっけいな変態になってしまいました。映画ではとても美しいのに。
僕の一番好きなエピソードは、映画の中で一番最後に登場する、以下のようなお話です。
ある若者(ヴァンサン・ペレーズ)が、たまたま見かけた一人の女性(イレーヌ・ジャコブ)に一目ぼれをする。さりげなく話しかけると、女性はこれからミサへ行くという。男性は、なんとか女性と懇意になりたくて、歩きながらいろいろな話をするが、二人の会話はいまいちかみ合わない。二人はそのまま教会にはいる。若者は、女性から少し離れた席に座る。
教会を出て後、見失った女性を再び発見した若者は、噴水のところで話をする。「”生”が怖い」という女性に対し、「僕らにあるのは人生だけ。生しか確かなものはない。この世で生きて、あの世では死人。この世では笑えても、死人の笑いは無視される。」と若者は語る。女性は男性を見つめて一言、「その考えは意味がないわ。」と言って歩き出す。
徐々に心を開いていく彼女に、若者はどんどん惹かれていく。雨の中を二人で歩き、彼女のマンションに到着し、部屋の前まで行く。彼女が部屋に入ろうとする直前に、若者は「あしたもあえるかな」と聞く。彼女は暫し沈黙し、「あした、修道院に入るの」と言い、ドアを閉める。
この最後の部屋の前のシーンの感動とかは、それまでの二人の会話を聞いていないといまいち伝わりにくいと思いますが、僕は初めてこの映画を観たとき、この彼女の最後の一言に完全にやられてしまって、映画が終了したあとも、しばらく席から立ち上がることができませんでした。今回もやられてしまったので、多分十年後に観てもやられてしまうと思います。
このエピソードの中に、教会で祈りを捧げている女性を見て、若者が感動をしているシーンがあります。祈りを捧げるイレーヌ・ジャコブの美しさは、映画を観てもらうしかないのですが、この時の若者の心情を、原作では以下のように表現しています。
この小説を購入したのは、映画が公開した当時なので、もう七年ぐらい前になります。当時、映画に感動して小説を購入したのですが、小説の方はさっぱりわけがわかりませんでした。今回、何年かぶりに小説を開いてみたのですが、以前よりは面白かったけれど、それでもまだこの小説の「良さ」がわかっていません。
僕はまだまだ若造です。あと何年したらわかるようになるのかな。

「偉大な芸術家の作品をコピーすることは、芸術家の動きをなぞることだ。彼とまったく同じ動作をするチャンスがある。それが悪いか?天才の動作を再現するんだぞ。自分の絵なんか描くより、僕はずっと満足できる。」(通りすがりの夫人に、描いている絵を「セザンヌのコピー」と揶揄されたアマチュア画家が)
久しぶりに映画館で気持ち良く眠りました。
何となく消化不良で、同じソフィー・マルソーが出演しているミケランジェロ・アントニオーニ監督の『愛のめぐりあい』をビデオレンタルで借りて観ました。
この映画は、映画監督である主人公(ジョン・マルコビッチ)を軸として、複数の愛の不毛をオムニバス風に描いている作品なのですが、いやあ、何度観ても素晴らしい。
男性が女性の肌に触れないようにして、体の線を撫でるようにぎりぎりのところをたどっていくシーンがあるのですが、そのシーンがとても良かったので、一度個人的なセックスでまねをしてみたことがあるのですが、僕がやるとただのこっけいな変態になってしまいました。映画ではとても美しいのに。
僕の一番好きなエピソードは、映画の中で一番最後に登場する、以下のようなお話です。
ある若者(ヴァンサン・ペレーズ)が、たまたま見かけた一人の女性(イレーヌ・ジャコブ)に一目ぼれをする。さりげなく話しかけると、女性はこれからミサへ行くという。男性は、なんとか女性と懇意になりたくて、歩きながらいろいろな話をするが、二人の会話はいまいちかみ合わない。二人はそのまま教会にはいる。若者は、女性から少し離れた席に座る。
教会を出て後、見失った女性を再び発見した若者は、噴水のところで話をする。「”生”が怖い」という女性に対し、「僕らにあるのは人生だけ。生しか確かなものはない。この世で生きて、あの世では死人。この世では笑えても、死人の笑いは無視される。」と若者は語る。女性は男性を見つめて一言、「その考えは意味がないわ。」と言って歩き出す。
徐々に心を開いていく彼女に、若者はどんどん惹かれていく。雨の中を二人で歩き、彼女のマンションに到着し、部屋の前まで行く。彼女が部屋に入ろうとする直前に、若者は「あしたもあえるかな」と聞く。彼女は暫し沈黙し、「あした、修道院に入るの」と言い、ドアを閉める。
この最後の部屋の前のシーンの感動とかは、それまでの二人の会話を聞いていないといまいち伝わりにくいと思いますが、僕は初めてこの映画を観たとき、この彼女の最後の一言に完全にやられてしまって、映画が終了したあとも、しばらく席から立ち上がることができませんでした。今回もやられてしまったので、多分十年後に観てもやられてしまうと思います。
このエピソードの中に、教会で祈りを捧げている女性を見て、若者が感動をしているシーンがあります。祈りを捧げるイレーヌ・ジャコブの美しさは、映画を観てもらうしかないのですが、この時の若者の心情を、原作では以下のように表現しています。
それでもその長いうつむきに沈んだ彼女の姿は、彼の心をつかんだ。血が血管を押し上げ始めているのを感じる。以前にも、いくらか麻薬をやった身体で女の子たちを前にした時に、これと同じ、彼女たちと結ばれ、彼女たちと一つになりたいという衝動と、それとともに性交を通じて自己の存在の不思議で充実した意識を抱いたことがあった。情欲のない、しかしきわめて強烈な至福感である。上記で引用したのは、アントニオーニが書いた『愛のめぐりあい』という小説の中の章のひとつで、こちらも映画と同様に、短い断片を集めたオムニバスの形式で構成されています。映画『愛のめぐりあい』は、この小説の中から抜き出したいくつかの短編を映像にしたものです。
この小説を購入したのは、映画が公開した当時なので、もう七年ぐらい前になります。当時、映画に感動して小説を購入したのですが、小説の方はさっぱりわけがわかりませんでした。今回、何年かぶりに小説を開いてみたのですが、以前よりは面白かったけれど、それでもまだこの小説の「良さ」がわかっていません。
僕はまだまだ若造です。あと何年したらわかるようになるのかな。

「偉大な芸術家の作品をコピーすることは、芸術家の動きをなぞることだ。彼とまったく同じ動作をするチャンスがある。それが悪いか?天才の動作を再現するんだぞ。自分の絵なんか描くより、僕はずっと満足できる。」(通りすがりの夫人に、描いている絵を「セザンヌのコピー」と揶揄されたアマチュア画家が)
02年07月25日(木)
古本屋で山折哲雄さんの『神秘体験』という本を50円で買いました。
「神秘体験」と聞くと、どうしてもオカルト的に考えてしまいがちですが、この本はそういった類のものではなく、文化人類学的に「神秘体験」を検証したものです。最後まで読んでも、さしたる結論に達するわけではないのですが、歴史に登場する神秘体験や、文学や音楽における神秘体験などエピソードが満載で、とても興味深いものでした。
山折哲雄は、「神秘体験」の種類を「空間」「エクスタシーとカタルシス」「音」「聖なるキノコ(ドラッグ)」「死」などいくつかの要素に章分けしています。そのなかで、各要素における神秘体験のエピソードを紹介していきます。
たとえば「空間」の章では、著者のチベットでの経験から初めて、風土と自然による精神状態への影響を説き、ユダヤ教やキリスト教が砂漠で誕生したことに触れています。また、「エクスタシーとカタルシス」では、マルチン・ルターが肛門の汚れたところに悪魔が姿を現すと信じていたことや、ラブレーの『ガルガンチュア物語』ではうんこに「自然的な宇宙」を見いだしていたことに言及しています。
また、「神秘主義の諸潮流」という章では、各宗教(キリスト教、イスラム教、グノーシス主義、ユダヤ教、インド思想、チベット密教などなど)による神秘体験の違いを説明しています。
この本では「神秘体験」の定義を「神もしくは超越的世界との直接交渉」と定めています。神秘体験から神という概念が生まれたのか?神という概念から神秘体験が生まれのか?ということは難しい問題ですが、この本のなかでは、以下のように書かれています。
宇宙遊泳中の彼を撮影しようとしたとき、突然カメラが故障してしまい、パートナーがそれを修理している間、彼はひとりで宇宙の完全な静寂の中に取り残されました。すべての音が遮断され、すべての視野は際限がなく、彼自身の肉体は地に足をつけるでもなく、空に飛んでいくでもなく、ただそこに浮かんでいました。それは、ほんの五分程度の時間でした。そして、その五分間に彼は突然思います。
(このラッセル・シュワイカートさんの詳しい話は、『地球交響曲』のほかにも、立花隆著『宇宙からの帰還』などでも読むことができます。っていうか、あっちこっちで同じ話をしているので、この人。)
『神秘体験』では、「聖なるキノコ」の章で、ベニテングダケからLSDまでの幻覚剤と神秘体験についても言及しています。
ベニテングダケは、古代インドにおいてシャーマンがトランス状態になるために飲むお酒「ソーマ」に使われていました。このような幻覚作用のあるきのこに関しては、世界中の宗教に記録が残っています。たとえば、マヤ文明では「神の肉」と呼ばれ呪術師に珍重されていたし、インディアンのシャーマンなんかも幻覚作用のあるマッシュルームを使用していました。
おもしろいのは、民族的に「キノコ好き」と「キノコ嫌い」があって、ロシアの民族や南ヨーロッパの人々は「キノコ好き」で、古代ギリシア人、ケルト人。スカンジナビア人、アングロ・サクソン民族は「キノコ嫌い」だそうです。
「聖なるキノコ」の章では、LSDに関して、その発見者であるアルベルト・ホフマンの発見に言及し、以下のように書いてあります。
最近Salon.comで書評がアップされた『Zig Zag Zen』という研究書があります。
この本は、仏教と幻覚剤の関係の論考集のようなものでして、仏教も幻覚剤も「the liberation of the mind(精神の開放)」と目的は同じなのに、何で幻覚剤は影に隠れているのさ、そもそも仏教と幻覚剤の関係ってなんなの?みたいなことを、いろいろな方々が真面目に論じている本です。
この本の序文で、スティーブン・バッチローは以下のように書いています。
仏教の側面からではありませんが、日本でも最近『サイケデリックスと文化—臨床とフィールドから』が出版されてます。この本もとても興味深いのですが、しばし後回しに。
ところで、「宗教と幻覚剤による神秘体験」というテーマからは少し離れますが、精神と物質(宗教と科学)に関しては、HotWiredに次のような記事が掲載されていました。
■チベット仏教と神経科学の融合は可能か
西洋科学(特に脳科学や精神科学など)がチベット式東洋の瞑想法と融合すれば、これまでの西洋医学では解決できなかった問題が解決し、さらなり発展が望めるのではないか、と言う記事です。
チベットに限らず、東洋の内観法と西洋的科学は、これまではある意味で対立とまではいかなくても、それに近い状態にあったと言えます。歴史的にそれぞれの立場を概観すると、東洋は精神的なアプローチをとり、西洋は物質的なアプローチをとってきました。2002年6月に行われた『科学と精神についての国際会議(a Science and the Mind conference)』では、そのような過去をふまえて、今後の科学と東洋的瞑想法のあり方を議論しています。この会議には、ダライ・ラマも出席しました。
このダライラマの言葉を会議に出席していた西洋の科学者たちがどのように受け止めているのかにとても興味があるのですが、記事の中ではその辺にはあまり触れていません。記事は、ペティグリュー教授の以下の言葉で締めくくられています。
まあ、このあたりのことはまたそのうちに。

「神秘体験」と聞くと、どうしてもオカルト的に考えてしまいがちですが、この本はそういった類のものではなく、文化人類学的に「神秘体験」を検証したものです。最後まで読んでも、さしたる結論に達するわけではないのですが、歴史に登場する神秘体験や、文学や音楽における神秘体験などエピソードが満載で、とても興味深いものでした。
山折哲雄は、「神秘体験」の種類を「空間」「エクスタシーとカタルシス」「音」「聖なるキノコ(ドラッグ)」「死」などいくつかの要素に章分けしています。そのなかで、各要素における神秘体験のエピソードを紹介していきます。
たとえば「空間」の章では、著者のチベットでの経験から初めて、風土と自然による精神状態への影響を説き、ユダヤ教やキリスト教が砂漠で誕生したことに触れています。また、「エクスタシーとカタルシス」では、マルチン・ルターが肛門の汚れたところに悪魔が姿を現すと信じていたことや、ラブレーの『ガルガンチュア物語』ではうんこに「自然的な宇宙」を見いだしていたことに言及しています。
また、「神秘主義の諸潮流」という章では、各宗教(キリスト教、イスラム教、グノーシス主義、ユダヤ教、インド思想、チベット密教などなど)による神秘体験の違いを説明しています。
この本では「神秘体験」の定義を「神もしくは超越的世界との直接交渉」と定めています。神秘体験から神という概念が生まれたのか?神という概念から神秘体験が生まれのか?ということは難しい問題ですが、この本のなかでは、以下のように書かれています。
神秘体験はイメージの所産であるといってもいい。神との精神的合一という体験も、「神」というイメージを回路にしてはじめて可能になる体験であるといわなければならない。それらの神秘体験を、哲学的、神学的に人間存在に意味づけをするものとして「思想的な言語」で語られると、それは「神秘主義」になります。
神秘主義は英語でmysticismという。これは一口にいって、神との直接的な交流や神的な合一を説く宗教思想である。自己が、神のような超越的存在や宇宙の根源と一体になる内面的な体験をえようとする立場であるといってもよい。そのような体験をラテン語では、ウニオ・ミスティカunio mystica(神秘的合一)といった。そのウニオ・ミスティカをうるために、純粋な瞑想、禁欲による特殊な心身訓練など、さまざまな実践形態が生み出された。たとえば、法皇に異端者と宣告されたキリスト教神学者であるエックスハルト(1260?〜1327)は以下のように言っています。
自己の内部に神の子が出現するのだ。自己の根底をつき破って神がみずからを開示してくるのであって、そのとき自我は根元的に滅却する。そしてその自己を開示する神の内奥は、「無」そのものなのだ。自己の根底がつき破られるこの「突破」の神秘体験は、「無」につつまれている。そこに人間における真の生の弁証法が存在するのではないか。この本を読んだ時にすぐに思い出したのが、『地球交響曲(ガイヤシンフォニー)』の第一番に出演していたラッセル・シュワイカートさんの話です。アポロ9号の乗組員だったラッセル・シュワイカートさんは、月着陸船のテスト中に次のような経験をしています。
宇宙遊泳中の彼を撮影しようとしたとき、突然カメラが故障してしまい、パートナーがそれを修理している間、彼はひとりで宇宙の完全な静寂の中に取り残されました。すべての音が遮断され、すべての視野は際限がなく、彼自身の肉体は地に足をつけるでもなく、空に飛んでいくでもなく、ただそこに浮かんでいました。それは、ほんの五分程度の時間でした。そして、その五分間に彼は突然思います。
ここにいるのは私であって私でなく、眼下に拡がる地球の全ての生命、そして地球そのものをも含めた我々なんだここで彼が感じたのは、宗教における神秘体験である「神聖なるもの、神的なものとの合一」ではなくて、むしろウパニシャッド哲学における「梵我一如」に近いもの、自己(我)と宇宙(梵)の融合に近いものでしょう。また、さらに言うなれば、『みんなのトニオちゃん』の「アルバイト」の章で、スネ郎が五億年の時を考え抜いて悟りを開き、空間に調和したということに近いものがあると思います。いずれにしても、シュワイカートさんの経験した神秘体験は「超越的なものとの合一」という意味で、人類が普遍的に経験してきた神秘体験と、なにも変わるところがありません。
(このラッセル・シュワイカートさんの詳しい話は、『地球交響曲』のほかにも、立花隆著『宇宙からの帰還』などでも読むことができます。っていうか、あっちこっちで同じ話をしているので、この人。)
『神秘体験』では、「聖なるキノコ」の章で、ベニテングダケからLSDまでの幻覚剤と神秘体験についても言及しています。
ベニテングダケは、古代インドにおいてシャーマンがトランス状態になるために飲むお酒「ソーマ」に使われていました。このような幻覚作用のあるきのこに関しては、世界中の宗教に記録が残っています。たとえば、マヤ文明では「神の肉」と呼ばれ呪術師に珍重されていたし、インディアンのシャーマンなんかも幻覚作用のあるマッシュルームを使用していました。
おもしろいのは、民族的に「キノコ好き」と「キノコ嫌い」があって、ロシアの民族や南ヨーロッパの人々は「キノコ好き」で、古代ギリシア人、ケルト人。スカンジナビア人、アングロ・サクソン民族は「キノコ嫌い」だそうです。
「聖なるキノコ」の章では、LSDに関して、その発見者であるアルベルト・ホフマンの発見に言及し、以下のように書いてあります。
LSDの発見による衝撃的な波紋は、しだいに各方面にひろがっていった。なかでも驚異とされたのは、この特殊な幻覚剤を飲むと、正常な人間のうちにも終末論的な錯乱のヴィジョンや神秘的で宗教的な深い意識がつくりだされるということであった。幻覚剤は、人間の心にたいして増幅効果と触媒効果をおよぼすことがわかったのである。しかもそのような経験の母胎が、正常な人間の無意識領域のなかに存するということまでが明らかにされた。人間の精神の無意識領域には、「終末論的な錯乱のヴィジョンや神秘的で宗教的な深い意識」が存在している、と『神秘体験』には書かれています。僕が今一番興味があるのは、精神とはなにか?意識とはなにか?無意識とはなにか?意識と無意識の差異とはいったい何なのか?ということです。人間の精神は、状況に応じていかなる状態にも変化します。中世時代に、天国が物理的に存在すると考えていた人々と、科学の時代に生きている僕たちとでは、その精神の働きが同じだとはとても思えません。僕は無神論者ではありませんが、人類が語ってきた「神」という概念には疑問を感じる点が多々あります。そのことを詳しく語るには、ぼくの思想はあまりにも未熟過ぎるので控えますが、もしも人類の意識に共通した「終末論的な錯乱のヴィジョンや神秘的で宗教的な深い意識」が存在するとしたら、その意識とはいったい何を意味するのでしょう。もっと煎じ詰めて言えば、人が、そして僕が「考える」ということは、いったいどういうことなのか。幻覚剤を使用しなければ到達できない意識があるとしたら、その意識はいったい何を意味しているのでしょうか。
最近Salon.comで書評がアップされた『Zig Zag Zen』という研究書があります。
この本は、仏教と幻覚剤の関係の論考集のようなものでして、仏教も幻覚剤も「the liberation of the mind(精神の開放)」と目的は同じなのに、何で幻覚剤は影に隠れているのさ、そもそも仏教と幻覚剤の関係ってなんなの?みたいなことを、いろいろな方々が真面目に論じている本です。
この本の序文で、スティーブン・バッチローは以下のように書いています。
1960年代に起こった仏教やその他の東洋的伝統へ引き寄せられた人々のかなりの割合は、(著者も含めて)彼らの宗教的態度に、マリファナやLSDのような、精神に作用を及ぼす薬物の経験が影響していたことは明らかだ。早速Amazonで取り寄せてみたのですが、読むのには相当時間がかかりそうです。読み終えたら、また感想を書きたいと思います。
仏教の側面からではありませんが、日本でも最近『サイケデリックスと文化—臨床とフィールドから』が出版されてます。この本もとても興味深いのですが、しばし後回しに。
ところで、「宗教と幻覚剤による神秘体験」というテーマからは少し離れますが、精神と物質(宗教と科学)に関しては、HotWiredに次のような記事が掲載されていました。
■チベット仏教と神経科学の融合は可能か
西洋科学(特に脳科学や精神科学など)がチベット式東洋の瞑想法と融合すれば、これまでの西洋医学では解決できなかった問題が解決し、さらなり発展が望めるのではないか、と言う記事です。
チベットに限らず、東洋の内観法と西洋的科学は、これまではある意味で対立とまではいかなくても、それに近い状態にあったと言えます。歴史的にそれぞれの立場を概観すると、東洋は精神的なアプローチをとり、西洋は物質的なアプローチをとってきました。2002年6月に行われた『科学と精神についての国際会議(a Science and the Mind conference)』では、そのような過去をふまえて、今後の科学と東洋的瞑想法のあり方を議論しています。この会議には、ダライ・ラマも出席しました。
さまざまな分野で、チベット人が実践してきたことの有効性が続々と明らかになっている。科学がやっと、検証できるだけの高度なテクノロジーを開発したわけだ。会議の中で、「急進的物質主義者を否定した」ことに関しての説明を求められたダライ・ラマは、以下のように述べています。
(中略)
問題は、現代科学が劣っていて、チベット的技法が優れているということではない。ただ、チベット人は経験的観察に基づいた科学的真理を数多く発見してきたということなのだ。
われわれが精神として体験することの本質は、より広い世界、宇宙、また宇宙の起源と進化といった事項に対するわれわれの理解と、直接かつ密接に結びつく言葉で理解しなければならないと私は考えている「われわれが精神として体験することの本質」を言葉で理解する。
このダライラマの言葉を会議に出席していた西洋の科学者たちがどのように受け止めているのかにとても興味があるのですが、記事の中ではその辺にはあまり触れていません。記事は、ペティグリュー教授の以下の言葉で締めくくられています。
われわれがチベット人から学べるものがあるのは明らかだ。薬剤に頼るだけが答えではない。こういった技法から学べるものは確かにある。将来、世界はチベット仏教と科学の融合に向かうだろうこの雑記でぼくが書きたかったのは、LSDのことでも宗教のことでも神様のことでもオカルトのことでも西洋科学と東洋の瞑想法のことでもなくて、人間の「精神」のことです。上の記事では、以下のようなダライラマの言葉を引用しています。
意識や精神について語ろうとすると、概念的に非常に難しい問題になる。この2つを明確に区別することはとても難しい。だが、個人レベルでは、日々の生活で皆実体験としてこの区別をつけているぼくは「意識」ということについてまともな勉強なんてしたこともないし、本を読んだこともありません。ですから、僕が言っていることは、哲学やあるいは心理学などに詳しい人たちから見れば、あまりにも幼稚に思えるかもしれません。そこらへんはごめんなさい。
まあ、このあたりのことはまたそのうちに。

02年07月26日(金)
今週の気になったニュースやサイトを。
■ "Henry Darger: In the Realms of the Unreal" by John M. MacGregor
ヘンリー・ダーガーについては以前にも書きましたが、そのときもちょいと触れたジョン・マガレガーの『Henry Darger: In the Realms of the Unreal』の書評がSalon.comにアップされてます。
■地球の大きさを測ろう!と東京−小樽をチャリンコ走破
「東京から北海道まで自転車で走破し、両地点の緯度を測って地球の大きさを算出する」というプロジェクト。
公式サイトには、こちらから。
ところで、上のニュースでも触れていますが、地球の円周距離を初めて測定したのは、アレキサンドリア(エジプト)の大図書館・ムセイオン館長を務めた科学者エラトステネスだとされています。
ビートルズの曲のタイトルで有名な『The Fool On The Hill』という言葉は、「丘の上の阿呆」という意味で、もともとはエラトステネスやアリストテレス、ガリレオ・ガリレイなどの地球球体説や地動説などを唱えた人たちを揶揄するために使われていた言葉でした。
■Newsweek「ニッポン大好き」
アメリカでの日本文化ブームを特集しています。
アニメ、空手、オタク、禅、芸者、スシ、などなど。
ブームとともに、日本に対する間違った見方もますます増加しております。
この記事がどこまで本当なのかは置いといて、とりあえず鉄割は早めにアメリカ公演を実現すべきであると思うのですが、そこらへんいかが。
■米紙、米国公演のパフィーを酷評
で、酷評しているとされる記事が、下のワシントンポストの記事です。
PUFFY AMIYUMI "An Illustrated History Of Puffy AmiYumi" Bar None
Puffy: Pop With A Japanese Accent
この記事を書いた記者はちょっと勘違いをしているような気がしないでもないですが、それでもここまで大きく取り上げられてすごいですね。
そんで、「意味不明(pure dada)」と評された英訳ですが、Puffyの英語サイトに行けば全部読むことができます。
ちなみに、「これが私の生きる道(That's the way,It is)」は、以下の通り。
■全国毒物食品連絡会
奇妙な味覚の食べ物を調査しているサイトです。なかには、僕の大好きな食べ物も入っていたり。
■邦画ファンが大注目のサイト「JMP」
■一橋大、セクハラ“王様”教授の評判
「教授は『セクハラ万歳!』と連呼していたらしい」「ほおとうなじに舌で『の』の字を書け!との命令を連発」「“短パン”というあだ名で呼ばれていた」
最初この記事を読んだとき、山内が逮捕されたのかと思いました。
それにしても、大学にこんな教授がいたら楽しいだろうな。「おい、短パン!セクハラダンス踊れ!」とか言って。
もし僕の恋人にセクハラしたらぶん殴るけど。
■少年がロバに急所を噛み切られたが…手術で接合に成功
七歳の少年がロバにおちんちんを食いちぎられたそうです。
トラウマ必至。

なんかしかし、この雑記はレイアウトが読みにくいですね。ちょっくら考えよう。
■ "Henry Darger: In the Realms of the Unreal" by John M. MacGregor
ヘンリー・ダーガーについては以前にも書きましたが、そのときもちょいと触れたジョン・マガレガーの『Henry Darger: In the Realms of the Unreal』の書評がSalon.comにアップされてます。
■地球の大きさを測ろう!と東京−小樽をチャリンコ走破
「東京から北海道まで自転車で走破し、両地点の緯度を測って地球の大きさを算出する」というプロジェクト。
公式サイトには、こちらから。
ところで、上のニュースでも触れていますが、地球の円周距離を初めて測定したのは、アレキサンドリア(エジプト)の大図書館・ムセイオン館長を務めた科学者エラトステネスだとされています。
ビートルズの曲のタイトルで有名な『The Fool On The Hill』という言葉は、「丘の上の阿呆」という意味で、もともとはエラトステネスやアリストテレス、ガリレオ・ガリレイなどの地球球体説や地動説などを唱えた人たちを揶揄するために使われていた言葉でした。
But the fool on the hill sees the sun going downこれ、全部通して読むと本当にいい歌詞ですよねえ。大好き。
And the eyes in his head see the world spinning round.
(それでも、丘の上の阿呆は太陽が沈むのを見ると、
彼の両目には、地球がぐるぐるまわっているが見えるのです)
■Newsweek「ニッポン大好き」
アメリカでの日本文化ブームを特集しています。
アニメ、空手、オタク、禅、芸者、スシ、などなど。
ブームとともに、日本に対する間違った見方もますます増加しております。
この記事がどこまで本当なのかは置いといて、とりあえず鉄割は早めにアメリカ公演を実現すべきであると思うのですが、そこらへんいかが。
■米紙、米国公演のパフィーを酷評
で、酷評しているとされる記事が、下のワシントンポストの記事です。
PUFFY AMIYUMI "An Illustrated History Of Puffy AmiYumi" Bar None
Puffy: Pop With A Japanese Accent
この記事を書いた記者はちょっと勘違いをしているような気がしないでもないですが、それでもここまで大きく取り上げられてすごいですね。
そんで、「意味不明(pure dada)」と評された英訳ですが、Puffyの英語サイトに行けば全部読むことができます。
ちなみに、「これが私の生きる道(That's the way,It is)」は、以下の通り。
We are pretty nice these days(近ごろ私たちは いい感じ)どうでもいいけど、このファンサイトが素敵すぎる。似てない!
Sorry but thanks(悪いわね ありがとね)
And keep it going please(これからも よろしくね)
Picking up the best part of the fresh fruit(もぎたての果実の いいところ)
If you keep it that way things will be nice.(そういう事にしておけば これから先も イイ感じ)
■全国毒物食品連絡会
奇妙な味覚の食べ物を調査しているサイトです。なかには、僕の大好きな食べ物も入っていたり。
■邦画ファンが大注目のサイト「JMP」
新聞社出身の大物映画記者らが結集、批評や現場取材リポートに健筆をふるう邦画情報ウェブサイト「JMP」が注目されている。普段はライバル同士の面々だが、良質な批評で、邦画を盛り上げていこうと手を携えている。映画会社もうれしいやら、恐いやら…。「邦画を」と限定ですって。サイトへはこちらから。
■一橋大、セクハラ“王様”教授の評判
「教授は『セクハラ万歳!』と連呼していたらしい」「ほおとうなじに舌で『の』の字を書け!との命令を連発」「“短パン”というあだ名で呼ばれていた」
最初この記事を読んだとき、山内が逮捕されたのかと思いました。
それにしても、大学にこんな教授がいたら楽しいだろうな。「おい、短パン!セクハラダンス踊れ!」とか言って。
もし僕の恋人にセクハラしたらぶん殴るけど。
■少年がロバに急所を噛み切られたが…手術で接合に成功
七歳の少年がロバにおちんちんを食いちぎられたそうです。
トラウマ必至。

なんかしかし、この雑記はレイアウトが読みにくいですね。ちょっくら考えよう。
02年07月27日(土)
さて、素敵な大人になることを夢見て、日夜精進を続けているぼくではありますが、素敵な大人になるためにはやはり『サライ』は必読でしょうということで、毎号かかさず購読しております。
その中に「セイコーの『ブライツ』と共に文化人ゆかりの地を訪ねる」という、いまいち趣旨の良く分からない連載があるのですが、今回の号で取り上げているのが、池波正太郎ゆかりの料亭旅館でもあった「京亭」でございます。
鮎料理で名高い料亭で、池波正太郎も足繁く通ったらしく、値段はちょっと張るものの、館の雰囲気がとても素敵です。
これは行かねばなるまいと、さっそく食通の奥村君に電話をかけて話をしたところ、ぜひ行きたい、今すぐ行きたいとえらい張り切りようで、まあ落ち着きなさいと僕の方がなだめる始末、しまいには、おまえはいつもそうだ、口先だけだ、などと口汚く罵られました。
そういうわけで近いうちに食事に行ってこようかと思っております。高いんだけどね。

その中に「セイコーの『ブライツ』と共に文化人ゆかりの地を訪ねる」という、いまいち趣旨の良く分からない連載があるのですが、今回の号で取り上げているのが、池波正太郎ゆかりの料亭旅館でもあった「京亭」でございます。
鮎料理で名高い料亭で、池波正太郎も足繁く通ったらしく、値段はちょっと張るものの、館の雰囲気がとても素敵です。
甲賀忍者を主人公とする連載小説の構想を練るべく、この京亭を訪れた池波正太郎。鮎料理を存分に賞味し、さらに《縁側に寝そべっていると、時がたつのを忘れてしまった》ほどに、くつろぐことができたという。そのせいか、当初死ぬ予定だった甲賀忍者は、生き永らえることになったとか。などというほのぼのとしたエピソードも語り継がれております。
これは行かねばなるまいと、さっそく食通の奥村君に電話をかけて話をしたところ、ぜひ行きたい、今すぐ行きたいとえらい張り切りようで、まあ落ち着きなさいと僕の方がなだめる始末、しまいには、おまえはいつもそうだ、口先だけだ、などと口汚く罵られました。
そういうわけで近いうちに食事に行ってこようかと思っております。高いんだけどね。

02年07月28日(日)
刺激のある生活を送りたくて、オリバー・ヒルシュビーゲルの『es[エス]』を観てきました。
ドイツ映画は『ラン・ローラ・ラン』以来だな、と思いながら観ていたら、いきなり『ラン・ローラ・ラン』に出演していたモーリッツ・ブライプトロイが出てきたのでびっくり。『ラン・ローラ・ラン』の印象があまり良くなかったので、ちょっぴり不安になりました。
けれども、そんなことはすぐに忘れて映画に集中してしまいました。もうね、映画を観てこんなに心拍数が上がったのはえらい久しぶりですよ。心臓がばくばく鼓動していました。本当に怖かった。つっこみたいところも多々ありますが、ここまでどきどきさせてくれれば文句はありません。
さて、映画のストーリーですが
実験の目的は、「正常な」人間の心理が、ある特定の状況下(この場合は抑圧する側(看守)と抵抗する側(囚人))に置かれた場合に、どのように変化していくのかを調査するというもの。当初は和やかな雰囲気で進行していた実験も、時間の経過とともに被験者達の精神状態が徐々に変化し、学者達の予想をはるかに越えた展開へと発展していきます。
ストーリは、オフィシャルサイトでも読むことができますが、このサイトの方が詳しいですね。
この映画の原作は、マリオ・ジョルダーノの『ブラックボックス』というフィクション小説で、1971年にスタンフォード大学で実際に行われた実験を基にデフォルメして書かれた作品です。このスタンフォード大学の心理学科が行なった実験は、最終的な結果こそ『es[エス]』と異なりますが、そこに行くまでの過程はほぼ同様で、学生を中心に集められた22人の被験者たちが、囚人と看守のグループに分けられ、『es[エス]』と全く同じルールで同じような環境のもと二週間を過ごし、その精神状態を観察するというものです。
このサイトを読むと、その実験で被験者達に起こったことが、『es[エス]』の登場人物たちに起こったことと酷似していることが分かります。
結局実験は、囚人役の被験者達の精神状態の悪化から、七日で中止となり、それ以降この実験は禁止されました。もしも七日以上実験が続けられていたら、あるいは『es[エス]』のラストと同じことが起こったかもしれません。
このスタンフォード大学の実験の様子は、Webとビデオで公開されています。なかなか衝撃的ですよ。
■Stanford Prison Experiment
『es[エス]』のサイトでも言及していますが、スタンフォード大学の実験と同様に、心理学上で有名な「アイヒマン実験」というものがあります。アイヒマンとは、ユダヤ人の無差別大量虐殺を事務的に処理していった、ナチスの有能な官吏の名前です。
アイヒマンは戦後の裁判で、「私はただ上官の命令に従っただけだ」と主張しました。彼自身の思想や、善悪の感情に基づいて行なった行為ではないと弁明したのです。
「アイヒマン実験」は、「正常な」人間が如何にたやすく善悪の判断無しに、「状況の力」に服従するかを調べる実験でした。ただし、被験者達にはその実験の目的は伝えられていません。彼らには「罰を与えることによって、生徒の学習能力があがるかどうか」を調べるための実験だと伝えられています。
最初に、被験者をそれぞれ実験者、教師、生徒という三人に役割します。実験者の役は実際の学者が担当し、教師役と生徒役にはそれぞれ一般の被験者に担当してもらいます。
まず、教師役が生徒に問題を出します。生徒が問題を間違えると、教師は電流を流します。流される電気の量は徐々に増やされていきます。
生徒役の被験者は、電気が流されると大声で叫びます。実際には電気は流れていないのですが、そのことは教師役には伝えられていません。生徒役が質問の答えを間違えるたびに、電流のレベルはあがっていき、それに合わせて生徒役の叫び声も激しくなっていきます。
教師役は、電気が実際に流れていると思っているので、叫び声を聞くと電気を流すことを躊躇します。しかしすぐに隣にいる学者が「大丈夫です、電気を流して下さい。」「そうすることが必要なのです。」「迷うことはありません。」などと、電気を流すことを促します。
実験は、教師役40人中、電気を流すことをやめた人は0人という結果に終わりました。教師役全員が、実験者に促されるままに生徒に電気を流し続けたのです。実験終了後、教師役の被験者にこの実験の真意を伝えると、被験者達は口々に「私はただ実験者の命令に従っただけだ」「実験だから、言う通りにしないといけないと思った」などと弁解をしました。
僕はこの実験のビデオを実際に観たことがあるのですが、教師役の被験者達は躊躇しながらも電気を流し続け、生徒役が悲鳴を上げると動揺のためか笑っている人さえいました。「これは実験だから」という考えが根底にあったために安心していたということも含めて、「状況の力」の恐ろしさ、その力によって、普通の人間が個人の善悪の価値観を越えた行動を起こしてしまうことの恐ろしさを強く感じました。もちろん、ぼくという個人も含めて。
この「アイヒマン実験」に関しては、S・ミルグラムの『服従の心理(アイヒマン実験)』という研究書に詳しく書かれています。

どうにもこうにも、より良く生きるということは難しいものです。
ドイツ映画は『ラン・ローラ・ラン』以来だな、と思いながら観ていたら、いきなり『ラン・ローラ・ラン』に出演していたモーリッツ・ブライプトロイが出てきたのでびっくり。『ラン・ローラ・ラン』の印象があまり良くなかったので、ちょっぴり不安になりました。
けれども、そんなことはすぐに忘れて映画に集中してしまいました。もうね、映画を観てこんなに心拍数が上がったのはえらい久しぶりですよ。心臓がばくばく鼓動していました。本当に怖かった。つっこみたいところも多々ありますが、ここまでどきどきさせてくれれば文句はありません。
さて、映画のストーリーですが
「被験者求む。模擬刑務所で2週間の心理テスト。報酬は4000マルク。」新聞に掲載された「被験者求む」の広告に集まってきた24人の男性たちが、実験という名のもとに、看守と囚人というふたつのグループに分けられて、二週間を刑務所と同じ環境で生活をすることになりました。
始まりは、大学心理学部が出した小さな新聞広告だった…。ある日、その募集記事に目を留めたオレは、この実験に参加して詳しいレポートを書き、記者として復活を果 たそうと考えた。
実験の目的は、「正常な」人間の心理が、ある特定の状況下(この場合は抑圧する側(看守)と抵抗する側(囚人))に置かれた場合に、どのように変化していくのかを調査するというもの。当初は和やかな雰囲気で進行していた実験も、時間の経過とともに被験者達の精神状態が徐々に変化し、学者達の予想をはるかに越えた展開へと発展していきます。
ストーリは、オフィシャルサイトでも読むことができますが、このサイトの方が詳しいですね。
この映画の原作は、マリオ・ジョルダーノの『ブラックボックス』というフィクション小説で、1971年にスタンフォード大学で実際に行われた実験を基にデフォルメして書かれた作品です。このスタンフォード大学の心理学科が行なった実験は、最終的な結果こそ『es[エス]』と異なりますが、そこに行くまでの過程はほぼ同様で、学生を中心に集められた22人の被験者たちが、囚人と看守のグループに分けられ、『es[エス]』と全く同じルールで同じような環境のもと二週間を過ごし、その精神状態を観察するというものです。
このサイトを読むと、その実験で被験者達に起こったことが、『es[エス]』の登場人物たちに起こったことと酷似していることが分かります。
結局実験は、囚人役の被験者達の精神状態の悪化から、七日で中止となり、それ以降この実験は禁止されました。もしも七日以上実験が続けられていたら、あるいは『es[エス]』のラストと同じことが起こったかもしれません。
このスタンフォード大学の実験の様子は、Webとビデオで公開されています。なかなか衝撃的ですよ。
■Stanford Prison Experiment
『es[エス]』のサイトでも言及していますが、スタンフォード大学の実験と同様に、心理学上で有名な「アイヒマン実験」というものがあります。アイヒマンとは、ユダヤ人の無差別大量虐殺を事務的に処理していった、ナチスの有能な官吏の名前です。
アイヒマンは戦後の裁判で、「私はただ上官の命令に従っただけだ」と主張しました。彼自身の思想や、善悪の感情に基づいて行なった行為ではないと弁明したのです。
「アイヒマン実験」は、「正常な」人間が如何にたやすく善悪の判断無しに、「状況の力」に服従するかを調べる実験でした。ただし、被験者達にはその実験の目的は伝えられていません。彼らには「罰を与えることによって、生徒の学習能力があがるかどうか」を調べるための実験だと伝えられています。
最初に、被験者をそれぞれ実験者、教師、生徒という三人に役割します。実験者の役は実際の学者が担当し、教師役と生徒役にはそれぞれ一般の被験者に担当してもらいます。
まず、教師役が生徒に問題を出します。生徒が問題を間違えると、教師は電流を流します。流される電気の量は徐々に増やされていきます。
生徒役の被験者は、電気が流されると大声で叫びます。実際には電気は流れていないのですが、そのことは教師役には伝えられていません。生徒役が質問の答えを間違えるたびに、電流のレベルはあがっていき、それに合わせて生徒役の叫び声も激しくなっていきます。
教師役は、電気が実際に流れていると思っているので、叫び声を聞くと電気を流すことを躊躇します。しかしすぐに隣にいる学者が「大丈夫です、電気を流して下さい。」「そうすることが必要なのです。」「迷うことはありません。」などと、電気を流すことを促します。
実験は、教師役40人中、電気を流すことをやめた人は0人という結果に終わりました。教師役全員が、実験者に促されるままに生徒に電気を流し続けたのです。実験終了後、教師役の被験者にこの実験の真意を伝えると、被験者達は口々に「私はただ実験者の命令に従っただけだ」「実験だから、言う通りにしないといけないと思った」などと弁解をしました。
僕はこの実験のビデオを実際に観たことがあるのですが、教師役の被験者達は躊躇しながらも電気を流し続け、生徒役が悲鳴を上げると動揺のためか笑っている人さえいました。「これは実験だから」という考えが根底にあったために安心していたということも含めて、「状況の力」の恐ろしさ、その力によって、普通の人間が個人の善悪の価値観を越えた行動を起こしてしまうことの恐ろしさを強く感じました。もちろん、ぼくという個人も含めて。
この「アイヒマン実験」に関しては、S・ミルグラムの『服従の心理(アイヒマン実験)』という研究書に詳しく書かれています。

どうにもこうにも、より良く生きるということは難しいものです。
02年07月29日(月)
本屋をぶらぶらして雑誌を物色していたところ、『40's!』という雑誌が創刊しているのを見つけました。
「『普通』が見えてくる日記マガジン」という副題のついたこの雑誌は、40代前後の一般の人々(この雑誌では市井の人々という言い方をしていますが)の2002年3月の日記だけで構成されています。
日記を書いている方々の職業は、大学教授からそば職人までさまざまです。それぞれの日記の頭には、年齢や家族構成、職業、年収、尊敬する人など、執筆した人のプロフィールが簡単に書かれています。書いてある内容は当然のことながら人それぞれ異なり、休日に「なぜ、フランスはルイジアナをアメリカに売ったのか?」という息子のレポートを手伝っている大学教授もいれば、連休を「地獄」と表現するギタリストもいるし、毎日何もしないで思索に勤しんでいる無職の人もいれば、テレビを観ても映画を観て文句ばかり書いている人もいます。
単なる個人の日記の寄せ集めと言ってしまえばそれまでなのですが、これが読み始めるとなかなか面白い。「平凡な人生なんて存在しない」という言葉がありますが、まさにその通り。日記によっては読んでいるだけでむかついてくるものもありますが、逆に癒されてしまうものもあります。
たとえば、地域の生活保護の担当をしているある女性は、90歳の男性の家に訪問したときのことを書いています。以前にも訪れたことのある家であるにもかかわらず、この90歳の男性は生活保護担当の女性が家に上がることを執拗に拒みます。女性は、部屋が汚いからいやなのか、あるいは知人が訪ねてきているのか、と考えますが、どうもそうではなさそうです。自分のことを忘れているのかと思い、「生活保護の担当です」と言うと、90歳の男性は困った顔をして言いました。
「友人は皆70代で死んでしまった。皆遊び過ぎたのだ。真面目にやって来た私は思いのほか長生きした。ここいらで好きなことをしてもいいと思う。だが・・・」彼は残念そうに言う。「もう女性を満足させてあげられない」
ぼくはもともと日記文学が大好きでして、古いものだと『紫式部日記』から、近代のものであれば永井荷風の『断腸亭日記』や夏目漱石の『漱石日記』、正岡子規の『仰臥漫録』、海外のものであれば『アナイス・ニンの日記』、ヴァージニア・ウルフの『ある作家の日記』、最近のものであれば坪内祐三の『三茶日記』や、昔ガロで連載していた松沢呉一の日記など、お気に入りの日記作品をあげるときりがありません。最近では、武田泰淳の妻である武田百合子の『富士日記』なんかを読み始めました。
雑誌『太陽』の1978年1月号はそのような日記文学の特集でして、どうしても手に入れたいのですが、どこにも売っていません。もし発見した方がいたら、御一報いただければ幸いです。
僕がこれらの日記文学に惹かれるのは、尊敬する人や、興味のある人、あるいは逆に大嫌いな人の生活を垣間見るという楽しみと、良い生活のお手本を読みたいという純粋な欲求によるものです。
たとえば、夏目漱石がロンドン留学中の1901年3月14日に書いた
あるいは、アナイス・ニンが1932年6月に書いた
このような日記文学を読むのは、そこに日記を書いた著者に対する(肯定的にしても否定的にしても)興味、手本とすべき生活への興味があるからです。興味もなにもない人が書いた日記を読みたいとは思いません。少なくとも今まではそうでした。しかし、『40's』を読んで感じたおもしろさは、そのような「著者への興味」によるものではありません。執筆者の名前は公表されていますが、それが誰なのかはわからないし、その人が実際に存在するのかどうかすらはっきりしないのですから。それでは、いったいどうしてこんなにおもしろく感じるのか?
ひとつには、同時代に生きる他人の生活に対する興味ということがあると思います。歴史的人物のような雲の上の人に対する興味とは別の、あくまでも自分と同じ時代に同じような生活をしている人に対する興味。
ぼくがこの『40's』を読みながら考えたのは、『記録を残さなかった男の歴史ーある靴職人の世界1798-1876』という本のことです。
この本は著者であるアラン・コルバンが、彼自身まったく興味を示さない歴史的に無名な人物をアトランダムに選んで、その彼の人生を調べるという、前代未聞の歴史書です。
全く無名の人物の人生を調べるわけですから、その調査は難航を極め、最終的には空白の部分がかなり残ります(高橋源一郎はこの空白について、「この真の空白以上に豊かな主人公を我々は想像できないのである」と言っています)。この本に関しては、書きたいことが山ほどあるのでまた改めて取り上げたいと思いますが、とりあえずここで書いておきたいのは、この本が前代未聞だった理由が、「歴史的に無名な人物を語る」というテーマによるものということです。この本が出る以前、また出た当時は、学問にしても芸術にしても、歴史的に無名な人物を語るということはあり得ませんでした。アラン・コルバンは、そのような歴史的に目に見える形で意味のある人物や出来事だけを取り上げてきた歴史学に対して、警鐘を鳴らそうとしたのです。
歴史的に無名な人物が記録を残さなかったのは、記録を残すだけの行動を行わなかったからです。もし彼が、歴史的に意味のある行動を行っていれば、歴史は彼の記録を残したでしょう。そして、僕たちも彼の記録を目にし、あるいは彼の書いた日記を読んだかもしれません。
しかし、ここ数年のインターネットの普及により、ぼくたちは「歴史的に意味のある」人々の日記から、「自分たちの生活に共通する」人々の書いた日記を読み始めています。世界中では、日記を公開している人が数えきれないほど存在します。それは最初から公開することを目的として書かれた日記であり、自分と同時代に生きる人々に向けられた日記です。そしてそれらの日記は、日を追うごとにその数を増やし続けています。
「人は本来的に語ることを欲する」と言いますが、今からほんの十年前ですら、一般の人々には世界に向けて語る術を持っていませんでした。現代では、歴史に名を残すような人物でもなくても、少しのパソコンの技術さえあれば、誰でも自分を語ることができるようになりました。そして、ぼくも含めて現代に生きる人々は、そのようにして公開された日記を楽しく読んでいます。みなさんも、友達がWebで公開している日記を読んでいるのではないでしょうか?っていうか、ぼくが今書いているこれも、その種の日記のひとつですし。
もちろん、Webで日記を書いたからといって、それが歴史に記録を残すことにはつながりません。しかし、(普通という言葉はあまり好きではありませんが、他に言い様がないので)普通の人々が自分と同じような普通の人々の日記を読む、または公開するという行為は、これまでの歴史上ではなかった出来事です。人々は、英雄でなくても、偉人でなくても、自分を語り、他人を読むという術を手に入れたのです。
『40's』を読みながら、普通の人の書いた普通の日々の日記が、今後文学や歴史にどのような意味を与えるのか、あるいは与えないのか、そんなことを考えてしまいました。アラン・コルバンが取り上げた靴職人も、現代に生きていたら、もしかしたら日記を公開していたかもしれませんね。

「『普通』が見えてくる日記マガジン」という副題のついたこの雑誌は、40代前後の一般の人々(この雑誌では市井の人々という言い方をしていますが)の2002年3月の日記だけで構成されています。
日記を書いている方々の職業は、大学教授からそば職人までさまざまです。それぞれの日記の頭には、年齢や家族構成、職業、年収、尊敬する人など、執筆した人のプロフィールが簡単に書かれています。書いてある内容は当然のことながら人それぞれ異なり、休日に「なぜ、フランスはルイジアナをアメリカに売ったのか?」という息子のレポートを手伝っている大学教授もいれば、連休を「地獄」と表現するギタリストもいるし、毎日何もしないで思索に勤しんでいる無職の人もいれば、テレビを観ても映画を観て文句ばかり書いている人もいます。
単なる個人の日記の寄せ集めと言ってしまえばそれまでなのですが、これが読み始めるとなかなか面白い。「平凡な人生なんて存在しない」という言葉がありますが、まさにその通り。日記によっては読んでいるだけでむかついてくるものもありますが、逆に癒されてしまうものもあります。
たとえば、地域の生活保護の担当をしているある女性は、90歳の男性の家に訪問したときのことを書いています。以前にも訪れたことのある家であるにもかかわらず、この90歳の男性は生活保護担当の女性が家に上がることを執拗に拒みます。女性は、部屋が汚いからいやなのか、あるいは知人が訪ねてきているのか、と考えますが、どうもそうではなさそうです。自分のことを忘れているのかと思い、「生活保護の担当です」と言うと、90歳の男性は困った顔をして言いました。
「友人は皆70代で死んでしまった。皆遊び過ぎたのだ。真面目にやって来た私は思いのほか長生きした。ここいらで好きなことをしてもいいと思う。だが・・・」彼は残念そうに言う。「もう女性を満足させてあげられない」
ぼくはもともと日記文学が大好きでして、古いものだと『紫式部日記』から、近代のものであれば永井荷風の『断腸亭日記』や夏目漱石の『漱石日記』、正岡子規の『仰臥漫録』、海外のものであれば『アナイス・ニンの日記』、ヴァージニア・ウルフの『ある作家の日記』、最近のものであれば坪内祐三の『三茶日記』や、昔ガロで連載していた松沢呉一の日記など、お気に入りの日記作品をあげるときりがありません。最近では、武田泰淳の妻である武田百合子の『富士日記』なんかを読み始めました。
雑誌『太陽』の1978年1月号はそのような日記文学の特集でして、どうしても手に入れたいのですが、どこにも売っていません。もし発見した方がいたら、御一報いただければ幸いです。
僕がこれらの日記文学に惹かれるのは、尊敬する人や、興味のある人、あるいは逆に大嫌いな人の生活を垣間見るという楽しみと、良い生活のお手本を読みたいという純粋な欲求によるものです。
たとえば、夏目漱石がロンドン留学中の1901年3月14日に書いた
穢い町を通ったら、目暗がオルガンを弾て黒い伊太利人がバイオリンを鼓していると、その傍に四歳ばかりの女の子が真赤な着物を着て真赤な頭巾を蒙って音楽に合わせて踊っていた。などいう日記を読むと、まるで自分がロンドンの片隅でそのような情景に出会っているように感じてしまいます。
あるいは、アナイス・ニンが1932年6月に書いた
シュルレアリストの自由な即興は意識の作りだす人工的な秩序や均整を打破する。混沌(khaos)には豊饒さがあるのだ。一瞬ごとに五つか六つある魂のうち一つを選ばねばならないとき、「誠実」であることは何とむずかしいのだろう。どの魂にしたがい、どの魂に合わせて誠実になればいいのか?などという日記を読むと、まるで自分が1930年代のシュールリアリズム運動の真っただ中にいるような、自分がヤリマンのバイセクシャルになったような気がして嬉しくなってしまいます。
このような日記文学を読むのは、そこに日記を書いた著者に対する(肯定的にしても否定的にしても)興味、手本とすべき生活への興味があるからです。興味もなにもない人が書いた日記を読みたいとは思いません。少なくとも今まではそうでした。しかし、『40's』を読んで感じたおもしろさは、そのような「著者への興味」によるものではありません。執筆者の名前は公表されていますが、それが誰なのかはわからないし、その人が実際に存在するのかどうかすらはっきりしないのですから。それでは、いったいどうしてこんなにおもしろく感じるのか?
ひとつには、同時代に生きる他人の生活に対する興味ということがあると思います。歴史的人物のような雲の上の人に対する興味とは別の、あくまでも自分と同じ時代に同じような生活をしている人に対する興味。
ぼくがこの『40's』を読みながら考えたのは、『記録を残さなかった男の歴史ーある靴職人の世界1798-1876』という本のことです。
この本は著者であるアラン・コルバンが、彼自身まったく興味を示さない歴史的に無名な人物をアトランダムに選んで、その彼の人生を調べるという、前代未聞の歴史書です。
全く無名の人物の人生を調べるわけですから、その調査は難航を極め、最終的には空白の部分がかなり残ります(高橋源一郎はこの空白について、「この真の空白以上に豊かな主人公を我々は想像できないのである」と言っています)。この本に関しては、書きたいことが山ほどあるのでまた改めて取り上げたいと思いますが、とりあえずここで書いておきたいのは、この本が前代未聞だった理由が、「歴史的に無名な人物を語る」というテーマによるものということです。この本が出る以前、また出た当時は、学問にしても芸術にしても、歴史的に無名な人物を語るということはあり得ませんでした。アラン・コルバンは、そのような歴史的に目に見える形で意味のある人物や出来事だけを取り上げてきた歴史学に対して、警鐘を鳴らそうとしたのです。
歴史的に無名な人物が記録を残さなかったのは、記録を残すだけの行動を行わなかったからです。もし彼が、歴史的に意味のある行動を行っていれば、歴史は彼の記録を残したでしょう。そして、僕たちも彼の記録を目にし、あるいは彼の書いた日記を読んだかもしれません。
しかし、ここ数年のインターネットの普及により、ぼくたちは「歴史的に意味のある」人々の日記から、「自分たちの生活に共通する」人々の書いた日記を読み始めています。世界中では、日記を公開している人が数えきれないほど存在します。それは最初から公開することを目的として書かれた日記であり、自分と同時代に生きる人々に向けられた日記です。そしてそれらの日記は、日を追うごとにその数を増やし続けています。
「人は本来的に語ることを欲する」と言いますが、今からほんの十年前ですら、一般の人々には世界に向けて語る術を持っていませんでした。現代では、歴史に名を残すような人物でもなくても、少しのパソコンの技術さえあれば、誰でも自分を語ることができるようになりました。そして、ぼくも含めて現代に生きる人々は、そのようにして公開された日記を楽しく読んでいます。みなさんも、友達がWebで公開している日記を読んでいるのではないでしょうか?っていうか、ぼくが今書いているこれも、その種の日記のひとつですし。
もちろん、Webで日記を書いたからといって、それが歴史に記録を残すことにはつながりません。しかし、(普通という言葉はあまり好きではありませんが、他に言い様がないので)普通の人々が自分と同じような普通の人々の日記を読む、または公開するという行為は、これまでの歴史上ではなかった出来事です。人々は、英雄でなくても、偉人でなくても、自分を語り、他人を読むという術を手に入れたのです。
『40's』を読みながら、普通の人の書いた普通の日々の日記が、今後文学や歴史にどのような意味を与えるのか、あるいは与えないのか、そんなことを考えてしまいました。アラン・コルバンが取り上げた靴職人も、現代に生きていたら、もしかしたら日記を公開していたかもしれませんね。

02年07月30日(火)
昨日の日記でも書いた通り、ここ数年、Webで日記を公開する人が急激に増えています。
最近よく耳にする「ウェブログ」という言葉は、もともとは「ウェブ上にある興味深いコンテンツへのリンクとその批評を記した、定期更新されているリストのこと(HotWired)」を意味していましたが、最近ではWebで公開されている日記全体の総称として使われたりしています。
ウェブログに関しては、HotWiredでも何度か取り上げられているので、下の記事を参考にしてください。
■人気急上昇中の「ウェブログ」とは
■ウェブ上で日記を公開する『ウェブログ』の可能性
■正統派ジャーナリズムが「ウェブログ」を認知?
■ウェブログってそんなにスゴいの?──ついに大学院の研究対象に
■「ナップスター革命」に匹敵する「ウェブログ革命」
これらの記事を読んでもわかる通り、ウェブログはインターネットの新しい表現の形として、日々その数を増やし続けています。また、誰でも簡単にウェブログを公開できるツールやサイトも、同様に増え続けています。ヤフーのカテゴリを探るとこんなにたくさん。
海外のおかしなサイトや音楽のアルバムを紹介している「Splash!」というウェブマガジンでは、ここ数ヶ月、そのように増え続けているウェブログの中から、面白いサイトやウェブログに関するニュースを紹介しています。
たとえば、最近紹介されていた「Blog Hot or Not」(ちなみにBlogというのはWebLogの略)というサイトは、自分のウェブログを登録して他人に採点をしてもらおう!という趣旨のもので、このサイトにアクセスすると、フレームの下側に登録されたウェブログが表示され、それを読んだ読者はフレームの上側で採点をします。
採点をすると、左側にそのサイトの平均点数が表示され、下のフレームには次のウェブログが表示されます。こまめに更新しているものや、情報性の高いもの、あるいは生活がユーモアなものなどはやはり点数が高いみたいですね。
ちなみに、上のフレームには、表示されているウェブログのキーワードが羅列してあり、ウェブログを読む際の目安になります。
HotWiredで紹介されたものや、Blog Hot or Notで紹介されていたもので個人的に興味を惹いたウェブログは....
■b00mb0x
僕がはじめて読んだ日は、チェ・ゲバラの「The motorcycle diaries」という本について書いてあったのですが、普段は音楽ネタが中心みたい。この「The motorcycle diaries」ってすごく面白そうなのですけど。
■Little Orange Crow
サンフランシスコ図書館で開催されているボルヘスの「The Time Machine」という展示会のことに言及していて、読んでいてとても面白いかった。っていうかうらやましかった。このサイトは「Splash!」でも取り上げていましたが、過去ログとかを読んでもとても面白かったです。
■urban-dyke.com
トップページに自分とガールフレンドの写真を載せているレズの方の恋愛日記。
■0format
デザインがとても僕好みでして。
■Why I Hate Life
タイトルからもわかる通り、ヘイト系のウェブログです。どーにもこーにも。
■Librarian.net
図書館員の方の書いている専門的なウェブログ。全然読んでいないのですが、なんとなく。
それにしても、上のウェブログを見ただけでも、みなさんすごくないですか。デザインもしっかりしているし、見ているとちゃんと更新もしているみたいだし。日本でも、これからウェブログの波はばんばん押し寄せてくると思うので、ちょっぴり楽しみです。

最近よく耳にする「ウェブログ」という言葉は、もともとは「ウェブ上にある興味深いコンテンツへのリンクとその批評を記した、定期更新されているリストのこと(HotWired)」を意味していましたが、最近ではWebで公開されている日記全体の総称として使われたりしています。
ウェブログに関しては、HotWiredでも何度か取り上げられているので、下の記事を参考にしてください。
■人気急上昇中の「ウェブログ」とは
■ウェブ上で日記を公開する『ウェブログ』の可能性
■正統派ジャーナリズムが「ウェブログ」を認知?
■ウェブログってそんなにスゴいの?──ついに大学院の研究対象に
■「ナップスター革命」に匹敵する「ウェブログ革命」
これらの記事を読んでもわかる通り、ウェブログはインターネットの新しい表現の形として、日々その数を増やし続けています。また、誰でも簡単にウェブログを公開できるツールやサイトも、同様に増え続けています。ヤフーのカテゴリを探るとこんなにたくさん。
海外のおかしなサイトや音楽のアルバムを紹介している「Splash!」というウェブマガジンでは、ここ数ヶ月、そのように増え続けているウェブログの中から、面白いサイトやウェブログに関するニュースを紹介しています。
たとえば、最近紹介されていた「Blog Hot or Not」(ちなみにBlogというのはWebLogの略)というサイトは、自分のウェブログを登録して他人に採点をしてもらおう!という趣旨のもので、このサイトにアクセスすると、フレームの下側に登録されたウェブログが表示され、それを読んだ読者はフレームの上側で採点をします。
採点をすると、左側にそのサイトの平均点数が表示され、下のフレームには次のウェブログが表示されます。こまめに更新しているものや、情報性の高いもの、あるいは生活がユーモアなものなどはやはり点数が高いみたいですね。
ちなみに、上のフレームには、表示されているウェブログのキーワードが羅列してあり、ウェブログを読む際の目安になります。
HotWiredで紹介されたものや、Blog Hot or Notで紹介されていたもので個人的に興味を惹いたウェブログは....
■b00mb0x
僕がはじめて読んだ日は、チェ・ゲバラの「The motorcycle diaries」という本について書いてあったのですが、普段は音楽ネタが中心みたい。この「The motorcycle diaries」ってすごく面白そうなのですけど。
■Little Orange Crow
サンフランシスコ図書館で開催されているボルヘスの「The Time Machine」という展示会のことに言及していて、読んでいてとても面白いかった。っていうかうらやましかった。このサイトは「Splash!」でも取り上げていましたが、過去ログとかを読んでもとても面白かったです。
■urban-dyke.com
トップページに自分とガールフレンドの写真を載せているレズの方の恋愛日記。
■0format
デザインがとても僕好みでして。
■Why I Hate Life
タイトルからもわかる通り、ヘイト系のウェブログです。どーにもこーにも。
■Librarian.net
図書館員の方の書いている専門的なウェブログ。全然読んでいないのですが、なんとなく。
それにしても、上のウェブログを見ただけでも、みなさんすごくないですか。デザインもしっかりしているし、見ているとちゃんと更新もしているみたいだし。日本でも、これからウェブログの波はばんばん押し寄せてくると思うので、ちょっぴり楽しみです。

02年07月31日(水)
テレビをつけっぱなしにてぼーっとしていたら、NHKで『祖母・幸田文への旅』という番組がやっていました。
幸田文さんは、その晩年に、全国各地の「崩れ」を巡って旅をし、そこで感じたことを『崩れ』というエッセーにまとめました。文さんがこの作品を書いたとき、すでに「年齢七十二歳、体重五十二キロ」であり、その旅路は簡単なものではありませんでした。そして四半世紀が過ぎた現在、孫である青木奈緒さんが再び文さんの旅した崩れの現場を旅しています。
番組は、文さんの娘である青木玉さんと孫の青木奈緒さんへのインタービューを中心に進行するのですが、このお二人、地球外生命体みたいでとても良かったです。玉さんなんか、最初ロボットかと思ってしまいました。文さんの生前のフィルムも少し流れて、ぼくは文さんの話しているところを初めて聞いたのですが、想像していた通りちゃきちゃきの江戸っ子という話し方で、聞いていてとても気持ちが良くなりました。
修復を終えた奈良の三重塔を訪れた文さんが関係者と話している映像には、完成した塔に感動したあまり落ち着きがないのか、声高になった文さんが「(重量感が)変わりましたね。そしてはっきり今度は勾配が見えるようになりましたね」と言っている場面が記録されているのですが、「変わりましたね。そしてはっきり今度は」の「そして」と言っているのがとても耳ごこち良いのです。普通、口語で「そして」とは言わないでしょう。言うかな。言うかもしれないけど、接続詞には「それに」とか、「あと」とか、言いませんか?この「それに」という接続詞の使い方が、とても素敵。江戸っ子っていいね、本当に。お孫さんである奈緒さんも、のほほんとした感じなのに、「そうさねえ」などと自然に言っていて、こんな嫁さんをもらったらぼくも江戸っ子になれるのかしら、などと思いました。
文さんは、木々を巡る旅の途中で訪れた安倍峠で大谷崩れに出会い、「崩れ」に強く惹かれます。
文さんが、雨が降ると崩れを起こす阿倍川と山のことを、「もてあましものなのですか?」と聞くと、関係者の方は「もてあましもの」という言葉を避けて、「人の力は自然の力の比じゃないし、その点がどうも仕様のないことです」と答えます。
『木』という随筆集に収められた『ひのき』というエッセーには、「アテ」という、使用することのできない欠陥した木材のことが書かれています。文さんは、八月の「ごうごうと相当ショッキングに音をたてている」ひのきを見に訪れます。そしてそこで、木材業の人に樹齢三百年ほどの二本立のひのきを見せられます。その二本は、「一本はまっすぐ、一本はやや傾斜し、自然の絵というか、見惚れさせる風趣」を持っていました。しかし、木材業の方は言います。「まっすぐなほうは申分ない、傾斜したほうは、有難くは頂けない」と。
木材業の方は続けて言います。この二本はある時期まではライバル同士だったのだろうが、何らかの理由で、いっぽんがもういっぽんに空間を譲る状態になり、傾斜したのだろう、二本立にはこういうのがよくある、そして、傾斜した方のひのきは、材に挽こうとしても抵抗が強く、使い物にならない。そのような木材を「アテ」と呼ぶ、と。
文さんは、傾斜したひのきを見て思います。
ところで、幸田文さんといえば、言わずと知れた幸田露伴さんの実の娘さんです。露伴さんの回想記である『ちぎれ雲』は、大好きな随筆のひとつなのですが、先に触れた『木』に収められている『藤』という作品にも、とても素敵なエピソードが書かれています。
ある日、文さんは、露伴さんに「町に育つおさないものには、縁日の植木をみせておくのも、草木へ関心をもたせる、かぼそいながらの一手段だ」と言われて、娘の玉さんを縁日に連れていきます。出かけに露伴さんは、「娘の好む木でも花でも買ってやれ」と言って、文さんにがま口を渡します。縁日に行くと、幼い玉さんは無邪気に、文さんの身長ほどもある、高価な藤の鉢植えをねだります。とてもじゃないががま口のお金で買える代物ではなかったので、文さんはそれを諦めさせて、結局玉さんは山椒の木を買います。
家に帰ると、書斎から出てきて話を聞いた露伴さんは、みるみる不機嫌になります。玉さんの藤の選択は間違っていないというのです。「市で一番の花を選んだとは、花を見るたしかな目を持っていたからのこと、なぜその確かな目に応じてやらなかったのか、藤は当然買ってやるべきものだったのに」とマジギレです。文さんが反論すると、露伴さんは理路整然とさらに百倍ぐらい言い返します。ちょっと面白いので引用すると
谷崎潤一郎は、幸田露伴が理解されるには100年はかかるだろうと言っていたと言います。ぼくは、ぜんぜん理解できていないことを承知の上で、少しでも心に良い養いをつけるために、露伴さんを一生読み続けたいと思っています。
それから、ぼくはとても長い間アヤさんのことを「こうだふみ」と読んでいました。気の遠くなるくらい長い間。

これの秋咲くものならぬこそ幸なれ。風冷えて鐘の音も清み渡る江村の秋の夕など、雲漏る薄き日ざしに此花の咲くものならんには、我必ずや其蔭に倒れ伏して死もすべし。虻の声は天地の活気を語り、風の温く軟きが袂軽き衣を吹き皺めて、人々の魂魄を快き睡りの郷に誘はんとする時にだも、此花を見れば我が心は天にもつかず地にもつかぬ空に漂ひて、物を思ふにも無く思はぬにも無き境に遊ぶなり。
幸田露伴『花のいろいろ』の中『紫藤』の項より
幸田文さんは、その晩年に、全国各地の「崩れ」を巡って旅をし、そこで感じたことを『崩れ』というエッセーにまとめました。文さんがこの作品を書いたとき、すでに「年齢七十二歳、体重五十二キロ」であり、その旅路は簡単なものではありませんでした。そして四半世紀が過ぎた現在、孫である青木奈緒さんが再び文さんの旅した崩れの現場を旅しています。
番組は、文さんの娘である青木玉さんと孫の青木奈緒さんへのインタービューを中心に進行するのですが、このお二人、地球外生命体みたいでとても良かったです。玉さんなんか、最初ロボットかと思ってしまいました。文さんの生前のフィルムも少し流れて、ぼくは文さんの話しているところを初めて聞いたのですが、想像していた通りちゃきちゃきの江戸っ子という話し方で、聞いていてとても気持ちが良くなりました。
修復を終えた奈良の三重塔を訪れた文さんが関係者と話している映像には、完成した塔に感動したあまり落ち着きがないのか、声高になった文さんが「(重量感が)変わりましたね。そしてはっきり今度は勾配が見えるようになりましたね」と言っている場面が記録されているのですが、「変わりましたね。そしてはっきり今度は」の「そして」と言っているのがとても耳ごこち良いのです。普通、口語で「そして」とは言わないでしょう。言うかな。言うかもしれないけど、接続詞には「それに」とか、「あと」とか、言いませんか?この「それに」という接続詞の使い方が、とても素敵。江戸っ子っていいね、本当に。お孫さんである奈緒さんも、のほほんとした感じなのに、「そうさねえ」などと自然に言っていて、こんな嫁さんをもらったらぼくも江戸っ子になれるのかしら、などと思いました。
文さんは、木々を巡る旅の途中で訪れた安倍峠で大谷崩れに出会い、「崩れ」に強く惹かれます。
文さんが、雨が降ると崩れを起こす阿倍川と山のことを、「もてあましものなのですか?」と聞くと、関係者の方は「もてあましもの」という言葉を避けて、「人の力は自然の力の比じゃないし、その点がどうも仕様のないことです」と答えます。
私は無遠慮にもてあましもといったけれど、県の人は笑うばかりで、その言葉を避けて言わなかった。言わないだけにかえって、先祖代々からの長い努力が費やされたのだろうと、推測せずにいられなかった。人も辛かったろうが、人ばかりが切なかったわけでもあるまい。川だって可哀想だ。好んで暴れるわけではないのに、災害が残って、人に嫌われ疎じられ、もてあまされる。川は無心だから、人にどう嫌われても痛痒はあるまいが、同じ無心の木でも石でも、愛されるのと嫌われるのとでは、生きかたに段のついた違いがでる。安倍川は人を困らせる川といえようが、私には可哀想な川だと思えてならなかった。文さんが「崩れ」に惹かれたのは、その姿があまりにも寂寞として物悲しかったからでした。文さんは、「崩れ」に惹かれる気持ちを、こんな感じに書いています。
あの山崩からきた愁いと寂しさは、忘れようとして忘れられず、あの石の河原に細く流れる流水のかなしさは、思い捨てようとして捨て切れず・・・人によっては、この『崩れ』という作品を、文さんの作品の中で異色なものとして考える方もいますが、ぼくはそうは思いません。文さんの書いた作品に一貫して共通する、弱いものに対する優しさが、『崩れ』には書かれています。「崩れ」という、猛々しいイメージのある言葉の中に、文さんの悲しみとやさしさが溢れているのです。
山の崩れを川の荒れをいとおしくさえ思いはじめていた...
『木』という随筆集に収められた『ひのき』というエッセーには、「アテ」という、使用することのできない欠陥した木材のことが書かれています。文さんは、八月の「ごうごうと相当ショッキングに音をたてている」ひのきを見に訪れます。そしてそこで、木材業の人に樹齢三百年ほどの二本立のひのきを見せられます。その二本は、「一本はまっすぐ、一本はやや傾斜し、自然の絵というか、見惚れさせる風趣」を持っていました。しかし、木材業の方は言います。「まっすぐなほうは申分ない、傾斜したほうは、有難くは頂けない」と。
木材業の方は続けて言います。この二本はある時期まではライバル同士だったのだろうが、何らかの理由で、いっぽんがもういっぽんに空間を譲る状態になり、傾斜したのだろう、二本立にはこういうのがよくある、そして、傾斜した方のひのきは、材に挽こうとしても抵抗が強く、使い物にならない。そのような木材を「アテ」と呼ぶ、と。
文さんは、傾斜したひのきを見て思います。
そのひのきは、生涯の傾斜を背負って、はるかな高い梢にいただいた細葉の黒い茂みを、ゆるく風にゆらせていた。そのゆるい揺れでも、傾斜の躯幹のどこかには忍耐が要求され、バランスを崩すまいとつとめているのだろう。木はものを言わずに生きている。かしいで生きていても、なにもいわない。立派だと思った。が、せつなかった。文さんには、懸命に生きようとするばかりに、日照に当たろうと躯幹を傾けて成長したひのきが、「よくないもの、悪いものとして、なにか最低の等級にも入れられない、それ以下のものとされているように」聞こえたのです。『崩れ』は、ここで書かれている「アテ」に対するものと同じ感情の上に書かれているのです。
ところで、幸田文さんといえば、言わずと知れた幸田露伴さんの実の娘さんです。露伴さんの回想記である『ちぎれ雲』は、大好きな随筆のひとつなのですが、先に触れた『木』に収められている『藤』という作品にも、とても素敵なエピソードが書かれています。
ある日、文さんは、露伴さんに「町に育つおさないものには、縁日の植木をみせておくのも、草木へ関心をもたせる、かぼそいながらの一手段だ」と言われて、娘の玉さんを縁日に連れていきます。出かけに露伴さんは、「娘の好む木でも花でも買ってやれ」と言って、文さんにがま口を渡します。縁日に行くと、幼い玉さんは無邪気に、文さんの身長ほどもある、高価な藤の鉢植えをねだります。とてもじゃないががま口のお金で買える代物ではなかったので、文さんはそれを諦めさせて、結局玉さんは山椒の木を買います。
家に帰ると、書斎から出てきて話を聞いた露伴さんは、みるみる不機嫌になります。玉さんの藤の選択は間違っていないというのです。「市で一番の花を選んだとは、花を見るたしかな目を持っていたからのこと、なぜその確かな目に応じてやらなかったのか、藤は当然買ってやるべきものだったのに」とマジギレです。文さんが反論すると、露伴さんは理路整然とさらに百倍ぐらい言い返します。ちょっと面白いので引用すると
好む草なり木なりを買ってやれ、といいつけたのは自分だ、だからわざと自分用のガマ口を渡してやった、子は藤を選んだ、だのになぜ買ってやらないのか、金が足りないのなら、がま口ごと手金にうてばそれで済むものを、おまえは親のいいつけも、子のせっかくの選択も無にして、平気でいる。なんと浅はかな心か、しかも、藤がたかいのバカ値のというが、いったい何を物差しにして、価値を決めているのか、多少値の張る買物であったにせよ、その藤を子の心の養いにしてやろうと、なぜ思わないのか、その藤をきっかけに、どの花をもいとおしむことを教えれば、それはこの子一生の心のうるおい、女一代の目の楽しみにもなろう、もしまたもっと深い機縁があれば、子供は藤から蔦へ、蔦からもみじへ、松へ杉へと関心の目をのばさないとはかぎらない、そうなればそれはもう、その子が財産をもったも同じこと、これ以上の価値はない、子育ての最中にいる親が誰しも思うことは、どうしたら子のからだに、心に、いい養いをつけることができるのか、とそればかり思うものだ、金銭を先に云々して、子の心の栄養を考えない処置には、あきれてものもいえない露伴さん、とても良いことを言っているのですが、こんなぐちぐちと言われたら、とりあえず蹴るでしょう。
谷崎潤一郎は、幸田露伴が理解されるには100年はかかるだろうと言っていたと言います。ぼくは、ぜんぜん理解できていないことを承知の上で、少しでも心に良い養いをつけるために、露伴さんを一生読み続けたいと思っています。
それから、ぼくはとても長い間アヤさんのことを「こうだふみ」と読んでいました。気の遠くなるくらい長い間。

これの秋咲くものならぬこそ幸なれ。風冷えて鐘の音も清み渡る江村の秋の夕など、雲漏る薄き日ざしに此花の咲くものならんには、我必ずや其蔭に倒れ伏して死もすべし。虻の声は天地の活気を語り、風の温く軟きが袂軽き衣を吹き皺めて、人々の魂魄を快き睡りの郷に誘はんとする時にだも、此花を見れば我が心は天にもつかず地にもつかぬ空に漂ひて、物を思ふにも無く思はぬにも無き境に遊ぶなり。
幸田露伴『花のいろいろ』の中『紫藤』の項より