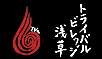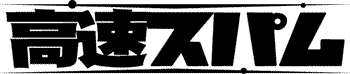「全くです。画工だから、小説なんか初からしまいまで読む必要はないんです。けれども、どこを読んでも面白いのです。あなたと話をするのも面白い。ここへ逗留しているうちは毎日話をしたいくらいです。何ならあなたに惚れ込んでもいい。そうなるとなお面白い。しかしいくら惚れてもあなたと夫婦になる必要はないんです。惚れて夫婦になる必要があるうちは、小説を初からしまいまで読む必要があるんです」
「すると不人情な惚れ方をするのが画工なんですね」
「不人情じゃありません。非人情な惚れ方をするんです。小説も非人情で読むから、筋なんかどうでもいいんです。こうして、御籤を引くように、ぱっと開けて、開いた所を、漫然と読んでるのが面白いんです」夏目漱石『草枕』
朝、寝坊をして八時起床。最悪。急いで着替えをして、ゲストハウスを出る。チェックアウトの時に、パクセ行きのバスのことを聞くと、今の時間だと渡し船で向こう岸の村へ渡らないといけないらしい。ゲストハウスの従業員が、隣の家から渡し舟の持ち主を呼んできてくれて、向こう岸へ渡る。
川を渡ると、今まで訪れた村の中でも、一番こじんまりとしている小さな村に着いた。渡し舟の船頭に、バスはどこから出るのか聞くと、道の先を指さす。この道を行けということなのだろうか?英語が通じないのでそれ以上聞くことも出来ず、とりあえず道を進んでみることにする。
しばらく進むが、バスが乗れそうな場所も、バスが来る気配も全くない。途中で会った人に、「ロットメー(バス)」「パクセ」と尋ねると、道の先の方を指さして何かを言っている。さらに進むと、T字路に出た。右と左、どちらへ行けば良いか分からないので、近くの売店で聞くと、店員は左の方を指さす。本当なのかな、と思いつつも、そちらへ行くしかないので、言われた方向へ進む。すぐにまた売店があったので、念の為にもう一度バスのことを聞くと、お店のおじさんがラオス語で何かをまくし立てる。もちろん、何を言っているのかさーっぱり分からない。お礼を言って店を出ようとすると、おじさんがまた何かをまくし立て、ここにいろ、というジェスチャーをする。ここに入ればバスが来るの?と片言で聞くと、おじさんは頷く。半信半疑のまま、ペプシとお菓子を買って、食べながら座って待っていると、とても体格の良いおばさんが店にやってきた。おじさんに挨拶をして二言三言話すと、おじさんがおばさんを指さして、「パクセー」と言う。どうやら、このおばさんもパクセへ行くらしい。とりあえず、これで安心だ。
十分ほど待つと、ソンテウがやって来た。おばさんが大声を張り上げ、手を振ってソンテウを停める。少し先まで行ってしまったソンテウは、バックで戻ってきてぼくとおばさんを乗せる。バスよりもソンテウのほうが好きなので、嬉しい。
無事にパクセ行きのソンテウには乗れた。さて、これからどうしようか。今日中にラオスを出てタイに行ってしまっても良いし、今日はパクセかその周辺で過ごして、明日タイに行っても良い。なんだかんだで、今回の旅行はばたばたと忙しかったので、パクセで一日休養をとろうか。しかし、パクセって二回通ったが、面白そうな街では全然なかった。やっぱり今日中にラオスを出国しようか。
昨日は四時間以上かかった道のりが、今日は二時間弱で到着。到着した場所が市場だったので、ぼろぼろになったサンダルの替わりに、新しいサンダルを購入する。8000キープ。日本円にして100円もしないサンダルは、とても履き心地が悪く、五分も歩くとすでに靴擦れができた。痛い足を引きずりながら、パクセの市街へ向かう。歩きながら町を見回すが、あまり魅力を感じない。やはり、今日中にラオスを出てタイへ行こうと思う。タイへ移動し、明日一日を過ごして、夜にバンコクへ向かおう。明日タイへ向かうとすると、バンコク行きの電車の出る駅があるウボンラチャータ二ーはほとんど通り過ぎるだけということになる。それは少し寂しい。今日中にウボンへ行って、明日一日をそこで過ごそう。そうと決まったら、ラオスとタイの国境の村、バーンタオを向かおう。サムローをひろって、例のごとく「バーンタオ」を連呼。バス停へ連れていってもらう。
サムローに乗せられて、先程とは別の市場に到着。ここからバーンタオ行きのソンテウが出ているらしい。市場の中へ入ると、食料品のほかにも家電も売っている。市場を抜けると、バスの停車場らしきものがある。近くにいた人にバーンタオへ行きたいことを伝えると、ソンテウの所まで連れてきてくれた。十分ほど待って、発車。ぼくの他に三人の欧米人が乗っている。どこに行くの?と聞かれたので、タイへ出るためにバーンタオへ行く、と言うと、タイへ行くにはバーンタオではなくて、チョンメックで降りたほうが良いとのこと。チョンメックはバーンタオの少し先らしい。チョンメックって、タイじゃないの?出入国審査を受けないと入れないんじゃない?、と聞くと、ラオスとタイのイミグレーションの両方がチョンメックにあるとのこと。よくわからないけど、とりあえず行ってみればわかるだろう。
とうとうラオスを出国する。結局、たった四日しかいなかったんだよなーと思うと、やはり名残おしい。少なくとも二週間は滞在したかった。今回の旅行は、いつか時間があるときに再びラオスに訪れるための予行旅行だと自分に言い聞かせる。予行にしては楽しすぎる旅行ではあったけど。

一時間ほどでチョンメック到着。あまりにも質素な村で、一瞬行き先を間違えたのかと思ったが、イミグレーションの場所を聞き、その方向へ進むと、店がたくさん並んでいて活気に満ちている。ペプシを飲んで少し休む。村人たちは、観光客を商売相手にしていないせいか、ぼくには見向きもしない。店を出てしばらく歩くと、でかい建物があったので、入って聞いてみると、そこがラオスのイミグレーションらしい。先程同行した欧米人が出国審査をしている。「ハローアゲイン」などと適当に挨拶をして、ぼくも出国審査をする。無事に審査を済ませてトイレに入ろうとしたら、五バーツ取られた。
徒歩による国境越えは初めての体験なのでわくわくする。ちょっとした旅人になった気分。先へ進むと、今度はタイのイミグレーションがある。入国審査をして、外に出る。近くにいた人に、「ウボンラチャータニーへ行きたいのだけど」と言うと、柵を越えて向こうへ行け、とのこと。柵を越えるとそこはタイ側の市場。ああ、徒歩による国境越えをしてしまったのね、ぼく。なんとなく感無量。
そういえば、今日は朝からなにも食べていない。市場に来たことだし、昼食でもとろうかしらと思っていると、でぶのタイ人女性が「どこへ行くの?」と聞くので、「ウボンラチャータニーに行きたい」と言うと、大型のソンテウのところまで連れていかれ、「このバスでピブーン・マンサハーンへ行き、そこでウボンラチャータニー行きのバスへ乗り換えればいい」とのこと。タイのガイドブックを持っていないので、少々不安だが言う通りにすることにした。それほど腹が減っているわけでもなかったので、昼食は後にして、バスに乗り込んで待っていると、欧米人カップルが乗り込んできた。ぼくと同じ説明をでぶから受けている。バスに乗り込むと、二人は市場で買ったと思われるお菓子を食べ始めた。物欲しそうにしていると、クッキーのようなものをくれた。有り難く頂く。
しばらくするとバスが出発し、ピブーン・マンサハーンへ向かう。二人に行き先を聞くと、やはりウボンラチャータニーだという。ピブーン・マンサハーンを経由するということはガイドブックにも書かれていることらしい。一安心。乗客は、ぼくと、欧米人カップルと、でぶと、他のタイ人が二人だけ。MDウオークマンを取り出して、Bomb The Bassを聞く。ふと、ラオス通貨のキープを両替するのを忘れていたことに気づく。2000バーツを両替して、結局半分も使わなかった。ということは、三泊四日で3000円ちょいしか使っていないのか。あーもったいねー、ステーキ食えば良かった。キープなんて、どこへ行っても両替できないよなーと後悔し、眠くなって、寝る。
起こされて目覚めると、ピブーン・マンサハーンに到着したらしい。バスを降りると、道路の向こう側に別のバスが待機している。このバスがウボンラチャータニー行きとのこと。欧米人カップルに次いで乗り込む。バスが出発し、ウボンラチャータニーへ向かう。
とても天気が良くて、雨が降った気配は全然ない。こちらも雨期のはずだが、気候の感じがラオスとは全然違う。国境なんてものは、人間が勝手に決めた国の境に過ぎないはずなのに、そこを越えると本当に別の土地へ来たような感じがする。カップルに話を聞くと、すでに一ヶ月以上二人で東南アジアを回っていて、旅はまだ当分続くらしい。ラオスの観光ビザが切れそうなのでとりあえずタイへ出て、これからどこへ行くかはまだ決めていないとのこと。心の底からうらやましく思う。っていうか、この彼女、とても美しいのに、汚い。風呂に入ったほうがいいですよ、と忠告をしようと思ったが、ぼくも人のことは言えないのでやめておく。
一時間以上バスに揺られて、ウボンラチャータニーの駅へ到着。バスはこの後市内へ向かうらしいが、少し歩きたかったのでここで降りる。早速トゥクトゥクが寄ってくる。市内までの距離を聞くと、二キロとのこと。歩きたいと言うと、意外なほどあっさりと引き下がって、道順まで教えてくれた。センキュー。
 が、ちょっと歩いただけで靴擦れがひどくて歩けなくなる。足の皮がべろんべろんに剥けている。絆創膏を貼って、ゆっくりと歩く。参った。トゥクトゥクに乗ろうにも、空車のトゥクトゥクが全然通らない。痛みをこらえて歩く。途中、川を二つ越える。後に越えたほうの川は、メコン川と同じ色をしていた。なんという川なのだろう?後で誰かに聞いてみよう。
が、ちょっと歩いただけで靴擦れがひどくて歩けなくなる。足の皮がべろんべろんに剥けている。絆創膏を貼って、ゆっくりと歩く。参った。トゥクトゥクに乗ろうにも、空車のトゥクトゥクが全然通らない。痛みをこらえて歩く。途中、川を二つ越える。後に越えたほうの川は、メコン川と同じ色をしていた。なんという川なのだろう?後で誰かに聞いてみよう。
歩いていると、目に入る風景があまりにも日本に似ていて驚く。日本の郊外と、ほとんど変わらない。車の工場や、ディーラー、デパートらしきものもある。ラオスから数時間乗り物に乗っただけで、ここまで変わるものなのか。ぼくの故郷の方がよほど田舎だ。うーん。明日一日、楽しめるだろうか?
たった二キロの道のりに二時間以上かけて、ようやく市内に到着。すんごい都会。ぼくの汚い格好はやばすぎる。さっさと宿を探して、シャワーを浴びたいが、どこに宿があるのかさっぱりわからない。通行人に聞くと、一件のホテルの場所を教えてくれた。足が痛くて死にそうになりながら、教えられたホテルへ向かう。ホテルは、しっかりとした立派なホテルだった。多少高くてもいいや、と思いながら受付に行って値段を聞くと、一晩330バーツとのこと。ホットシャワーも出るということなので、チェックインする。
今回の旅行初のテレビ付部屋。シャワーを浴びて、きれいな洋服に着替える。今まで着ていた服は、汚いし、何よりも臭い。軽く洗って室内に干し、時計を見ると六時を過ぎている。そういえば、今日はなにも食べていない。何かを食べようと思い、外へ出る。
 ホテルを出ると、道路を渡ったすぐ先に屋台が並んでいる。腹がぐーぐー鳴っている。屋台で、色のついた御飯と、チキンの唐揚げのようなものを食べる。一緒についてきた調味料をかけたら、死ぬほど辛い。思わず一緒に出てきた生水をごくごくと飲んでしまう。大丈夫かしら。辛いものを食べたら、甘いものを食べたくなったので、バナナクレープが車に踏まれて汚くなったような食べ物を買う。うまい。他にも、気になる食べ物がたくさん屋台に並んでいる。また後で来てみようっと。
ホテルを出ると、道路を渡ったすぐ先に屋台が並んでいる。腹がぐーぐー鳴っている。屋台で、色のついた御飯と、チキンの唐揚げのようなものを食べる。一緒についてきた調味料をかけたら、死ぬほど辛い。思わず一緒に出てきた生水をごくごくと飲んでしまう。大丈夫かしら。辛いものを食べたら、甘いものを食べたくなったので、バナナクレープが車に踏まれて汚くなったような食べ物を買う。うまい。他にも、気になる食べ物がたくさん屋台に並んでいる。また後で来てみようっと。
痛い足を堪えて歩いていると、セブンイレブンを発見。絆創膏を買う。足のあっちこっちに絆創膏を貼りまくり、どうにか歩けるようになったので、夜のウボンラチャータニーを徘徊。本当に日本の郊外のような町で、それほど面白みはなさそう。途中、インターネットが出来る店を発見。こじんまりとした一間に、壁に向かってマシンが十台ほど並べられている。聞くと、日本語は使えないが、ランゲージパックをダウンロードすれば、日本語のサイトをみることは出来るという。日本語のランゲージパックをダウンロードしながら周りを見回すと、ほとんどの客が子供で、3Dゲームをやったり、インターネットをやったり、ワードで文章を書いたりしている。子供の僧侶が、3Dゲームで敵を銃でばんばん撃ち殺している。三十分以上かかってようやくダウンロード完了。鉄割のサイトを見る。鉄割のサーバは家に置いてあるので、鉄割のサイトが見られるということは、家も無事ということ。安心して店を出る。
時計を見ると、九時を過ぎている。道は車で溢れている。二人乗りのバイクがぼくを追い越していく。仲間同士らしい複数のグループが、町を徘徊している。ラオスでは寂しいと感じたことはほとんどなかったが、このような町に来るとひとりが寂しくなる。前回の旅行では、毎晩タイ人の若者のグループに強引に割り込んでは、一緒にお酒を飲んだりしたが、一人でそこまでやる勇気はない。宿に帰ることにする。
ホテルに到着。ウォークマンで音楽を聞きながら読書をする。『日本的霊性』はようやく第一篇読了。ここからがおもしろくなるところだ。『姑獲鳥の夏』は、三分の二ほど読み終えた。この本が面白すぎて、他の本を読むことが出来ない。一時間ほど読書をして、寝る。が、咽が渇いて夜中に目が覚める。今回の旅行で夜中に目を覚ましたのは初めてだ。受付へ行き、咽が渇いたことを伝えると、ホテルの外へ導かれ、となりの大衆食堂のような店に連れていかれる。時計を見ると十二時を過ぎたところだ。ペプシを飲んで部屋に戻り、今度こそ就寝。なんだか体がだるい。風邪をひいたのだろうか?

十年以上連絡を取っていない友人と一緒に、行方不明になった知人を探しにポルトガルを旅する夢を見る。『リスボン物語』のような夢だった。
私は日の出とともに起きて、幸せだった。私は散歩をして、幸せだった。私はママンに会い、幸せだった。私は彼女のもとを離れ、幸せだった。私は森や丘を巡り、谷間をさまよい、読書をし、何もせず、庭仕事をし、果物を採り、家事を手伝い、幸せがいたるところ私についてきた。幸せは何か特定のものの中にあったのではなく、それはそっくり私の中にあり、一瞬も私から離れることはできなかった。ジャン=ジャック・ルソー『告白』
 朝六時起床。雨は小雨に変わっている。昨日、シャワーをきちんと浴びることができなかったので、シャ ワーを浴びる。朝は、さすがにシャワーの水が冷たくてきつい。水を浴びながら考える。昨日、ワット・プーに行った。今回の旅行の一応の目的は果たした。今日は十四日だ。明後日の十六日にバンコクに戻る列車を予約している。今日、明日、明後日をどうやって過ごそうか。そういえば、飛行機のリコンファームをするのを忘れていた。とりあえずパクセに戻ってリコンファームをし、その先のことは後で考えよう。
朝六時起床。雨は小雨に変わっている。昨日、シャワーをきちんと浴びることができなかったので、シャ ワーを浴びる。朝は、さすがにシャワーの水が冷たくてきつい。水を浴びながら考える。昨日、ワット・プーに行った。今回の旅行の一応の目的は果たした。今日は十四日だ。明後日の十六日にバンコクに戻る列車を予約している。今日、明日、明後日をどうやって過ごそうか。そういえば、飛行機のリコンファームをするのを忘れていた。とりあえずパクセに戻ってリコンファームをし、その先のことは後で考えよう。
部屋の外に出ると、空気がさわやかでとても気持ちがいい。ゲストハウスの前を、托鉢の僧侶たちが通り過ぎていく。僧侶と言っても大半がまだ子供と言って良い少年で、全員が裸足で歩いている。明らかに歩くのを嫌がって、仏頂面で付いていく少年が最後に続く。どこから来てどこへ行くのかは分からないが、裸足で歩く彼らを少し羨ましく思う。
ゲストハウスをチェックアウトするときに、パクセに戻るにはどうすれば良いか聞くと、とりあえず船着き場に行って、渡し舟でメコン川を渡り、向こう岸の村からソンテウでパクセに行くことができるとのこと。昨日ソンテウで到着した船着き場まで、歩いて二キロ程度なので、そこまで歩くことにする。
歩き始めると、雨が止んだ。やはり天候はぼくの味方をしている。昨日、泥溜まりを歩いたせいで、サンダルの革の部分がぶよぶよに伸びていて歩きにくい。足を引きずるようにして歩く。どこかで新しいサンダルを買わないと駄目だな。雨はやんだものの、空はどんよりと曇っている。昨日聞いた"I Know Where Syd Barrett Lives"を頭の中で繰り返す。向こう側から僧侶の托鉢の列が来る。待っていた女性が、僧侶のひとりひとりに御飯を施している。大乗である日本では、出家という宗教的修業はそれほど浸透していない(どころか、新興宗教のせいで偏見すら持たれている)が、南伝系では出家することは宗教に生きる人々にとっては当たり前のことなので、歩いているとこのように托鉢する僧侶達をよく見かける。ラオスはタイに比べて一般家庭への仏教の浸透がいまいちであるということを聞いたことがあるが、こうして食べ物を施してもらっている僧侶の一団を見ると、実際のところはどうなのだろうかと気になる。
 船着き場に着く。ここから渡し舟でメコン川を渡らなくてならない。とりあえず、適当な店に入って「パクセ、パクセ」と言うと、最初はきょとんとしているが、どうにか分かってくれたようで、船の乗り場まで連れていってくれた。昨日とは大型船とは異なり、人を運ぶための小さめの渡し舟に乗り込む。ソンテウに乗って渡し舟で川を渡ったときは、メコンを渡っている実感がそれほどなかったが、こうして直に風を浴びて渡し舟に揺られて川を進むと、如何にも川を渡っているという気がして嬉しい。それにしても、メコン川は本当に広い。四年前に行ったインドのガンジス川の川幅を思いだそうとするが、思い出せない。おそらく、メコン川の方が広いと思う。川は茶色に濁っている。この川の底には何が棲んでいるのだろう。川の半分を過ぎたぐらいで、小雨が降り出してきた。対岸に着くと、岸から少し離れたところで渡し舟が止まる。ここから歩いていけと言う。これ以上渡し舟では進めないらしい。仕方がないので、水に足を入れると、腰までは届かないものの、それに近い深さで、思いっきりズボンが水に浸る。リュックを濡らすのだけは避けたかったので、転ばないように慎重に歩く。
船着き場に着く。ここから渡し舟でメコン川を渡らなくてならない。とりあえず、適当な店に入って「パクセ、パクセ」と言うと、最初はきょとんとしているが、どうにか分かってくれたようで、船の乗り場まで連れていってくれた。昨日とは大型船とは異なり、人を運ぶための小さめの渡し舟に乗り込む。ソンテウに乗って渡し舟で川を渡ったときは、メコンを渡っている実感がそれほどなかったが、こうして直に風を浴びて渡し舟に揺られて川を進むと、如何にも川を渡っているという気がして嬉しい。それにしても、メコン川は本当に広い。四年前に行ったインドのガンジス川の川幅を思いだそうとするが、思い出せない。おそらく、メコン川の方が広いと思う。川は茶色に濁っている。この川の底には何が棲んでいるのだろう。川の半分を過ぎたぐらいで、小雨が降り出してきた。対岸に着くと、岸から少し離れたところで渡し舟が止まる。ここから歩いていけと言う。これ以上渡し舟では進めないらしい。仕方がないので、水に足を入れると、腰までは届かないものの、それに近い深さで、思いっきりズボンが水に浸る。リュックを濡らすのだけは避けたかったので、転ばないように慎重に歩く。
川を渡ると、昨日ソンテウで渡った川向かいの村に着く。さて、ここからパクセ行くのソンテウは、いつ出るのだろうか?船着き場に隣接している店で聞くと、ここで待っていろ、と言うのでペプシを飲みながら待つ。三十分もすると、ソンテウがやって来た。パクセ行きであることを確認して、乗り込む。
ソンテウは、昨日よりは乗客も少なく、ゆったりと座れる。雨がどんどん激しさを増してくる。昨日と同じように一本道をひたすら突き進む。
パクセに到着後、サムローで国際電話をかけられる店に連れていってもらい、無事にリコンファーム完了。さてこれからどうしようか。時計を見ると、九時を少し過ぎたところだ。今からバス停に向かえば、コーン島に行けるだろうか?とりあえず、バス停まで歩いてみようと思い、バス停の方向へ歩き出す。サンダルがぶよぶよで、歩きにくい。足に変なふうに力を入れるので、指が痛くなってくる。三十分ほど過ぎたところで、市場にようなところに出る。入り口に、警察官のような服装の男達がたむろっているので、「コーン島に行きたいのだけど」と英語で言うと、「おまえは、英語を話しているのか?」と逆に聞かれる。どうにか意志を伝えると、コーン島行きのバスは、ここから七キロほど先にあるバス停から乗れるという。七キロはさすがに歩けないので、適当なサムローをとめて交渉をしていると、別の小型ソンテウが止まって、バス停まで送ってくれるという。
バス停に到着。ソンテウの運転手が、コーン島行きのバスの前まで連れていってくれた。バスは、日本のバスが百倍ぐらいボロくなったようなバスだった。そういえば、ラオスに来て初めてバスに乗る。乗り込むと、満席を通り越してすし詰め状態。強引に乗り込み、乗客に両手を合わせて挨拶をする。見ると、観光客らしき外国人も数人乗っている。
バスは、その後も乗客を乗せて十時過ぎに出発。ガイドブックには、コーン島まで二時間と書いてある。二時間、立ちっぱなしなのだろうか、とちょっと不安になる。ラオス人は、皆うまい具合に席をつくって床に座っている。バスだと、直接風を浴びることができないのが残念だが、窓の外の風景はやはり面白いし、車内の人々の様子も、見ているだけで興味深い。バスは、ソンテウと同様に時々の村に停車する。物売りの女の子が大量にバスに乗り込み、あるいはバスを取り囲み、物を売ろうとする。昨日は何も買えなかったが、ジュースと焼き鳥のようなもの、もち米のビニール詰めを買う。うまい。
一時間を過ぎたあたりから、乗客が徐々に減り、ようやく席に座ることが出来た。さらに一時間ほど進むと、船着き場に到着。バスを運ぶフェリーを待っていると、日本人が話しかけてきた。聞くと、最初からバスに乗り込んでいたという。全然気づかなかった。話してみるととても面白い人で、ラオス語を話せるらしく、ラオス人ともどうにか会話をしている。コーン島に行くというので、向こうで一緒になったら嫌だな、と思いながらも、面白い人なので別にかまわないか、とも思う。
船着き場で一時間程待ち、バスを載せたフェリーでメコン川を渡る。川を渡るとコーン島に到着。フェリーの着いた村が、ゲストハウスがあるムアンコーンという村かと思ったが、見回してもそれらしきものは何もない。乗っている欧米人も降りない。仕方がないのでそのままバスに乗る。バスが島を走る。今まで以上に一面の田園風景が広がっている。雨が降っているせいか、道を歩く人はあまりいない。とても静かな島だ。さらに三十分ほど走り、終点に到着。どうやらここがムアンコーンらしく、ゲストハウスらしき建物が何件か建っている。結局四時間以上かかった。とりあえず、目の前にある雑貨店兼レストランのような店に入る。バスで話しかけてきた日本人が寄ってきて、「どこに泊まります?」と聞いてきた。二人でイスに座ってガイドブックを見ていると、雨が突然激しさを増す。ゲストハウスを決めないと何もすることが出来ないので、メコン川に面するポーン・ゲストハウスに泊まることにする。雨の中、二人で走っていくと、ポーン・ゲストハウスの隣に、結構きれいなゲストハウスがあるのを発見。ガイドブックには出ていないので、最近建てられたものかもしれない。値段を聞くと、二万キープとのこと。部屋を見せてもらうと、十分すぎるぐらい広くてきれい。シャワーは水しか出ないが、ここに泊まることにする。
部屋に入って荷物を置いた後、日本人のなんとかさん(名前失念)とゲストハウスのレストランで食事をとる。話を聞くと、埼玉の高校の非常勤講師をしていて、暇を見つけては南米やアジアによく旅行に行くとのこと。性格が適当で、話も面白いので、一緒にいて疲れない。ラオビールを飲み、つまみにラープともち米を食べる。この人は、九時前からバスに乗って待機していたらしい。本来であれば、バスは九時出発の予定だったらしい。もし、予定通りに九時に出発していたら、ぼくはここにこれなかったかもしれないわけだ。良かった。
一時間程雑談をしていると、雨が小降りになってきた。なんとかさんは、体調が思わしくないというので、一人で散歩に出る。一緒に行くと言われたらどうしようかと心配だったので、一人で歩けることがとても嬉しい。この旅行始まって以来の、雨の中の散歩だ。
 ゲストハウスの前の道を、来た方向と逆に進む。橋を渡って少し行くと、男の子たちがメコン川で遊んでいる。声をかけると、とてもノリが良い。さらに進むと、寺院が現れる。入っていいのかな、と躊躇するが、中から御経のようなものが聞こえてきたので、我慢できずに敷地内に入る。御経は、僧侶全員で読経する日本のやりかたとは異なり、一人が経を唱えると、輪唱のように残りの僧が経を反復する。経を唱えているのは、どうやら女性らしい。雨音の中に経が響く。暫し聞き惚れ、佇む。
ゲストハウスの前の道を、来た方向と逆に進む。橋を渡って少し行くと、男の子たちがメコン川で遊んでいる。声をかけると、とてもノリが良い。さらに進むと、寺院が現れる。入っていいのかな、と躊躇するが、中から御経のようなものが聞こえてきたので、我慢できずに敷地内に入る。御経は、僧侶全員で読経する日本のやりかたとは異なり、一人が経を唱えると、輪唱のように残りの僧が経を反復する。経を唱えているのは、どうやら女性らしい。雨音の中に経が響く。暫し聞き惚れ、佇む。
寺院を越えると、道が急に狭くなり、民家のようなところに入ってしまった。道は、完全に水没している。ぼくのサンダルはもうぐっちょぐっちょで使い物にならないので、躊躇なく水の中をじゃぶじゃぶと進む。しばらく進むと、完全に住居の敷地に迷い込んでしまった。と、家の軒下で、ハンモックのようなものに座っているおばさんを発見。挨拶をして、ジェスチャーでどこへ行けばよいのか聞くと、座っている軒の先の方を指す。向こうと言うことらしい。おばさんの隣を通って、御礼を言って先へ進む。
軒先をくぐると、田んぼの畦道に出た。田に落ちないように慎重に進むが、いかんせんサンダルが履物としての機能をはたしていないため、足への負担がすごい。指が打撲したように痛む。田んぼを越えると、広い道路に出た。雨のせいか、チャンパーサックと比べると人の通りはかなり少ない。時折、自転車に乗った人が通りすぎる程度で、歩いている人にはほとんど会わない。静かだ。
 ヴィエンチャンも、チャンパーサックも、何もないと言われているけれど、実際に行ってみると何かしらあった。けれども、このコーン島には本当に何もないようだ。一本道が視界の先まで続き、道の両わきには田圃が広がる。道の左先には山が聳え、右先にはメコン川が流れる。一本道がとても気持ち良い。ぼろぼろのサンダルを引きずりながら、一歩一歩、踏みしめて歩く。この道がどこに続くのか、ぼくは知らない。散歩好きなある友人が、歩いていると必ず目的地に到着するのが良いよね、と言っていたが、こうやって目的地の分からない散歩もとても楽しい。歩きながら思う。いつか、歩くだけの旅行をしてみたい。どこの国でも良いので、バスも、電車も、飛行機も使わずに、一年ぐらい歩き続けたい。もちろん、それがどれだけ困難なことであるか、散歩程度の歩行しかしたことがないぼくにでも想像は出来る。けれども、人間はもともと歩くことによって移動を行なってきたわけだし、歴史を見れば多くの人々が徒歩で国々を渡り歩いていたこともわかる。人にもよるとは思うが、歩くことはそれだけで人間を成長させると思う。十年後でも、二十年後でも良いので、徒歩による旅行をしてみたい。
ヴィエンチャンも、チャンパーサックも、何もないと言われているけれど、実際に行ってみると何かしらあった。けれども、このコーン島には本当に何もないようだ。一本道が視界の先まで続き、道の両わきには田圃が広がる。道の左先には山が聳え、右先にはメコン川が流れる。一本道がとても気持ち良い。ぼろぼろのサンダルを引きずりながら、一歩一歩、踏みしめて歩く。この道がどこに続くのか、ぼくは知らない。散歩好きなある友人が、歩いていると必ず目的地に到着するのが良いよね、と言っていたが、こうやって目的地の分からない散歩もとても楽しい。歩きながら思う。いつか、歩くだけの旅行をしてみたい。どこの国でも良いので、バスも、電車も、飛行機も使わずに、一年ぐらい歩き続けたい。もちろん、それがどれだけ困難なことであるか、散歩程度の歩行しかしたことがないぼくにでも想像は出来る。けれども、人間はもともと歩くことによって移動を行なってきたわけだし、歴史を見れば多くの人々が徒歩で国々を渡り歩いていたこともわかる。人にもよるとは思うが、歩くことはそれだけで人間を成長させると思う。十年後でも、二十年後でも良いので、徒歩による旅行をしてみたい。
 遠くの方から、カランコロンと風鈴のような奇麗な音色が聞こえてくる。なんだろうと思って歩み進むと、田圃の中で水牛が草を食み、その先にはまるで水墨画のように霞がかかっている山々の風景が広がる。カラン、コロンと不思議な音色が八方から聞こえてくる。この音は、何の音なのだろうか?水牛のいるほうへ行ってみようかと思うが、田圃が水に埋まっていて行くことが出来ない。道を過ぎる人は誰もいない。なんだかあの世に来てしまったような錯覚を覚え、通り過ぎる。カラン、コロンと音が背後から聞こえる。
遠くの方から、カランコロンと風鈴のような奇麗な音色が聞こえてくる。なんだろうと思って歩み進むと、田圃の中で水牛が草を食み、その先にはまるで水墨画のように霞がかかっている山々の風景が広がる。カラン、コロンと不思議な音色が八方から聞こえてくる。この音は、何の音なのだろうか?水牛のいるほうへ行ってみようかと思うが、田圃が水に埋まっていて行くことが出来ない。道を過ぎる人は誰もいない。なんだかあの世に来てしまったような錯覚を覚え、通り過ぎる。カラン、コロンと音が背後から聞こえる。
 自転車に乗った男の子達が三人、後ろから走って来て、すれ違いざまに険しい顔をしてぼくを一瞥する。両手を合わせて挨拶をすると、険しい顔が急に笑顔になる。二人はそのまま先へ走るが、一人は自転車を停めたまま動かない。どうしたのだろうと思って横を通りすぎると、後から付いてくる。何を話すわけでもなく、にこにこしながら付いてくる。ラオス語で話しかけようにも、ガイドブックは宿に置いてきてしまった。英語で話しかけるが、やはり通じない。仕方がないので、そのまま歩く。しばらく歩くと、男の子がいきなりラオス語で何かを言ってきた。が、何を言っているのかさっぱり分からない。わからないよ、とジェスチャーで示すが、男の子はニコニコしているだけ。ぼくもニコニコして、そのまま歩く。
自転車に乗った男の子達が三人、後ろから走って来て、すれ違いざまに険しい顔をしてぼくを一瞥する。両手を合わせて挨拶をすると、険しい顔が急に笑顔になる。二人はそのまま先へ走るが、一人は自転車を停めたまま動かない。どうしたのだろうと思って横を通りすぎると、後から付いてくる。何を話すわけでもなく、にこにこしながら付いてくる。ラオス語で話しかけようにも、ガイドブックは宿に置いてきてしまった。英語で話しかけるが、やはり通じない。仕方がないので、そのまま歩く。しばらく歩くと、男の子がいきなりラオス語で何かを言ってきた。が、何を言っているのかさっぱり分からない。わからないよ、とジェスチャーで示すが、男の子はニコニコしているだけ。ぼくもニコニコして、そのまま歩く。
三十分もそのような状態で歩く。突然、男の子が左手の田圃の中に建っている高床式の家を指さして何かを言った。どうやら、あそこが彼の家らしい。ぼくの部屋よりも小さい家だ。家の下で、水牛の親子が草を食み、犬が男の子を見て尻尾を振っている。男の子が家に向かって何かを叫ぶ。家の中から女性の声が聞こえ、母親らしき人が顔を出す。挨拶をすると、微笑んで応えてくれる。男の子にさようならを言って先へ進む。ぼくは昨日聞いたテレビジョン・パーソナリティの歌を思い出す。
There's a little man
In a little house
With a little pet dog
And a little pet mouse...............
さらに進むと、今度は道の右手から、美しい蛙の鳴き声が聞こえてくる。「美しい鳴き声」というのは誇張した表現ではなく、本当に美しい声で鳴いている。声は、八方どころかありとあらゆる場所から聞こえてくる。田舎育ちのぼくは、雨の日に田圃で鳴く蛙の声は聞き慣れているはずなのに、こんなに美しい鳴き声を聞くのは初めてだ。蛙の声の他に、鳥の声も聞こえる。蛙も、鳥も、姿は全く見えない。この美しい鳴き声は、どのようなオーディオ技術をもってしても、再現することは不可能だろう。この素晴らしい音響は、今ぼくが立っているこの場所でしか聞くことはできないのだ。この蛙や鳥たちは、いつから鳴いていたのだろう。さっき聞いた御経と同じように、音が心に染み渡る。もし、コーン島に来なかったら、ぼくは人生でこの音を聞きのがしていたかもしれない。来てよかった。目を閉じて、蛙と鳥と風と雨と土の音に耳を傾ける。音以外のすべてから、意識が遠くなる。
音に身を委ねながら考える。今、ぼくが歩いてきた道も、この場所も、この音も、すべてはぼくがここに来る以前から存在していたし、ぼくがここを去った後も存在し続けるだろう。けれども、ぼくがここに来て、こうやって観察をするまでは、「ぼくに観察されるこの場所」は存在しなかったはずだ。ぼくがここに来て、この場所を観察して初めて、「ぼくに観察された場所」が誕生したのだ。それは、今回の旅行で訪れたすべての場所に対して言えることであり、今まで生きてきて訪れたすべての場所に対しても言えるはずだ。それらの「ぼくに観察された場所」は、あくまでも「ぼくに観察された場所」であって、それ以外の何処でもない。別の人がその場所を観察しても、それはぼくが観察した場所とは大きく異なる。ぼくに観察されるまで、「ぼくに観察された場所」は存在しなかったのだ。
突然、「観察をする義務」を感じる。世界はぼくに観察されるまで、ぼくに観察されることはない。保坂和志は「私が生まれる前から世界はあり、私が死んだ後も世界はありつづける」と書いている。レヴィ・ストロースは『悲しき熱帯』の中で、「世界は人間なしに始まったし、人間なしに終わるだろう」と書いている。ぼくに観察される場所あるいは物は、ぼくが生まれる前からそこに存在していたし、ぼくが死んだ後もそこに存在を続けるだろう。けれども、「観察された対象」はぼくに観察されるまで、存在することは有り得ない。同時に思う。観察するということは、解釈するということとは全く異なる行為だ。たとえば、発展途上のこの国の人々が、貧しくても先進国の人々が失った幸せの中で生きているのだろうなんてことを考えるのは、自己満足の感傷に過ぎない。あるいは、訪れた異国に対して郷愁を感じることも、逆に憂いを抱くことも、そのような情感を否定するつもりは毛頭ないが、「観察」という観点から見れば、それらはすべて違う世界に住む「他人」による勝手な感情に過ぎない。人は、何かを見れば何かを感じる。何かに触れれば何かを感じる。何かを聞けば何かを感じる。それを避けることはできないし、それがなかったら人生はとても味気ないものになってしまうだろう。けれども、それは「観察」ではない。「観察すること」とは、あくまで「観察すること」に過ぎない。ぼくは「観察をする義務」を強く感じている。「観察すること」を現象学的な意味に取る人もいるかもしれないが、「観察」に「ぼくという人間」が必須である以上、現象学的な考え方では決してない。かといって「ぼくという個人」を「主観」という言葉に置き換えることにも抵抗を感じる。人間は、ひとりひとりが唯一の存在であるが故に、「かけがえのない命」なんて言い方をされるが、全員が唯一ということは、逆に言えば「かけがえのない命」なんてものは存在しないし、個人がかけがえのないものであるとしたら、世界に存在するすべてのものは同様に唯一無二なはずだから、全存在が「かけがえのない」もの、存在自体に意味のあるものということになり、翻して考えれば、全存在は「かけがえのある」ものだということになる。つまり、「かけがえ」の「在る」「無し」は、同じ意味を成すことになる。それと同じ考えで、ぼくという個人がこの世界に生まれた意味は「ない」と思っている。ぼくが生まれてきたのは、必然でも偶然でもなく、あえて言うなら「生まれるべくして、たまたま生まれてきた」のだろう。そして、諸行無常の言説通り、いつの日かは消滅する。そこから生じる結果はあっても、意味はないし、かけがえのないものでもない。こうやって言うと、虚無的な考えに聞こえるかも知れないが、「意味がない」ということは、「死んでも良い」と言うことではないし、「価値がない」ということでもない。ただ単に意味が発生しないというだけだ。生きているということは、意味を発生するものではなくて、「観察すること」に等しいのではないか。対象は、別に異国でなくても良いし、特別なものでなくても良い。いつの間にか生まれてきて、いつの間にか死んでいく(消滅する)すべての生き物にとって、「観察すること」は義務なのではないだろうか。今のぼくには「観察すること」について、これ以上考えること、説明することは出来ない。けれども、強く義務感を感じる。そんなことを考えながら、蛙の音に意識を揺るがせる。
 時計を見ると、六時を過ぎている。辺りが少し暗くなってきた。ここに来るまで、一度も街灯を見なかったので、暗くなる前に帰らないと、完全に真っ暗になってしまうだろう。名残惜しいが、今来た道を戻り始める。しばらく歩くと、さっき別れた男の子が、大声で歌いながら向こうから歩いてくる。ぼくに気づくと、歌うのをやめてこちらに手を振り、道沿いの川に降りて、水浴びを始めた。家に風呂がないので、毎日ここに来て水浴びをしているのだろう。男の子は、水を浴びながらニコニコとぼくに微笑みかける。ガイドブックを持ってくれば、この子ともう少し話が出来たのに、ととても残念に思う。元気でね。
時計を見ると、六時を過ぎている。辺りが少し暗くなってきた。ここに来るまで、一度も街灯を見なかったので、暗くなる前に帰らないと、完全に真っ暗になってしまうだろう。名残惜しいが、今来た道を戻り始める。しばらく歩くと、さっき別れた男の子が、大声で歌いながら向こうから歩いてくる。ぼくに気づくと、歌うのをやめてこちらに手を振り、道沿いの川に降りて、水浴びを始めた。家に風呂がないので、毎日ここに来て水浴びをしているのだろう。男の子は、水を浴びながらニコニコとぼくに微笑みかける。ガイドブックを持ってくれば、この子ともう少し話が出来たのに、ととても残念に思う。元気でね。
足下が覚束ないほど真っ暗になった頃に、ゲストハウスに到着。他の国であれば、こんな真っ暗な時間に外を歩くなんてことは絶対にしないが、ラオスだと気が緩んでしまう。気をつけよう。部屋に戻り、読書をしているとなんとかさんが部屋にやって来たので、レストランで一緒に夕飯を食べる。明日一緒にコン島、デッド島に行かないかと誘われる。さらにその先のカンボジアの国境までも行けるらしい。そうか、もうカンボジアの近くまで来ているのか。旅行の日程はまだ余っているので、それも良いかなとちょっと考えるが、なんとかさんが「その次の日に、一緒にラオスを出ましょうよ」と言い出したので、それはちょっといやだなあと思い、明日の予定も断る。明日だけ一緒に行動するのは構わないが、ラオスを出国するときはひとりでいたい。ソンテウやバスに乗っているときに、話しかけられるのも煩わしい。結局、ぼくは明日コーン島を後にして、パクセに戻ることにする。
寝る前に、MDで『Routine』を聞きながら、いつものように『日本的霊性』と『姑獲鳥の夏』を読む。他にも数冊持ってきているが、この両書がおもしろすぎて、他の本を読む気がしない。こういうときは、飽きるまで読むに限る。

ここからパクセへ戻るバスは、一番遅くても九時ぐらいに出てしまうらしい。明日は絶対に遅刻できない。

朝、寝坊をして八時起床。パクセ行きの飛行機のチェックインが八時半なので、急いで着替えてゲストハウスを出る。トゥクトゥクで空港まで向かう。急いでチェックインカウンターに行くと、航空券に書いているチェックインの時間は間違いで、実際のチェックインは九時ということが判明。
九時にチェックインする。日本人の観光客がひとりいて、話しかけてくる。ぼくよりもかなり年上で、甲高い声で早口でぺらぺらと話す。一目で気が合わないのがわかったので、無視。十時に離陸。飛行機は思ったよりも小さい。外務省から注意喚起が出ている飛行機ではないので、墜落はしないと思うが、良い噂を聞かないラオス航空だけに少し緊張する。ぼくの隣には、英語が話せるラオス人の男性が座った。それほど流暢な英語ではないが、ぼくも同じようなものなので、片言同士でちょうど良い。話してみると、ぼくよりも年下なのになかなかの実業家らしく、パクセにセカンドハウスがあるという。パクセに着くまで、一時間ほど雑談をする。歳が近いこともあって、楽しかった。名前を聞いたが、すぐに忘れた。
十一時過ぎ、パクセに到着。雨がぱらぱらと降っている。空港を出ると、トゥクトゥクが一台しかいない。日本人の男性が、なにかにつけて気持ちの悪い声で笑い、しゃべり、それが癇に障る。トゥクトゥクに乗り込むと、フランス人の女性二人が先に乗っている。女性と言っても、二人とも十代に見える。長いこと待たされているのか、この町が気にくわないのか、二人ともむすっとしている。
ぼくたちが乗り込んでも、トゥクトゥクは一向に走り出す気配がない。見ると、運転手が観光客の外国人のおばさん相手に何か話し込んでいる。おそらく値段の交渉をしているのだろう。「早く行こうよ!」と怒鳴ると、「もうちょっと待って!」と怒鳴り返してくる。フランス人の女の子が「まだ来ないの?」と聞くので、「なんかおばさんと交渉しているんだけど」というと、二人はトゥクトゥクの天井をどんどんと叩き出した。ぼくも一緒に叩く。トゥクトゥクが揺れる。それから五分ほどして、ようやく運転手が戻ってきた。やっと走り出したと思ったら、いきなり給油所に立ち寄る。いい加減頭にきたので文句を言おうとしたら、日本人のおやじが甲高い声で笑いだした。その声の方にいらいらして、なにも言う気がなくなる。
パクセの市内に到着する前に、女の子達がゲストハウスの前でトゥクトゥクを降りる。このおやじとこれ以上一緒にいたくないので、ぼくもそこで降りる。雨が激しを増してきた。ここは一体どこなのだろう?ちょうど良くサムローのような乗り物が来たので、停めて、「チャンパーサックに行きたいのだけど」と言うと、英語は通じないようだが、乗れ、乗れ、と後部座席を指さす。「チャンパーサック?」と聞くと、「バス、バス」と言う。バス停まで連れていってくれるらしい。雨に濡れながら、バス停へ向かう。
バス停には、十分ほどで到着。サムローのおやじさんが、チャンパーサックへ行くソンテウを教えてくれる。ソンテウとは、小型トラックの後部の荷台に席があるようなもの。ぼくが着いたときには、席はすでに満席で、ぼくの顔をみると強引に詰めて席を作ってくれた。両手を合わせて、乗っている皆さんに「サヴァーイディー」と挨拶をする。しかしこれ、本当にチャンパーサックに行くのだろうか。聞きたくても、英語がまったく通じない。
 出発直後に、数人のラオスの若者がソンテウに乗り込んできた。そのうちのひとりが、少しだけ英語を話せるみたいだ。このソンテウは、確かにチャンパーサックへ行くとのこと。ほっと一安心。青年の名前を聞くが、一秒後に忘れる。しかしこの青年、英語を習い始めてまだ半年ということで、なにかにつけて英語を話したがる。ぼくは風景でも見ながら静かにソンテウに揺られたかったのだが、次から次へと話を続ける。最初は楽しかったけど、途中からうざくなって無視をすると、たばこを吸いながら友人たちの方へ戻っていった。
出発直後に、数人のラオスの若者がソンテウに乗り込んできた。そのうちのひとりが、少しだけ英語を話せるみたいだ。このソンテウは、確かにチャンパーサックへ行くとのこと。ほっと一安心。青年の名前を聞くが、一秒後に忘れる。しかしこの青年、英語を習い始めてまだ半年ということで、なにかにつけて英語を話したがる。ぼくは風景でも見ながら静かにソンテウに揺られたかったのだが、次から次へと話を続ける。最初は楽しかったけど、途中からうざくなって無視をすると、たばこを吸いながら友人たちの方へ戻っていった。
 パクセを出てから、延々と一本道を進む。この距離だとさすがに歩くことはできないが、一度も道を曲がらず、ひたすらに一本道を走り続ける。ぼくは一本道が大好きなので、直接に風を受け、ラオスの人々に押しつぶされそうになりながら走るこのソンテウが楽しくて仕方がない。周りには田んぼが広がっている。田んぼの中に、高床式の家がまばらに建っている。ソンテウは、数キロごとに村に止まる。村の物売りの子供たちが一斉にソンテウを取り囲み、飲み物やら食べ物やらを売ろうとするが、ぼくに気づくとはっと固まってしまう。が、両手を合わせて挨拶をすると、ニコッと笑ってくれる。歩くことも楽しいけれど、こうやってただ風景を眺めながら移動するのも、とても楽しい。
パクセを出てから、延々と一本道を進む。この距離だとさすがに歩くことはできないが、一度も道を曲がらず、ひたすらに一本道を走り続ける。ぼくは一本道が大好きなので、直接に風を受け、ラオスの人々に押しつぶされそうになりながら走るこのソンテウが楽しくて仕方がない。周りには田んぼが広がっている。田んぼの中に、高床式の家がまばらに建っている。ソンテウは、数キロごとに村に止まる。村の物売りの子供たちが一斉にソンテウを取り囲み、飲み物やら食べ物やらを売ろうとするが、ぼくに気づくとはっと固まってしまう。が、両手を合わせて挨拶をすると、ニコッと笑ってくれる。歩くことも楽しいけれど、こうやってただ風景を眺めながら移動するのも、とても楽しい。
約二時間ほどで、メコン川沿いの船着き場に到着。巨大な筏にソンテウを乗せて、メコン川を渡る。雄大なメコンの川上を、ソンテウとぼくを乗せた筏がゆっくりと流れる。雨も、いつの間にかやんでいる。
 川を渡ると、小さな村に到着。英語を話せる若者が、「ここがチャンパーサックだ」と言う。うっわー、何もねー!!と思いながら、ソンテウを降りる。ガイドブックに、何件かゲストハウスが紹介されていたけど、そんなものはどこにも見当たらない。若者に、「このへんにゲストハウスは・・・」と聞くと、周りの人と何かぼそぼそと話し、「この道をずっと先に行ったところにあるから、サムローで行け」とのこと。歩いては行けないか?と聞くと、二キロぐらいだという。それならば歩こうと思って歩き出すと、若者が後ろから追っかけてきて、ゲストハウスまでソンテウで送ってくれるという。お言葉に甘えて、再びソンテウに乗る。
川を渡ると、小さな村に到着。英語を話せる若者が、「ここがチャンパーサックだ」と言う。うっわー、何もねー!!と思いながら、ソンテウを降りる。ガイドブックに、何件かゲストハウスが紹介されていたけど、そんなものはどこにも見当たらない。若者に、「このへんにゲストハウスは・・・」と聞くと、周りの人と何かぼそぼそと話し、「この道をずっと先に行ったところにあるから、サムローで行け」とのこと。歩いては行けないか?と聞くと、二キロぐらいだという。それならば歩こうと思って歩き出すと、若者が後ろから追っかけてきて、ゲストハウスまでソンテウで送ってくれるという。お言葉に甘えて、再びソンテウに乗る。
五分ほどで、ソンテウを降りる。今度こそ本当にお別れなので、乗っているすべての人に丁寧にお礼を言って別れる。ソンテウが去り、周りを見回すと、何もない。こんなところに本当にゲストハウスがあるのかな、と思って少し歩くと、「ハロー」と何処からか声をかけられる。振り向くと、家の中から女性がぼくを呼んでいる。よく見ると、ゲストハウスと書いてある。部屋を見せてもらって、値段を聞くと一万キープ(140円)だという。時間もないことだし、ここに泊まることにする。
 ゲストハウスにはレストランが併設しているので、レストランで昼食をとる。ラープという挽肉を香草で炒めたものと、もち米のようなライス。うまい。食後、外に出ると観光客と思しき欧米人四人組が、トゥクトゥクとなにやら言い争っている。言い争っているというか、おそらく値段の交渉なのだろう。ワット・プーに行くのであれば、ぼくも一緒に乗っていこうかと思い、「ワット・プーに行くの?」と外国人に聞くと、「そうだけど、一緒に行く?」と誘ってくれた。渡りに船ですから、お言葉に甘えて参加することにして、値段の交渉は彼らに任せる。
ゲストハウスにはレストランが併設しているので、レストランで昼食をとる。ラープという挽肉を香草で炒めたものと、もち米のようなライス。うまい。食後、外に出ると観光客と思しき欧米人四人組が、トゥクトゥクとなにやら言い争っている。言い争っているというか、おそらく値段の交渉なのだろう。ワット・プーに行くのであれば、ぼくも一緒に乗っていこうかと思い、「ワット・プーに行くの?」と外国人に聞くと、「そうだけど、一緒に行く?」と誘ってくれた。渡りに船ですから、お言葉に甘えて参加することにして、値段の交渉は彼らに任せる。
 値段の折り合いがついて、トゥクトゥクに乗る。話を聞くと、四人は一緒に旅をしているわけではなく、お互いにカップルで旅をしていて、ぼくと同様にさっき出会ったばかりだという。四人の名前をそれぞれ聞くが、速攻で忘れる。一組のカップルに、どこから来たの?と聞くと、アイルランドとのこと。アイルランドと言えば、今回の旅行に持ってきた本の中に、「チェ・ゲバラ モーターサイクル南米旅行日記」があるので、「今、ゲバラの本を読んでいるのです」と言うと、二人は不思議そうな顔をした。あれ?ゲバラって、アイルランドじゃなくてアルゼンチンじゃん、とすぐに思い出し、ごめんごめん、勘違いしちった!と言おうしたが、英語力の不足でなかなか通じず、気がついたらぼくはアイルランドに二年間暮らしていたということになっていた。面倒くさいので否定をせずに、子供のころ住んでいたから、街の名前とか覚えていないとか適当な嘘をつく。コミュニケーションとは難しいものです。
値段の折り合いがついて、トゥクトゥクに乗る。話を聞くと、四人は一緒に旅をしているわけではなく、お互いにカップルで旅をしていて、ぼくと同様にさっき出会ったばかりだという。四人の名前をそれぞれ聞くが、速攻で忘れる。一組のカップルに、どこから来たの?と聞くと、アイルランドとのこと。アイルランドと言えば、今回の旅行に持ってきた本の中に、「チェ・ゲバラ モーターサイクル南米旅行日記」があるので、「今、ゲバラの本を読んでいるのです」と言うと、二人は不思議そうな顔をした。あれ?ゲバラって、アイルランドじゃなくてアルゼンチンじゃん、とすぐに思い出し、ごめんごめん、勘違いしちった!と言おうしたが、英語力の不足でなかなか通じず、気がついたらぼくはアイルランドに二年間暮らしていたということになっていた。面倒くさいので否定をせずに、子供のころ住んでいたから、街の名前とか覚えていないとか適当な嘘をつく。コミュニケーションとは難しいものです。
猛スピードで走るトゥクトゥクから外を眺める。こうして見ると、ヴィエンチャンはやはり首都だったのだなと感じる。チャンパーサックは、まさしく田舎!という感じで、のどかな田園風景がひたすら続く。途中、木に寄り掛かるようにして座っている巨大な仏像を発見。道路に背を向けているため、顔が見えない。正面から見たかったけど、トゥクトゥクは猛スピードで通り過ぎる。帰りは歩いて帰ろう、と心に決める。
三十分ほどでワット・プーに到着。遠くに、遺跡が広がっているのが見える。うおおおお!と感動する。時計を見ると、三時を過ぎている。受付で、何時まで見れます?と聞くと、五時までとのこと。カップルのうち一組は、受付の傍にあるレストランで食事をしてから行くという。もう一組のカップルは、受付を済ませてさっさと入っていった。ぼくはひとりで歩きたかったので、少し時間差で中に入る。
ワット・プーは、十二世紀ごろに建てられたとされるクメールの寺院の大遺跡で、自然災害や戦乱などによる人為的な被害のために、全体に損傷が激しい。それでも、クメールの遺跡を初めて観たということもあって、そのあまりの壮麗さ、そして、時間と共に正しく朽ちていくその姿に圧倒される。泥と草で荒れ果てた地面のあちこちには、寺院内に飾られていたであろう像たちが散乱している。寺院は、ところどころ補強されてはいるものの、かろうじて残っているかのように脆い印象を受ける。雨が降った後のため、地面はぬかるみ、足場が悪い。寺院に入ると、歩けるところがほとんどないぐらいに荒れ果てている。その荒れ具合が、とてもいい。ぼくは、不意に京極堂の台詞を思い出す。
「量子力学が示唆する極論はーこの世界は過去を含めて<観察者が観察した時点で遡って創られた>だ」
ぼくは、クメールの歴史に対して憧憬というものを持ち合わせていない。そのためか、この遺跡に対して「強者どもが夢の跡」のような感傷的な感想は全く持たない。ただ、この朽ちていく姿が美しいと思うだけだ。けれども、何百年か前にはさぞや絢爛であったであろうこれらの建物が、長年の風雨や、人為的あるいは自然現象により腐食しているこの状態を見れば、ぼくが生まれるずっと以前からこの場所にこの寺院が存在していたであろうことは容易に想像できる。この目の前に広がる風景や遺跡群が、ぼくがここに来てそれらを観察する以前からここに存在していたことは間違いない。けれども、京極堂の台詞がどうしても頭から離れない。この目の前の世界は、ぼくがここに来る以前から、あるいは観察をする以前から本当にここに存在していたのだろうか?
 |  |
 |  |
 |  |
正面の、勾配の急な階段を上って本殿に向かう。途中、人程の大きさの仏像があり、そばでお線香を売っている親子(?)がいる。汗をかきながら階段を登り終えると、本殿がある。ヒンドゥー様式の浮彫で装飾された寺院は、思ったよりも小さい。中に入ると、あとから持ち込まれたという仏像が四体、静かに座っている。皆、右手を膝にのせ、左手の掌を上に向ける例のポーズをとっている。たくさんのお供え物がある。今にも崩れ落ちそうな壇に座る仏像を、ゆっくりと眺める。
結局、五時ぎりぎりまで粘ってワット・プーを後にする。ふたたび欧米人カップルたちと合流し、トゥクトゥクで帰る。十分ほど進んだところで、トゥクトゥクを停めてもらい、そこから歩くことにする。
 しばらく歩くと、先ほどの木々の間に座っている仏像のところへ着いた。これだー!と駆け寄ると、そばで子供たちが遊んでいる。挨拶をすると、笑顔で応えてくれる。仏像を正面から見るために回り込むと、子供たちもついてくる。仏像は、凛々しい顔つきをしている。この仏像は、特に観光されるわけでもなく、昔からただここにあるものとしてここに座っているのだろう。臼杵の磨崖仏のことを思い出す。それらの石仏群は、何百年もの間、村人たちにただそこにあるものとして扱われ、子供たちの遊び場となっていたが、今では完全に修復され、国宝にも指定されて立派に保護されている。
しばらく歩くと、先ほどの木々の間に座っている仏像のところへ着いた。これだー!と駆け寄ると、そばで子供たちが遊んでいる。挨拶をすると、笑顔で応えてくれる。仏像を正面から見るために回り込むと、子供たちもついてくる。仏像は、凛々しい顔つきをしている。この仏像は、特に観光されるわけでもなく、昔からただここにあるものとしてここに座っているのだろう。臼杵の磨崖仏のことを思い出す。それらの石仏群は、何百年もの間、村人たちにただそこにあるものとして扱われ、子供たちの遊び場となっていたが、今では完全に修復され、国宝にも指定されて立派に保護されている。 文化財を保護することに対して異議を唱えるつもりはないけれど、ぼくがより心を惹かれるのは、今ぼくの目の前にあるような、雨や風にさらされながら蕭々とそこにある仏像で、そこには何とも言えない寂しさと、ただあるだけで放たれるような神々しさがある。子供たちは、恥ずかしそうにぼくの方を見ている。ガイドブックを片手に話しかける。お姉さんが、三人の弟の子守をしているらしい。とても頭の良い子で、ぼくがたどたどしいラオス語で言おうとすることを、すぐに汲んで答えてくれる。お姉さんの年齢を聞くと、十一歳だという。お礼を言って、その場を去る。
文化財を保護することに対して異議を唱えるつもりはないけれど、ぼくがより心を惹かれるのは、今ぼくの目の前にあるような、雨や風にさらされながら蕭々とそこにある仏像で、そこには何とも言えない寂しさと、ただあるだけで放たれるような神々しさがある。子供たちは、恥ずかしそうにぼくの方を見ている。ガイドブックを片手に話しかける。お姉さんが、三人の弟の子守をしているらしい。とても頭の良い子で、ぼくがたどたどしいラオス語で言おうとすることを、すぐに汲んで答えてくれる。お姉さんの年齢を聞くと、十一歳だという。お礼を言って、その場を去る。
 歩いてみると、想像以上に素晴らしい風景に出会う。右手にはメコン川が流れ、左手には田園が広がる。道には動物が悠然と闊歩し、道路の左右にある高床式の家からは、子供の声、親の声、音楽、様々な音が聞こえてくる。道を歩く子供も大人も、ぼくに気づくと怪訝そうな顔でじっと見つめるが、両手を合わせて挨拶をするととても優しい笑顔で応えてくれる。日が落ちてきた。田んぼから、蛙の声が聞こえる。日本の田舎で聞いた蛙の声よりも、良い声で鳴いている。トンボが群れをなして飛んでいる。数が半端じゃない。大気の色が、夕方に移り行く過程の、とても良い色に変化している。周りを見渡しても街灯なんてものは見当たらない。このままでは、ゲストハウスに辿り着く前に真っ暗になってしまいそうだ。少し歩く速度を早めよう。
歩いてみると、想像以上に素晴らしい風景に出会う。右手にはメコン川が流れ、左手には田園が広がる。道には動物が悠然と闊歩し、道路の左右にある高床式の家からは、子供の声、親の声、音楽、様々な音が聞こえてくる。道を歩く子供も大人も、ぼくに気づくと怪訝そうな顔でじっと見つめるが、両手を合わせて挨拶をするととても優しい笑顔で応えてくれる。日が落ちてきた。田んぼから、蛙の声が聞こえる。日本の田舎で聞いた蛙の声よりも、良い声で鳴いている。トンボが群れをなして飛んでいる。数が半端じゃない。大気の色が、夕方に移り行く過程の、とても良い色に変化している。周りを見渡しても街灯なんてものは見当たらない。このままでは、ゲストハウスに辿り着く前に真っ暗になってしまいそうだ。少し歩く速度を早めよう。
ふと左手を見ると、メコン川に向かって座っている仏像がある。夕刻と重なって、仏像の背中がやけに寂しそうに見える。仏像の方へ行きたいが、バリケードが張ってあって、向こう側へ行けないようになっている。近くに牛を連れているおじさんがいたので、入っていいか?と聞くと、全然問題ないようなので、バリケードをくぐって仏像の方へ行く。地面がぬかるんでいて、サンダルがずぶずぶと地面に埋まる。もつれる足をどうにか動かして、仏像のもとへ。正面へ周り、仏像を御顔を拝む。仏像は、静かにメコンの流れを眺めている。ただ、メコンの流れを眺めている。メコンを眺めることを強いられた仏像に、ちょっとだけ哀れみを感じる。

結局、ゲストハウスに着いた頃には辺りは真っ暗になっていた。昼と同じレストランで、夕食をとる。あまりおなかが空いていなかったので、フライドポテトと、スクランブルエッグ、それからラオス特製のアイスコーヒーを注文する。アイスコーヒーは、まるでチョコレートを飲んでいるのかと思うぐらい濃く、甘い。レストランには壁がないので、すべての食べ物に満遍なく虫が集っている。食べながら、読書をする。突然、スコールのように激しい雨が降りだす。
食事を終えて、走って部屋に戻る。ほんの数メートルしか離れていないのに、全身びしょ濡れになる。シャワーを浴びたいが、シャワーは部屋から少し離れたところにある。ふたたびダッシュ。どうにかシャワー室に入るが、電気がつかない。辺りは真っ暗で、ドアを閉じると完全に何も見えなくなる。仕方がないので、ドアを開けたままシャワーを浴びる。雨音が、どんどん激しさを増す。雷が鳴りだす。風が室内まで吹き込んでくる。幽霊や妖怪の類はそれほど信じてはいないけれど、さすがに怖くなり、さっさとシャワーを浴びてほとんど半裸のまま部屋に駆け込む。
部屋に戻っても、雨は一向に止む気配を見せない。風が窓とドアをがんがん叩いている。横になり、MDでテレビジョン・パーソナリティの一番好きなアルバムを聞きながら、さっきの読書の続きをする。MDから、"I Know Where Syd Barrett Lives"が流れる。
There's a little man
In a little house
With a little pet dog
And a little pet mouse
I know where he lives
And I'll visit him
We have Sunday tea
Sausages and beans
I know where he lives....
ahhhhhhhhhhh
'Cause I know where Syd Barrett lives

大好きな国で、大好きな音楽を聞きながら、大好きな書物を読む。
外の嵐がその幸せをよりいっそう引き立たせる。
それにしても、雨はぼくの予定に合わせて降ったりやんだりしているようだ。
ありがとうございます。