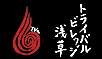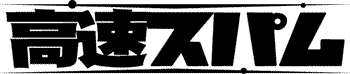中島君から電話がきて、「素敵な女性の方々とお酒を飲むのだけど、もしよかったら来ませんか」というお誘いを受けました。場所を聞くと新百合ヶ丘とのこと。我が家から新百合ヶ丘までは、忌忌しいことに電車を二本も乗り継がなくてはいけないので少々躊躇しましたが、素敵な女性とお会いしたかったので、「よろこんで参加させていただます」と快諾しました。
それでもやはり電車に乗ることを考えると憂鬱になり、結局原付きで新百合ヶ丘まで行くことにしたのですが、なんせ距離があるものですから少し早めに家を出たところ、九時に待ち合わせが六時に到着してしまいました。仕方がないので新百合ヶ丘をぶらぶらとしていたら、いつの間にか隣の駅である百合ヶ丘まで歩いてしまい、さらに歩くと銭湯を発見しました。
銭湯に入ったは良いが、とにかく人が多くて落ち着いて身体を洗うこともできません。ううむ、と唸ること十分、ようやく席が空いたので、即効で身体を洗い、髪をすすぎ、歯を磨き、ジャグジー風呂で人心地。あまりの気持ちの良さに眠りそうになりましたが、僕がジャグジーから出るのを待っているくそじじいがいたので、身体を暖めることもほどほどに、ジャグジーから出ました。
露天風呂に入ろうとしたところ、出口の付近に「電気風呂」なるものを発見しました。なんだこれはと説明を読むと、文字通り風呂の中に電気が流れているということ。足をお湯に浸けてみると、びびびびび、と確かに電気が流れています。左側が微弱電流で、右に行くほど電気が強くなるらしいので、最初は電気の弱い左側に入ったのですが、うほお、理科の実験で電気を流されたカエルのように、ぼくの手がわけのわからない曲がり方をしました。これはおもしろいと電流の強い方へ行くと、思った以上に衝撃が強くて、手どころか胃袋までへんな形に曲がってしまい、その感覚が面白くて、ひとりできゃっきゃきゃっきゃとはしゃいでしまいました。
しばらく遊んでいたら、ちんちんにが電気に触れてしまい、干からびる寸前のみみずのようになってしまったので、電気風呂を出ました。
銭湯を出ると七時半になっていました。少し歩くと、公園に出ました。世の公園というものは、夜になると恋人同士のいちゃつきの場になってしまうのでしょうか。目の前でペッティングを行っているカップルがぼくに気づき、「見てんじゃねーよ!」と怒鳴ってきたので、無視して俳句を詠みました。
そのまま電車に乗って新百合ヶ丘まで戻り、本屋さんで大好きな川上弘美さんの新作『竜宮』と、東浩紀の『郵便的不安たち#』と、この間ビデオで『エヴォルーション』を観たので今西錦司の『進化とは何か』を買って、駅前のヴェローチェでしばし読書。ああ、川上弘美さんの作品はどうしてこんなに面白いのだろう。
そして、九時に中島君と合流して、素敵な女性陣とお酒を飲みました。

■シャマラン監督の最新作「サイン」の試写会“禁止令”
期待大。公式サイトはこちら。
■「小惑星が地球に衝突?」という報道が増えたわけ
確かにやたらと増えている。人類を脅かす存在は、いつの時代でも形を変えてささやかれ続けるものなのか。
■好評を博すイギリスの図書館ネット接続プロジェクト
すばらしい。是非日本でも。
■「普通の人」をモデルにしたゲーム理論を
このゲーム理論ってやつに、とても興味があるのですが。ちなみに、『ビューティフルマインド』のジョン・ナッシュさんも発言をしております。
■Films selected to compete at 59th Venice festival
ベネチア国際映画祭のコンペティション部門が発表されました。
北野武の『Dolls』もノミネートされてますけど、個人的にはサム・メンデスの『Road to Perdition』に興味あり。
■Scientists Discover Why Cuddling Feels So Good
これは科学で解明するような事なのでしょうか。
■Japan in 24 Days
マイケル君の24日間日本一周バイクの旅。僕の故郷はあっさりと通り過ぎています。
■HAIKU TECHNIQUES
英語で俳句を書いちゃいます。5-7-5は無視して、精神面をしっかりと。
■RedDragon
ハンニバル・ヘクター博士の最新作。とはいっても、物語は『羊たちの沈黙』以前のお話です。公式サイトはこちら。
■Japander: Panderers in Japan
日本のCMに出ているハリウッドスターさんをこき下ろしております。とてもおもしろい。
■Modern Ruins Photographic Essays
海外の廃虚探訪。したい。
■ctrl + z T-Shirt
かっこよいTシャツでして。っていうか、Tシャツはどうでも良いのですけど。
■Helthy Penis2002
健康なおちんちんでして。

ぼくの甥である宇饗君は、毎年長期の休みになると、僕の両親、つまり宇饗君の祖父母の家で過ごします。ですから、夏休みなどに実家に帰ると、ずっと甥と遊ぶことになるのですが、いかんせん頼りがいのない伯父なものですから、男の子らしい遊びなどしてあげることができません。
今年も、キャッチボールをやりたがる甥に対して、散歩に行きましょうと無理やり散歩に連れ出し、ふたりでぼくの青春の土地を逍遥してまいりました。
ぼくの実家というところは、本当に田舎でありまして、ほんの数分も歩くとすぐに視界が開けてます。あたり一面田んぼだらけ!それにしても、このあたりを散歩するのは久しぶりです。ぼくのあまり好きではない映画に、「おもいでポロポロ」という作品があるのですが、その作品のなかで、田舎の風景を見て感動している主人公の女性に対して、その田舎で農業を行っている男性が、都会の人は田舎の風景を自然だ自然だというけれど、田舎の風景はすべて人間が作り出したものであり、自然からいろいろな恩恵を受けている百姓が自然に感謝したり、時には自然と戦ったりして作り上げた風景なのであり、自然ではないのだよ、などと講釈ぶるシーンがある(ちょっと記憶があいまい)のですが、そんなシーンを思い出します。
しばらく歩くと、大きな湖に出ます。実家にいた頃は、天気の良い日はここに来て読書をしたものです。エロ本なんかもよく拾いました。ぼくの友達がアオカンしていたのもこのあたりです。上野君に殴られたのもこのあたりだし、後輩の竹隅君が若いリビドーに苦しんで裸でうろうろしているのを発見したのもこの近くでした。なんだかんだで思い出の多い場所なのです。そういえば、酔っぱらったおやじが水死体で発見されたこともありました。夏の夜は、肝試しなんかを行なって、ヤンキーにからまれてボッコボコにされたこともありました。冬になると湖全体が凍りつくので、早朝にやってきて氷の上で遊んでいたらばりばりと氷が割れて肝を冷やしたこともありました。ああ、やはり懐かしい。
住んでいたころはなにも感じませんでしたが、今こうして歩いてみるとなかなか良い場所ですね。湖畔にたっている小さな家を見ると、H.D.ソローのことを考えます。アメリカの自然分学者であるH.D.ソローは、ウォールデン湖畔の森の中での自足の生活の様子を『森の生活』という随筆集に書いています。湖畔の森で、読書と思索の日々。
夏の朝など、いつものように水浴をすませると、よく日あたりのいい戸口に座り、マツやヒッコリーやウルシの木に囲まれて、かき乱すものとてない孤独と静寂にひたりながら、日の出から昼ごろまで、うっとり夢想にふけった。あたりでは鳥が歌い、家のなかをはばたきの音も立てずに通り抜けていった。やがて西側の窓にさしこむ日ざしや、遠くの街道をゆく旅びとの馬車のひびきでふとわれに返り、時間の経過に気づくのだった。(中略)私は東洋人の言う瞑想とか、無為という言葉の意味を悟った。(『森の生活』より)昔は、いやでいやでたまらなかった田舎ぐらしですが、最近ではさっさと隠居したくてたまりません。
午後は、甥が観たいというので『アイスエイジ』を観に行きました。この種の映画は、技術は進歩しても、内容は僕たちが子供のころに観た映画と全然変わらないのですね。甥がスクラッチの一挙一動に大笑いしていました。しかし、甥と一緒に観るのは楽しかったのですが、こんな映画を飛行機の中で見たくないな、と思いました。

旅行の準備をするのは楽しいものですが、一番楽しいのは持っていく本を選ぶことです。
今回持っていこうと思っている本は、アントニオ・タブッキ『夢のなかの夢』、ラテンアメリカ文学のアンソロジー『美しい水死人』、川端康成『掌の小説』、ウィリアム・ギブソン『ニューロマンサー』、鈴木大拙『日本的霊性』、それとこの間Amazonから届いたばかりのジョン・リドリーの『愛はいかがわしく』などなど。ちょっと多いかしら。
アントニオ・タブッキの『夢のなかの夢』は、タブッキ自身が尊敬する、多くの芸術家のひとりひとりが見たであろう夢を、タブッキが想像して書き綴った短編集です。彼が夢を想像した芸術家は、ダイダロスからラブレー、チェーホフ、フロイトなど、さまざま。
最初に引用されている中国古謡がとても素敵で。
恋人の胡蝶の木の下に立ち、
八月の新月が家の裏手からのぼるとき、
もし神々が微笑んでくれるなら、
きみは他人の見た夢を
夢に見ることができるだろう。
『美しい水死人』というアンソロジーは、最近某友人からいただいたもので、収録されている作家のうちガルシア=マルケスやオクタビオ・パスなどはさすがに知っていますが、他の作家はほとんど知りません。かなりの絶賛とともに譲り受けた本なので、丁寧に読みたいと思っています。
川端康成の『掌の小説』は、以前にも日記に書きましたが、ウィリアム・T・ヴォルマンが強く影響を受けた作品です。ヴォルマンはこの小説にインスパイアされ、同じ手法を用いて「The Atlas」を書き上げました。ぼくはお恥ずかしながら未読なので、これを機に読んでみたいと思っています。かるくぺらぺらページをめくってみると、なかなかいい感じ。独立した短いお話が集合して、ひとつ世界を作り出す。ポール・オースターが同じ手法で小説を書いたら、すごく面白くなりそうだと思いませんか。
ウィリアム・ギブソンの『ニューロマンサー』は、なんで今更と思われるでしょうが、先日本屋さんで『90年代SF傑作集』を立ち読みしたところ、やたらと面白かったので、そこらへんの作品を読んでみようかと思っているのですが、実はぼくは80年代のサイバーパンクを全く経験していないので、せめて『ニューロマンサー』ぐらいは読んでおかなくてはいけないかな、と思いまして。ラオスで読むサイバー・パンクはなかなかおつなものではないでしょうか。
鈴木大拙の『日本的霊性』は、かなり昔から我が家にあるのに読んでいない本の一冊で、なんども完読をとチャレンジはしているのですが、毎回挫折してしまっています。旅行先のような、邪魔をするものがまったく存在しない場所でないと、これを読むことは不可能です。
実は、ぼくは相当昔から西田幾多郎という人の思想に興味があるのですが、彼の著書を読んでも全く理解できません。本当であれば、彼の著作を持っていくべきなのでしょうが、彼の作品は、たとえ旅行先であっても、難解すぎて読むことはできないでしょう。そこで、替わりというわけではありませんが、彼の親友でもある鈴木大拙さんの本を読もうという思惑でもあるのです。

長々と書いてしまいましたが、実際に旅行に持っていく本は旅行当日の朝になるまで決定しません。とにかく、こんなふうに本を選ぶことが、とてもとても楽しいのです。
昨日の雑記でも少し触れましたが、禅を世界に伝えた宗教家である鈴木大拙と絶対矛盾的自己同一という概念を確立した哲学者である西田幾多郎は同じ金沢の出身で、生涯を通してお互いに親友として交友しました。
森清さんの書いた『大拙と幾多郎』は、鈴木大拙と西田幾多郎という二人の思想家を中心に、明治時代以降、東洋の文化を世界に伝えようと奮闘した彼らと彼らの友人を描いた作品です。
鈴木大拙、西田幾多郎、安宅弥吉、和辻哲郎、岩波茂雄、安倍能成、野村洋三、野上豊一郎、釈宗演。明治から太平洋戦争までの動乱の時代を共に生きた彼らは、全員が今では鎌倉の東慶寺に眠っています。
文明開化以降の日本の文化は、西洋の文化をいかにして日本に消化するか、あるいは融合するかということへの試行錯誤だったようなイメージがあります。それはおそらく、絵画や文学における西洋的技巧の浸透が影響しているのかもしれません。そのような時代背景のなか、東慶寺に眠る彼らは、東洋の文化、ひいては日本の文化をいかにして海外へ伝え、理解してもらうかということに奮闘しました。日本は三流国であるという海外の評価、そして日本国内の評価をものともせず、どうどうと日本の文化を世界に広めたのです。
『大拙と幾多郎』は、大拙と幾多郎が生まれた明治三年から、昭和四十一年までを描いています。彼らがどれだけお互いに尊敬しあっていたか、影響しあっていたか、作者がそうあって欲しいと願う理想的な書き方が気になる点も多少ありますが、全編を通してその友情と信仰の深さに驚かされます。
読み進めていくうちに気づくのは、大拙と幾多郎がそれぞれ送った人生間の大きな相違です。大拙は若いうちからアメリカに渡り、アメリカ人の妻をもらい、日本に帰国後も多くの講演や執筆活動を行い、松ケ岡文庫という文庫をつくり禅と思想の普及に努めます。一方幾多郎はと言えば、若いうちより身内の不幸が続き、学問の道も思うままにならず、海外に行くことは生涯一度もなく、講演や執筆活動に関しては、そのようなことをするのであれば、その時間を自身で思索に使ったほうが良い、という性格でした。
久松真一さんは、その違いをこんなふうに書いています。
鈴木先生と西田先生とは、先に見た如くだと、相似どころか、返って性格的に相反するとさえ憶え、また真理探究のアプローチにしても、一は無分別知より分別知へ、直感より論理へ、平等より差別へであり、他はその逆である。さらに東西文化の架橋という世界文化史的寄与にしても、一は東洋独特のさまざまな具象的資料を、西洋に初めて投入することによって、東洋の神髄を広く西洋に知らしめて、画期的な新風を吹き込み、他は西洋古今の哲学を自家薬籠中のものとして自由に駆使し、東洋文化の独自性を哲学的に表詮することによって、西洋文化の真只中に東洋的なものを基礎づけるという内面的根本的な架橋を創めて起工したのである。
それでもそのような性格の違いはお互いを尊敬するのになんの障壁にもなりませんでした。
あるとき幾多郎は、主治医に聞かれます。
「先生はむつかしい顔をして何を考えていなさるのか」
すると幾多郎は答えます。
「わしは円いものをかんがえているのだ。これが見つかると、いろいろの学説が、種々の宗教が、みなうまく説明出来るのだ。その円いものを考えているのだ」
この話を、幾多郎の弟子の森本省念が大拙に伝えると、大拙はとても喜びました。幾多郎の気持ちがよくわかり、自分の考えにもよくにているので喜んだのでしょう。省念は「その円いものを大拙全集も説いているのだ。その円い奴を西田全集が評唱している、といってはどうか」と書いています。(「大拙全集の読み方」)
幾多郎は、大拙より先に昭和二十年六月七日に七十五歳で亡くなります。高齢とは言え、やり残したことはまだまだたくさんありました。
石井光男が知人と鎌倉の自宅で昼食をとっていると、そこへ大拙がきました。石井が玄関にでると、大拙はそこに座り込んで泣いています。大拙は、「とうとう西田が死んだ」といってまた激しく泣きました。
電車の中でこのエピソードを読んだとき、不覚にもぼくも泣いてしまいました。文章を読んで泣いたことなんてほとんどないのに、『大拙と幾多郎』でふたりの人生を追っていくうちに、彼らの人生がぼくのなかでどんどんリアリティを増していき、幼なじみを失った老人の気持ちが、痛いほどわかるような気がして泣いてしまいました。そんなもの、わかるはずがないのに。
大拙は、この前年に『日本的霊性』を著しています。太平洋戦争において大和魂が叫ばれる中、大拙はあえて「霊性」という言葉を使いました。
大拙は、この中で日本の霊性を鎌倉時代まで遡り、妙好人を例に出して説明します。
妙好人というのは、浄土系の信者のうち、ことに信仰が厚く、実世間での日常生活で徳があるひとをいう。妙好人は、学者や学僧にはいない。(中略)浄土系の思想をおのずからに体得して、その体得したものに生きている、そういうひとが妙好人なのだ。(中略)阿弥陀仏が自分で、自分が阿弥陀仏だ。そんな風に妙好人は考える。妙好人浅原才市を例にして、大拙はこう説く。何をいっても「あみだぶつ」になってしまうのが才市の世界だ。「有り難い、なむあみだぶつ」、「あさましい、なむあみだぶつ」、「弥陀の親さまがなむあみだぶつ」、「下さるお慈悲がなむあみだぶつ」、「出入りの息がなむあみだぶつ」、「夜があけてなむあみだぶつ」、「日がくれてなむあみだぶつ」すべて才市の言葉である。
太平洋戦争が終わると、「大拙はいよいよ『日本的霊性』が大事になる」と信じ、その必要性を説きました。しかし、大和魂が崩れ落ちた日本は、「それまでとはまるで反対の方向へ走ろうとして科学、技術を第一とし、その上に何よりも物質的能力の拡大を銃挺とする考えが」主流になりました。大拙は、このような考え方を、日本を再び戦争へといざなう考え方だといって非難します。「日本的霊性」は、敗戦で打ちひしがれた日本で、すんなりと受け入れられはしませんでした。
鈴木大拙は、その後も精力的に講演や執筆活動を行います。むしろ、これ以降の彼の活動は、より活発になっていくといっても良いでしょう。
そして昭和四十一年七月十七日、前日に飲んだミルクが原因で、大拙は九十六歳の生涯を閉じます。

『大拙と幾多郎』は、たんなる青春群像記としてもとても面白く読めると思います。興味のある方は、ぜひ読んでみて下さい。
それから、大拙さんの猫好きに関しては、以前の雑記でちょこっとだけ書いています。
億劫相別れて須弥も離れず(大燈国師)
楽しみにしていたダニエル・クロウズ原作の『ゴースト・ワールド』をようやく観ました。
映画『ゴースト・ワールド』は、アメリカのオルタナティブコミック作家ダニエル・クロウズの作品が原作の、イーニド(ソーラ・バーチ)とレベッカ(スカーレット・ヨハンスン)という性格の悪いふたりのハイティーンの女の子を描いた青春映画?です。
性格の悪いイーニドとレベッカは、文句と愚痴の日々を過ごしています。町を歩いて見かけのおかしいカップルを見つければ悪魔主義者呼ばわりをしたり、出会い系雑誌でおもしろそうな記事をみつければ、いたずら電話したりと、十代の皆さんが過ごしているであろう日常をこのふたりも過ごしています。この映画が普通の青春ものと違うのは、出てくるキャラクターがみんなとても面白くて、その面白さもなんといいましょうか、微妙な面白さなのです。行き過ぎていないのに、十分奇妙、という感じの人々がイーニドとレベッカのまわりにたくさん現れて、見ていてとても楽しかった。
数年前に、日本で女子高生ブームのようなものが起こって、村上龍が『ラブ&ポップ』を書いたり、知識人はこぞって女子高生論を書いたり、朝まで生テレビでは「女子高生」そのものがテーマになったりした時期があったじゃないですか。その頃にトゥナイトで、ある女子高生が日常の不満を書きつづったエッセイが発売されて、それがたいそうな売れ行きを見せているという特集がやっていました。さっそく本屋でその本をぱらぱらとめくってみると、なんだかよくわからないけど、なんだかんだと大人に対する文句ばかりが書かれていて、これはぼくが読んでもおもしろくないのではないかと思い購入するのをやめたのですが、結局のところイーニドが『ゴースト・ワールド』の中で言っていることも、その女子高生がエッセイの中で言っていることも、その内容にたいした差はないように思います。けれどもどうしてぼくがこんなにも『ゴーストワールド』を楽しめるのかといえば、そこにある差は、原作のダニエル・クロウズあるいは監督のテリー・ツワイゴフの手腕による語り口であり、それがたんなる文句で終わるか、作品として人を楽しませられるかの違いなのでしょう。優れた作品を評価する際に、「面白さに気づかされた」なんてことを言いますし。
原作を書いたダニエル・クロウズは、1961年シカゴ生まれ。86年に「Lioyd Llewallyn」でデビュー、その後「Eight Ball」を中心に、「Like A Velvet Glove Cast In Iron」「Caricature」「Devid Boring」などを発表。「クロウズが性を描写すると途端にしがらみめいた空気が発生するのは不思議な現象だが、垂れた乳首を描くのも上手だ。郊外生活の、退屈きわまりない日常の中にひそむ狂気や、強迫観念めいた不安感、ファインアートに対するフクザツな思い、悪夢のような不条理、孤独、暴力・・などのネガティブなキーワードでクロウズを読み解くのは誤解を招くであろう。『ゴースト・ワールド』の中で主人公のイーニドがはくこんなセリフに、以外とクロウズの本質があるように思えるのだ。『ねえ、ぶさいくなカップルが愛し合っているのを見るとこの世も捨てたもんじゃないってきぶんにならない?』(スタジオボイス2002年1月号より)」
さて、スタジオボイスといえば、今月号のスタジオボイスの特集は『レッツ・ガールズ』でして、その特集で取り上げられていたガールズ系ウェブサイトで面白かったものをちょっとだけ引用させていただきます。
■SucideGirls
最近、Wiredでも取り上げられたゴス、パンク系の女の子のセルフヌードサイト。 この「ゴス系」という言葉をぼくはよく知らないのですが、このサイトを見たときはびびりました。サイトのデザインがすごくかわいいし、女の子たちの写真もとても素敵です。でも有料なのがちょっと悲しい。
■Dame Darcy
アルタナティブ系コミックアーティストのデイム・ダーシーのオフィシャルサイト。オフィシャルなだけコンテンツは豊富ですが、怖いです。
■less rain
イギリスのウェブサイト制作集団。だまされたと思って見てみて下さい。ウェブデザインの仕事をしている人であれば、びびると思います。

ちなみに、『ゴースト・ワールド』でとてもブシェミが演じていたシーモアという人物は、映画オリジナルのキャラクターで、原作には登場しません。
以前から個人のサイトを開きたいと思っていたのですが、それはちょっと大変そうなので、この雑記をそのままウェブログの形式にしてみようかと思い、さっそくちょっと作ってみました。
内容は鉄割の雑記そのままですが、個人的に使いやすいリンク集のようなものにしようかと思っています。どこまで続くかはわかりませんが。
おまけ。
ちょっと最初は怖いのですが、途中から素敵なメーティング・ダンス
■get your freak on

早速ですが、明日からしばらくは更新がなくなります。ぼくのことを忘れないで。
本日八月八日は、日本を代表する民俗学者、柳田国男さんの命日でございます。
柳田さんは、見かけによらず厳格な人でしたから、御年八十七歳になっても、食事をするときは正座をしてしっかりと御飯をいただきました。けれども、その日は少し様子が違いました。お食事をしていた柳田さんは、不意にパサッと倒れ込み、そのまま静かに息を引き取りました。享年八十七歳。大往生でございます。
燃えたものが灰になっても、灰のままその形を保っているときがある。その灰が崩れるように床の上にパサッと倒れてしまった。鎌田久子さんの回想より
柳田さんは、皆さんもご存知の通り『遠野物語』を編纂したお方でして、民族学者として有名ですが、もともとは文学を志していて、花袋君や島崎君、独歩君や有明君などと「イプセン会」なるサロンを開いたりもしておりました。しかし、柳田さんが文学を志した明治時代は、自然主義が文学の主流になろうという時代でして、私小説という文学形態が、柳田さんの周辺をどんどんと埋め立てていきます。さて、困りました。柳田さんは、自然主義的な狭隘の世界ではなくて、もっともっと広々とした世界のことに興味があったのです。
明治四十一年十一月四日。柳田さんは遠野出身のストーリーテーラー佐々木喜善君と出会います。佐々木君は、柳田さんに故郷の伝承を伝え聞かせます。柳田さんは興奮しました。佐々木君の語るお話には、柳田さんが当時唱えていた「山男=異人種説」を解明する鍵になるような山人伝説が多く含まれていたからです。
それだけではありませんでした。佐々木君の語る物語群は、それがたとえ山人伝説に関係なくても、そのすべてが柳田さんの心を魅了するのに十分な力を持っているものだったのです。
ザシキワラシ、河童、猿の経立、神女、デンデラ野とシルマシ、マヨイガ、山男、オシラサマ、オクナイサマ・・・。
柳田さんは、佐々木君の口から発せられる言葉のひとことをも聞き漏らさないように集中して物語を聞き、遠野の村を夢想しました。そして、そのすべてを『遠野物語』に書き記すことを決心します。
此話はすべて遠野の人佐々木鏡石君より聞きたり。作明治四十二年の二月頃より始めて夜分折々訪ね来り此話をせられしを筆記せしなり。鏡石君は話上手には非ざれども誠実なる人なり。自分も一字一句をも加減せず感じたるまゝを書きたり。思ふに遠野郷には此類の物語猶数百件あるならん。我々はより多くを聞かんことを切望す。『遠野物語』序文より
柳田さんは、その生涯を通して多くの土地を旅しました。草鞋を履き、笠をかぶり、日本全国を歩き続けました。農道を歩き、農民たちを観察し、その風土の底にある「微妙なもの」を肌で感じようとしました。
そんな柳田さんは、旅で農村を歩くことを「しんみり歩く」と表現しました。そして、旅そのものを「ういもの、つらいもの」であると言いました。柳田さんは、旅で何を見たのでしょう。旅で何を感じたのでしょう。

旧家にはザシキワラシという神の住みたまふ家少なからず。此神は多くは十二三ばかりの童児なり。折々人に姿を見することあり。土淵村大字飯豊の今淵勘十郎と云う人の家にては、近き頃高等女学校に居る娘の休暇にて帰りてありしが、或日廊下にてはたとザシキワラシに行き遭ひ大いに驚きしことあり・・・・『遠野物語』「十七(ザシキワラシ)」より
『recoreco』という雑誌に池袋の書店ガイドが掲載されていると聞いて、早速買って読んでみました。この雑誌は先日創刊されたばかりらしく、以前から此処其所の本屋で見かけてはいたのですが、似たような雑誌がまた創刊したなあと思って立ち読みもしませんでした。けれども、いざ読んでみるとこれがなかなかおもしろくて。
キャッチフレーズが「本と書店で遊ぶレコメンデーションブック」ということからもわかる通り、ミュージックマガジンの「本」バージョンのようなものでして、東京や大阪、京都の本屋に関するガイドや、大量の(短い)書評、微妙に豪華な執筆陣による連載で構成されています。書評好き、ブックガイド好きのぼくにとっては、なかなか嬉しい内容でした。これで「本を読む場所」について言及している記事があればさらに楽しめたのですけど、残念。
この種のブックガイドは、昔から多く出版されていますが、うざいのは『必読書 150』のように「これを読まなくては猿だ!」などと偉そうなことを言っているものとか、立花隆の『ぼくはこんな本を読んできた』の「小学生の時に漱石やディケンズにはまりまくってねえ、あっはっは」みたいな、だから何なの?的なもので、この種ブックガイドは、根底に「ぼくのように賢くなりたいだろう、きみい」といういやらしさが漂っていて、体中が痒くなってしまいます。ひねくれすぎ?子供のころの、課題図書のトラウマが未だに残っているのかしら。
ではどのようなブックガイド、書評が好きなのかというと、たとえば『recoreco』に掲載されている記事で言えば、豊崎由美さんの『読点を打つ旅の記録』という書評のように、自慢でもなく、嫌みでもなく、その人がその本を愛する理由がのほほんと述べられているような、その書評を書いた人自体に共感してしまうような、そのような書評が好きです。
豊崎さんは、『読点を打つ旅の記録』の冒頭で、作家の種類を「時代の気分を増幅させるタイプ(典型として村上龍)」と、「抵抗する炭坑のカナリア型というふたつのタイプ」のふたつに分けます。そして、後者のタイプは「素材やテーマに一直線には切り込んでいかない。むしろ迂回して迂回して、興味をひく虫か何かを見つけた時の仔猫のような身振りで時折飛び退ったり、近づいたり」する作家であると書き、そのたとえとして平出隆を紹介します。
豊崎さんは、平出隆の『ベルリンの瞬間』を引用しながら書きます。
「日本にいながら、なぜ自分がこの土地において、この国語において、ある種致命的な欠落を抱え続けるか、ということを、ぼくは考えないでいられなくなっていた。」という一文を、つっかえるような読点と共に記さずにいられない作家は、「持て余すほどに巨き」くて、「歴史のあらゆる断絶が、あらゆる角度から襲いなおしてきて、感情の壁を逆立てるよう」な都市ベルリンを精力的に、しかし、つつましやかな足取りで歩きます。早々に結論づける安易な句点を許さない、自問に強いるがごとき独特の読点を打ちながら。
書評の楽しみを知ったのはつい最近のことで、幾万とある書評の中に、時折それ自身に共感してしまうような書評があることに気付きました。「共感」という表現は適切ではないかもしれません。ぼく自身が経験したことのある素晴らしい読後感、あるいは経験してみたい読後感を連想させる感覚、とでもいいましょうか。その本を読むことによって感じたことを、その人の経験と知識を駆使して適切な言葉で表現してくれるような、そのような書評。書評自体で感動してしまうような書評のことです。
そのような書評を読むと、紹介されている本自体に興味を持つというよりも、「そのような書評を書く人が推薦する(しない場合もあるけど)本」を読んでみたいという気持ちになります。この書評を書いた人が、このように感じた本を、ぼくはどのように読み、感じるのだろう、と。
豊崎さんは書きます。
平出氏はそうやってたくさんの読点を踏み、自ら打ちながらも、しかし、大変な繊細さをもって句点を避けようとしているかのように、わたしには読めます。大勢の先達の思考や行動を自らのそれに重ねるように、ベルリンという謎に近づいては遠ざかりながら思索を深めるこの書物が持つ時空間の広がりに感嘆しながら、その奥行きの深さにも共感を覚えずにはいられません。
読みながらぼくは想像します。たくさんの読点を踏み、句点を避けようとしているかのような文章が綴る旅の記録のことを。そして思います。ぼくは、『ベルリンの瞬間』を読んだときに、その奥行きの深さに共感を覚えることができるのだろうか、と。
最後に、豊崎さんはこう結論づけます。
ベルリンでの一年間が平出氏にとって切実なテーマを伴う経験である限り、読者も迂回し、近づいては飛び退る作家の精神の働きを共に経験し直すほかないのです。そして、そのひそやかな追走こそが読書という行為の歓びの確信なのではないか。短兵急を求めるときだからこそ、深く得心する次第です。
この最後の文章を読んで、豊崎さんの書く「近づいては飛び退る作家の精神の働きの再体験」ということや、「ひそやかな追走こそが読書という行為の歓びの確信」であるということに、ぼくは強い共感を覚えます。そして同時に、いままさにぼく自身が、豊崎さんという書評家の読書体験を迂回しながら再体験し、そのひそやかな追走に歓びを感じているということを、強く確信するのです。

そして、本屋さんに『ベルリンの瞬間』を買いにダッシュ。
In the street the Thai criers wore suits and ties. They looked at me in contempt or else they said: Japanese only! or they shouted: Members only!
How can I become a memeber? I said. How can I become Japanese?
But to this they had no answer.Willian T. Vollmann,THE ATLAS
朝、眠い目をこすりながら六時に起床し、成田へ向かう。チェック・インして搭乗券を受け取ると、なぜか名前がインド人に、行き先はデリーになっている。インドに行けという何らかの啓示なのだろうかと思いつつ、カウンターに戻って事情を話し、正しい搭乗券を受け取る。
ほぼ定刻通り日本を発つ。航空会社がエア・インディアのため、乗客の半分以上がインド人。うるさい。何かにつけて文句を言っている。インド人は、人の文句は聞かないくせに他人に対してはどんな些細なことでもクレームをつける。ぼくの隣には、チェック・インカウンターで、すべての荷物を機内に持ち込みたいと騒いで注目を集めていたインド人が座った。こいつ、絶対テロリストだよなー、と思いつつ、テロリストがナイフを出した瞬間にそれをたたき落として乗客を救う自分を想像する。ニッポンさようなら。
今回の旅行の目的は、ラオスのワット・プーというクメールの遺跡を訪れるということ。しかし、目的と行っても便宜上のもので、ワット・プーは長い間放置され、遺跡としての損傷が激しく、現在日本の某大学が援助をして遺跡の復旧を行っているという話を聞き、復旧があまり進んでいない今を見ておきたいと思っただけだった。もちろん、クメールの遺跡には興味があるし、ヒンドゥーの寺院に、後から持ち込まれたという仏像にも興味がある。けれども、それは後付けの理由であって、この旅行自体の目的ではない。本当の目的は、歩くことだった。
バンコクからラオスへ入国するには、タイの北部のノーンカイという町を中継することになる。飛行機で直接ラオスの首都ヴィエンチャンに入国することもできるけれど、予算のことを考えてノーンカイまで寝台電車で行くことにした。ドン・ムアン空港から、タクシーでファランポーン駅へ向かう。ところが、間違ってちょっぴり豪華なタクシーに乗ってしまい、ファランポーン駅まで650バーツかかった。ファランポーン駅までなら、300バーツもあればいけたよなー、としばし後悔。アホみたいに貧乏旅行をするつもりは毛頭ないけれど、使う必要の金を使うつもりもさらさらない。まあ、これから気をつけましょう。
初めて来たファランポーン駅は、おもったよりもきれいで、整然としている。早速外国人専用カウンターに並ぶ。恰幅の良い無愛想な係員が、こちらを一瞥もせずに事務的に対応する。今晩のチケットは完売していたので、仕方なしに明日のチケットを購入する。ファーストクラスで548バーツ。ここに来るまでのタクシー代より安いというのは、いまいち釈然としない。
トゥクトゥクでカオサンロードに向かいながら、道々を記憶する。決して歩けない距離ではない。明日はここまで歩いてこよう、と思う。トゥクトゥクに乗っても微々たる金額ではあるけれど、とにかく歩きたい。
カオサンロードで適当なゲストハウスにチェックインし、水のシャワーを浴びて、こちら用の服に着替える。ぼろぼろの汚い服だけど、これでやっと旅行をしているという気持ちになった。旅行者で賑やかなカオサンロードにいると寂しくなるので、少し離れたタナオロードへ行く。
三年前にこのタナオロードを訪れたとき、欧米の観光客はほとんどおらず、タイの少し裕福な育ちの若者たちが集まって騒いでいて、夜中を過ぎるぐらいまでそうとう盛り上がっていた記憶があるのだけど、今来てみると、とても閑散としている。あれれ、道を間違えたのかな、と思って周りを見回すと、景色に見覚えがある。とりあえず先に進んでみると、やはり見覚えのある店を発見したが、名前が違っている。中をのぞくと、なにやら怖い人たちがたむろっている。ああ、怖い。旅行初日で殺されてはたまりません。そそくさと店の前を通り過ぎる。
そのまま、カオサンロードへは戻らずに適当に歩く。チャイナタウンへでも行ってみようか。歩いていると、トゥクトゥクがぼくに向かって叫んでいる。「ヘイ!マンコ!マンコ!アタミ!マンコ!」ぼくは「マンコ、ノーサンキュー」と応えて、歩く。狭い道路を挟むようにして伸びている狭い歩道を挟むようにして乱立している商店群をながめながら、歩く。少しでもお金を稼ごうと笛を吹いたり歌を歌ったり子供を抱いたり泣きまねをしたり一点を凝視したり地面に思いっきり寝転がったりしている浮浪者たちに挨拶をしながら、歩く。日本の歌舞伎町並にあるいは日本の歌舞伎町以上に混雑して雑然とした交通渋滞の車の間をぎりぎりの間隔で猛スピードで通り抜けていくモータバイクを眺めながら、歩く。一時間も歩くと、チャイナタウンに入る。チャイナタウンは、道路にはみ出るほどに屋台で溢れている。少し奥に入ると、おばあさんが座って地面に何かを並べている。並べているのは人形やらお守りやらがらくたやらで、どうやら売り物らしい。おばあさんはぼくを一瞥もしないが、「サワッディー・クラップ」と挨拶をすると、笑顔で応えてくれた。
一時間ほどチャイナタウンをぶらぶらしたあと、屋台で食事をとる。炒めたご飯に、鳥の唐揚げのようなものを刻んで載せたシンプルなものと、香草のスープ。うまい。けど辛い。
深夜、ゲストハウスに戻る。一階がディスコのため、夜中二時にもかかわらず大音量でダンスミュージックが流れている。前回泊まったときには、ディスコはなかった。あまりの騒音に、眠ることが出来ず、持ってきた『日本的霊性』を読む。西田幾多郎の著作と比べて、鈴木大拙の文章はとても分かりやすく、且つ面白い。「なにか二つのものを包んで、二つのものがひっきょうずるに二つでなくて一つであり、また一つであってそのまま二つであるということを見るものがなくてはならぬ。これが霊性である。」なんていう文章を読むと、わくわくしてしまう。大拙は書く。「霊性は民族が或る程度の文化段階に進まぬと覚醒せられぬ。」或る程度の文化段階とは、いったいどういうことなのだろう、と思って読み進める。大拙は書く。「原始民族の意識には精練せられた霊性そのものはない」「ある段階に向上した民族でも、その民族に属するすべての人間が霊性を有するものではない」この「或る程度の文化段階」という表現にいやな引っ掛かりを感じながら読み進めると、日本が「或る程度の文化段階」に達したのは、禅と浄土系思想が確立した鎌倉時代であるという。そうしてさらに、禅と浄土系思想に関する説明が続く。ちょっと疲れたので『日本的霊性』を閉じて、京極夏彦の『姑獲鳥の夏』を開く。京極夏彦の作品は、以前からぼくの尊敬する複数の友人に勧められてはいたのだけど、その分厚さに気圧されてどうしても読むことが出来なかった。ところが、読み始めたら死ぬほど面白い。びっくりするぐらい面白い。結局明け方まで読んでしまい、いつの間にかディスコの音楽も消えていた。

明日はなにをしようかしら。考えながら眠る。
午前十時起床。シャワーを浴び、ホテルをチェックアウトする。今日の夜にバンコクを出るので、それまでの間荷物を預かってくれませんか?と尋ねたところ、それは出来ないとのこと。では、荷物を預かってくれる場所を知りませんか、と聞くと、知らない、 とそっけない答え。

昼間のカオサン通りは、欧米人で溢れてはいるものの、夜のような騒々しさはなく、必要以上の寂しさを感じることもない。雨期だというのに、湿気を全く感じない。気温も丁度よく、風が心地よい。しばらくぶらぶらと歩く。ノーンカイ行きの寝台特急に乗るのは今夜八時四十五分なので、それまでの時間をどうやって過ごすか考える。何度来てもバンコクはやることがない。それはバンコクのせいではなくて、都市に興味を覚えないぼくの性格のせいなのかもしれない。途中、荷物を預かってくれるゲストハウスを発見、荷物を預ける。その後、とりあえず食事をするために、適当なレストランに入る。
一時間ほどレストランで読書をするが、なにをするべきか一向に思いつかない。このままだと一日ここで読書をしてしまいそうなので、とりあえずレストランを出て、適当に歩くことにする。昨日はチャイナタウンに向かったので、今度は逆方向に行ってみることにした。
少し歩くと、サナーム・ルアンにでた。たくさんの屋台が並んでいる。中央には、イベント用の土台らしきものが組み立てられている。近いうちにお祭りでもあるのだろうか?道路の脇で、おっさんたちが輪になってボールを蹴りあっている。ボールを落とさないように、足でキャッチボールをしているらしいが、めちゃくちゃ上手い。落とすのは大抵若いやつで、年をとっているおっさんほど落とさない。
 途中、右手に入る道があったので、入ってみる。道の左手には仏教関係の店が、歩道には仏像やレリーフを売っている人たちが並んでいて、一般の人たちや僧侶達が群がっている。どうやらこの通りは、仏教系の方々の通りらしい。店を覗いてみると、仏教だけでなく、ヒンディー関係の書物なんかも置いてある。とても良い仏像も置いてある。CDやテープなんかも置いてある。明らかにトリップ系のCDなんかも置いてある。店を巡回しているだけも面白い。もともとが観光客を相手にしている店ではないためか、あまり英語は通じない。タイは仏像の国外持ち出しが禁止なので、良い仏像があったけど買うのはやめた。
途中、右手に入る道があったので、入ってみる。道の左手には仏教関係の店が、歩道には仏像やレリーフを売っている人たちが並んでいて、一般の人たちや僧侶達が群がっている。どうやらこの通りは、仏教系の方々の通りらしい。店を覗いてみると、仏教だけでなく、ヒンディー関係の書物なんかも置いてある。とても良い仏像も置いてある。CDやテープなんかも置いてある。明らかにトリップ系のCDなんかも置いてある。店を巡回しているだけも面白い。もともとが観光客を相手にしている店ではないためか、あまり英語は通じない。タイは仏像の国外持ち出しが禁止なので、良い仏像があったけど買うのはやめた。
道を進むと、船乗り場に突き当たった。仕方がないので戻ると、途中「National Museum Bangkok」を発見。そういえば、バンコクで美術館や博物館に入ったことがないなと思い、入館してみると、思った以上に広い。敷地内に建物がいくつも建っていて、テーマごとに分類されている。パンフレットを見て、仏像関係のフロアーを探すと、「ASIAN ART」というコーナーがあるので、そこに行ってみる。
ぼくは日本の仏像に関しては興味も手伝って多少の知識は持っているつもりだけど、東南アジア系の仏像に関してはほとんど無知に等しい。前回の北部旅行でも多少は観てまわったが、それ以降で観るのはこれが初めてかもしれない。わくわくしながら展示室に入ると、そこにはたくさんの仏像が並んでいた。
こうして仏像を観ると、どうしても日本の仏像と比べてしまう。この博物館に展示されているだけの仏像で南伝系のすべてを総括するつもりはないけれど、たとえば顔に関して言えば、日本の仏像の顔はやはり美しいと思う。南伝系の仏像には、感情の繊細さを感じることができない。日本の仏像は、たとえば聖徳太子の時代、つまり日本に仏教が伝来してすぐの仏像に関して言っても、表情の微妙な美しさ、繊細さがある。もっとも、あの時代の仏像は、大陸の影響を思いっきり受けているし、あるいは大陸から渡ってきた仏像そのものなので、日本というよりは、大陸の仏像、大乗の仏像と言った方が良いかも知れないけど。
とはいえ、これだけの数の南伝系の仏像を一度に観るのは初めてだし、博物館に納められているだけあって、なかなか良い仏像が揃っているので、さすがに興奮する。ロンパリの仏像がある。体型的にガネーシャっぽいその仏像は、大きなものと、小さなものとふたつあるが、その両方とも素晴らしい。ガネーシャを想像してもらうと分かりやすいが、頭がでかく、目がロンパリなので、多少コミカルな印象を受けるが、じっと目を凝らして観ていると、何とも言えない神々しさがある。これはなんという名前の仏像なのだろう。
進むと、釈迦如来蔵と思われる仏像が続く。それらの両手の形が気になる。日本の仏像は、釈迦如来像に関して言えば、たいていの場合右手はこちらに手のひらを向け(施無畏印)、左手はひざの上において何らかの印を結んでいる。少なくとも、僕が観てきた釈迦如来像に関しては、ほとんどがそのような形をしていた。けれども、ここに並んでいる南伝系の釈迦如来像と思われる仏像は、右手を右膝の上に手のひらを下にして乗せ、左手は腹の下辺りに手のひらを上にしている。すべてがそうだというわけではないけれど、そのような形の仏像が非常に多い。これらの仏像は、釈迦如来像ではないのだろうか?そもそもこの印は、なんという名前の印なのだろうか?そういえば僕は、仏像のリリーフの指輪をひとつ持っているのだが、そこに描かれている仏像も同じような形をしている。特に冠を有するわけでもなく、光背を持つわけでもなく、特徴のある法衣を着ているわけでもない。やはり釈迦如来だとしか思えないのだが、もしかしたら、南伝系特有の如来像、あるいは観音像なのかも知れない。日本に帰ったら、調べてみよう。
別のフロアーでは、手のひらをこちらに向けて、足を一歩後ろに引いている仏像を見つけた。これは一体どのような仏像なのだろうか。日本では、たとえば湖北の十一面観音などは、衆生を救おうと今一歩歩みでんとする姿が描かれている。それと比べると、この仏像は「ちょっと待った!」とまるで一歩引いているように見える。説明がほとんど書かれていないので、いったい何を描いているのか、検討がつかない。さらに、乳首が異様に立っている仏像もあった。奈良の興福寺の金剛力士像などは、乳輪が異様にでかくて 、セックスの時萎えるなこれ、などと思ったものだけど、それでもさすがに乳首は立っていなかった。どうして仏像の乳首を立たせる必要があったのだろう。知りたい。そして、この仏像は美しい。
*日本に帰国後、インターネットで調べてみたところ、以下のようなサイトがありました。
■タイの仏像(タイ語で書かれているので、読めません)
■東南アジアの仏像(日本語)
たとえば、ぼくが釈迦如来かどうかわからなかった仏像は、このページの上段に掲載されている形の仏像で、一歩引いている形の仏像は、同じページの真ん中より下ぐらいにあります。それらの仏像が一体どのような系統に属するのかは、まだ調べていないので分かりません。
帰り際に、中央の建物に入ると、ガネーシャ特集をやっていた。フロアー全体がガネーシャで埋め尽くされている。そう言えば、さっき通った仏教通りには、仏教だけでなくてシヴァやガネーシャ、ヴィシュヌ神に関する書物やポスターもたくさん売っていた。一時間近くうろうろする。
 閉館ぎりぎりまで博物館を逍遥し、その後カオサンに戻る。マッサージを一時間程してもらい、荷物を受け取り、ファランポーン駅まで歩く。昨日歩いた道なので、道順は覚えている。今日は、結局一度もトゥクトゥクに乗らなかった。歩くと、いろいろなことを考えることができる。明日からも、出来るだけ歩くことにしよう。
閉館ぎりぎりまで博物館を逍遥し、その後カオサンに戻る。マッサージを一時間程してもらい、荷物を受け取り、ファランポーン駅まで歩く。昨日歩いた道なので、道順は覚えている。今日は、結局一度もトゥクトゥクに乗らなかった。歩くと、いろいろなことを考えることができる。明日からも、出来るだけ歩くことにしよう。
チャイナタウンで夕食をとり、八時にファランポーン駅に到着。駅の掲示を見ると、電車の遅れはないようだ。売店で水とお菓子を買い、電車を待つ。八時半に構内に入り、電車を見つけて乗り込む。
八時四十五分、定刻通り電車が出発する。出発するとすぐに車掌が寝台を組み立てに来る。ぼくは上の台なので、寝台になると外が見れなくなる。仕方がないので『日本的霊性』と『姑獲鳥の夏』の続きを読む。『日本的霊性』は、思ったよりも過激で、「万葉集」などの平安文化の日本的宗教性を完全に否定している。「万葉集」を、「ただのなげきでしかない」「淳朴」だと断言する。さらに「思想において、情熱において、意気において、宗教的あこがれ・霊性的おののきにおいて、学ぶべきものは何もない」と身も蓋もない。なんだか心臓に悪い。『姑獲鳥の夏』に切り替える。昨日、三分の一程度まで読んだ。物語の中で、京極堂の語る存在や記憶、時間、そして幽霊に関する説は、真新しさはないもののとても面白い。そんな彼が量子力学について語る場面がある。
「量子力学が示唆する極論はーこの世界は過去を含めて<観察者が観察した時点で遡って創られた>だ」
ぼくは、このセリフが気になって仕方がない。もちろん、この一文でもって量子力学を理解したとは思っていないし、理解できるわけもない。そもそも、この一文は京極堂が物語の語り手である関口に、ある事実を示唆するために極論的に言った台詞なので、どこまで真実なのか分からない。けれども、どうも気になる。

昨日あまり眠っていないせいか、やたらと眠い。明日はいよいよラオス入国。ようやく本当の旅行が始まる。今日はもう眠ろう。
午前七時、がたがたという音と車掌の声で起床。寝台のカーテンを開けると、ベットの片づけが始まっている。下に降りて窓から外を眺めると、一面に田んぼが広がり、その中に南国系(?)の樹木が生えているのが見える。早朝だというのに、農業に勤しむ人々がすでに作業している。ああ、これがタイの東北部なのね!と感激し、しばし眺めを楽しむ。
九時過ぎにノーンカイ到着。ぼくの他にも、観光客と思しき外国人が何人かいるが、会話から察するに、みんなフランス人のようだ。リュックを背負い、電車を降りる。
駅を出ると、たくさんのトゥクトゥクが待っている。ここからタイのイミグレーションまではトゥクトゥクで行くらしい。イミグレーションへ向かう。
タイの出国管理事務所で出国手続きをして、シャトルバスで友好橋を渡り、メコン川を越える。ああ、メコン川だ!思った以上に巨大な川だ。これから数日間、あなたの傍を離れずに、あなたと共に旅行をするのですよ、と心の中で川に話しかける。
橋を越え、ラオス側のイミグレーションへ向かう。ぼくはラオスのビザを持っていないので、入国手続きをする前に、ビザの申請をしなくてはならない。写真と申請書と金を渡して申請をすると、パスポートを受け取ったまま返してくれない。あれ?これ返してくれないのかしら。でも、他の外国人もパスポートを預けて待っているし、まあいいやと思って待つこと三十分、突然「オネダ!オネダ!」と呼ばれる。パスポートを受け取ると、しっかりとビザのスタンプが押してある。すぐ先にある入国審査の窓口に並び、入国カードを提出。なにやらコンピュータで照合をしている様子。無事に通過し、とうとうラオス入国。外に出ると、またもやトゥクトゥクやタクシーがたくさん待っている。近くにいた日本人の女性に声をかけて、市内までトゥクトゥクをシェアすることにする。
 とうとうラオスにやってきた。ビエンチャンの市内に向かうトゥクトゥクの中で、風に吹かれて髪の毛が七三になる。通りゆく道々の風景を眺めていたら、インドの田舎を思いだした。道路はほとんど舗装されていない。間隔を挟んで、木造の家々が並んでいる。牛が平気で道路で寝そべっている。けれども、時々通り過ぎるラオスの人は、こちらを気にする様子は全くない。そこがインドとの大きな違いだ。
とうとうラオスにやってきた。ビエンチャンの市内に向かうトゥクトゥクの中で、風に吹かれて髪の毛が七三になる。通りゆく道々の風景を眺めていたら、インドの田舎を思いだした。道路はほとんど舗装されていない。間隔を挟んで、木造の家々が並んでいる。牛が平気で道路で寝そべっている。けれども、時々通り過ぎるラオスの人は、こちらを気にする様子は全くない。そこがインドとの大きな違いだ。
ビエンチャンのメイン市場、タラート・サオに到着。女性に丁寧にお礼をして別れる。ビエンチャン!とうとうやって来ました!もちろん、この町に来ることが旅行の第一の目的だから、ここは単なる出発地点に過ぎないのだが、それでもやはり感動してしまう。さて、とりあえず宿を探さなくては。それから、南ラオスの町、パクセーへ行く飛行機のチケットを予約しなくては。
ガイドブックよると、メコン川沿いにゲストハウスが幾つかあるらしい。とりあえず、メコン川に向かって歩くことにしよう。雨期のせいか、道路がぬかるんでいるので、水たまりを避けながら歩く。歩きながら、町を観察する。仮にも首都だというのに、喧騒というものを全く感じない。車も走っているし、人々も歩いているけれど、タイの北部の田舎よりも静かな感じがする。ぼくは、もしかしたらとても素晴らしい国に来てしまったのかもしれない。
 地図を見ながら進んでいたら、大きな広場に出た。歩いてきた距離と、周りの風景から察するに、ここはおそらくタートダムなのだろうと思って、近くにいる人に聞くと、ここはナンプ広場だという。地図で見ると、タラート・サオから相当離れているように見えるけれど、もうこんな距離を歩いたのだろうか?というか、町自体がこんなに狭いのか!嬉しくなる。
地図を見ながら進んでいたら、大きな広場に出た。歩いてきた距離と、周りの風景から察するに、ここはおそらくタートダムなのだろうと思って、近くにいる人に聞くと、ここはナンプ広場だという。地図で見ると、タラート・サオから相当離れているように見えるけれど、もうこんな距離を歩いたのだろうか?というか、町自体がこんなに狭いのか!嬉しくなる。
途中、ラオス航空のオフィスを発見。外国人用のカウンターでパクセー行きのチケットを予約する。飛行機の席数自体が少ないので、チケットを取れるかどうか不安だったが、あっさり予約できた。これで安心してヴィエンチャンを歩くことが出来る。メコン川沿いの道路に出て、川に沿って歩く。川の向こうには、タイが見える。何度ラオスを実感しても、し足りない。ぼくは今、ラオスにいるのか。道路沿いには、レストランやマッサージ屋さんが軒を連ねている。エクスチェンジでバーツをラオスの通貨キープに変える。ラオスでどれぐらい使うか検討がつかないので、とりあえず2000バーツを両替する。日本円にして7000円足らず。ラオス通貨で491500キープ。びっくりするぐらい分厚い札束を受け取る。ラオスでは、自国の通貨に対する信用が低いので、みんなキープよりもバーツやドルを欲しがるらしい。使い切れるだろうか?
川沿いのレストランに入って、昼食を取る。何を頼んだら良いか分からなかったので、適当に注文をしたら、クリスピーヌードルのあんかけに野菜がたっぷり入った、日本で言えばかた焼きそばのようなものが来た。食ってみるとなかなかうまい。
メコン川付近のゲストハウスに部屋をとり、シャワーを浴びて一段落。明日の朝早くにヴィエンチャンを発つので、今日のうちに少しでもぶらつこうと思う。ガイドブックを見ると、市内から少し離れた所にブッダパークという、敷地内に大量の仏像が点在している公園があるらしい。とりあえずそこへ行ってみよう。
パークまでバスで行こうと思っていたら、途中でトゥクトゥクに声をかけられ、値段を交渉してみると意外と安いので、トゥクトゥクで行くことにする。パークに向かいながら、道順を覚える。覚えると言っても、一度左折した後はひたすら一本道。絶対に迷うことはないだろう。ブッダパーク到着。
 入園すると、ぼくはすぐに動けなくなった。目の前に阿修羅像のような、三面十二臂の像が立っている。うおー!かっこいいいーー!なんだこの像!!多分阿修羅で間違いないとおもうけど、腕が十二ついてる!日本で一番有名だと思われる、興福寺の国宝館にある阿修羅像は三面六臂で、その腕の華奢な感じがとても好きなのだが、今目の前にあるこの阿修羅は、如何にも力強い。阿修羅という意味で言ったら、こちらの方が本家に近いのかな?悲しみを全く感じさせないその表情が気に入って、しばらくその場から動けなくなる。
入園すると、ぼくはすぐに動けなくなった。目の前に阿修羅像のような、三面十二臂の像が立っている。うおー!かっこいいいーー!なんだこの像!!多分阿修羅で間違いないとおもうけど、腕が十二ついてる!日本で一番有名だと思われる、興福寺の国宝館にある阿修羅像は三面六臂で、その腕の華奢な感じがとても好きなのだが、今目の前にあるこの阿修羅は、如何にも力強い。阿修羅という意味で言ったら、こちらの方が本家に近いのかな?悲しみを全く感じさせないその表情が気に入って、しばらくその場から動けなくなる。
その先に行くと、巨大な寝仏がある。涅槃像だ。ガネーシャ像もある。とにかく公園(実際は寺院跡なのだが)の一面に様々な仏像が立っている。いかにも南伝系の仏像らしい、日本では見慣れない少し滑稽な仏像もたくさんある。その他にもヒンドゥーの神なのだろうか、まるで魔王のような像も幾つかある。一つ一つを丹念に見る。仏像好きにはたまらないな、ここは。仏像は、やはり雨ざらしが一番美しい。
 |  |
 |  |
仏像をすっかり楽しんでしまい、写真をばしゃばしゃとアホのように撮り、満足して公園を後にする。トゥクトゥクで帰る途中、やはり歩きたくなって、途中で止めてもらって「ここからは歩くから」と説明して、往復分の金を渡してトゥクトゥクを降りる。運転手のお兄ちゃんは、「ここからなら一時間半ぐらいで市内に着くよ」と教えてくれた。
 道は一本道なので、迷うことはない。国境から市内へ来る途中で見た風景と変わらない風景が続く。トゥクトゥクに乗っていると、誰もぼくのことを気にしないけれど、歩いているとさすがにじろじろ見られる。「サヴァーイディー」と手を合わせて挨拶をすると、皆笑顔で応えてくれる。途中、コカコーラの工場や、日本車のディーラーなども見かける。その周りには飲食店が並んでいる。そのうちの一件に入ると、まだ十代と思われる女の子が店番をしていて、ぼくを見ると驚いて慌てている。が、挨拶をするとニコッと笑って応えてくれた。ペプシを買うと、指で二を表して、二千キープであることを教えてくれる。ストローとペプシを受け取ると、そこで飲んで下さい、というように外のベンチを指さす。この子、かわいすぎる。というか、ラオスの子供は皆かわいすぎる。
道は一本道なので、迷うことはない。国境から市内へ来る途中で見た風景と変わらない風景が続く。トゥクトゥクに乗っていると、誰もぼくのことを気にしないけれど、歩いているとさすがにじろじろ見られる。「サヴァーイディー」と手を合わせて挨拶をすると、皆笑顔で応えてくれる。途中、コカコーラの工場や、日本車のディーラーなども見かける。その周りには飲食店が並んでいる。そのうちの一件に入ると、まだ十代と思われる女の子が店番をしていて、ぼくを見ると驚いて慌てている。が、挨拶をするとニコッと笑って応えてくれた。ペプシを買うと、指で二を表して、二千キープであることを教えてくれる。ストローとペプシを受け取ると、そこで飲んで下さい、というように外のベンチを指さす。この子、かわいすぎる。というか、ラオスの子供は皆かわいすぎる。
タイと同様に、ラオスも雨期のせいか太陽の日ざしが少しもきつくない。湿気も思ったほど辛くない。歩いていると汗ばみはするものの、心地良い風のおかげで歩くことが少しも苦痛にならない。皮のサンダルは長距離を歩くのには適してないかとも思ったけれど、それほどでもない。歩きながら、『姑獲鳥の夏』の京極堂の台詞を頭の中で反芻する。
「量子力学が示唆する極論はーこの世界は過去を含めて<観察者が観察した時点で遡って創られた>だ」
この台詞を前後の文脈から判断すると、世界はぼくが観察した瞬間にその態度を決める、ということになる。ぼくという個人が観察するまで、その世界は存在しないということだ。今、ぼくがこうやって歩いているこの町は、ぼくがここに来る以前から存在していたはずだ。それは間違いない。しかし、京極堂の言葉によると、この町の存在はぼくの観察後に創られたものということになる。
京極堂は続ける。
「僕等の科学で知り得る宇宙というのは、実に我々の生存に都合良くできているじゃないか。(中略)その理由はただひとつ、観察しているのが人間だからーさ。(中略)我々の内なる世界は言葉という呪によって覚醒したが、外なる世界もまた科学という呪によって覚醒したのさ。」
観察者が対象に影響を与えるのは、人間が「世界を語る」ことができるからだ、と言っているようにぼくには聞こえる。もしそれが正しいとして、それでは、「語られる世界」とは、一体なんなのだろうか?世界は、人間が存在しなければ「語られる」ことはなかった。世界が語られた瞬間、そこに一体どのような影響が及ぼされるのだろうか?ぼくは尊敬する作家のひとりである保坂和志の『世界を肯定する哲学』のことを思いだす。保坂は書いている。「私が生まれる前から世界はあり、私が死んだ後も世界はありつづける。」今、このとてもシンプルな命題が「世界」を考えるときにどれだけ重要な意味を持つか、少しだけ分かったような気がした。そして「観察すること」について、もっと深く考えたいと思ったが、それ以上考えることは出来なかった。
さらに歩く。歩くということは、足を交互に動かすという同じ動作の繰り返しで、それがぼくにはとても心地よい。ポール・オースターは「シティ・オブ・グラス」の冒頭で以下のように書いている。
散歩をするたびに、彼は自分を置き去りにしているように感じた。人の流れに身をまかせることによって、自分がひとつの目になることによって、考える義務から逃れることができた。このことは何よりも彼にある種の平安を、健康な空白をもたらした。世界は彼の外に、彼の周りに、彼の前にあった。刻々と変化するそのスピードが、彼にひとつのことを長く考える余裕を与えなかった。身体を動かすことが肝心だった。一方の足を前に踏み出し、それに合わせて体を動かすことだ。目的もなくさまよい歩いていると、どこへ行っても同じことで、自分がどこにいるかは問題でなくなる。気が乗っているときは、自分がどこにも存在しないように感じられた。そして、それこそ彼が求めてきた状態だった。
ぼくは、歩きながら色々なことを考える。何も考えないということは絶対にない。くだらないこと、つまらないことを常に考えている。ぼくが上記の主人公に共感するには、「考える義務」から逃れて、「自分を置き去りにしているように感じ」るという点で、「考えること」と「考える義務から逃れること」は、ぼくにとって同義であり、「考える義務」から逃れることによって考えられることを考えることがとても楽しい。などと訳の分からないことを考える。そんなことを考えながら、さらに歩く。
 途中、道を左に入った先に塔のようなものを発見。好奇心に駆られて、左に入り坂を上ってその方向へ行ってみると、大きめの寺院がある。中を覗いてみると、大きな仏像が見える。ワクワクしながら中に入る。昨日、バンコク国立博物館でみた釈迦如来像と同じ形をした仏像が四体、互いに背中を合わせて座っている。眺めていると、僧侶が近づいてきた。サヴァーイディー。挨拶をして、勝手に入った無礼を詫びるが、にこにことしていて全然気にしていない様子。「どうしてこの寺に来た?」と聞かれたので、「見かけたら」と応えたら、可笑しそうに笑っている。仏像が好きなので、写真を撮っても良いですか?と聞くと、快く了承してくれた。いろいろと聞きたいことがあったが、英語力の問題で断念。
途中、道を左に入った先に塔のようなものを発見。好奇心に駆られて、左に入り坂を上ってその方向へ行ってみると、大きめの寺院がある。中を覗いてみると、大きな仏像が見える。ワクワクしながら中に入る。昨日、バンコク国立博物館でみた釈迦如来像と同じ形をした仏像が四体、互いに背中を合わせて座っている。眺めていると、僧侶が近づいてきた。サヴァーイディー。挨拶をして、勝手に入った無礼を詫びるが、にこにことしていて全然気にしていない様子。「どうしてこの寺に来た?」と聞かれたので、「見かけたら」と応えたら、可笑しそうに笑っている。仏像が好きなので、写真を撮っても良いですか?と聞くと、快く了承してくれた。いろいろと聞きたいことがあったが、英語力の問題で断念。
結局、ヴィエンチャンには六時半過ぎに戻った。三時間以上歩いたことになる。夕方のメコンを散歩する。川岸で、数十人のおばちゃんが全員でダンスを踊っている。屋台でラオビールを買って、メコンを眺めながら飲む。わたくしは、ラオスに来ております。楽しくて嬉しくて、にやにやしてしまう。

明日はとうとう南ラオス。うまくいけば、明日中にはワット・プーに辿り着けるかも知れない。今回の旅行は、予想以上にうまく進んでいる。この調子で最終日までいってほしいものです。


朝、寝坊をして八時起床。パクセ行きの飛行機のチェックインが八時半なので、急いで着替えてゲストハウスを出る。トゥクトゥクで空港まで向かう。急いでチェックインカウンターに行くと、航空券に書いているチェックインの時間は間違いで、実際のチェックインは九時ということが判明。
九時にチェックインする。日本人の観光客がひとりいて、話しかけてくる。ぼくよりもかなり年上で、甲高い声で早口でぺらぺらと話す。一目で気が合わないのがわかったので、無視。十時に離陸。飛行機は思ったよりも小さい。外務省から注意喚起が出ている飛行機ではないので、墜落はしないと思うが、良い噂を聞かないラオス航空だけに少し緊張する。ぼくの隣には、英語が話せるラオス人の男性が座った。それほど流暢な英語ではないが、ぼくも同じようなものなので、片言同士でちょうど良い。話してみると、ぼくよりも年下なのになかなかの実業家らしく、パクセにセカンドハウスがあるという。パクセに着くまで、一時間ほど雑談をする。歳が近いこともあって、楽しかった。名前を聞いたが、すぐに忘れた。
十一時過ぎ、パクセに到着。雨がぱらぱらと降っている。空港を出ると、トゥクトゥクが一台しかいない。日本人の男性が、なにかにつけて気持ちの悪い声で笑い、しゃべり、それが癇に障る。トゥクトゥクに乗り込むと、フランス人の女性二人が先に乗っている。女性と言っても、二人とも十代に見える。長いこと待たされているのか、この町が気にくわないのか、二人ともむすっとしている。
ぼくたちが乗り込んでも、トゥクトゥクは一向に走り出す気配がない。見ると、運転手が観光客の外国人のおばさん相手に何か話し込んでいる。おそらく値段の交渉をしているのだろう。「早く行こうよ!」と怒鳴ると、「もうちょっと待って!」と怒鳴り返してくる。フランス人の女の子が「まだ来ないの?」と聞くので、「なんかおばさんと交渉しているんだけど」というと、二人はトゥクトゥクの天井をどんどんと叩き出した。ぼくも一緒に叩く。トゥクトゥクが揺れる。それから五分ほどして、ようやく運転手が戻ってきた。やっと走り出したと思ったら、いきなり給油所に立ち寄る。いい加減頭にきたので文句を言おうとしたら、日本人のおやじが甲高い声で笑いだした。その声の方にいらいらして、なにも言う気がなくなる。
パクセの市内に到着する前に、女の子達がゲストハウスの前でトゥクトゥクを降りる。このおやじとこれ以上一緒にいたくないので、ぼくもそこで降りる。雨が激しを増してきた。ここは一体どこなのだろう?ちょうど良くサムローのような乗り物が来たので、停めて、「チャンパーサックに行きたいのだけど」と言うと、英語は通じないようだが、乗れ、乗れ、と後部座席を指さす。「チャンパーサック?」と聞くと、「バス、バス」と言う。バス停まで連れていってくれるらしい。雨に濡れながら、バス停へ向かう。
バス停には、十分ほどで到着。サムローのおやじさんが、チャンパーサックへ行くソンテウを教えてくれる。ソンテウとは、小型トラックの後部の荷台に席があるようなもの。ぼくが着いたときには、席はすでに満席で、ぼくの顔をみると強引に詰めて席を作ってくれた。両手を合わせて、乗っている皆さんに「サヴァーイディー」と挨拶をする。しかしこれ、本当にチャンパーサックに行くのだろうか。聞きたくても、英語がまったく通じない。
 出発直後に、数人のラオスの若者がソンテウに乗り込んできた。そのうちのひとりが、少しだけ英語を話せるみたいだ。このソンテウは、確かにチャンパーサックへ行くとのこと。ほっと一安心。青年の名前を聞くが、一秒後に忘れる。しかしこの青年、英語を習い始めてまだ半年ということで、なにかにつけて英語を話したがる。ぼくは風景でも見ながら静かにソンテウに揺られたかったのだが、次から次へと話を続ける。最初は楽しかったけど、途中からうざくなって無視をすると、たばこを吸いながら友人たちの方へ戻っていった。
出発直後に、数人のラオスの若者がソンテウに乗り込んできた。そのうちのひとりが、少しだけ英語を話せるみたいだ。このソンテウは、確かにチャンパーサックへ行くとのこと。ほっと一安心。青年の名前を聞くが、一秒後に忘れる。しかしこの青年、英語を習い始めてまだ半年ということで、なにかにつけて英語を話したがる。ぼくは風景でも見ながら静かにソンテウに揺られたかったのだが、次から次へと話を続ける。最初は楽しかったけど、途中からうざくなって無視をすると、たばこを吸いながら友人たちの方へ戻っていった。
 パクセを出てから、延々と一本道を進む。この距離だとさすがに歩くことはできないが、一度も道を曲がらず、ひたすらに一本道を走り続ける。ぼくは一本道が大好きなので、直接に風を受け、ラオスの人々に押しつぶされそうになりながら走るこのソンテウが楽しくて仕方がない。周りには田んぼが広がっている。田んぼの中に、高床式の家がまばらに建っている。ソンテウは、数キロごとに村に止まる。村の物売りの子供たちが一斉にソンテウを取り囲み、飲み物やら食べ物やらを売ろうとするが、ぼくに気づくとはっと固まってしまう。が、両手を合わせて挨拶をすると、ニコッと笑ってくれる。歩くことも楽しいけれど、こうやってただ風景を眺めながら移動するのも、とても楽しい。
パクセを出てから、延々と一本道を進む。この距離だとさすがに歩くことはできないが、一度も道を曲がらず、ひたすらに一本道を走り続ける。ぼくは一本道が大好きなので、直接に風を受け、ラオスの人々に押しつぶされそうになりながら走るこのソンテウが楽しくて仕方がない。周りには田んぼが広がっている。田んぼの中に、高床式の家がまばらに建っている。ソンテウは、数キロごとに村に止まる。村の物売りの子供たちが一斉にソンテウを取り囲み、飲み物やら食べ物やらを売ろうとするが、ぼくに気づくとはっと固まってしまう。が、両手を合わせて挨拶をすると、ニコッと笑ってくれる。歩くことも楽しいけれど、こうやってただ風景を眺めながら移動するのも、とても楽しい。
約二時間ほどで、メコン川沿いの船着き場に到着。巨大な筏にソンテウを乗せて、メコン川を渡る。雄大なメコンの川上を、ソンテウとぼくを乗せた筏がゆっくりと流れる。雨も、いつの間にかやんでいる。
 川を渡ると、小さな村に到着。英語を話せる若者が、「ここがチャンパーサックだ」と言う。うっわー、何もねー!!と思いながら、ソンテウを降りる。ガイドブックに、何件かゲストハウスが紹介されていたけど、そんなものはどこにも見当たらない。若者に、「このへんにゲストハウスは・・・」と聞くと、周りの人と何かぼそぼそと話し、「この道をずっと先に行ったところにあるから、サムローで行け」とのこと。歩いては行けないか?と聞くと、二キロぐらいだという。それならば歩こうと思って歩き出すと、若者が後ろから追っかけてきて、ゲストハウスまでソンテウで送ってくれるという。お言葉に甘えて、再びソンテウに乗る。
川を渡ると、小さな村に到着。英語を話せる若者が、「ここがチャンパーサックだ」と言う。うっわー、何もねー!!と思いながら、ソンテウを降りる。ガイドブックに、何件かゲストハウスが紹介されていたけど、そんなものはどこにも見当たらない。若者に、「このへんにゲストハウスは・・・」と聞くと、周りの人と何かぼそぼそと話し、「この道をずっと先に行ったところにあるから、サムローで行け」とのこと。歩いては行けないか?と聞くと、二キロぐらいだという。それならば歩こうと思って歩き出すと、若者が後ろから追っかけてきて、ゲストハウスまでソンテウで送ってくれるという。お言葉に甘えて、再びソンテウに乗る。
五分ほどで、ソンテウを降りる。今度こそ本当にお別れなので、乗っているすべての人に丁寧にお礼を言って別れる。ソンテウが去り、周りを見回すと、何もない。こんなところに本当にゲストハウスがあるのかな、と思って少し歩くと、「ハロー」と何処からか声をかけられる。振り向くと、家の中から女性がぼくを呼んでいる。よく見ると、ゲストハウスと書いてある。部屋を見せてもらって、値段を聞くと一万キープ(140円)だという。時間もないことだし、ここに泊まることにする。
 ゲストハウスにはレストランが併設しているので、レストランで昼食をとる。ラープという挽肉を香草で炒めたものと、もち米のようなライス。うまい。食後、外に出ると観光客と思しき欧米人四人組が、トゥクトゥクとなにやら言い争っている。言い争っているというか、おそらく値段の交渉なのだろう。ワット・プーに行くのであれば、ぼくも一緒に乗っていこうかと思い、「ワット・プーに行くの?」と外国人に聞くと、「そうだけど、一緒に行く?」と誘ってくれた。渡りに船ですから、お言葉に甘えて参加することにして、値段の交渉は彼らに任せる。
ゲストハウスにはレストランが併設しているので、レストランで昼食をとる。ラープという挽肉を香草で炒めたものと、もち米のようなライス。うまい。食後、外に出ると観光客と思しき欧米人四人組が、トゥクトゥクとなにやら言い争っている。言い争っているというか、おそらく値段の交渉なのだろう。ワット・プーに行くのであれば、ぼくも一緒に乗っていこうかと思い、「ワット・プーに行くの?」と外国人に聞くと、「そうだけど、一緒に行く?」と誘ってくれた。渡りに船ですから、お言葉に甘えて参加することにして、値段の交渉は彼らに任せる。
 値段の折り合いがついて、トゥクトゥクに乗る。話を聞くと、四人は一緒に旅をしているわけではなく、お互いにカップルで旅をしていて、ぼくと同様にさっき出会ったばかりだという。四人の名前をそれぞれ聞くが、速攻で忘れる。一組のカップルに、どこから来たの?と聞くと、アイルランドとのこと。アイルランドと言えば、今回の旅行に持ってきた本の中に、「チェ・ゲバラ モーターサイクル南米旅行日記」があるので、「今、ゲバラの本を読んでいるのです」と言うと、二人は不思議そうな顔をした。あれ?ゲバラって、アイルランドじゃなくてアルゼンチンじゃん、とすぐに思い出し、ごめんごめん、勘違いしちった!と言おうしたが、英語力の不足でなかなか通じず、気がついたらぼくはアイルランドに二年間暮らしていたということになっていた。面倒くさいので否定をせずに、子供のころ住んでいたから、街の名前とか覚えていないとか適当な嘘をつく。コミュニケーションとは難しいものです。
値段の折り合いがついて、トゥクトゥクに乗る。話を聞くと、四人は一緒に旅をしているわけではなく、お互いにカップルで旅をしていて、ぼくと同様にさっき出会ったばかりだという。四人の名前をそれぞれ聞くが、速攻で忘れる。一組のカップルに、どこから来たの?と聞くと、アイルランドとのこと。アイルランドと言えば、今回の旅行に持ってきた本の中に、「チェ・ゲバラ モーターサイクル南米旅行日記」があるので、「今、ゲバラの本を読んでいるのです」と言うと、二人は不思議そうな顔をした。あれ?ゲバラって、アイルランドじゃなくてアルゼンチンじゃん、とすぐに思い出し、ごめんごめん、勘違いしちった!と言おうしたが、英語力の不足でなかなか通じず、気がついたらぼくはアイルランドに二年間暮らしていたということになっていた。面倒くさいので否定をせずに、子供のころ住んでいたから、街の名前とか覚えていないとか適当な嘘をつく。コミュニケーションとは難しいものです。
猛スピードで走るトゥクトゥクから外を眺める。こうして見ると、ヴィエンチャンはやはり首都だったのだなと感じる。チャンパーサックは、まさしく田舎!という感じで、のどかな田園風景がひたすら続く。途中、木に寄り掛かるようにして座っている巨大な仏像を発見。道路に背を向けているため、顔が見えない。正面から見たかったけど、トゥクトゥクは猛スピードで通り過ぎる。帰りは歩いて帰ろう、と心に決める。
三十分ほどでワット・プーに到着。遠くに、遺跡が広がっているのが見える。うおおおお!と感動する。時計を見ると、三時を過ぎている。受付で、何時まで見れます?と聞くと、五時までとのこと。カップルのうち一組は、受付の傍にあるレストランで食事をしてから行くという。もう一組のカップルは、受付を済ませてさっさと入っていった。ぼくはひとりで歩きたかったので、少し時間差で中に入る。
ワット・プーは、十二世紀ごろに建てられたとされるクメールの寺院の大遺跡で、自然災害や戦乱などによる人為的な被害のために、全体に損傷が激しい。それでも、クメールの遺跡を初めて観たということもあって、そのあまりの壮麗さ、そして、時間と共に正しく朽ちていくその姿に圧倒される。泥と草で荒れ果てた地面のあちこちには、寺院内に飾られていたであろう像たちが散乱している。寺院は、ところどころ補強されてはいるものの、かろうじて残っているかのように脆い印象を受ける。雨が降った後のため、地面はぬかるみ、足場が悪い。寺院に入ると、歩けるところがほとんどないぐらいに荒れ果てている。その荒れ具合が、とてもいい。ぼくは、不意に京極堂の台詞を思い出す。
「量子力学が示唆する極論はーこの世界は過去を含めて<観察者が観察した時点で遡って創られた>だ」
ぼくは、クメールの歴史に対して憧憬というものを持ち合わせていない。そのためか、この遺跡に対して「強者どもが夢の跡」のような感傷的な感想は全く持たない。ただ、この朽ちていく姿が美しいと思うだけだ。けれども、何百年か前にはさぞや絢爛であったであろうこれらの建物が、長年の風雨や、人為的あるいは自然現象により腐食しているこの状態を見れば、ぼくが生まれるずっと以前からこの場所にこの寺院が存在していたであろうことは容易に想像できる。この目の前に広がる風景や遺跡群が、ぼくがここに来てそれらを観察する以前からここに存在していたことは間違いない。けれども、京極堂の台詞がどうしても頭から離れない。この目の前の世界は、ぼくがここに来る以前から、あるいは観察をする以前から本当にここに存在していたのだろうか?
 |  |
 |  |
 |  |
正面の、勾配の急な階段を上って本殿に向かう。途中、人程の大きさの仏像があり、そばでお線香を売っている親子(?)がいる。汗をかきながら階段を登り終えると、本殿がある。ヒンドゥー様式の浮彫で装飾された寺院は、思ったよりも小さい。中に入ると、あとから持ち込まれたという仏像が四体、静かに座っている。皆、右手を膝にのせ、左手の掌を上に向ける例のポーズをとっている。たくさんのお供え物がある。今にも崩れ落ちそうな壇に座る仏像を、ゆっくりと眺める。
結局、五時ぎりぎりまで粘ってワット・プーを後にする。ふたたび欧米人カップルたちと合流し、トゥクトゥクで帰る。十分ほど進んだところで、トゥクトゥクを停めてもらい、そこから歩くことにする。
 しばらく歩くと、先ほどの木々の間に座っている仏像のところへ着いた。これだー!と駆け寄ると、そばで子供たちが遊んでいる。挨拶をすると、笑顔で応えてくれる。仏像を正面から見るために回り込むと、子供たちもついてくる。仏像は、凛々しい顔つきをしている。この仏像は、特に観光されるわけでもなく、昔からただここにあるものとしてここに座っているのだろう。臼杵の磨崖仏のことを思い出す。それらの石仏群は、何百年もの間、村人たちにただそこにあるものとして扱われ、子供たちの遊び場となっていたが、今では完全に修復され、国宝にも指定されて立派に保護されている。
しばらく歩くと、先ほどの木々の間に座っている仏像のところへ着いた。これだー!と駆け寄ると、そばで子供たちが遊んでいる。挨拶をすると、笑顔で応えてくれる。仏像を正面から見るために回り込むと、子供たちもついてくる。仏像は、凛々しい顔つきをしている。この仏像は、特に観光されるわけでもなく、昔からただここにあるものとしてここに座っているのだろう。臼杵の磨崖仏のことを思い出す。それらの石仏群は、何百年もの間、村人たちにただそこにあるものとして扱われ、子供たちの遊び場となっていたが、今では完全に修復され、国宝にも指定されて立派に保護されている。 文化財を保護することに対して異議を唱えるつもりはないけれど、ぼくがより心を惹かれるのは、今ぼくの目の前にあるような、雨や風にさらされながら蕭々とそこにある仏像で、そこには何とも言えない寂しさと、ただあるだけで放たれるような神々しさがある。子供たちは、恥ずかしそうにぼくの方を見ている。ガイドブックを片手に話しかける。お姉さんが、三人の弟の子守をしているらしい。とても頭の良い子で、ぼくがたどたどしいラオス語で言おうとすることを、すぐに汲んで答えてくれる。お姉さんの年齢を聞くと、十一歳だという。お礼を言って、その場を去る。
文化財を保護することに対して異議を唱えるつもりはないけれど、ぼくがより心を惹かれるのは、今ぼくの目の前にあるような、雨や風にさらされながら蕭々とそこにある仏像で、そこには何とも言えない寂しさと、ただあるだけで放たれるような神々しさがある。子供たちは、恥ずかしそうにぼくの方を見ている。ガイドブックを片手に話しかける。お姉さんが、三人の弟の子守をしているらしい。とても頭の良い子で、ぼくがたどたどしいラオス語で言おうとすることを、すぐに汲んで答えてくれる。お姉さんの年齢を聞くと、十一歳だという。お礼を言って、その場を去る。
 歩いてみると、想像以上に素晴らしい風景に出会う。右手にはメコン川が流れ、左手には田園が広がる。道には動物が悠然と闊歩し、道路の左右にある高床式の家からは、子供の声、親の声、音楽、様々な音が聞こえてくる。道を歩く子供も大人も、ぼくに気づくと怪訝そうな顔でじっと見つめるが、両手を合わせて挨拶をするととても優しい笑顔で応えてくれる。日が落ちてきた。田んぼから、蛙の声が聞こえる。日本の田舎で聞いた蛙の声よりも、良い声で鳴いている。トンボが群れをなして飛んでいる。数が半端じゃない。大気の色が、夕方に移り行く過程の、とても良い色に変化している。周りを見渡しても街灯なんてものは見当たらない。このままでは、ゲストハウスに辿り着く前に真っ暗になってしまいそうだ。少し歩く速度を早めよう。
歩いてみると、想像以上に素晴らしい風景に出会う。右手にはメコン川が流れ、左手には田園が広がる。道には動物が悠然と闊歩し、道路の左右にある高床式の家からは、子供の声、親の声、音楽、様々な音が聞こえてくる。道を歩く子供も大人も、ぼくに気づくと怪訝そうな顔でじっと見つめるが、両手を合わせて挨拶をするととても優しい笑顔で応えてくれる。日が落ちてきた。田んぼから、蛙の声が聞こえる。日本の田舎で聞いた蛙の声よりも、良い声で鳴いている。トンボが群れをなして飛んでいる。数が半端じゃない。大気の色が、夕方に移り行く過程の、とても良い色に変化している。周りを見渡しても街灯なんてものは見当たらない。このままでは、ゲストハウスに辿り着く前に真っ暗になってしまいそうだ。少し歩く速度を早めよう。
ふと左手を見ると、メコン川に向かって座っている仏像がある。夕刻と重なって、仏像の背中がやけに寂しそうに見える。仏像の方へ行きたいが、バリケードが張ってあって、向こう側へ行けないようになっている。近くに牛を連れているおじさんがいたので、入っていいか?と聞くと、全然問題ないようなので、バリケードをくぐって仏像の方へ行く。地面がぬかるんでいて、サンダルがずぶずぶと地面に埋まる。もつれる足をどうにか動かして、仏像のもとへ。正面へ周り、仏像を御顔を拝む。仏像は、静かにメコンの流れを眺めている。ただ、メコンの流れを眺めている。メコンを眺めることを強いられた仏像に、ちょっとだけ哀れみを感じる。

結局、ゲストハウスに着いた頃には辺りは真っ暗になっていた。昼と同じレストランで、夕食をとる。あまりおなかが空いていなかったので、フライドポテトと、スクランブルエッグ、それからラオス特製のアイスコーヒーを注文する。アイスコーヒーは、まるでチョコレートを飲んでいるのかと思うぐらい濃く、甘い。レストランには壁がないので、すべての食べ物に満遍なく虫が集っている。食べながら、読書をする。突然、スコールのように激しい雨が降りだす。
食事を終えて、走って部屋に戻る。ほんの数メートルしか離れていないのに、全身びしょ濡れになる。シャワーを浴びたいが、シャワーは部屋から少し離れたところにある。ふたたびダッシュ。どうにかシャワー室に入るが、電気がつかない。辺りは真っ暗で、ドアを閉じると完全に何も見えなくなる。仕方がないので、ドアを開けたままシャワーを浴びる。雨音が、どんどん激しさを増す。雷が鳴りだす。風が室内まで吹き込んでくる。幽霊や妖怪の類はそれほど信じてはいないけれど、さすがに怖くなり、さっさとシャワーを浴びてほとんど半裸のまま部屋に駆け込む。
部屋に戻っても、雨は一向に止む気配を見せない。風が窓とドアをがんがん叩いている。横になり、MDでテレビジョン・パーソナリティの一番好きなアルバムを聞きながら、さっきの読書の続きをする。MDから、"I Know Where Syd Barrett Lives"が流れる。
There's a little man
In a little house
With a little pet dog
And a little pet mouse
I know where he lives
And I'll visit him
We have Sunday tea
Sausages and beans
I know where he lives....
ahhhhhhhhhhh
'Cause I know where Syd Barrett lives

大好きな国で、大好きな音楽を聞きながら、大好きな書物を読む。
外の嵐がその幸せをよりいっそう引き立たせる。
それにしても、雨はぼくの予定に合わせて降ったりやんだりしているようだ。
ありがとうございます。
私は日の出とともに起きて、幸せだった。私は散歩をして、幸せだった。私はママンに会い、幸せだった。私は彼女のもとを離れ、幸せだった。私は森や丘を巡り、谷間をさまよい、読書をし、何もせず、庭仕事をし、果物を採り、家事を手伝い、幸せがいたるところ私についてきた。幸せは何か特定のものの中にあったのではなく、それはそっくり私の中にあり、一瞬も私から離れることはできなかった。ジャン=ジャック・ルソー『告白』
 朝六時起床。雨は小雨に変わっている。昨日、シャワーをきちんと浴びることができなかったので、シャ ワーを浴びる。朝は、さすがにシャワーの水が冷たくてきつい。水を浴びながら考える。昨日、ワット・プーに行った。今回の旅行の一応の目的は果たした。今日は十四日だ。明後日の十六日にバンコクに戻る列車を予約している。今日、明日、明後日をどうやって過ごそうか。そういえば、飛行機のリコンファームをするのを忘れていた。とりあえずパクセに戻ってリコンファームをし、その先のことは後で考えよう。
朝六時起床。雨は小雨に変わっている。昨日、シャワーをきちんと浴びることができなかったので、シャ ワーを浴びる。朝は、さすがにシャワーの水が冷たくてきつい。水を浴びながら考える。昨日、ワット・プーに行った。今回の旅行の一応の目的は果たした。今日は十四日だ。明後日の十六日にバンコクに戻る列車を予約している。今日、明日、明後日をどうやって過ごそうか。そういえば、飛行機のリコンファームをするのを忘れていた。とりあえずパクセに戻ってリコンファームをし、その先のことは後で考えよう。
部屋の外に出ると、空気がさわやかでとても気持ちがいい。ゲストハウスの前を、托鉢の僧侶たちが通り過ぎていく。僧侶と言っても大半がまだ子供と言って良い少年で、全員が裸足で歩いている。明らかに歩くのを嫌がって、仏頂面で付いていく少年が最後に続く。どこから来てどこへ行くのかは分からないが、裸足で歩く彼らを少し羨ましく思う。
ゲストハウスをチェックアウトするときに、パクセに戻るにはどうすれば良いか聞くと、とりあえず船着き場に行って、渡し舟でメコン川を渡り、向こう岸の村からソンテウでパクセに行くことができるとのこと。昨日ソンテウで到着した船着き場まで、歩いて二キロ程度なので、そこまで歩くことにする。
歩き始めると、雨が止んだ。やはり天候はぼくの味方をしている。昨日、泥溜まりを歩いたせいで、サンダルの革の部分がぶよぶよに伸びていて歩きにくい。足を引きずるようにして歩く。どこかで新しいサンダルを買わないと駄目だな。雨はやんだものの、空はどんよりと曇っている。昨日聞いた"I Know Where Syd Barrett Lives"を頭の中で繰り返す。向こう側から僧侶の托鉢の列が来る。待っていた女性が、僧侶のひとりひとりに御飯を施している。大乗である日本では、出家という宗教的修業はそれほど浸透していない(どころか、新興宗教のせいで偏見すら持たれている)が、南伝系では出家することは宗教に生きる人々にとっては当たり前のことなので、歩いているとこのように托鉢する僧侶達をよく見かける。ラオスはタイに比べて一般家庭への仏教の浸透がいまいちであるということを聞いたことがあるが、こうして食べ物を施してもらっている僧侶の一団を見ると、実際のところはどうなのだろうかと気になる。
 船着き場に着く。ここから渡し舟でメコン川を渡らなくてならない。とりあえず、適当な店に入って「パクセ、パクセ」と言うと、最初はきょとんとしているが、どうにか分かってくれたようで、船の乗り場まで連れていってくれた。昨日とは大型船とは異なり、人を運ぶための小さめの渡し舟に乗り込む。ソンテウに乗って渡し舟で川を渡ったときは、メコンを渡っている実感がそれほどなかったが、こうして直に風を浴びて渡し舟に揺られて川を進むと、如何にも川を渡っているという気がして嬉しい。それにしても、メコン川は本当に広い。四年前に行ったインドのガンジス川の川幅を思いだそうとするが、思い出せない。おそらく、メコン川の方が広いと思う。川は茶色に濁っている。この川の底には何が棲んでいるのだろう。川の半分を過ぎたぐらいで、小雨が降り出してきた。対岸に着くと、岸から少し離れたところで渡し舟が止まる。ここから歩いていけと言う。これ以上渡し舟では進めないらしい。仕方がないので、水に足を入れると、腰までは届かないものの、それに近い深さで、思いっきりズボンが水に浸る。リュックを濡らすのだけは避けたかったので、転ばないように慎重に歩く。
船着き場に着く。ここから渡し舟でメコン川を渡らなくてならない。とりあえず、適当な店に入って「パクセ、パクセ」と言うと、最初はきょとんとしているが、どうにか分かってくれたようで、船の乗り場まで連れていってくれた。昨日とは大型船とは異なり、人を運ぶための小さめの渡し舟に乗り込む。ソンテウに乗って渡し舟で川を渡ったときは、メコンを渡っている実感がそれほどなかったが、こうして直に風を浴びて渡し舟に揺られて川を進むと、如何にも川を渡っているという気がして嬉しい。それにしても、メコン川は本当に広い。四年前に行ったインドのガンジス川の川幅を思いだそうとするが、思い出せない。おそらく、メコン川の方が広いと思う。川は茶色に濁っている。この川の底には何が棲んでいるのだろう。川の半分を過ぎたぐらいで、小雨が降り出してきた。対岸に着くと、岸から少し離れたところで渡し舟が止まる。ここから歩いていけと言う。これ以上渡し舟では進めないらしい。仕方がないので、水に足を入れると、腰までは届かないものの、それに近い深さで、思いっきりズボンが水に浸る。リュックを濡らすのだけは避けたかったので、転ばないように慎重に歩く。
川を渡ると、昨日ソンテウで渡った川向かいの村に着く。さて、ここからパクセ行くのソンテウは、いつ出るのだろうか?船着き場に隣接している店で聞くと、ここで待っていろ、と言うのでペプシを飲みながら待つ。三十分もすると、ソンテウがやって来た。パクセ行きであることを確認して、乗り込む。
ソンテウは、昨日よりは乗客も少なく、ゆったりと座れる。雨がどんどん激しさを増してくる。昨日と同じように一本道をひたすら突き進む。
パクセに到着後、サムローで国際電話をかけられる店に連れていってもらい、無事にリコンファーム完了。さてこれからどうしようか。時計を見ると、九時を少し過ぎたところだ。今からバス停に向かえば、コーン島に行けるだろうか?とりあえず、バス停まで歩いてみようと思い、バス停の方向へ歩き出す。サンダルがぶよぶよで、歩きにくい。足に変なふうに力を入れるので、指が痛くなってくる。三十分ほど過ぎたところで、市場にようなところに出る。入り口に、警察官のような服装の男達がたむろっているので、「コーン島に行きたいのだけど」と英語で言うと、「おまえは、英語を話しているのか?」と逆に聞かれる。どうにか意志を伝えると、コーン島行きのバスは、ここから七キロほど先にあるバス停から乗れるという。七キロはさすがに歩けないので、適当なサムローをとめて交渉をしていると、別の小型ソンテウが止まって、バス停まで送ってくれるという。
バス停に到着。ソンテウの運転手が、コーン島行きのバスの前まで連れていってくれた。バスは、日本のバスが百倍ぐらいボロくなったようなバスだった。そういえば、ラオスに来て初めてバスに乗る。乗り込むと、満席を通り越してすし詰め状態。強引に乗り込み、乗客に両手を合わせて挨拶をする。見ると、観光客らしき外国人も数人乗っている。
バスは、その後も乗客を乗せて十時過ぎに出発。ガイドブックには、コーン島まで二時間と書いてある。二時間、立ちっぱなしなのだろうか、とちょっと不安になる。ラオス人は、皆うまい具合に席をつくって床に座っている。バスだと、直接風を浴びることができないのが残念だが、窓の外の風景はやはり面白いし、車内の人々の様子も、見ているだけで興味深い。バスは、ソンテウと同様に時々の村に停車する。物売りの女の子が大量にバスに乗り込み、あるいはバスを取り囲み、物を売ろうとする。昨日は何も買えなかったが、ジュースと焼き鳥のようなもの、もち米のビニール詰めを買う。うまい。
一時間を過ぎたあたりから、乗客が徐々に減り、ようやく席に座ることが出来た。さらに一時間ほど進むと、船着き場に到着。バスを運ぶフェリーを待っていると、日本人が話しかけてきた。聞くと、最初からバスに乗り込んでいたという。全然気づかなかった。話してみるととても面白い人で、ラオス語を話せるらしく、ラオス人ともどうにか会話をしている。コーン島に行くというので、向こうで一緒になったら嫌だな、と思いながらも、面白い人なので別にかまわないか、とも思う。
船着き場で一時間程待ち、バスを載せたフェリーでメコン川を渡る。川を渡るとコーン島に到着。フェリーの着いた村が、ゲストハウスがあるムアンコーンという村かと思ったが、見回してもそれらしきものは何もない。乗っている欧米人も降りない。仕方がないのでそのままバスに乗る。バスが島を走る。今まで以上に一面の田園風景が広がっている。雨が降っているせいか、道を歩く人はあまりいない。とても静かな島だ。さらに三十分ほど走り、終点に到着。どうやらここがムアンコーンらしく、ゲストハウスらしき建物が何件か建っている。結局四時間以上かかった。とりあえず、目の前にある雑貨店兼レストランのような店に入る。バスで話しかけてきた日本人が寄ってきて、「どこに泊まります?」と聞いてきた。二人でイスに座ってガイドブックを見ていると、雨が突然激しさを増す。ゲストハウスを決めないと何もすることが出来ないので、メコン川に面するポーン・ゲストハウスに泊まることにする。雨の中、二人で走っていくと、ポーン・ゲストハウスの隣に、結構きれいなゲストハウスがあるのを発見。ガイドブックには出ていないので、最近建てられたものかもしれない。値段を聞くと、二万キープとのこと。部屋を見せてもらうと、十分すぎるぐらい広くてきれい。シャワーは水しか出ないが、ここに泊まることにする。
部屋に入って荷物を置いた後、日本人のなんとかさん(名前失念)とゲストハウスのレストランで食事をとる。話を聞くと、埼玉の高校の非常勤講師をしていて、暇を見つけては南米やアジアによく旅行に行くとのこと。性格が適当で、話も面白いので、一緒にいて疲れない。ラオビールを飲み、つまみにラープともち米を食べる。この人は、九時前からバスに乗って待機していたらしい。本来であれば、バスは九時出発の予定だったらしい。もし、予定通りに九時に出発していたら、ぼくはここにこれなかったかもしれないわけだ。良かった。
一時間程雑談をしていると、雨が小降りになってきた。なんとかさんは、体調が思わしくないというので、一人で散歩に出る。一緒に行くと言われたらどうしようかと心配だったので、一人で歩けることがとても嬉しい。この旅行始まって以来の、雨の中の散歩だ。
 ゲストハウスの前の道を、来た方向と逆に進む。橋を渡って少し行くと、男の子たちがメコン川で遊んでいる。声をかけると、とてもノリが良い。さらに進むと、寺院が現れる。入っていいのかな、と躊躇するが、中から御経のようなものが聞こえてきたので、我慢できずに敷地内に入る。御経は、僧侶全員で読経する日本のやりかたとは異なり、一人が経を唱えると、輪唱のように残りの僧が経を反復する。経を唱えているのは、どうやら女性らしい。雨音の中に経が響く。暫し聞き惚れ、佇む。
ゲストハウスの前の道を、来た方向と逆に進む。橋を渡って少し行くと、男の子たちがメコン川で遊んでいる。声をかけると、とてもノリが良い。さらに進むと、寺院が現れる。入っていいのかな、と躊躇するが、中から御経のようなものが聞こえてきたので、我慢できずに敷地内に入る。御経は、僧侶全員で読経する日本のやりかたとは異なり、一人が経を唱えると、輪唱のように残りの僧が経を反復する。経を唱えているのは、どうやら女性らしい。雨音の中に経が響く。暫し聞き惚れ、佇む。
寺院を越えると、道が急に狭くなり、民家のようなところに入ってしまった。道は、完全に水没している。ぼくのサンダルはもうぐっちょぐっちょで使い物にならないので、躊躇なく水の中をじゃぶじゃぶと進む。しばらく進むと、完全に住居の敷地に迷い込んでしまった。と、家の軒下で、ハンモックのようなものに座っているおばさんを発見。挨拶をして、ジェスチャーでどこへ行けばよいのか聞くと、座っている軒の先の方を指す。向こうと言うことらしい。おばさんの隣を通って、御礼を言って先へ進む。
軒先をくぐると、田んぼの畦道に出た。田に落ちないように慎重に進むが、いかんせんサンダルが履物としての機能をはたしていないため、足への負担がすごい。指が打撲したように痛む。田んぼを越えると、広い道路に出た。雨のせいか、チャンパーサックと比べると人の通りはかなり少ない。時折、自転車に乗った人が通りすぎる程度で、歩いている人にはほとんど会わない。静かだ。
 ヴィエンチャンも、チャンパーサックも、何もないと言われているけれど、実際に行ってみると何かしらあった。けれども、このコーン島には本当に何もないようだ。一本道が視界の先まで続き、道の両わきには田圃が広がる。道の左先には山が聳え、右先にはメコン川が流れる。一本道がとても気持ち良い。ぼろぼろのサンダルを引きずりながら、一歩一歩、踏みしめて歩く。この道がどこに続くのか、ぼくは知らない。散歩好きなある友人が、歩いていると必ず目的地に到着するのが良いよね、と言っていたが、こうやって目的地の分からない散歩もとても楽しい。歩きながら思う。いつか、歩くだけの旅行をしてみたい。どこの国でも良いので、バスも、電車も、飛行機も使わずに、一年ぐらい歩き続けたい。もちろん、それがどれだけ困難なことであるか、散歩程度の歩行しかしたことがないぼくにでも想像は出来る。けれども、人間はもともと歩くことによって移動を行なってきたわけだし、歴史を見れば多くの人々が徒歩で国々を渡り歩いていたこともわかる。人にもよるとは思うが、歩くことはそれだけで人間を成長させると思う。十年後でも、二十年後でも良いので、徒歩による旅行をしてみたい。
ヴィエンチャンも、チャンパーサックも、何もないと言われているけれど、実際に行ってみると何かしらあった。けれども、このコーン島には本当に何もないようだ。一本道が視界の先まで続き、道の両わきには田圃が広がる。道の左先には山が聳え、右先にはメコン川が流れる。一本道がとても気持ち良い。ぼろぼろのサンダルを引きずりながら、一歩一歩、踏みしめて歩く。この道がどこに続くのか、ぼくは知らない。散歩好きなある友人が、歩いていると必ず目的地に到着するのが良いよね、と言っていたが、こうやって目的地の分からない散歩もとても楽しい。歩きながら思う。いつか、歩くだけの旅行をしてみたい。どこの国でも良いので、バスも、電車も、飛行機も使わずに、一年ぐらい歩き続けたい。もちろん、それがどれだけ困難なことであるか、散歩程度の歩行しかしたことがないぼくにでも想像は出来る。けれども、人間はもともと歩くことによって移動を行なってきたわけだし、歴史を見れば多くの人々が徒歩で国々を渡り歩いていたこともわかる。人にもよるとは思うが、歩くことはそれだけで人間を成長させると思う。十年後でも、二十年後でも良いので、徒歩による旅行をしてみたい。
 遠くの方から、カランコロンと風鈴のような奇麗な音色が聞こえてくる。なんだろうと思って歩み進むと、田圃の中で水牛が草を食み、その先にはまるで水墨画のように霞がかかっている山々の風景が広がる。カラン、コロンと不思議な音色が八方から聞こえてくる。この音は、何の音なのだろうか?水牛のいるほうへ行ってみようかと思うが、田圃が水に埋まっていて行くことが出来ない。道を過ぎる人は誰もいない。なんだかあの世に来てしまったような錯覚を覚え、通り過ぎる。カラン、コロンと音が背後から聞こえる。
遠くの方から、カランコロンと風鈴のような奇麗な音色が聞こえてくる。なんだろうと思って歩み進むと、田圃の中で水牛が草を食み、その先にはまるで水墨画のように霞がかかっている山々の風景が広がる。カラン、コロンと不思議な音色が八方から聞こえてくる。この音は、何の音なのだろうか?水牛のいるほうへ行ってみようかと思うが、田圃が水に埋まっていて行くことが出来ない。道を過ぎる人は誰もいない。なんだかあの世に来てしまったような錯覚を覚え、通り過ぎる。カラン、コロンと音が背後から聞こえる。
 自転車に乗った男の子達が三人、後ろから走って来て、すれ違いざまに険しい顔をしてぼくを一瞥する。両手を合わせて挨拶をすると、険しい顔が急に笑顔になる。二人はそのまま先へ走るが、一人は自転車を停めたまま動かない。どうしたのだろうと思って横を通りすぎると、後から付いてくる。何を話すわけでもなく、にこにこしながら付いてくる。ラオス語で話しかけようにも、ガイドブックは宿に置いてきてしまった。英語で話しかけるが、やはり通じない。仕方がないので、そのまま歩く。しばらく歩くと、男の子がいきなりラオス語で何かを言ってきた。が、何を言っているのかさっぱり分からない。わからないよ、とジェスチャーで示すが、男の子はニコニコしているだけ。ぼくもニコニコして、そのまま歩く。
自転車に乗った男の子達が三人、後ろから走って来て、すれ違いざまに険しい顔をしてぼくを一瞥する。両手を合わせて挨拶をすると、険しい顔が急に笑顔になる。二人はそのまま先へ走るが、一人は自転車を停めたまま動かない。どうしたのだろうと思って横を通りすぎると、後から付いてくる。何を話すわけでもなく、にこにこしながら付いてくる。ラオス語で話しかけようにも、ガイドブックは宿に置いてきてしまった。英語で話しかけるが、やはり通じない。仕方がないので、そのまま歩く。しばらく歩くと、男の子がいきなりラオス語で何かを言ってきた。が、何を言っているのかさっぱり分からない。わからないよ、とジェスチャーで示すが、男の子はニコニコしているだけ。ぼくもニコニコして、そのまま歩く。
三十分もそのような状態で歩く。突然、男の子が左手の田圃の中に建っている高床式の家を指さして何かを言った。どうやら、あそこが彼の家らしい。ぼくの部屋よりも小さい家だ。家の下で、水牛の親子が草を食み、犬が男の子を見て尻尾を振っている。男の子が家に向かって何かを叫ぶ。家の中から女性の声が聞こえ、母親らしき人が顔を出す。挨拶をすると、微笑んで応えてくれる。男の子にさようならを言って先へ進む。ぼくは昨日聞いたテレビジョン・パーソナリティの歌を思い出す。
There's a little man
In a little house
With a little pet dog
And a little pet mouse...............
さらに進むと、今度は道の右手から、美しい蛙の鳴き声が聞こえてくる。「美しい鳴き声」というのは誇張した表現ではなく、本当に美しい声で鳴いている。声は、八方どころかありとあらゆる場所から聞こえてくる。田舎育ちのぼくは、雨の日に田圃で鳴く蛙の声は聞き慣れているはずなのに、こんなに美しい鳴き声を聞くのは初めてだ。蛙の声の他に、鳥の声も聞こえる。蛙も、鳥も、姿は全く見えない。この美しい鳴き声は、どのようなオーディオ技術をもってしても、再現することは不可能だろう。この素晴らしい音響は、今ぼくが立っているこの場所でしか聞くことはできないのだ。この蛙や鳥たちは、いつから鳴いていたのだろう。さっき聞いた御経と同じように、音が心に染み渡る。もし、コーン島に来なかったら、ぼくは人生でこの音を聞きのがしていたかもしれない。来てよかった。目を閉じて、蛙と鳥と風と雨と土の音に耳を傾ける。音以外のすべてから、意識が遠くなる。
音に身を委ねながら考える。今、ぼくが歩いてきた道も、この場所も、この音も、すべてはぼくがここに来る以前から存在していたし、ぼくがここを去った後も存在し続けるだろう。けれども、ぼくがここに来て、こうやって観察をするまでは、「ぼくに観察されるこの場所」は存在しなかったはずだ。ぼくがここに来て、この場所を観察して初めて、「ぼくに観察された場所」が誕生したのだ。それは、今回の旅行で訪れたすべての場所に対して言えることであり、今まで生きてきて訪れたすべての場所に対しても言えるはずだ。それらの「ぼくに観察された場所」は、あくまでも「ぼくに観察された場所」であって、それ以外の何処でもない。別の人がその場所を観察しても、それはぼくが観察した場所とは大きく異なる。ぼくに観察されるまで、「ぼくに観察された場所」は存在しなかったのだ。
突然、「観察をする義務」を感じる。世界はぼくに観察されるまで、ぼくに観察されることはない。保坂和志は「私が生まれる前から世界はあり、私が死んだ後も世界はありつづける」と書いている。レヴィ・ストロースは『悲しき熱帯』の中で、「世界は人間なしに始まったし、人間なしに終わるだろう」と書いている。ぼくに観察される場所あるいは物は、ぼくが生まれる前からそこに存在していたし、ぼくが死んだ後もそこに存在を続けるだろう。けれども、「観察された対象」はぼくに観察されるまで、存在することは有り得ない。同時に思う。観察するということは、解釈するということとは全く異なる行為だ。たとえば、発展途上のこの国の人々が、貧しくても先進国の人々が失った幸せの中で生きているのだろうなんてことを考えるのは、自己満足の感傷に過ぎない。あるいは、訪れた異国に対して郷愁を感じることも、逆に憂いを抱くことも、そのような情感を否定するつもりは毛頭ないが、「観察」という観点から見れば、それらはすべて違う世界に住む「他人」による勝手な感情に過ぎない。人は、何かを見れば何かを感じる。何かに触れれば何かを感じる。何かを聞けば何かを感じる。それを避けることはできないし、それがなかったら人生はとても味気ないものになってしまうだろう。けれども、それは「観察」ではない。「観察すること」とは、あくまで「観察すること」に過ぎない。ぼくは「観察をする義務」を強く感じている。「観察すること」を現象学的な意味に取る人もいるかもしれないが、「観察」に「ぼくという人間」が必須である以上、現象学的な考え方では決してない。かといって「ぼくという個人」を「主観」という言葉に置き換えることにも抵抗を感じる。人間は、ひとりひとりが唯一の存在であるが故に、「かけがえのない命」なんて言い方をされるが、全員が唯一ということは、逆に言えば「かけがえのない命」なんてものは存在しないし、個人がかけがえのないものであるとしたら、世界に存在するすべてのものは同様に唯一無二なはずだから、全存在が「かけがえのない」もの、存在自体に意味のあるものということになり、翻して考えれば、全存在は「かけがえのある」ものだということになる。つまり、「かけがえ」の「在る」「無し」は、同じ意味を成すことになる。それと同じ考えで、ぼくという個人がこの世界に生まれた意味は「ない」と思っている。ぼくが生まれてきたのは、必然でも偶然でもなく、あえて言うなら「生まれるべくして、たまたま生まれてきた」のだろう。そして、諸行無常の言説通り、いつの日かは消滅する。そこから生じる結果はあっても、意味はないし、かけがえのないものでもない。こうやって言うと、虚無的な考えに聞こえるかも知れないが、「意味がない」ということは、「死んでも良い」と言うことではないし、「価値がない」ということでもない。ただ単に意味が発生しないというだけだ。生きているということは、意味を発生するものではなくて、「観察すること」に等しいのではないか。対象は、別に異国でなくても良いし、特別なものでなくても良い。いつの間にか生まれてきて、いつの間にか死んでいく(消滅する)すべての生き物にとって、「観察すること」は義務なのではないだろうか。今のぼくには「観察すること」について、これ以上考えること、説明することは出来ない。けれども、強く義務感を感じる。そんなことを考えながら、蛙の音に意識を揺るがせる。
 時計を見ると、六時を過ぎている。辺りが少し暗くなってきた。ここに来るまで、一度も街灯を見なかったので、暗くなる前に帰らないと、完全に真っ暗になってしまうだろう。名残惜しいが、今来た道を戻り始める。しばらく歩くと、さっき別れた男の子が、大声で歌いながら向こうから歩いてくる。ぼくに気づくと、歌うのをやめてこちらに手を振り、道沿いの川に降りて、水浴びを始めた。家に風呂がないので、毎日ここに来て水浴びをしているのだろう。男の子は、水を浴びながらニコニコとぼくに微笑みかける。ガイドブックを持ってくれば、この子ともう少し話が出来たのに、ととても残念に思う。元気でね。
時計を見ると、六時を過ぎている。辺りが少し暗くなってきた。ここに来るまで、一度も街灯を見なかったので、暗くなる前に帰らないと、完全に真っ暗になってしまうだろう。名残惜しいが、今来た道を戻り始める。しばらく歩くと、さっき別れた男の子が、大声で歌いながら向こうから歩いてくる。ぼくに気づくと、歌うのをやめてこちらに手を振り、道沿いの川に降りて、水浴びを始めた。家に風呂がないので、毎日ここに来て水浴びをしているのだろう。男の子は、水を浴びながらニコニコとぼくに微笑みかける。ガイドブックを持ってくれば、この子ともう少し話が出来たのに、ととても残念に思う。元気でね。
足下が覚束ないほど真っ暗になった頃に、ゲストハウスに到着。他の国であれば、こんな真っ暗な時間に外を歩くなんてことは絶対にしないが、ラオスだと気が緩んでしまう。気をつけよう。部屋に戻り、読書をしているとなんとかさんが部屋にやって来たので、レストランで一緒に夕飯を食べる。明日一緒にコン島、デッド島に行かないかと誘われる。さらにその先のカンボジアの国境までも行けるらしい。そうか、もうカンボジアの近くまで来ているのか。旅行の日程はまだ余っているので、それも良いかなとちょっと考えるが、なんとかさんが「その次の日に、一緒にラオスを出ましょうよ」と言い出したので、それはちょっといやだなあと思い、明日の予定も断る。明日だけ一緒に行動するのは構わないが、ラオスを出国するときはひとりでいたい。ソンテウやバスに乗っているときに、話しかけられるのも煩わしい。結局、ぼくは明日コーン島を後にして、パクセに戻ることにする。
寝る前に、MDで『Routine』を聞きながら、いつものように『日本的霊性』と『姑獲鳥の夏』を読む。他にも数冊持ってきているが、この両書がおもしろすぎて、他の本を読む気がしない。こういうときは、飽きるまで読むに限る。

ここからパクセへ戻るバスは、一番遅くても九時ぐらいに出てしまうらしい。明日は絶対に遅刻できない。

「全くです。画工だから、小説なんか初からしまいまで読む必要はないんです。けれども、どこを読んでも面白いのです。あなたと話をするのも面白い。ここへ逗留しているうちは毎日話をしたいくらいです。何ならあなたに惚れ込んでもいい。そうなるとなお面白い。しかしいくら惚れてもあなたと夫婦になる必要はないんです。惚れて夫婦になる必要があるうちは、小説を初からしまいまで読む必要があるんです」
「すると不人情な惚れ方をするのが画工なんですね」
「不人情じゃありません。非人情な惚れ方をするんです。小説も非人情で読むから、筋なんかどうでもいいんです。こうして、御籤を引くように、ぱっと開けて、開いた所を、漫然と読んでるのが面白いんです」夏目漱石『草枕』
朝、寝坊をして八時起床。最悪。急いで着替えをして、ゲストハウスを出る。チェックアウトの時に、パクセ行きのバスのことを聞くと、今の時間だと渡し船で向こう岸の村へ渡らないといけないらしい。ゲストハウスの従業員が、隣の家から渡し舟の持ち主を呼んできてくれて、向こう岸へ渡る。
川を渡ると、今まで訪れた村の中でも、一番こじんまりとしている小さな村に着いた。渡し舟の船頭に、バスはどこから出るのか聞くと、道の先を指さす。この道を行けということなのだろうか?英語が通じないのでそれ以上聞くことも出来ず、とりあえず道を進んでみることにする。
しばらく進むが、バスが乗れそうな場所も、バスが来る気配も全くない。途中で会った人に、「ロットメー(バス)」「パクセ」と尋ねると、道の先の方を指さして何かを言っている。さらに進むと、T字路に出た。右と左、どちらへ行けば良いか分からないので、近くの売店で聞くと、店員は左の方を指さす。本当なのかな、と思いつつも、そちらへ行くしかないので、言われた方向へ進む。すぐにまた売店があったので、念の為にもう一度バスのことを聞くと、お店のおじさんがラオス語で何かをまくし立てる。もちろん、何を言っているのかさーっぱり分からない。お礼を言って店を出ようとすると、おじさんがまた何かをまくし立て、ここにいろ、というジェスチャーをする。ここに入ればバスが来るの?と片言で聞くと、おじさんは頷く。半信半疑のまま、ペプシとお菓子を買って、食べながら座って待っていると、とても体格の良いおばさんが店にやってきた。おじさんに挨拶をして二言三言話すと、おじさんがおばさんを指さして、「パクセー」と言う。どうやら、このおばさんもパクセへ行くらしい。とりあえず、これで安心だ。
十分ほど待つと、ソンテウがやって来た。おばさんが大声を張り上げ、手を振ってソンテウを停める。少し先まで行ってしまったソンテウは、バックで戻ってきてぼくとおばさんを乗せる。バスよりもソンテウのほうが好きなので、嬉しい。
無事にパクセ行きのソンテウには乗れた。さて、これからどうしようか。今日中にラオスを出てタイに行ってしまっても良いし、今日はパクセかその周辺で過ごして、明日タイに行っても良い。なんだかんだで、今回の旅行はばたばたと忙しかったので、パクセで一日休養をとろうか。しかし、パクセって二回通ったが、面白そうな街では全然なかった。やっぱり今日中にラオスを出国しようか。
昨日は四時間以上かかった道のりが、今日は二時間弱で到着。到着した場所が市場だったので、ぼろぼろになったサンダルの替わりに、新しいサンダルを購入する。8000キープ。日本円にして100円もしないサンダルは、とても履き心地が悪く、五分も歩くとすでに靴擦れができた。痛い足を引きずりながら、パクセの市街へ向かう。歩きながら町を見回すが、あまり魅力を感じない。やはり、今日中にラオスを出てタイへ行こうと思う。タイへ移動し、明日一日を過ごして、夜にバンコクへ向かおう。明日タイへ向かうとすると、バンコク行きの電車の出る駅があるウボンラチャータ二ーはほとんど通り過ぎるだけということになる。それは少し寂しい。今日中にウボンへ行って、明日一日をそこで過ごそう。そうと決まったら、ラオスとタイの国境の村、バーンタオを向かおう。サムローをひろって、例のごとく「バーンタオ」を連呼。バス停へ連れていってもらう。
サムローに乗せられて、先程とは別の市場に到着。ここからバーンタオ行きのソンテウが出ているらしい。市場の中へ入ると、食料品のほかにも家電も売っている。市場を抜けると、バスの停車場らしきものがある。近くにいた人にバーンタオへ行きたいことを伝えると、ソンテウの所まで連れてきてくれた。十分ほど待って、発車。ぼくの他に三人の欧米人が乗っている。どこに行くの?と聞かれたので、タイへ出るためにバーンタオへ行く、と言うと、タイへ行くにはバーンタオではなくて、チョンメックで降りたほうが良いとのこと。チョンメックはバーンタオの少し先らしい。チョンメックって、タイじゃないの?出入国審査を受けないと入れないんじゃない?、と聞くと、ラオスとタイのイミグレーションの両方がチョンメックにあるとのこと。よくわからないけど、とりあえず行ってみればわかるだろう。
とうとうラオスを出国する。結局、たった四日しかいなかったんだよなーと思うと、やはり名残おしい。少なくとも二週間は滞在したかった。今回の旅行は、いつか時間があるときに再びラオスに訪れるための予行旅行だと自分に言い聞かせる。予行にしては楽しすぎる旅行ではあったけど。

一時間ほどでチョンメック到着。あまりにも質素な村で、一瞬行き先を間違えたのかと思ったが、イミグレーションの場所を聞き、その方向へ進むと、店がたくさん並んでいて活気に満ちている。ペプシを飲んで少し休む。村人たちは、観光客を商売相手にしていないせいか、ぼくには見向きもしない。店を出てしばらく歩くと、でかい建物があったので、入って聞いてみると、そこがラオスのイミグレーションらしい。先程同行した欧米人が出国審査をしている。「ハローアゲイン」などと適当に挨拶をして、ぼくも出国審査をする。無事に審査を済ませてトイレに入ろうとしたら、五バーツ取られた。
徒歩による国境越えは初めての体験なのでわくわくする。ちょっとした旅人になった気分。先へ進むと、今度はタイのイミグレーションがある。入国審査をして、外に出る。近くにいた人に、「ウボンラチャータニーへ行きたいのだけど」と言うと、柵を越えて向こうへ行け、とのこと。柵を越えるとそこはタイ側の市場。ああ、徒歩による国境越えをしてしまったのね、ぼく。なんとなく感無量。
そういえば、今日は朝からなにも食べていない。市場に来たことだし、昼食でもとろうかしらと思っていると、でぶのタイ人女性が「どこへ行くの?」と聞くので、「ウボンラチャータニーに行きたい」と言うと、大型のソンテウのところまで連れていかれ、「このバスでピブーン・マンサハーンへ行き、そこでウボンラチャータニー行きのバスへ乗り換えればいい」とのこと。タイのガイドブックを持っていないので、少々不安だが言う通りにすることにした。それほど腹が減っているわけでもなかったので、昼食は後にして、バスに乗り込んで待っていると、欧米人カップルが乗り込んできた。ぼくと同じ説明をでぶから受けている。バスに乗り込むと、二人は市場で買ったと思われるお菓子を食べ始めた。物欲しそうにしていると、クッキーのようなものをくれた。有り難く頂く。
しばらくするとバスが出発し、ピブーン・マンサハーンへ向かう。二人に行き先を聞くと、やはりウボンラチャータニーだという。ピブーン・マンサハーンを経由するということはガイドブックにも書かれていることらしい。一安心。乗客は、ぼくと、欧米人カップルと、でぶと、他のタイ人が二人だけ。MDウオークマンを取り出して、Bomb The Bassを聞く。ふと、ラオス通貨のキープを両替するのを忘れていたことに気づく。2000バーツを両替して、結局半分も使わなかった。ということは、三泊四日で3000円ちょいしか使っていないのか。あーもったいねー、ステーキ食えば良かった。キープなんて、どこへ行っても両替できないよなーと後悔し、眠くなって、寝る。
起こされて目覚めると、ピブーン・マンサハーンに到着したらしい。バスを降りると、道路の向こう側に別のバスが待機している。このバスがウボンラチャータニー行きとのこと。欧米人カップルに次いで乗り込む。バスが出発し、ウボンラチャータニーへ向かう。
とても天気が良くて、雨が降った気配は全然ない。こちらも雨期のはずだが、気候の感じがラオスとは全然違う。国境なんてものは、人間が勝手に決めた国の境に過ぎないはずなのに、そこを越えると本当に別の土地へ来たような感じがする。カップルに話を聞くと、すでに一ヶ月以上二人で東南アジアを回っていて、旅はまだ当分続くらしい。ラオスの観光ビザが切れそうなのでとりあえずタイへ出て、これからどこへ行くかはまだ決めていないとのこと。心の底からうらやましく思う。っていうか、この彼女、とても美しいのに、汚い。風呂に入ったほうがいいですよ、と忠告をしようと思ったが、ぼくも人のことは言えないのでやめておく。
一時間以上バスに揺られて、ウボンラチャータニーの駅へ到着。バスはこの後市内へ向かうらしいが、少し歩きたかったのでここで降りる。早速トゥクトゥクが寄ってくる。市内までの距離を聞くと、二キロとのこと。歩きたいと言うと、意外なほどあっさりと引き下がって、道順まで教えてくれた。センキュー。
 が、ちょっと歩いただけで靴擦れがひどくて歩けなくなる。足の皮がべろんべろんに剥けている。絆創膏を貼って、ゆっくりと歩く。参った。トゥクトゥクに乗ろうにも、空車のトゥクトゥクが全然通らない。痛みをこらえて歩く。途中、川を二つ越える。後に越えたほうの川は、メコン川と同じ色をしていた。なんという川なのだろう?後で誰かに聞いてみよう。
が、ちょっと歩いただけで靴擦れがひどくて歩けなくなる。足の皮がべろんべろんに剥けている。絆創膏を貼って、ゆっくりと歩く。参った。トゥクトゥクに乗ろうにも、空車のトゥクトゥクが全然通らない。痛みをこらえて歩く。途中、川を二つ越える。後に越えたほうの川は、メコン川と同じ色をしていた。なんという川なのだろう?後で誰かに聞いてみよう。
歩いていると、目に入る風景があまりにも日本に似ていて驚く。日本の郊外と、ほとんど変わらない。車の工場や、ディーラー、デパートらしきものもある。ラオスから数時間乗り物に乗っただけで、ここまで変わるものなのか。ぼくの故郷の方がよほど田舎だ。うーん。明日一日、楽しめるだろうか?
たった二キロの道のりに二時間以上かけて、ようやく市内に到着。すんごい都会。ぼくの汚い格好はやばすぎる。さっさと宿を探して、シャワーを浴びたいが、どこに宿があるのかさっぱりわからない。通行人に聞くと、一件のホテルの場所を教えてくれた。足が痛くて死にそうになりながら、教えられたホテルへ向かう。ホテルは、しっかりとした立派なホテルだった。多少高くてもいいや、と思いながら受付に行って値段を聞くと、一晩330バーツとのこと。ホットシャワーも出るということなので、チェックインする。
今回の旅行初のテレビ付部屋。シャワーを浴びて、きれいな洋服に着替える。今まで着ていた服は、汚いし、何よりも臭い。軽く洗って室内に干し、時計を見ると六時を過ぎている。そういえば、今日はなにも食べていない。何かを食べようと思い、外へ出る。
 ホテルを出ると、道路を渡ったすぐ先に屋台が並んでいる。腹がぐーぐー鳴っている。屋台で、色のついた御飯と、チキンの唐揚げのようなものを食べる。一緒についてきた調味料をかけたら、死ぬほど辛い。思わず一緒に出てきた生水をごくごくと飲んでしまう。大丈夫かしら。辛いものを食べたら、甘いものを食べたくなったので、バナナクレープが車に踏まれて汚くなったような食べ物を買う。うまい。他にも、気になる食べ物がたくさん屋台に並んでいる。また後で来てみようっと。
ホテルを出ると、道路を渡ったすぐ先に屋台が並んでいる。腹がぐーぐー鳴っている。屋台で、色のついた御飯と、チキンの唐揚げのようなものを食べる。一緒についてきた調味料をかけたら、死ぬほど辛い。思わず一緒に出てきた生水をごくごくと飲んでしまう。大丈夫かしら。辛いものを食べたら、甘いものを食べたくなったので、バナナクレープが車に踏まれて汚くなったような食べ物を買う。うまい。他にも、気になる食べ物がたくさん屋台に並んでいる。また後で来てみようっと。
痛い足を堪えて歩いていると、セブンイレブンを発見。絆創膏を買う。足のあっちこっちに絆創膏を貼りまくり、どうにか歩けるようになったので、夜のウボンラチャータニーを徘徊。本当に日本の郊外のような町で、それほど面白みはなさそう。途中、インターネットが出来る店を発見。こじんまりとした一間に、壁に向かってマシンが十台ほど並べられている。聞くと、日本語は使えないが、ランゲージパックをダウンロードすれば、日本語のサイトをみることは出来るという。日本語のランゲージパックをダウンロードしながら周りを見回すと、ほとんどの客が子供で、3Dゲームをやったり、インターネットをやったり、ワードで文章を書いたりしている。子供の僧侶が、3Dゲームで敵を銃でばんばん撃ち殺している。三十分以上かかってようやくダウンロード完了。鉄割のサイトを見る。鉄割のサーバは家に置いてあるので、鉄割のサイトが見られるということは、家も無事ということ。安心して店を出る。
時計を見ると、九時を過ぎている。道は車で溢れている。二人乗りのバイクがぼくを追い越していく。仲間同士らしい複数のグループが、町を徘徊している。ラオスでは寂しいと感じたことはほとんどなかったが、このような町に来るとひとりが寂しくなる。前回の旅行では、毎晩タイ人の若者のグループに強引に割り込んでは、一緒にお酒を飲んだりしたが、一人でそこまでやる勇気はない。宿に帰ることにする。
ホテルに到着。ウォークマンで音楽を聞きながら読書をする。『日本的霊性』はようやく第一篇読了。ここからがおもしろくなるところだ。『姑獲鳥の夏』は、三分の二ほど読み終えた。この本が面白すぎて、他の本を読むことが出来ない。一時間ほど読書をして、寝る。が、咽が渇いて夜中に目が覚める。今回の旅行で夜中に目を覚ましたのは初めてだ。受付へ行き、咽が渇いたことを伝えると、ホテルの外へ導かれ、となりの大衆食堂のような店に連れていかれる。時計を見ると十二時を過ぎたところだ。ペプシを飲んで部屋に戻り、今度こそ就寝。なんだか体がだるい。風邪をひいたのだろうか?

十年以上連絡を取っていない友人と一緒に、行方不明になった知人を探しにポルトガルを旅する夢を見る。『リスボン物語』のような夢だった。
ぼくは河向うのジャージー・シティ側の対岸をながめた。それは荒涼として見えた。水の干上がった河の石だらけの河床よりも荒涼としていた。まだここでは人類にとって重要なことは何ひとつ起こらなかった。おそらく何千年たっても起こらないだろう。ニュー・ジャージーの住民よりも、ピグミー族のほうが、はるかに興味深く、研究に光を投げかけてくれた。ぼくはハドソン河をながめ渡した。いつもぼくがきらっていた河だ。はじめてヘンリ・ハドソンと彼の血なまぐさい半月号のことを読んだときいらい、ぼくはこの河をきらっていたのだ。ぼくは河の両岸をひとしく嫌悪した。この河の名にまつわる伝説を嫌悪した。この河の流域全体がビールにつかって鈍重になったオランダ人の空虚な夢に似ていた。ポウハッタンであろうと、マンハッタンであろうと、そんなものは糞くらえだ。ぼくはニッカーボッカーどもを憎んだ。いっそ、この河の両岸に一万本の火薬の木が散在していて、そいつがいっせいに爆発してくれればいいと願った・・・。ヘンリー・ミラー『セクサス』

朝十時起床。シャワーを浴びて、外出の準備。足が恐ろしいことになっている。絆創膏を貼りまくって、ホテルをチェックアウトする。今日一日町を逍遥するには、荷物が邪魔になるので、夕方まで預かってくれないかと聞くと、出来ないとのこと。すぐ近くにツーリストインフォメーションがあるというので、教えられた場所に行く。中に入ると、女性が三人楽しそうにおしゃべりをしている。ぼくに気づくと、三人とも笑顔で挨拶をしてきた。三人ともめちゃくちゃかわいくて、早口の英語でぺらぺらとまくし立てる。予想外の雰囲気にびっくりしながら「この近くで荷物を預かってもらえる場所ってありますか?」と聞くと、「それはないけど、もしよければここで預かりますよ」と言ってくれる。まじ?まじですか?と聞き返すと、このTATは四時半までなので、四時までには戻ってきて欲しいとのこと。丁寧にお礼を言って荷物を預ける。ウボンラチャータニーの案内マップをもらうが、全部タイ語で書かれていて何が何だかさっぱりわからない。仏像のあるお寺をまわりたいのだけど、と言うと、マップにいくつか印をつけてくれた。昨日通りかかった寺もいくつかある。一日でまわりきれるだろうか?マップに記されている一番遠い寺まで歩いて行けるかどうかを聞くと、バスが出ているのでバスで行ったほうが良いとのこと。うーん。歩いていけそうなのだけどなあ。お礼を言ってTATを出て、歩けるところまで歩くことにする。
途中、デパートやらコンビニやらビデオレンタルやら、旅情を忘れてしまうようなものがどんどんと現れる。TUTAYAまでありやがる。一ヶ月も旅行をすれば、このような風景も懐かしく感じるのかもしれないが、たかだか一週間の旅行だと、懐かしくもなんともない。あーあ、旅情旅情、と愚痴をこぼしながら、目を塞ぐようにして歩く。目的の寺院Wat Nong Buaまで、一時間もかからなかった。
 寺院は、大通りから少し離れたところにあった。きれいな寺院で、敷地内に入ると目の前に巨大なストゥーパがそびえ立っている。ストゥーパの中に入ると、南伝系特有の仏像が鎮座している。隅で僧侶が机に座って何やら書き取りをしている。写経でもしているのだろうか?と思って見ていると、突然ストゥーパの中に宇宙戦艦ヤマトのテーマが鳴り響き、僧侶が懐からおもむろに携帯電話を取り出して大声で話し始めた。声が響く。濁ったような輝きを放つ仏像が座っている。ぼくもその場に座り、仏像と向き合う。南伝系は、教典を何語で読経するのだろう?電話で話す僧侶の言葉は、ある一定のリズムを持っていて、聞こうと思えば読経にも聞こえる。目を閉じる。瞼の向こうで、仏像が瞬くように輝いている。
寺院は、大通りから少し離れたところにあった。きれいな寺院で、敷地内に入ると目の前に巨大なストゥーパがそびえ立っている。ストゥーパの中に入ると、南伝系特有の仏像が鎮座している。隅で僧侶が机に座って何やら書き取りをしている。写経でもしているのだろうか?と思って見ていると、突然ストゥーパの中に宇宙戦艦ヤマトのテーマが鳴り響き、僧侶が懐からおもむろに携帯電話を取り出して大声で話し始めた。声が響く。濁ったような輝きを放つ仏像が座っている。ぼくもその場に座り、仏像と向き合う。南伝系は、教典を何語で読経するのだろう?電話で話す僧侶の言葉は、ある一定のリズムを持っていて、聞こうと思えば読経にも聞こえる。目を閉じる。瞼の向こうで、仏像が瞬くように輝いている。
 ストゥーパから出て歩くと、一人の僧侶がぼくを呼び止め、先の方向を指さす。指さす先には大きな寺院が建っている。入っていいのですか?と聞くと、笑顔で頷く。寺院に入ると、タイ人の子供たちが熱心に寺院内を写生している。学校の課題だろうか?間を通って奥へ進む。最奥には壮麗な涅槃像がある。壮麗、と書いたが、実際にはプラスチックのような印象を受けた。強引に絢爛なイメージを作りだそうとしている感じだ。
ストゥーパから出て歩くと、一人の僧侶がぼくを呼び止め、先の方向を指さす。指さす先には大きな寺院が建っている。入っていいのですか?と聞くと、笑顔で頷く。寺院に入ると、タイ人の子供たちが熱心に寺院内を写生している。学校の課題だろうか?間を通って奥へ進む。最奥には壮麗な涅槃像がある。壮麗、と書いたが、実際にはプラスチックのような印象を受けた。強引に絢爛なイメージを作りだそうとしている感じだ。 それよりも、壁に描かれている壁画の方が気になる。阿弥陀如来の来迎図のようなものがある。バンコクの博物館に行ったときも、同じような壁画をみた。浄土信仰はインドで発生したものだから、南伝系に伝わっていてもおかしくはないが、実際のところどうなのかわからない。これは、本当に来迎図なのだろうか?京都の知恩院の阿弥陀来迎図を思い出し、目の前にある壁画に物足りなさを感じる。
それよりも、壁に描かれている壁画の方が気になる。阿弥陀如来の来迎図のようなものがある。バンコクの博物館に行ったときも、同じような壁画をみた。浄土信仰はインドで発生したものだから、南伝系に伝わっていてもおかしくはないが、実際のところどうなのかわからない。これは、本当に来迎図なのだろうか?京都の知恩院の阿弥陀来迎図を思い出し、目の前にある壁画に物足りなさを感じる。
寺院を出て、今来た道を戻る。地図で確認すると、昨日ぼくが眺めた川はMoonRiverという名前のようだ。MoonRiverまで戻り、昨日見かけたWat Supattanaramという寺院に入る。中に入ると、子供が山のようにいて、球技のようなものをしている。日本の幼稚園のように、寺と学校が一緒になっているのだろうか?奥の方へ進むと、本堂らしき建物があるが、鍵が閉まっていて入ることができない。うろうろしていると、でぶのおじさんに呼び止められる。おじさんはこの学校の先生だという。英語が話せるらしい。あの建物に入りたいのですが、と言うと、今は改装中のために入ることは出来ないとのこと。そのかわり、その先にある宝蔵庫でよければ、鍵を開けてくれるという。喜んで開けてもらうことにする。「この寺に来た観光客で、この宝蔵庫に入れる人はあまりいないんだよ」とおじさんが言う。「いつも鍵をかけているのですか?」と聞くと、もともと一般公開をしているものではなくて、本当の意味での収蔵庫らしい。サンキューサンキューと何度もお礼を言って、中に入る。
中には、このお寺を建てた開祖のお坊さんが持ち込んだという仏像やらなんやらが山ほど収められている。うおー、すげーと感動し、ひとつひとつをじっくりと眺める。南伝系ではあまり見ない、大乗の仏像らしきものもたくさんある。ヒンディー系の仏像、特にガネーシャの像なんかもいくつかある。正直なところ、さっきの寺院でみた仏像よりも、ここにある仏像の方がずっと素敵だ。ケースに入っている仏頭を外に出して、じっくりと鑑賞したいと思うが、それはさすがに言いだせなかった。
 おじさんは、昔はマレーシアでエンジニアをしていて、その時に英語を覚えたと言う。仕事は?と聞かれたので、コンピュータのプログラマーですと答えると、最近出来たパソコンの教室があるので見てみないか?と言う。とても興味があるので、喜んで申し出を受ける。このおじさん、本当にいい人だ。学校の中に入ると、子供たちがおじさんに飛びついてくる。子供たちをあやしながら二階に上がり、コンピュータ教室に入ると、黄色の僧侶服を来た子供の僧侶が、大勢でパソコンに向かっている。おじさんが皆にぼくを紹介する。挨拶をして、パソコンを見せてもらうと、思ったよりも良いスペックのパソコンを使っていて、タイ語のワードで何やら入力をしている。聞くと、作文だそうだ。子供たちは、ぼくをみてちょっと引いている。いきなりこんな汚い格好をした変なやつが現れたら、嫌がるか。しばらく教室内を見せてもらい、お礼を言って教室を出る。
おじさんは、昔はマレーシアでエンジニアをしていて、その時に英語を覚えたと言う。仕事は?と聞かれたので、コンピュータのプログラマーですと答えると、最近出来たパソコンの教室があるので見てみないか?と言う。とても興味があるので、喜んで申し出を受ける。このおじさん、本当にいい人だ。学校の中に入ると、子供たちがおじさんに飛びついてくる。子供たちをあやしながら二階に上がり、コンピュータ教室に入ると、黄色の僧侶服を来た子供の僧侶が、大勢でパソコンに向かっている。おじさんが皆にぼくを紹介する。挨拶をして、パソコンを見せてもらうと、思ったよりも良いスペックのパソコンを使っていて、タイ語のワードで何やら入力をしている。聞くと、作文だそうだ。子供たちは、ぼくをみてちょっと引いている。いきなりこんな汚い格好をした変なやつが現れたら、嫌がるか。しばらく教室内を見せてもらい、お礼を言って教室を出る。
おじさんとアドレスの交換をして、学校と寺院を出る。本当に素敵なおじさんだった。時計を見ると、まだ二時を過ぎたところだ。近くの別の寺院に行くが、本堂は閉じていて入ることができない。仕方がないので昨日泊まったホテルの近くの博物館に行くが、改装中であまりおもしろくない。パンフレットを見ると、美しい黄金の仏像(というか、タイの仏像はたいてい黄金なのだが)がある寺院が載っているので、そこへ行くことにする。三十分ほど歩いて、Wat Pa Yaiに到着。白い修業服のようなものを着たおばさん達が、数人本堂で寝ていて、時々起きだしてお祈りを捧げている。ぼくもそこに座って、暫し黙想。
そんなこんなで、四時近くになったので、TATに荷物を受け取りに行く。朝三人いた受付のお姉さんたちは、一人になっている。お礼を言って荷物を受けとると、含み笑いで「中が無事かどうか調べたほうがいいわよ」というので、かわいいなあこの人はと思いながら、「必要ないよ」とカッコつける。汚い格好だけど。何度もお礼を言って、TATを出る。
そういえば、今日は何も食べていないことに気づき、食堂に入ってとても苦労をしてチャーハンを注文する。言葉が通じないうえに、チャーハンをジェスチャーで表すのはとても難しい。チャーハンをがつがつ食べて、水をがんがん飲む。うまい。
足の絆創膏を貼り直して、駅まで歩くことにする。途中、MoonRiverで一休みしよう。歩き出すと、腹がぐるぐると鳴りだす。昨日から、あまり頓着せずに食べ物や飲み物をとっていたので、腹を壊したのだろうか?とりあえず、我慢できるところまで歩こう。明日で旅行も終わるというのに、最後の最後でついていない。
MoonRiverに到着。釣りをしている人が何人かいる。腹が限界に達する。川岸に降りると、なかなか良い案配に草むらがある。おなかがきゅーきゅー鳴いている。耐えきれず、荷物を放り出してティッシュだけを持ち草むらに走る。そのまま座ると、草がお尻に当たって痛いので、足で草を踏みつけて馴らし、ズボンを脱いで生まれて初めての野うんこをする。おなかが。おなかが痛いのです。
 うんこをしながら、目の前にMoonRiverを臨む。生まれて初めての野うんこは、出来れば日本でしたかったと思う。うんこをしながら、考える。これが野うんこだったからよかったが、もしこれが「死」だとしたらどうだろう。二葉亭四迷は、ロシアから日本への帰国の途中、インド洋の海上でその生涯を閉じた。二葉亭の性格を考慮すれば、彼の死に場所が日本から遠く離れた船上であったことが、彼に悔恨の念を抱かせたということは考えにくいが、ぼく個人の感情としては異国の地で死ぬのはいやだと思う。ぼくは相当いい加減な性格なので、多少のことは気にしないけれど、死に場所だけは常に気にしている。西行法師は「願わくば 花の下にて 春死なむ」と詠った。死んだ後のことはどうでも良いけれど、死に場所は住み慣れた場所で、死ぬ瞬間は愛するものの傍で逝きたいと思う。誰だかが「畳の上では死なねえぜ!」なんて歌っていたが、ぼくは畳の上でなくても良いが、心を緩やかにして安心して死にたい。それがぼくにとっての唯一の夢だ。そのような意味での理想の死に方は、和辻哲郎さんのそれで、彼の最後の作品(未完)となった『自叙伝の試み』では、和辻君の奥さんが後書きにかえて彼の最後の様子を記している。
うんこをしながら、目の前にMoonRiverを臨む。生まれて初めての野うんこは、出来れば日本でしたかったと思う。うんこをしながら、考える。これが野うんこだったからよかったが、もしこれが「死」だとしたらどうだろう。二葉亭四迷は、ロシアから日本への帰国の途中、インド洋の海上でその生涯を閉じた。二葉亭の性格を考慮すれば、彼の死に場所が日本から遠く離れた船上であったことが、彼に悔恨の念を抱かせたということは考えにくいが、ぼく個人の感情としては異国の地で死ぬのはいやだと思う。ぼくは相当いい加減な性格なので、多少のことは気にしないけれど、死に場所だけは常に気にしている。西行法師は「願わくば 花の下にて 春死なむ」と詠った。死んだ後のことはどうでも良いけれど、死に場所は住み慣れた場所で、死ぬ瞬間は愛するものの傍で逝きたいと思う。誰だかが「畳の上では死なねえぜ!」なんて歌っていたが、ぼくは畳の上でなくても良いが、心を緩やかにして安心して死にたい。それがぼくにとっての唯一の夢だ。そのような意味での理想の死に方は、和辻哲郎さんのそれで、彼の最後の作品(未完)となった『自叙伝の試み』では、和辻君の奥さんが後書きにかえて彼の最後の様子を記している。
何分間位だったろう。この時ほど何も思わずにぼんやりしていたことはない。ふっと何かに引かれた心持で主人の顔を見た。すると主人は大きな眼をあいてじっと天井を見つめていた。ずんずん顔色が青くなって行く。私は息がとまりそうになった。
「どうなすったの?どこかお苦しいの?」
覗き込んで思わず大声を出した。が目はぼんやり開いたままで返事はなかった。
「ね、どこかお苦しいの?」
「どこかお苦しいの?」
続けて二度夢中で言うと、目が生きて静かに私を見て、
「どこも苦しくない」と返事をした。
「どこかお痛いの?」
手を握ってもう一度聞くと、
「どこも痛くない」
とはっきり言った。それなり目をつぶり意識がなくなって行くようなので、私はあわてて廊下から孫共を呼び立てた。孫共はとんで来た。その隙に医者に電話をかけた。
「おじいちゃま」
「おじいちゃま」
孫達は両方からすがり付くようにして叫びながら大声で泣き出した。それが聞えたのか主人は眼をあいて孫共に
「何か言った?大丈夫 大丈夫」
と、頭でも撫でてやっているような調子で言った。そして静かに眼をつぶった。そこへ医者が駆けつけて呉れて注射を打ったがもう反応はなかった。二つくしゃみをし、大きく二度息をはいた。十二時四十分。あんなにも好きだった太陽が明るく障子にあたっていた。和辻哲郎『自叙伝の試み』より
鬼平犯科帳なんかを読んでいると、「殺生をしなかったから畳の上で死ぬことができた」なんていう因果的な表現がよく出てくるが、日ごろの行いで死に方や死に様が決まってしまうのであれば、こんなに簡単なことはない。そうじゃないから困ってしまう。結果が必ずしも原因を伴うとは限らないから、生きるということは難しいのだ。とにかく、野うんこは図らずも異国の地で初体験を迎えてしまったが、この経験を無駄にせず、死ぬときは必ず日本で死のう。まだ数十年は先の話ではあるけれど。
とはいうものの、川を眺めながらするうんこもそれほど悪くない。ラオスで見た、メコン川に臨むようにして座っていた仏像を思い出す。彼ももしかしたら野うんこをしていたのかもしれない。うんこ仲間だ。
午後六時、ウボンラチャータニー駅に到着。駅に隣接する売店でコーラを買って時間をつぶし、午後七時十五分、ほぼ定刻通りバンコク行き寝台特急が出発。腹痛は、今は治まっているが、なんとなく調子が悪い。

夜中、腹痛で目が覚める。今回の旅行で初めて夜中に目を覚ました。ちょっと調子に乗りすぎたかも知れない。クーラーが効きすぎて、体がだるい。吐き気もする。なんとなく、インド洋を渡る二葉亭四迷の気分。
文は拙を以て進み、道は拙を以て成る。一の節の字、無限の意味あり。桃源に犬吠え、桑間に鶏鳴くが如きは、何等の淳廊ぞ。寒潭の月、古木の鴉に至っては、工巧の中に、便ち衰颯の気象あるを覚ゆ。菜根譚より

朝六時、バンコク到着。クーラーが効きすぎで、体がだるい。腹痛も続いている。うー、参った。駅を出て、カオサンロードまで歩こうかと思っていたが、さすがに無理っぽいのでトゥクトゥクに乗る。カオサン到着。いつものゲストハウスにチェックインする。そのまま、寝る。
十一時すぎに起床。腹がビックバン。足が靴擦れでぐちゃぐちゃ。さすがに動く気になれず、ベットに寝たまましばらく読書。昼過ぎ、腹痛が少し治まってきたので、町へ出る。最初にサンダルを買う。100バーツ。めちゃくちゃ履き心地が良い。これなら、歩ける。歩くか。けど腹が。
マッサージ屋に入り、一時間半マッサージをしてもらう。気持ち良すぎる。途中でうんこをもらしたらどうしましょう、と心配だったが、無事に終了。一時間半で200バーツ。
コーヒーの飲めるインド料理屋に入って、インド料理を頼まずにカフェラテとチーズのサンドウィッチを注文する。カフェラテを飲みながら、しばし読書。まるで日本にいるみたい。
腹痛が全然治まらない。腹を押さえながら、散歩をする。サナーム・ルアンのほうにやたらと人が集まっている。なんだろうと思って行ってみると、ライブのような歓声と音楽が聞えてくる。近くにいた人に聞くと、野外コンサートのようなものが行われているらしい。近づけば近づくほど、人が混みあっている。あんなところで押し合ったら、絶対にうんこをもらしてしまう。早々に退散する。
ああ、今日で旅行はおしまいなのか。やっぱり、一週間というのはさすがに短すぎる。放浪をしたいなんてことはこれっぽっちも思わないけれど、せめて長期の旅をしたい。二ヶ月ぐらいかけて、東南アジアを横断するとか、ヨーロッパを巡るとか。
お土産を買ったり、ぶらぶらしたりで時間をつぶす。今回の旅行でつきまとわれた釈迦如来像のちっちゃいやつを一つ買う。鉄割のみなさんには、糞まずいお菓子を購入。野外コンサートがあったためか、カオサンロードがいつもにも増して混みあっている。花火まで上がっている。みな踊っている。さびしくなりますからやめて下さい、とつぶやく。夜九時過ぎにバンコクを後にする。どうせまたすぐに来るんだろうなあ。バンコク、こんなにも嫌いなのに。
空港でチェックインをした後に、空港内カフェで時間を潰す。『姑獲鳥の夏』、読了。面白すぎて、感動。日本に帰ったら、京極夏彦の作品を全部チェックしよう。『日本的霊性』は半分程読み終えた。他の本はほとんど読んでいない。それだけこの二冊がおもしろかったということだろう。
結局、観察者によって対象物が変化するということの本当の意味が、ぼくにはよくわかっていないような気がする。ぼくが考えていることは、結局のところ「万物の尺度は人間である」のような相対的認識主義にすぎないわけで、それは「観察」ではなくて、主観的な思い込みに過ぎない。ポール・ボウルズにとって、タンジールという国は旅の目的地、あるいは通過点としてのみ存在した。越川芳明さんはボウルズについてこんなふうに書いている。
(ボウルズが)通常の旅行作家とちがうのは、観察の対象となる異国の土地の文化的・民族的な特徴を記述しようとしたのではないという点だ。むしろかれが執筆のために旅した世界はもっとミクロな世界だった。つまり、旅する人間自身の内面という、地図のない世界だった。ボウルズの小説では、旅する異国の土地の特性ではなく、見る者(主体)自身の想像力が検証されるのだ。越川芳明『果てしない旅が作家をつくりだす』
まあ、人生はまだまだ長いのですから、ゆっくりと考えていきましょ。

胃袋の痛みを抑えつつ、飛行機に乗り込む。これにて心やすめの旅行はおしまい。おやすみなさい。
そんなわけで、日本に帰って参りました。
帰りに池袋のリブロに寄って、京極夏彦の『魍魎の匣』と『妖怪馬鹿』を購入。『妖怪馬鹿』は、京極夏彦をはじめとする妖怪好き三人の座談会。ちょっと立ち読みしただけでも、めちゃくちゃおもしろい。しばらくは京極さんから離れられそうにありません。
東南アジア系の仏像の本を探すが、一冊も置いていない。ジュンク堂に行けば置いてあるだろうが、腹痛がひどいので、今日のところはやめて家に帰る。下痢はしていないのに、一歩歩くごとに腹に痛みが走る。ほとんど生理痛と化しております。

帰宅後、旅行中に唯一録画しておいた『海底二万海里』の映画を観る。『八十日間世界一周』を読みたくなりました。
すっかり京極夏彦に取り憑かれてしまいました。
とりあえず、今出ているすべての作品を耽読するつもりでございます。一冊一冊がとても分厚いので、なかなか読みごたえがありそうです。
そんで、Bk1なんかをみていたところ、こんなインタビューを発見しました。
これを読むと、小学生の頃から柳田国男にはまっていたとか言っていて、予想通りいやなガキだったみたいですが、そういわれてみると、主要登場人物のひとりである京極堂の妖怪や超常現象に対するスタンスは、柳田くんのそれに近いものがあるような気もします。

■Daily Photo Project(Via KOI)
毎日毎日自分の顔写真を撮り続けております。一年や二年ではあまり面白くないかも知れないけど、十年とか続けたら見ごたえがありそう。
■All Look Same(Via 100SHIKI)
某ラジオ番組で「音楽の偶然」などというコーナーがございますが、こちらはサイトの偶然です。
■love story(Via EverLasting Blort)
愛とは切ないもの。
■THE SEXIEST CARTOON BABES(Via 気になるWeb)
セクシーな漫画の登場人物をご紹介。個人的にはバンピレラさんが素敵でした。
■Long Live The King....(via b00mbl0g)

■乾燥大麻…実は雑草 所持の少年を厳重注意
少しずつ、大人になっていくのです。

雑誌『BRUTUS』の今回の特集は、「日本美術?現代アート?」です。
(今回の特集と言っても、この文章を書いている時点ではすでに次の号が出てしまっていますが)
縄文時代から18世紀までの日本美術と、現代の日本美術それぞれの中から、イメージの共通する作品をひとつずつ抽出して対比させ、その類似性を探る!というこの特集、とても面白くてすっかり読み入ってしまいました。
狩野山雪の『梅に遊禽図襖』と村上隆の『Hiropon』という無理のある組み合わせがあれば、三十三間堂の『千体千手観音像』とグルーヴィジョンズの『Chappie 33』というなるほどと感心してしまうような組み合わせもあり、牧谿の『老子図』はバカボンのパパに、雪村の『拾得図』はレレレのおじさんになっちまってます。
日本美術には疎いぼくでも、楽しく読むことができました。
それで思い出したのが雑誌『太陽』1992年2月号の「仏像は今を生きているか」という特集で、日本の古典美術作品と他の美術作品を類似点という観点から比較するという点では今回の『BRUTUS』と同様なのですが、異なるのは扱う古典美術がすべて仏像であるという点と、対比させる作品が日本の現代美術のみならず、古今東西和洋問わず、ありとあらゆる芸術作品、さらには芸術作品でないものからも選ばれているという点です。
たとえば、奈良の東大寺の五劫思惟阿弥陀像には1930年代のハリウッド・女優のヘアスタイルを、京都の神童寺の愛染明王には、ラファエロの描いたキューピットを、『BRUTUS』でも扱われていた西往寺の宝誌和尚像は映画『トータルリコール』を、禅林寺の見返り阿弥陀像には切手『見返り美人』を引合にだしています。
さらにぼくが感動したのは、女型の仏像、伎芸天像や吉祥天像など十七体の仏像に対して、それらの仏像にイメージする「貝殻」を引合に出して紹介していたページです。ぼくの大好きな秋篠寺の伎芸天像には「コガネタカラ」を、阿修羅像には「ハリナガリンボウ」を、などなど。仏像のイメージが明確になると同時に、貝殻の美しさに初めて気付きました。
とても良い特集でした。まじでー。

仏像は好きだけど日本美術には疎いぼくには、今回の『BRUTUS』はとてもお勉強になりました。センキュー。
胃痛が一向に治まらず、お医者さんに行って診断を受けたところ、念のために胃カメラを飲んでおいたほうが良いとのことなので、翌日の早朝に診察に向かい、胃カメラを飲むことになりました。
咽の奥に麻酔薬を塗って咽の通りを良くし、さらに筋肉を緩和させるための麻酔を注射されたところまでは記憶にあるのですが、次の瞬間に意識を失い、気付くとベットに寝ておりました。
そんなわけで胃カメラを飲んだ記憶というものは一切無いのですが、ぼくの胃の中の写真はしっかりと撮影されておりまして、暴飲暴食による胃炎であるから心配しなくても良い、という結果でした。ほっと一安心。
しかし、軽い麻酔を打たれた程度で、あっという間に意識を失ってしまうぼくは、愛する女性を守るにはあまりにも柔なのではないかと、ちょっぴり悲しくなりました。
高橋源一郎氏の『日本文学盛衰史』は、明治の日本文学界と現代を、文字通り時空を越えて交差させながら描いた、明治文学好きにはたまらない作品です(逆に言うと、明治文学が好きでない人にはこれは面白いのかしら?と疑問に思ってしまいます)。
その中で、高橋源一郎本人が胃潰瘍を患って原宿の病院に入院した経緯を、夏目漱石の「修禅寺の大患」にならって「原宿の大患」と言うタイトルで、とても素晴らしいオマージュとして高橋氏本人の胃カメラの写真付きで書かれた章があります。
夏目漱石さんも、高橋源一郎さんも、ぼくにとってはとても尊敬する作家でありますし、せっかくぼくも胃カメラで初撮影をしたのですから、ぜひとも拙胃も観てやって下さい。二人とは異なり、ぼくのは単なる胃炎ですが。

ところで、『日本文学盛衰史』に関しては、ご存知の方もいると思いますが、批評空間のWebCritiqueでちょびっと論争になった、というかなりかけました。きっかけは高橋源一郎さんが書いた、スガ秀実さんの『『帝国』の文学』の書評なのですが、全体を通して非難されているのは、『日本文学盛衰史』とそれに対する高橋源一郎さんの態度です。ぼくは『『帝国』の文学』を読んでいないので、どちらが正しいと思うかを明言することはできませんが、明治文学をより深く楽しく読むには、『『帝国』の文学』は読んでおいたほうがよさそうです。今度図書館で借りてこよう。

「超長期天気予報によれば我が一億年後の誕生日 曇り」明治四十二年四月二十七日の石川啄木のローマ字日記『日本文学盛衰史』より
外出先でパソコンが使えたら便利だろうなと思い、ThinkPad535という古いノートパソコンを12000円で購入しました。Pentium150Mhzのメモリが40Mという代物です。
辞書系のアプリケーションをインストールするために、ハードディスクを6.4G(それ以上だと認識しない場合があるらしい)に増設、さらにバッテリーのセルを新しいものに交換して、三時間ほどは持つようにしました。これでどうにか使い物になります。
このパソコンは、『電脳売文党宣言』という座談会本で、ジョイスの翻訳で有名な柳瀬尚紀さんが使用していたのと同じものでして、この本が出版された1997年の当時は、結構なスペックの軽量ノートパソコンだったはずなのですが、5年経った現在では見る影もありません。それでも、柳瀬さんがこのパソコンを使っていろいろな翻訳や編集をしていたいということを考えれば、十分に使えるパソコンのはずなのです。と自分に言い聞かせているのです。軽いしね。
この『電脳売文党宣言』は、コンピュータと本の関係を、書き手の側から語った座談会を収録したものです。読み手の側から、つまりコンピュータで読書をすることに関しては『本とコンピュータ』などでも昔から取り上げていますが、書き手の側からこの問題を取り上げた書籍は、これ以外にはないのではないでしょうか?ぼくが知らないだけかもしれませんが。
座談会に出席しているのは、島田雅彦をホストとして、笠井潔、井上夢人、柳瀬尚紀、加藤弘一といった錚々たる皆さんで、扱うテーマも再販制の問題から文字コードの問題まで、あっちへ飛びこっちへ飛びしながらかなり広い範囲で語られています。加藤弘一さんはUnicodeを利用することによって消えていく漢字に関して警鐘を鳴らしているし、柳瀬尚紀さんは内容の無いサイトはウィルスを使ってでも削除したほうが良いと冗談を言っているし、笠井潔さんはCD-ROMを利用することによって書籍の「原則絶版なし」を主張しているし、島田雅彦さんはバカみたいに自分が手書きであることを強調していたりします。今読むと少し古い話題もありますが、大半が現在でも問題のまま残っていることばかりです。
先日テレビを観ていたところ、某文化人が「本が無くなる無くなると言われているけれど、コンピュータの解説書が爆発的に売れているおかげで発行部数が増えている。だから本は無くならない」などと非常に短絡的なことを言っていましたが、本はコンピュータに取って変わられるのか?という問題に関しては、世界中でいろいろと議論されておりますし、個人的にはいきなり本が無くなってしまうなんてことはあり得ないので、もし入れ替わるとしても50年から100年ぐらいは必要なのではないか、と思っております。コンピュータはハード的にはどんどん進化していますが、ソフトウェアの面では無駄な機能をつけてCPUのパワーを浪費しているだけで、全然進化していないし。

それにしても、まだまだ使えるノートパソコンが12000円で買えるのですから、良い時代になったものです。