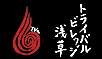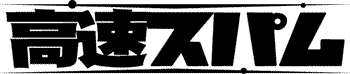一度は作る気万々だった鉄割本も、そんなものは必要ないという陰の声を聞いたせいですっかりやる気を失ってしまい、だったらもう何もしねーよと半分きれているのですが、それでも本屋なんかに行って手ごろな雑誌なんかを手にすると、これぐらいの本を作ったらいくらぐらいかかるかしらとついつい考えてしまいます。そんな折、ぼくの中で構想していた鉄割本に一番近い構成の雑誌を発見しました。雑誌の名前は『超世代文芸クォリティマガジン[エンタクシー]』。創刊第一号らしく、柳美里、福田和也、坪内祐三、リリー・フランキー責任編集ですって。この癖の強い四人の方々に関しては、人それぞれ好みがあるとは思いますが、内容は読みごたえたっぷり、500円という値段もお手ごろです。最近の雑誌ってすぐに800円とかするじゃないですか、それを考えるとこの値段でこの内容というのは、お得ではないかと思ったり。
そんで読み進めていくと、坪内祐三氏が安原顯氏について書いているエッセイがありました。前にもちょいと書きましたけれど、先程亡くなられた安原氏と坪内氏は、以前にちょっとしたもめごとを起こしておりまして、安原氏が亡くなられた時に坪内氏の反応なんかが野次馬的に気になったりしていたのですが、さすがは坪内さん、死んだからと言って容赦しません、びしばしと安原さんのことを批判しております。「私は死をもってその人を赦すことをしない」「私は氏から『愛の鞭』も『励まし』も受けなかった。私が受けたのは(中略)嫉妬による言いがかりである」「安原氏が他人をいきなり罵倒するのは、自分の駒だと思っていたはずの筆者が、その思い通りに動かなくなった時だ」などなど。うわー、まじぎれだよ!こえー!こえーよ!死んだのだから赦してやればいいじゃん、というのは意志の弱いぼくの意見に過ぎず、このような対象(人、作品)に対する真摯な態度があるからこそ、坪内祐三氏の評論は力強く、読む人に響くのでありましょう。ぼく、多分、坪内祐三氏の著書って全部読んでるよ、ファンですから。あ、最近出た『雑読系』はまだ読んでないか。

でも、もし安原氏ともめごとがなかったら、ここまで氏を非難したかな、とも思います。結局は、けんかを売られたから氏の性格や行為を非難しているのではないかしら、などと。
代官山に良い感じの本屋さんがオープンしました。サイトも良い感じ。
主にインテリアやデザイン関係の洋書を扱っているそうです。まだお店には行っていないのでなんとも言えませんが、サイトを見る限り、お店に置く本をとても丁寧に選んでいるように感じます。大型書店と比べて、このような小規模(失礼!)の本屋さんはこだわりが出ていれば出ているほど良いですね。
サイトから書籍を購入することもできるそうですが、全体的に値段が少し高めかも。ちょいと眺めただけでも、Amazon.co.jpで4000円ちょいで買える「Babylon Babies」が8800円、Amazon.co.jpで9000円弱で買えるハーバード・リストの写真集は14800円。うーん。
別にこのお店がぼったくっているわけではなくて、日本で洋書を買おうとするとどうしてもこれぐらいの値段になってしまうみたいで、以前にAmazonで3000円弱で購入したAdrian Tomineの『Summer Blonde』は、ジュンク堂で倍以上の値段がついていたし、同じくAmazonで2000円ちょいで買ったDaniel Clowesの『Like a velvet glove cast in iron』も、5000円近い値段で売っているのを見たことがあります。コミックに五千円はねえ、きついよねえ。あれって何なのでしょう、手数料?ネットが普及していなかった一昔前ならいざ知らず、誰でもオンラインのブックショップで自由に洋書を購入することができる現在では、やたらと高い値段をつけると誰も買わないと思うのですけど。
でもhacknetは素敵なので、皆さん行って本を買ってください。つぶれたら悲しいでしょう。ぼくも今度の日曜日にでも行ってみようと思います。何も買わないけど。

そういえば、何年か前に倉俣史朗氏が好きで編集者になったという素敵な女性と一度だけ飲んだことがあるのですが、あの方はいまいずこへ。
最近気がついてびっくりしたことがいくつかありまして、ひとつは人生が思ったよりも長いということで、もう随分と生きてきたような気がするのですが、人生八十年の点から見れば、おそらくまだ人生の半分も生きていないわけでして、そう考えると焦眉の急と思っていた所用の類も、それほど焦る必要もなく、ゆっくりと頑張ればよいのですなと安心の気付き。
もうひとつは、随分と長いことデートをしていないということで、これは相当切実な事態であります。ぼくは接する人々の精を吸収させて頂くことにより日々を生きているので、たまには女性と一緒に遊園地行ったりお寺巡りとかしないと、心身ともに老け込んでしまいます。野郎どもは臭いし、汚いし、うんことかするでしょ、だから嫌い。デートをするならやはり女性がよろしい。これは焦りの気づき。
最後は、プレステ2はテレビがないとなんの役にも立たないということで、今年に入ってからのこの三ヶ月、ほとんど何の思い出もないのはプレステ2のせいではないだろうかなどといつものごとく自らの非を他へ転嫁して安心し、ならばテレビもないことだし売り払ってしまおうと思い立ち様、近所のファミコンショップへ持ち込んだところ、20000円で売れました。24800円で購入して、ビックポイントも2480円ついたので、2000円ちょいで三ヶ月間遊びまくったことになります。お得!そんでその金をもとに、テレビとDVDプレイヤーを買いました。
もっと気づかなくてはいけないことが他にあるような気もしますが、気づかないほうが幸せなことも。あったりなかったり。
今週末から映画『ぼくんち』が公開になりますね。
西原理恵子ファンとしては期待半分不安半分の気持ちでして、予告編は何度も観ているのですが、果たしてどんな感じなんでしょうねえ。映画と原作は、異なる作品として考えなさいとはよく言われることでありますが、どんなに頑張っても鉄割の人を役者としては評価できないように、原作と映画をわけて考えるのって、けっこう難しいのよねえ。
ぼくの一番すきなお話は、第三巻第二十二話。ねえちゃんが二太に、死んだはずのおばあちゃんがやってきたと言います。おばあちゃんがやってきたので、うどんを作ってあげたら、どこかへ行ってしまったと言います。二太は、ねえちゃんが大好きなので、そのうそっぽい話につきあいます。その後、裏庭に草むしりに行ったねえちゃんのところに、再びおばあちゃんが現れます。
「おばあちゃん、おうどん何で食べてってくれへんのよ。せっかく作ったのに、もう。」
「おばあちゃん死んでるもん。うどん食われへん。」
「あははは。そうゆうたらそうやなあ。」
ねえちゃんとおばあちゃんは、一緒に草むしりをします。
「なあ、おばあちゃん。人は生きててな、どこまでがしんどくて、どこまでがしあわせなんやろか。」
「そらカンタンや。食わせてもろてるうちがシアワセで、くわせなならんなったらしんどい。
そのうちええ天気で空が高うて、
風がように通る、
死ぬのにちょうどええ日がくる。それまでしんどい。」
ねえちゃんは草むらにねっころがります。そんなねえちゃんを見て、二太は思います。
「『今ばあちゃんが空にのぼっていった』
ねえちゃんがまたウソをつく。
草むらにねっころがったねえちゃんは、ぼくが昔読んだ絵本のおやゆび姫みたいにちいさく見えた。」
何度読んでも、涙があふれてとまりましぇん。うぐぐ。西原さんの漫画は全部好きだけど、やっぱり『ぼくんち』は特別です。
『ぼくんち』に出てくる家族は、みんなろくでなしばかりです。けれども、先に生まれた者は、後に生まれてきた者たちを、必死で育てようとします。ねえちゃんは一太と二太を育てようとするし、一太は二太を育てようとするし、こういちくんは二太を育てようとするし、こういちくんのねえちゃんはこういちくんを育てようとします。先に生まれたものは、後に生まれた者に、シアワセになるための生き方を教えようとします。たとえその生き方が、結果的にシアワセになれない生き方だとしても。

最近よく考えるのですが、そこそこの年齢になってしまったぼくは、後から生まれてきた彼ら彼女らに、一体なにを教えてあげることができるのだろう。教えてもらうことはたくさんあるけど、「何かを」教えてあげることなんて出来るのかしらね、ぼく。
"The world of the quark has everything to do with a jaguar circling in the night."
(闇夜を彷徨うジャガーのすべてに、クォークの世界が存在する)--"The Leaves of a Dream Are the Leaves of an Onion,"
by Arthur Sze, from River, River
物理学などに造詣の深い方はご存知かもしれませんが、マレイ・ゲルマンという方は、原子核を構成する最小の粒子であるクォークの発見者であり、ノーベル物理学賞の受賞者でもあります。彼は、友人である中国系アメリカ人の詩人、アーサー・シー氏の書いた詩に触発されてこの本を書きました。驚くべきことに、この本が氏の初めての著作になります。
物理学者による複雑系を扱った本というと、難解な印象を与えるかもしれませんが、この本は難解である以上に刺激的かつ文学的(複雑系そのものが文学だしね)であり、ある一定の知的好奇心さえ持っていれば、読み通すことは簡単ではありませんが不可能ではないと思います。もちろん、量子力学や数学的知識が必要な場所も多々ありますが、ゲルマンも言っているとおり、そんなところは読み飛ばせば良いのです。ぼくも読み始めたところなので、偉そうなことは言えませんが。
マレイ・ゲルマン氏は著書の中で、物理学はもちろんのこと、その他あらゆる知識を駆使し、「単純なもの」と「複雑なもの」の関係について考えていきます。彼は、本書を書くに至った動機的な疑問を、以下のように書いています。
クォークはすべての物質を作っている基本的構成要素である。私たちが目にするあらゆるものは、クォークと電子で構成されている。古来、力と獰猛さのシンボルであるジャガーでさえ、クォークと電子の固まりである。しかし、何という固まりであろうか!それは、何十億年という生物の進化の果てにたどりついた、途方もない複雑さを表している。しかし、ここでいう複雑さとはいったい何を意味しており、それはどこから生じたのだろうか?
暗闇のジャングルを徘徊するジャガー。そのジャガーのあらゆる運動に、クォークの世界が存在している。そこに彼は感動したのです。マレイ・ゲルマン氏がインスパイアされたアーサー・シー氏の詩の原文は、一番最初にも引用していますが、訳書には以下のように訳されています。「クォークの世界は、夜に徘徊するジャガーと、あらゆる点でかかわりをもっている」。これ、あまり良い訳とは思えないので、上の引用はぼくが訳してみました。ぼくの訳の方がかっこいいし、正確やイメージを伝えませんか。調子に乗りすぎかしら。
一時期あほのように見かけた「複雑系」という言葉も、最近ではめっきり見かけなくなりました。いまだ進化を続け、日々おもしろくなっている複雑系という分野が、一時のブームで終わってしまうのは極めて寂しいことだと思います。複雑系については後ほどもっともっと書きたいと思っていますが、今はとにかく、『クォークとジャガー』を熟読し、理解を深めましょう。コーヒーなんかを飲みながら。

ちなみに、ゲルマンさんは二年ほど前にお亡くなりになっているそうです。
遅ればせながら『ボーリング・フォー・コロンバイン』を観ました。
鉄割の台本を書いているお方などは、あまり面白くなかった(というか『ロジャー&ミー』の方が面白かった)と言っておりましたが、なかなかどうして面白かったし考えされる映画でした。観る前は、アメリカにおける銃規制の問題がテーマの映画だと思っていたのですが、監督であるマイケル・ムーア氏がこの映画で考えようとしていたことは、「銃規制」の問題よりもむしろ、アメリカの白人(WASPと限定しても良いと思います)が恐れている恐怖とはいったい何なのか、アメリカの白人は、恐怖によって先住民族を迫害し、恐怖によって奴隷制を始め、恐怖によって他国を攻撃し続けてきた、その恐怖の原因は一体何なのか、何をそれほどまでに恐れているのか?ということだったように思います。
ムーア氏は、アメリカで銃犯罪、あるいは殺人事件が頻発していることについて、アメリカが「歴史的に暴力を行使してきたから」とか「異なる民族が共存しているから」とか「銃の所持が認められているから」とかいう紋切り型の言い訳を一切受け入れません。それはあくまでも言い訳であって、理由ではない。イギリスやドイツはアメリカと同様に暴力的な歴史を持つ(そもそも、暴力的な歴史を持たない国なんて存在しない)し、カナダでも銃の所持は認められているし異民族は住んでいる。けれどもどうしてアメリカだけがここまで銃犯罪が多いのか?アメリカのコロンバイン高校の事件で被害者となった少年の父親が映画の中で言っていたセリフを引用すれば、「この国は、なにかがおかしい」。ムーア氏は、スクリーンの中で何度も問いかけます。なぜ?どうして?どうしてアメリカだけが?
結局、映画の中でその答えの結論は出ません。観終えた観客は、ムーア氏が提示したさまざまな事件や人々へのインタビューをもとに、自分なりに答えを考えることになります。けれども、ムーア氏は、本当に何も答えを持っていないかなあ。もしムーア氏が、「アメリカ人は一体何を恐れているのか?」という疑問の答えを持たないとしたら、あのアカデミー賞授賞式でのスピーチは一体何だったのだろう。
それで劇場で『アホでマヌケなアメリカ白人』というマイケル・ムーア氏の著書を買って、カフェでばばばっと読んだのですが、家に帰って長島さんのサイトをみたらちょうどその本の紹介が出ておりました。この本を読みながらぼくが一番思ったのは、こんなでぶが近くにいたらうぜーよなーということだったので、長島さんの文章を読んでいたらそんな自分がちょっぴり恥ずかしくなったよ。えへへ。
正直、日本に住んでいてアメリカには旅行ぐらいでしか行ったことのない僕には、アメリカの現状というものを、ニュースやWeb、雑誌や書籍等のメディアを通してしか知ることができません。そう考えると『アホで・・』も、そのような情報源のひとつということになるので、その内容を丸々鵜呑みにすることは危険かもしれませんが、それでも自分大好きアメリカ人の中からこのような本をかく人物が現れて、しかもそれがベストセラーになっているというのは驚きだし、ここまで過激に書かれた本に対して反論本が出ていないということも考えるべきことかもしれません。ブッシュさんとかはこの本に対してなにかコメントしているのかしら。気になるう。
ちなみに、『ボーリング・・』に関しては、映画の中の捏造について言及しているこんなサイトもあります。ご参考までに。「コロンバイン校の殺人者の二人はあの日ボーリングしてなかった」って、おいおいマジですか。
あ、そういえば、今月の青山南氏の『ロスト・オン・ザ・ネット』では、『ブッシュ一族の奇々怪々』と題してマイケル・ムーア氏のことも取り上げています。とても面白かったので、ぜひ読んでみてください。
とにかく今、ぼくの中でアメリカという国はとても気になる存在です。とんでもなくアメリカに行きたい。っていうか住みたい。今の世界に生きていてアメリカが気にならない人なんていないと思いますが、ぼくはアメリカの現状よりも、アメリカの歴史の方が気になる。そして、アメリカにはヴォルマンとか、エリクソンとか、ピンチョン(読んだことないけど)とか、アメリカの歴史を文学で再構築して素晴らしい作品を書いている作家がたくさんいるのに、日本にはそのような作家がひとりもいないことが気になる。

鉄割の勉蔵君は現在、オリジン弁当の真実を暴くというドキュメンタリー『オリジン』を撮影中です。ムーア氏以上に辛辣な質問をオリジンの幹部たちに対して行っているそうで、はやく完成しないかしら。とても楽しみ。
いつもお世話になっているAmazon.co.jpでこのような特集が。
外国文学って、翻訳によって本当に面白さが変わりますからね。自分が好きな小説家の作品が、つまらない翻訳をされていたりすると本当にむかつきます。心の底から安心できる翻訳家さんはそれほど多くありませんが、その中のひとりである柴田元幸さんによる翻訳を紹介する特集です。今更言うまでもないけど、柴田さんは翻訳が良いだけでなく、訳する本のチョイスも良いのよね。
でね、この特集の趣旨は確かに「柴田元幸さんによる翻訳の素晴らしさを紹介する」ことなんですけど、その称賛が笑ってしまうくらいの激賛で、ほとんど誉め殺しみたいになっております。はは。
ところで、『ライ麦畑でつかまえて』が、村上春樹氏による新訳で『キャッチャー・イン・ザ・ライ』として出版されましたね。楽しみ。過去に翻訳された他の作品も、どんどん新しい訳で出版して欲しいなあ。ケルアックの『路上』とか、ヘンリー・ミラーとか。そう思っているのって、ぼくだけではないと思うのですけど。

ちらしの打ち合わせで新宿へ。
集まった面子は鉄割の演出家さんと脚本家さんで、この三人で飲んだのって、ぼくの記憶にある限りでは、鉄割が始まった次の年の一月一日と、数年前に一度(その時もちらしの打ち合わせ)と、今回の三回だけだと思います。二人とも大学の先輩で、付き合いは長いのにね。
沖縄料理屋に入って、チラシに使う絵を演出家さんに書いてもらってそれをぼくがそのまま持って帰ってチラシをつくるということになっていたのですけど、演出家さんがこんなところじゃ書けねえよと言い出したので、それでは後日郵送してくださいということになり、じゃあ集まった意味ないじゃんという思いを胸に秘めたままただの飲み会となってしまいました。
そんで酔っぱらって何を話したのかさっぱり覚えていないのですけど、本を読んで走って、本を読んで、走るのです、というようなことを話したように思います。家に帰って寝ようとしたら、ふとんが湿っていてとてもいやな気持ちになったので、小一時間ほど走ってシャワーを浴びて、チェーホフの短編を一編だけ読んだら少しだけ楽しくなったので、今だとばかりふとんに入っておやすみなさい。
ふと思ったのですが、アメリカは、人々の命を犠牲にして体を張ったギャグをかましているんじゃないのかしら。芸人魂で。そう考えるとほら、フセイン像に星条旗かぶた時のブーイングも、すぐにイラクの国旗に取り換えられたのも、完全なぼけとつっこみだし。
最近『たかがバロウズ本』を出版された山形浩生さんによるこんな記事が。
短い記事なのですが、とても興味深いことがたくさん書かれています。独裁政権を倒して自由な民主国家を作るという能書きのもと、アメリカに爆弾を落とされたアフガニスタン。「復興と民主主義確立まで面倒を見る」と言っていたアメリカは、その後アフガニスタンに対してどのような支援を行っているのでしょう。
ニューヨーク・タイムズのクルーグマン連載によれば、アメリカ政府の04年予算案で、アフガニスタン復興予算はなんとゼロ。あとから議会の方があわてて3億ドルほど追加したほどだそうな。
ね、ギャグでしょう。
これを書いているのは17日なのですが、今、タイでは水掛け祭りで三百人を超す死者が出ているそうです。去年は五百人以上死んでいるので、まだまだ増えるでしょう。さすがタイ。こういうことを書くとまた怒られるかもしれませんが、ギャグみたいな戦争で死ぬぐらいなら、水掛け祭りで死にたいよ、ぼく。
なのでこんなサイトをみて癒されよう。

次の標的はどこになることやら。
夕方、バスを降りるときに吹かれた風に、かすかな夏の匂いをみつけました。まだ四月だというのに、夏はすぐそこまできているようです。
清少納言は『枕草子』の中で、春はあけぼの、夏は夜、秋は夕暮れ、冬はつとめて(早朝)が素敵だと書いています。ぼくは、春は昼間、夏は夕暮れ、秋は早朝、冬は夜が一番好きです。特に夏の夕暮れは子供のころから大好きで、日が長くなって夕暮れが青く清涼とし始めると、心が嬉しくなります。
ぼくのよく行く古本屋さんは、営業時間が午前中から日が沈むまでとちょーいいかげんなので、日が沈むのが早い冬などは、一日の仕事を終えてから行くと閉まっていることが多いのですが、最近は空気が暖かくなるにつれ、日が沈むのが遅くなったおかげで、営業時間が長くなり、帰りに寄ってもまだ開いております。開いていれば毎日寄ってしまうのがぼくですから、春から秋にかけては読みもしない本がどんどんと増えてしまうのですが、先日その古本屋さんで購入した藤枝静男氏の小説は、ぼくの心を完全に捉えてしまったわけです。
今、ぼくの前にその藤枝静男氏の小説が二冊あります。一冊は『田紳有楽;空気頭』、もう一冊は『悲しいだけ;欣求浄土』。この小説について語るには、まだ十分な精読ができておりませんので、もうしばらく時間をいただきたいと思いますが、なんと申されても藤枝静男さん、生涯のつきあいになることはまちがいありませんから、今後ともよろしく。もう死んでるけど。
私は池の底に住む一個の志野筒形グイ呑みである。高さ約五センチ、美濃の千山という陶工の作で、三年半ばかりまえに私の主人が仕事で多治見へ行ったとき裸のままもらってポケットに入れてきた品である。『田紳有楽』より
島田雅彦さんを好きになれないのと全く同じ理由で好きになれない中沢新一さんのインタビュー。けれどもこの方の著作、どうしても気になってしまってついつい読んでしまいます。そんで理解できなくてまた嫌いになります。『カイエ・ソバージュ』シリーズもね、今のところ全部読んでるし。このシリーズは、大学の講義だけあってそれほど難しくないのですけど。
対談とかでも、中沢さんしゃべりすぎ。もう少し相手の話も聞きたいので、少し黙ってください。
うー、ようやく次の公演のちらし作りが終わったよ。今回のちらし、ごっちゃんごっちゃんぐちゃぐちゃしていて、なかなか素敵なのではないでしょうか。これから印刷にかけるので、完成はまだ先ですけど。あれ?公演まであと一ヶ月ないじゃん。
ちらしを作る前に聞いたコンセプトは、チェ・ゲバラの『チェ・ゲバラ モーターサイクル南米旅行日記』とギャートルズで、全体的に新太陸みたいな感じにしてくれと言われたのですが、新太陸みたいなちらしってわけわかんねーとか思って、いざとなったら戌井さんのケツの穴に割りばしぶっさして殺して逃げてやれと画策しておりましたが、でき上がってみたらすっかり新大陸になっていて一安心。ぐっちゃんぐっちゃんだけど。

ところで、自宅で使用している我が愛しのMacintoshは、四年ほど前のG3の350Mhzでして、いい加減もうやばいです。遅いし、OSXとか試すのも怖いし。三十万ぐらいのG4でも買っちまおうかとも思うのですが、また借金するのはいやなので躊躇しております。これだけ頑張っているのだから、鉄割の経費で買ってもらおうかとも思ったのですけど、公演ごとにメンバーから三千円ずつもらってどうにか公演を行っている集団に、三十万くれとはさすがに言いづらくて。
だれか安く売ってください、G4。
久しぶりにお会いしたお友達が、舞城王太郎氏の作品を全部読んでいるということを聞いてびっくり。初めてです、ぼくのまわりで舞城氏の作品を読んでいるという人。
お話をしていてぼくが一番聞きたかったのは、『熊の場所』に収録された『ピコーン』のことで、あのフェラチオの描写は素晴らしいよねー、と言いたかったのですけど、下手なことをいうとセクハラになってしまうのかしらと危惧して聞くことが出来ませんでした。言いたいこともまともに言えない、世知辛い世の中です。
それでその方とお話をしてたら、今読んでいる本の話になって、ぼくが舞城王太郎氏の最新作『九十九十九』を出したところ、その方は池谷裕二氏と糸井重里氏の『海馬』という本を教えてくれました。この池谷裕二というお方、どこかで聞いたことがある名前だと思っていたのですが、先日紀伊国屋で本を購入したときに、レジの横にこの方の著書が並べてあったのがこの方の別の著書でした。『海馬』の中身をちょこっと見せてもらったところ、なかなか面白そうな内容で、記憶力が人百倍悪いぼくには興味深いことがたくさん書かれていました。
早速次の日に本屋に行って『海馬』と同じ池谷氏の著書である『記憶力を強くする』の二冊を購入して読んでみたのですけど、うーん、なんか、生きる希望が湧いてきます。最初はよくあるHow-To本かと思っていたのですがそんなことは全然なくて(HowToなんて全然書かれてないし)、脳というものは使えば使うほど鍛えられるものであり、年齢を重ねるごとに記憶力が悪くなるというのは、努力を怠っている人の言い訳に過ぎないとかいうことが科学的に書かれていて、脳という構造に興味はあるけど知識は全然ないぼくのような人間には、なかなか勉強になる本でした。ごめんなさい、まだ半分ぐらいしか読み終えていないので、あまり具体的なことは書けないのです。とにかく、脳は三十才を越えてからがいい感じらしいよ。
この本を読んで初めて知ったのですが、「海馬」という大脳皮質は、記憶を貯蔵する場所ではなく、すべき記憶を取捨選択する場所なのだそうです。記憶は、一ヶ月ほどは海馬に留まりはするものの、その後は「側頭葉」に移動して貯蔵されるということです。ふへー、そうなんだ。てっきり、記憶はすべて海馬に貯蔵されているのだと思っていました。
また、海馬を失った場合、エピソード記憶(個人の思い出など、出来事に関する記憶)に影響が出るけれど、手続き記憶(身体で覚える記憶)には影響しないとのことです。海馬を失ったある被験者に、鏡を見ながら文字や図形を書いてもらうテストを行ったところ、テストを行ったという記憶は失われるものの、文字や図形を書く技術は日々上がっていったというのです。「身体で覚える」記憶は、海馬を失っても正常に貯蓄されているのです。はー、すげー。
とくに興味深かったのは、「海馬」と「感情」の関係で、これは個人的なことなのですが、何か出来事があったり、あるいは何かを思い出したりして、悲しくなったり嬉しくなったりしたあとに、その感情の原因である出来事や思い出が何であったのかを忘れてしまい、感情だけが残る場合があります。あれ、なんでぼく今嬉しいの?とか、なんで悲しいんだっけ?とか。でも感情だけは残っているから、妙にやきもきするの。おかしいでしょう。この話を人にすると、大抵おかしいと思われます。これに関連することが『海馬』の中に書かれていて、それによると、「感情」は「扁桃体」という皮質から生まれ、海馬はその「感情」の記憶とは関係がないらしいのです。ようするに、「エピソード記憶」と「感情」は別々に処理されているわけですね。そう考えると、何で嬉しいのかとか、なんで悲しいのかとか、その原因を忘れることがあっておかしくないわけです。まあそれでも、現在進行の感情に関する記憶を忘れてしまうというのは、ぼくはそうとう馬鹿ということになるのでしょうけど。えへへ。
数年前にテレビで、病気で海馬を失った人を観たことがあります。(『記憶力を強くする』で少しだけ触れているRBという人がもしかしたらそうなのかもしれません)その人は熱病から回復した後に、海馬の神経細胞がすべて死んでしまい、それ以来記憶するということが出来なくなっていました。朝食を食べたかどうか忘れてしまうために、朝食を食べたらメモをする。昼食を食べたかどうか忘れてしまうために、昼食を食べたらメモをする。とにかくすべてを忘れてしまうために、片っ端からメモをする。そして、メモをしたことを忘れてしまうからまたメモをするという具合で、側頭葉に貯蓄されるべき記憶を取捨選択する海馬を失ったその人は、一切の記憶をすることが出来なくなり、インタビュー中に、自分がなにをしているのか忘れてしまうこともしばしばありました。記憶を貯蔵している側頭葉はダメージを受けていないので、ある期間以前の記憶はすべて残っているのに、海馬を失った以降の記憶は一切ないのです。
脳に関するそのような症例は、たとえばオリヴァー・サックスの『妻を帽子と間違えた男』などで詳しく読むことが出来ます。「妻の頭を帽子とまちがえてかぶろうとする男。日々青春のただなかに生きる90歳のおばあさん。記憶が25年まえにぴたりと止まった船乗り。頭がオルゴールになった女性」など、いろいろな脳障害の症例が紹介されています。
記憶というのは、個人のアイデンティティと強く関わってくると思います。映画『アイリス』を観たときにも感じたのですが、たとえばアルツハイマーで自分の記憶をすべて失ったとき、その人は、その人でいることができるのか。もしその人が記憶に関係なくその人であるとしたら、アイデンティティとは一体なんなのか。以前の雑記でも同じようなことを書いていますが、このことは脳死や臓器移植の問題にも深く関わってくるので、ここで短絡的なことを書くことは控えますが、今後も深く考えていきたいと思います。
去年ぐらいから考えていることがあって、脳という構造、とりわけそこから生まれる「記憶」というもののことを考えるとき、記憶と歴史の関係というか、どうして動物には歴史がないのかとか、どうして人間は伝達された記録を記憶として認識し、歴史として記述できるのかとか、記憶と物語のこととか、物語と現実のこととか、延いては言えば記憶と歴史と物語の関連性とか、動物にとっての言語とか世界とか、動物が木を見るときのこととか、まとめて動物についてとか、そのようなことに興味があります。どうしてそんなことに興味を持ったのかといえば、『脳』の大家である養老猛司さんの『身体の文学史』を読んだからなのですが、本日の雑記はずいぶんと長くなったので、この件に関してはまた後ほど。
それにしてもこのような脳に関する本を読むたびに感じるのは、たとえばぼくが今、脳の専門家に頭をぱかっと開けられて、ちょちょいといじくり回されたら、それだけで感情も記憶もこの世界も、すべてあっという間に消滅してしまうのかという恐怖心(殺されるよりもそちらのほうが怖い)と、結局のところ脳が生み出す世界以上を感じることは絶対にできないという複雑な感情で、とか書くと観念論的にものごとを考えているように思われるかもしれませんが、そんなことは全然なくて、とりあえず自分の中でも考えがまとまっていないのでこちらも後ほど。
日本では多くの場合、文学は精神の面から語られてきました。退屈な学校の国語の勉強でも「この時のKの気持ちを説明せよ」などといううんこみたいな問題がたくさんでてきたでしょう。脳医学の権威が書いた文芸批評というだけでも異色なのに、この本がそれ以上に面白いのは、そのような日本文学の「精神性」ではなく、これまであまり論じられることのなかった「身体性」という観点から近代の文学を論じているところで、養老さんはその前書きで「文学のなかで身体がどう扱われてきたか、それを解析するつもりである」と書いています。
たとえば、森鴎外の『ヰタ・セクスアリス』に身体は存在していません。夏目漱石は『こころ』は書いていても『からだ』は書いていません。それは一体どうしてなのでしょうか?意識的なものとして、初めて身体の役割を文学に登場させる芥川龍之介は、『鼻』『好色』で身体に主人公を引きまわさせ、『羅生門』においては、死者の毛を抜く老婆に対して、現代人としての感情を下人に抱かせています。そんな芥川の作品を、田山花袋はまったく理解できませんでした。自然主義の田山花袋が、芥川の作品の面白さをまったく理解できなかったのは、一体どうしてなのでしょうか。
養老さんは書きます。「見なしとしての身体は、この国ではほとんど常識と化している。江戸以降の世界では、身体は統御されるべきものであり、それ自身としては根本的には存在しない」。
中世的世界では、人はまず身体的イメージで描かれました。しかし江戸、すなわち近世社会では、乱世を導くという理由から、身体の自然性は徹底的に排除され、人は心で描かれることになりました。さらにそこに明治維新、すなわち欧化による社会制度の変革が起こり、そこから明治以降の文学に通底する「我」の問題が生じるのです。
大正時代の作家である芥川はこの「我」の問題について、どのように取り組んでいたのでしょうか。夏目漱石は、文学は心理主義が当然であるとし、それを好みました。芥川はそのような「漱石の内政的な心理主義をさらに拡張し、身体そのものを、心理主義で規定される近代文学の領域に取り込んだ」のです。養老さんはこのことを、「中世を近世に変換したといってもいい」と書いています。ようするに芥川は、漱石たちが心理で語ったことを、身体という形式を使って語ったのです。
養老さんは、芥川が『今昔物語』の話の組立を改変していることについて、次のように書きます。
芥川はこの改変によって、「死体の髪の毛を抜く」行為は、盗みという反社会的行為を誘発する、より根源的な反倫理的行為に、いわば「昇格する」。これを私は、江戸的感情の発露と呼んだのである。臓器移植に対するなにものともつかない「おそれ」、芥川はそれを、自分すなわち下人の感情として、みごとに描き出したことになる。現在のわれわれもまた、この感情から、一歩も踏み出していない。
「現在のわれわれもまた、この感情から、一歩も踏み出していない」どころか、ぼくたちの感情は、より複雑なものになっています。科学が現代のように発達する以前は、「私」とは「神」の関係で語られるものでした。しかし科学の時代を生きるぼくたちが「私」について考えるとき、それはとても複雑なものなります。「私」とは、「身体」のことなのか。あるいは、「こころ」のことなのか。「こころ」は脳から生まれるものなのか、あるいは、「身体」から生まれるものなのか。「こころ」が「私」だとしたら、脳死は死ということになるのか。あるいは「身体」が「私」だとしたら、臓器移植の問題はどのように解決したら良いのだろう。「こころ」と「身体」を統合したものが「私」であるとした場合、そのいずれかを失った場合、あるいは分離した場合、「私」はいったいどこへ行くのだろうか?またあるいは、「私」のクローンは、「私」なのか、あるいは「あなた」なのか。
『身体の文学史』はこんな感じで、明治から昭和にかけての文学史を、身体という観点から論じていきます。うーんスリリング。
ところで、養老さんは『身体の文学史』の前書きで「歴史一般がなぜ可能なのか」という疑問を投げかけています。「シーラカンスから人に至るまでにも、すでに五億年が経過している。なぜそれが、一時間で読める『物語』になるのか」。この一文を読んだとき、どきっとしちゃいました。
養老さんはさらに続けて、「歴史」は「脳」の機能であるとして、次のように書きます。
歴史は、(・・)脳が持つことができる、時空系の処理形式の一つである。その形式を、昔から「物語」と呼ぶのであろう。だから、歴史は神話からはじまる。
先日の雑記でも書きましたが、ぼくは今、「どうして動物には歴史がないのか」という、まことに阿呆臭いことを考えておりまして、そのようなことを考えるときに「記憶」というものは非常に重要なファクターとなります。「記憶」は明らかに脳の機能のひとつであり、同様に脳の機能である「歴史」と、その形式である「物語」の関係。それがとても気になるのです。

とても気になるのよう。
この雑記でも何度か触れておりますが、鉄割の本を作ろうという計画がありまして、話ばかりはどんどんと膨らむものの、有言不実行のぼくたちでありますから、計画はなかなか先に進まず二年ほどが過ぎていたのですが、知り合いのエディターの方が編集をやってくださるということになりまして、ようやく具体的な計画を練り始めました。
本を作ると申しましても、またいつものように悪ふざけになってちんちんとかの本になってしまっては意味がありませんから、内容に関しては真剣に話し合いまして、20ページにわたる勉蔵レポートをはじめとして、コンテンツに関してはなかなか面白いものになるのではないかと思っております。詳細は秘密ですけど。
それにしても話し合いをした居酒屋さん、会計をしてみたら一人六千円はちょっと高いと思います。つぼ八気分で呑みまくったのがいけなかったようで。
『小さな中国のお針子』を観ました。
1971年の中国。医者を親に持つ二人の少年が、文化大革命の嵐に巻き込まれ、チベットとの国境境の村へと「再教育」のために送り込まれます。それまでの生活とは正反対の、屈辱的で過酷な労働を強いられ、労働階級の生活を送ることになるのですが、そこで彼らは仕立屋の孫娘である美しいお針子と出会います。彼らは、彼女を無知から救うために、当時の中国ではご法度だった外国小説(フロベール、ユーゴー、トルストイ、ディケンズ、ロマン・ロラン、デュマ、ルソー、そしてバルザックなどなど)を読み聞かせます。(もっと詳しいストーリーを知りたい方は、公式サイトをごらんください)
お話自体は普通に面白かったし、映像も美しかったし、役者さんたちもとても上手で、映画としてはなかなか良い映画だったと思うのですが、なぜか釈然としない気持ちが残るのは、何となく映画全体に漂う嘘臭さ(というと言葉が悪いですが)、例えばマーが初めてバルザックを読んで世界観が変わったシーンとかが、なぜか心に響かなかったからかももしれません。小説を読んで世界が変わるということは、小説が好きな人であれば誰もが一度は経験することだと思うし、中国の知的階級に育ったマーが、バルザックを読んで世界観を変えてしまうというのも、言葉にすると理解できるのですが、映画を観ていて思ったのは、うっそっくっせーということで、同様にラストのシーン(これは物語に関係するので詳しくは言えないのですが)にも、おいおいとつっこみを入れたくなりました。ぼくが意地悪なのかしら。
ぼくの大好きな映画評論家の川本三郎さんがパンフレットの冒頭で紹介文を書いていて、それを読むと「この映画は、リアリズムというより、どちらかといえば寓話的な作り方をしている」と書いています。そう、寓話的な物語として考えれば、この映画はとても素晴らしい映画だと思うし、ステレオタイプな「都会の若者と村の少女」像も、「進歩的な西洋文明と保守的なアジア文明」像も受け入れることが出来るのですが、ぼくはただ単に心を落ち着かせてくれる映画を観たかったわけではなくて、かと言ってカルチュラル・スタディーズ系の馬鹿学者が喜ぶような映画を観たかったわけでもなくて、文化大革命の時代と、文明から取り残された村と、禁じられた西洋文学というテーマから、もっと刺激的な映画を想像していたわけであります。少なくとも、西洋の「個人」という概念を、たやすく受け入れる田舎の少女(あ、言っちゃった)を観たかったわけではないのね。
だいたい、この映画、皆さん誤解しているかもしれませんが、フランス映画なんですよ。そこがまた、ね。
などとちょいと批判的なことを書いてしまいましたが、実は相当楽しんでしまいました。二時間あっという間で、くそつまんねーとかは全く思わなかったし、普通に面白い映画でしたよ。この手の映画が好きな方には、とてもお勧めです。
この映画を観た人の感想を聞きたい。ぼくのまわりで、誰か観た人いないかしら。
今年に入ってから旅行に行っていません。
お金がないので海外旅行は無理ですが、来月ぐらいにどっか国内旅行に行こうかしらと画策しております。どこが良いだろう。沖縄か、島根か、熊本か、とか考えているのですけど。
でも自転車も欲しいしなー。黄色くてかわいいやつ。洋服も欲しいしなー。最近、春だからかオシャレモード入ってきちゃって。でも、海外にも行きたいから貯金しないとなー。欲しい本も三百冊ぐらいたまってるしー。うーん、どうしたら良いのかわからなくなってきた。
海外だったら中国に行きたいのです、今、無性に。今はお金的にもサーズ的にも行けないけど。サーズが落ち着く頃にはお金たまってるかな。
古本屋さんのただで持ってけコーナーで、1992年7月のSWITCHを発見しました。特集『ウィリアム・バロウズ[異境にて]』。へへ。もうけ。
表紙を飾るギンズバーグとバロウズの写真、よく見るとふたりとも禅定印を結んでいて、とてもかわいい写真です。この雑誌が出版された時、お二人はもちろんご健在でしたが、ちょうどカウントダウンが始まった頃ですね。

特集は、バロウズの家にギンズバーグが遊びに行くというものなのですが、ギンズバーグ君がバロウズ君の家に入ると、さすがスーパーじじいです、ちょうどインディアンのシャーマンを呼んで、変な儀式やっているところでした。次の日に、その儀式のことなどを足掛りとして、ギンズバーグ君がバロウズ君をインタビューするのですが、その内容は儀式のことから映画『裸のランチ』のこと、最近読んでいる本のこととか、影響を受けた作家と作品、などに様々に言及していて、とても面白かったです。
ギンズバーグ「うーん・・・ウィルスっていったい何だ?」
バロウズ「うん、先ず第一に、特定の環境だけで生存できる細胞の寄生菌だ。」
ギンズバーグ「細胞の中に入っていく寄生菌。それじゃ、どういう風に、ウィルスという言葉を君は使っているの?」
バロウズ「ウイルスは、自ら自らを複写する。だが、文字通り、『言葉のための言葉』を複写するのみだ。ウイルスが複写するのは、ウイルス自体のイメージ、すなわち『言葉のための言葉』を複写するんだ。」
その特集とは別に、ノーマン・メイラーの短中編『売春婦の亡霊についての聖話』が掲載されていて、今まで彼の作品は一冊も読んだことがなかったのですが、この短編はとても面白かった。先日Salon.comにノーマン・メイラーの新作が紹介されていていて、新作と言っても過去の作品や批評、エッセイなどを未発表のものも含めて集成したものなのですが、この記事を読んでちょうど彼のことが気になっていたところで、バロウズもギンズバーグとの会話の中で、ノーマン・メイラーの作品を褒めていたことだし、良い機会なので彼の作品をまとめて読んでみようと思います。今の時代だからこそ『なぜぼくらはヴェトナムへ行くのか?』などを読んでみよう。
他にもティモシー・リアリーやポール・ボウルズに関する文章とか、ロバート・クーヴァーの『女中の臀』の書評とか、なんだか時代を感じさせる内容が盛りだくさんで、池澤夏樹さんがヴォネガットとバースとピンチョンのことを書いているエッセイなども掲載されていて、八十年代のアメリカ文学ブームの最後の晩餐を目撃したような気持ちになりました。今ではなかなかないですよね、こんな特集。
そんな感じで、ただでもらった本なのに相当楽しませていただいたのですが、その中で一番びびったのが田口賢司さんという方で、どうも小説家らしいのですが、この方の書いた文章がすごすぎて、ここ数年に読んだ文章の中でも相当衝撃を受けました。
自分にとってもっともチャーミングなたたずまいをさがしながら、ぼくはワード・プロセッサーのキーボードをたたく。文学とか、小説とか、そういった「ライティング」へのアプローチはそうやってはじまり、いまも続いている。ほかにたいそうな目的はない。たったそれだけ。うまくいっているような気もする。ぜんぜんだめ、っていうかんじもある。
だけど、チャーミングな方向はまちがっていないような気がする。耳の奥のほうで、ぼくはそう判断する。そこでは、ライ・クーダーのスライド・ギターやフラーコ・ヒメネスのアコーディオンや、トム・ウェイツのしゃがれ声が響きわたっている。なによりもぼくが、そんな耳の奥の住人たちの音楽を信頼している。心の底から愛してる。文学とか小説とかいったものへのアプローチは、彼らなしにはありえない。ほんのこれっぽちだって、ない。意味をなさない、といってもいい。ほくのなかでは、音楽を聴くという体験と文章を書くという体験が、キュートに癒着している。
愛とか悪とか、しあわせとかいじわるとか、すべて音楽から学んだ。もちろんいまも学んでいる。「ライティング」はその整理と編集のようなもの。ときどきややこしい気持ちにさせられるけれど、「ライティング」ってたのしいな、と思う。
このアコースティックなマシーンは、そんなしあわせをめいっぱいアンプリフィケイションしてくれそうな気がする。耳のなかでビューティフルな昼寝ができそうだ。
すごくないですか、この文章。「チャーミングなたたずまいをさがしながら、ぼくはワード・プロセッサーのキーボードをたたく」ですよ。「耳のなかでビューティフルな昼寝ができそうだ」ってなんですか。「音楽を聴くという体験と文章を書くという体験が、キュートに癒着している」って。癒着かよ!っと突っ込みいれたくなります。80年代がまだ抜け切れていない、微妙な時代だったのですね、92年。
それでは、コンピュータのキーボードをたたくのにもタイヤードなので、チャーミングなうんこをして、ビューティフルにおやすみなさい。
昨日はカミュの『異邦人』を読んだのですが、あまりの面白さにびっくり。高校生ぐらいで先生に騙されてこの小説を読んだ人ってたくさんいると思うのですが、当時全然面白いと思わなかった人、今改めて読んで見たら面白いかもよ。っていうかそんな小説たくさんあるんだろーなー。
休日って、本当に素晴らしい。
ブラック・ジャックのピノコみたいなお話。しかも実話。
■Boy 'pregnant' with twin brother(from BBC)
以下拙訳。
少年、双子の弟を身ごもる
腹痛で病院に収容された七歳の少年は、実は双子の弟を「妊娠」していた
カザフスタンにあるチムケント小児科医院の医師たちは、当初ムーラット・ザナイダロフ少年の病状を、嚢腫によるものと考えていた。
しかしいざ手術をしてみると、ザナイダロフ君の体内から発見されたのは、死亡した彼の双子の兄弟だった。
胎児は腫瘍化してはいたものの、髪の毛や爪、骨などの存在が認められた。
医師がBBCに語ったところによると、腫瘍はムーラット少年の双子の兄弟の遺骸だという。
すでに生命反応はなかったが、少年の血液中の養分を吸収しており、そのまま発見されずに体内に残っていた場合、ムーラット少年の生命を脅かす可能性もあったという。
現在、腫瘍の摘出は無事に終了している。
胎児は、母親の子宮にいる時点で、ムーラット少年の体内に入り込んだと思われる。
医師たちは、二人の胎児は本来シャム双生児になるはずだったのではないだろうかと考えている。
ある外科医はBritish newspaperに次のように語った。「最初に我々は、少年の臓器が黒い髪の毛に覆われた巨大で硬質なこぶのようなものによって圧迫されていることに気付いた」
「彼の体内を洗浄したところ、その内部に、彼自身の双子の兄弟がいることが判明した。ムーラット少年はシャム双生児だったのに、誰もそのことに気づかなかったのだ」
「母親の妊娠時に何らかの変異が起こり、そのために胎児はムーラット少年の体内で身体が成長したのではないだろうか」
チムケント小児科医院のチーフ外科医であるヴァレンティナ・ヴォストリコヴァ氏は、新聞の取材に対して「実に驚くべきことだ。七年もの間、双子の兄弟は少年の内部で寄生虫のように生きていたのだから」と話した。
病院の医師はBBCに対して、この現象を説明することは不可能であり、母親の栄養不良などの多くの要素が、様々な役割を果たした結果だと思う、と述べた。
「日本の漫画『ブラック・ジャック』に同様のストーリーが云々」というコメントは、当然のごとくありません。っていうかさー、生命ってすごいね。意志なんてありようもないのに、それでも兄弟の血液から養分を吸収して生きようとするんだもんね。